- セメントを発明したのはローマ人です。 ローマ人は、石灰岩を焼いてつくった石灰に砂を練り合わせたモルタルをつくりました。さらに、このモルタルにポッゾラーナ(ナポリ近郊のポッツォリに産する良質の火山灰)を加えると硬度と水密性が良くなることを発見しました。現在のセメントです。 彼らは、それに砂利を混ぜて、カエメントウムとして、道路・水路・浴場をつくるのに利用します。それが、現在のコンクリートです。なお、5000年前の中国でもセメントは用いられています。
| 4-1 (注1) コンクリート-発明の歴史 | ||
|
||
| |
| 4-1 (注2) セメント発明の歴史 | ||||||||||
|
||||||||||
| |
| 4-3(注3) 鉄筋コンクリート-発明の歴史 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| |
|
4-3(注4) ゲルバー桁橋 |
||
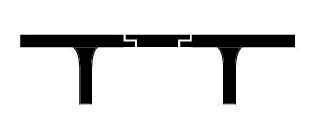 |
||
|
||
| |
| 4-5(注5) プレストレスト・コンクリートの原理 | ||||||||||
 |
||||||||||
|
引張りに強いPC鋼線(ストランド)を金属製の管の中に入れ、これをコンクリートに埋め込みます。 コンクリートが固まった後、PC鋼線を油圧ジャッキで強く引っ張り、そのままの状態で桁の両面のコンクリート面にクサビ或いはナットで固定し、固定が完了すると、ジャッキを取り外します。
その結果、ジャッキでつくられた引張り力は、コンクリートに伝えられ、桁の上側にも、下側にも圧縮応力が働きます。 桁に荷重がかかると、桁の上側には圧縮応力が増加していくのです。(この圧縮応力はコンクリートが支える一方、桁の下側でも、ある限度までは、圧縮応力が働いています。)
しかし、桁の荷重が大きくなり、PC鋼線が予め導入した応力を越えて初めて、圧縮力から引張り力に変わることになります。 そして、PC鋼線が支えうる引張り強度の限界を越えるまでは、桁は破壊されることなく、橋の荷重を支えることができるのです。 プレストレスト・コンクリート-発明の歴史
|
||||||||||
| |
| 4-7(注6) 片持梁構造 (カンチレバー構造) |
||
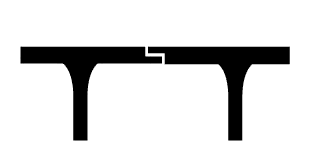 |
||
|
||
| |
All right reserved,Copyright (c) KAJIMA CORPORATION