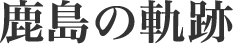第23回 日本初のスキーリフト
日本で現在営業しているスキー場は606箇所あるといわれる。北は北海道稚内市のこまどりスキー場から、南は宮崎県の五ヶ瀬ハイランドスキー場まで、ゴンドラやリフトのないスキー場はない。
新潟県の上越国際スキー場には25基ものリフトがある。リフトでより高い場所に登り、滑り降りる楽しさはスキーの醍醐味でもある。しかし、昭和22(1947)年、進駐軍(*1)が日本にリフトのシステムを持ち込むまで、日本のスキー場にはリフトもゴンドラもなかった。
| *1 | 正式名称は連合国軍最高司令官総司令部。昭和20(1945)年9月から昭和27(1952)年4月まで日本を占領していた連合国軍を統括し、日本を間接統治していた。当時日本政府と報道機関は、「進駐軍」と呼ぶように指導されていたため、鹿島に残る文書も「進駐軍」と記されている。GHQは総司令部(General Headquarters)の略だが、連合国軍最高司令官総司令部、進駐軍と同義語で使われていた。 |
|---|
八甲田山雪中行軍を契機に
スキーは元々移動手段として用いられたのが起源である。スカンジナビアの人々が雪上を移動するために細長い板切れを利用しており、その歴史は紀元前、神話時代まで遡ることができる。中世ヨーロッパの雪国の軍隊ではスキーが必需品だったため、軍事目的でより早いスキーが開発され、スキー競技が盛んになっていった。イギリスの上流階級でサンモリッツ(スイス)などに冬にスキーに行くことが流行となるのは、1900年をすぎたころからであった。
日本でスキーについての記述が見られるのは、1808年に間宮林蔵が著した北方調査の記録「北蝦夷図説」が最初である。ここで樺太の原住民がはいていたスキーが図とともに紹介されている。
 「北蝦夷図説」にある樺太地方探検時に見た原住民
「北蝦夷図説」にある樺太地方探検時に見た原住民
海外では縦型で板状のスキーの原型とも言うべき滑走機能を持った道具が古くから使われており、目的や時代とともに発達していった。これに対して日本の積雪地帯では、雪に埋もれずに歩くことのできる「かんじき」などの歩行具はあったが、スキーの原型となるような滑走のできる歩行具はなぜか生まれなかった。
明治35(1902)年、青森歩兵5連隊約200名が遭難した八甲田山雪中行軍事件(*2)をきっかけに、雪上交通手段としてスキーの研究と導入の機運が高まってきた。これほど大規模の山岳遭難事件は世界でも初めてだったため、海外にも大きく報道される。ノルウェー国王やスウェーデン軍隊から見舞いにそれぞれスキー2台が贈られた。しかしそれらのスキーは使用方法がわからないため、そのまま置かれていたという。
| *2 | 明治35(1902)年1月27日の東京朝日新聞で「兵士雪に阻まる」と題し、「一泊の予定で田代温泉に行軍した兵が帰営せず、救援のために食物を携えた兵士80余名と筒井村から100余名が八甲田山に向かった」とあり、29日には「一隊の士卒皆凍死」という見出しで、捜索隊が雪中に倒れている2名を発見、うち1名に意識があり出発時より大雪に阻まれ食料は2日分、燃料の用意はなかったことを聴取。1月31日にはこの遭難の号外も出、海外にも広く報じられた。 |
|---|
日本スキーの父・レルヒ少佐
明治41(1908)年、スイスのハンス・コラが北海道大学予科に赴任時スキーを持参。明治42(1909)年、英国大使館付き武官が北海道月寒で滑る。明治43(1910)年12月、東京高等師範教授・永井道明がスウェーデンより持ち帰ったスキーを秋田の講習会で試乗している。同じ月、スウェーデンの杉村虎一行使がスウェーデンの軍隊用スキー2台と解説書3冊を陸軍省に送ってきた。陸軍省はこれらを新潟県高田(現・上越市)の第13師団に送り、スキーの研究を命ずる。そして明治44(1911)年1月にレルヒ少佐(オーストリア)が、オーストリア軍用スキー10台とともに高田に着任したのである。彼はスキー専修員14名に計34回のスキーの指導を行い、これが日本での本格的なスキーの始まりとなる。
同じころ、日本における最初の民間スキー場が山形県の五色温泉に作られた。明治44(1911)年、オーストラリア人のオゴン・フォン・クラッツァが泊りがけでスキーをしたことが、スキー場開場のきっかけとなったという(*3)。このように明治時代後期に各地にスキーが持ち込まれたことがわかる。ストックが2本のノルウェースキー術は北海道を中心に、ストックが一本のアルペン山岳スキー術は信越地方を中心に広まった。
当時のスキーのスタイルは1mぐらいのケヤキやクリ材の板の中央より後方に金属締め具をつけたもの。明治44(1911)年2月には新潟県知事の命により新潟県内の中学校体育教師を集めて講習会が開催され、最終日には日本初のスキークラブ高田スキー倶楽部(*4)が発足した。翌年にはこの倶楽部主催で日本初のスキー競技会が開催され、レルヒコースと名づけられた全長4キロのコースで速さを競う。その後大正4(1915)年までに13回の大会が開催され、全国的な交流がほとんどなかった時代に、軍人から学生、逓信・営林・鉄道などの社会人が参加する大会となり、見物人も大勢詰め掛けるようになり、競技としてのスキーは日本に定着するようになる。昭和に入ると北海道など雪国の小学校では体育の授業でスキーが行われるようになる。ストックのグリップとバスケット部分には鹿皮が巻かれていたという。
| *3 | 五色温泉スキー場。平成10(1998)年リフトの老朽化に伴い閉鎖された。 |
|---|---|
| *4 | 明治45(1912)年2月には越信スキークラブと改称。8月には全国的組織となったため日本スキークラブと改称。その後組織は自然消滅して一部地元の高田スキークラブとして残っていたものを、大正10(1921)年、高田スキー団として再結成。昭和7(1932)年の第3回冬季オリンピック(アメリカ・レイクプラシッド)では高田スキー団から上石巌がクロスカントリー男子耐久50kmに出場するなど、オリンピック選手を多く輩出、同団は現在も存続している。 |
東洋のサンモリッツ・志賀高原の誕生
志賀高原(長野県)は、21のスキー場が集合する日本最大規模のスキーリゾート地で、71基のリフトとゴンドラのある85本のコースはシャトルバスで結ばれており、その歴史は100年近くに及ぶ。この地はもともと変化に富んだ山々の連なる雪質のいい地域である。そのため、大正時代からスキーエリアとして親しまれていた。スキー場が開場したのが大正2(1913)年、昭和4(1929)年には長野電鉄初代社長・神津藤平が志賀の山野に「志賀高原」と名づけ、本格的開発に乗り出したといわれる。そのころ世界的ジャンパーでありノルウェーのスキー連盟副会長でもあったヘルゼット中尉とその一行がここを訪れ、東洋のサンモリッツと称えた。昭和5(1930)年の丸池ヒュッテ建設を皮切りにいくつかの旅館やヒュッテが建設されたが、バスはなく冬は徒歩で宿泊施設まで登った。コースは6本ほどあり、ツアースキーの根拠地となる。特に文人、芸術家が好んでこの地を訪れ、そういった人々のゆかりの品々が多い場所でもある。
昭和10(1935)年12月、鉄道省観光局は志賀、妙高、菅平を含む一帯を日本初の国際スキー場として指定した。上林から丸池までスキーヤーの輸送には馬橇が使われたという。しかし戦局が進むにつれ、スキー場は資材供給、食料調達の場となり、旅館は学童疎開受け入れの場となっていき、終戦を迎えた。
日本初のスキーリフト
昭和21(1946)年6月30日、志賀高原ホテルとその敷地、丸池スキー場と付属施設が進駐軍に接収された。10月、志賀高原ホテルの進駐軍初代隊長として赴任したラフェンス・パーカー大尉は日本の終戦処理に基づく賠償業務の一環として丸池スキー場にスキーリフト1基を架設するよう終戦処理委員会(特別調達庁)に申し入れる。このスキー場とリフトは進駐軍第8軍のスキー大会を開催するためのものだったが、第8軍スキーディレクターのフレデリック・ルードラーは、「米軍にとっては一時的なものだが施設は長く残るため、後々日本のスキーヤーが利用できる」場所を選ぼうとした。
11月6日、パーカー大尉は長野県終戦処理委員会と協議し、貨物索道(ケーブル)の施工経験がある鹿島組の技師を招き、同年中に完成させる至上命令を下す。これを担当したのが千秋晴三だった。千秋は当時軽井沢出張所長をしていた建築の設計技師で、松代大本営工事の後始末をしていた。施工途中で中止となった同工事に使用される予定だった建材を東京へ発送する手はずを整えていた10月、鹿島組本店の営業の者から志賀高原現場視察の案内を依頼される。
千秋はルードラーの説明するスキーリフトというものの便利さに驚き、彼から貰ったアメリカのスキー雑誌「Western Skiing」に載っているスキー場やスキーリフトの写真に胸を躍らせた。ルードラーはカリフォルニア大学を卒業した鉱山技師で、スキーリフトは鉱山用索道を改造したものでいいと言う。鉱山工事を数多く手がけている鹿島にとって、鉱山用索道はお手のものだった。しかし本店の土木部に相談を持ちかけると「鉱山用索道に人を乗せるなどとんでもない、危険だ」と否定される。千秋はルードラーから人身事故補償不担保の了解を取り、試行錯誤で索道のバケットを椅子に、緊張所をリフト乗り場(山麓)に、原動所を終点(山頂)にして設計をする。コースは、ジャンプ台1台と3つのスキーコースを作ることが決まり、11月20日ごろから湯田中から丸池へ資材運搬が始まった。
しかし工事が佳境に入ると思われた12月初め、10数年ぶりの大雪となり一晩で人の背丈ほども雪が降り積もる。丸池までの県道は車輌通行止めとなり、資機材の運搬には人力を頼るしかなくなる。「このような事態になって地元の人の協力は実に偉大であった。除雪も運搬も人力だった。あの波坂に行ってみた。幾重にも折り重なった九十九折の旧道、藁沓あるいはゴム長をはき、荷を背負った一列縦隊が黙々と音もなくゆっくりと進行していた。2m位の間をおいて老いも若きも、それぞれ自信のある目方を量って引き受け運んでいた。列は延々と、遠く、高く、上のほうへと小さく見え隠れして空まで続いていた。青年達ばかりでなく老人も、女性も、子供までが働いていた。本当に力強い人たちだった。」(*5)このあとにもまた大雪が来て、人海戦術によってリフトのワイヤーロープを運ぶこととなった。250m以上あるロープを肩に担いで山の上に運んだという。雪の下2mに埋もれた資材も地元の人が雪を掻き分けて掘り出した。
二度の大雪の後は晴天が続き、作業は急速に進む。急斜面に太い丸太の支柱が組み立てられ、ステーションの木造建家も完成した。スキーコースの伐採後、岩石はダイナマイトで砕かれ、コースが均された。1月20日にはペンキも塗り終わりリフトの試運転、調整を終了。無事米軍スキー大会の開会に間に合わせることができた。
 終点側から見た丸池スキーリフト(昭和22年1月) クリックすると拡大します
終点側から見た丸池スキーリフト(昭和22年1月) クリックすると拡大します
 丸池スキーリフト全景 クリックすると拡大します
丸池スキーリフト全景 クリックすると拡大します
 宣伝用と思われる丸池スキー場写真 クリックすると拡大します
宣伝用と思われる丸池スキー場写真 クリックすると拡大します
 千秋晴三(左) クリックすると拡大します
千秋晴三(左) クリックすると拡大します
同じころ、札幌の藻岩山にも進駐軍のスキーリフトが完成した。しかしこの藻岩山も丸池も進駐軍専用のゲレンデにかけられたリフトで、スキー場一帯にはロープがかけられ、一般人は利用できなかった。プロスキーヤーの三浦雄一郎は、当時「私は学生で通訳ができる」と言っては進駐軍しか利用できない藻岩山のスキーリフトに乗ったとテレビ番組で語っていた。『サンデー毎日』昭和24(1949)年1月30日号では表紙の絵(石川滋彦)に丸池スキー場のリフトが描かれており、当時スキーリフトというものが話題になっていたことがわかる。「登らず歩かず、下りだけ楽しめるスキーなど、到底、想像もできなかった戦後の貧しい日本人に、真から平和の喜びを与えてくれた進駐軍のスキーリフトはすばらしい贈り物であった。」(*6)
昭和23年の営業経歴書には進駐軍工事の部に「志賀高原工事」が記載されている。「工期:昭和21年11月-昭和22年1月 工事金額:4,519,000円」昭和21年から22年にかけて、消費者物価指数は125.3%上昇しているため、この金額の多寡はわからない。千秋は後に「私は、設計経験はあったが工事施工の経験はなかった。この工事は普通の経済観念を必要としなかったため、私にもできたのかもしれない」(*5)と述べている。
日本人がこのリフトに自由に乗れるようになったのは、進駐軍の接収が解除された昭和27(1952)年10月のことであった。スキーリフトの魅力に取り付かれた千秋はその後、スキーリフトの資料を集めて整理し、設計にも施工にも対応できる用意をしたが実現には至らず、昭和35(1960)年、設計部次長を最後に、現役を退いている。
| *5 | 千秋晴三「志賀高原スキーリフト建設の思い出」志賀高原観光開発『二十年のあゆみ:志賀高原観光開発株式会社』(1978) |
|---|---|
| *6 | 志賀高原観光開発『二十年のあゆみ:志賀高原観光開発株式会社』(1978)p62 |
参考図書
志賀高原スキークラブ『志賀高原スキー史1920-1991』(1991)
志賀高原観光開発『二十年のあゆみ:志賀高原観光開発株式会社』(1978)
山ノ内町『山ノ内町誌』(1973)
村上貞助編『北蝦夷図説 : 一名・銅柱余録』(1970 安政2年刊本の複製)
(2008年12月24日公開)