| ザ・サイト |
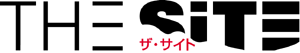 一般国道333号佐呂間町新佐呂間トンネル工事 北海道常呂郡佐呂間町。ここで当社JVは,道内で2番目に長い「新佐呂間トンネル」を施工中である。延長4,110mを,当社JVで両方向から掘り進み,2007年5月の貫通を目指す。 約40ヵ月の短工期である。10月下旬,訪れた現場はすでに初冬の佇まいだった。 厳しい自然と闘い,毎分3tの湧水を克服し,24時間施工で難工事に挑む現場の社員,作業員たち。「この工事の完成を地元の人たちが心待ちしている」。その士気は高かった。 本記事は10月23,24日の取材をもとに構成されています。 |
| |
| 工事概要 一般国道333号佐呂間町新佐呂間トンネル工事 場所:北海道常呂郡佐呂間町栃木〜北見市北陽 発注者:国土交通省北海道開発局網走開発建設部 設計:国土交通省北海道開発局 規模:施工延長6,490m トンネル延長(NATM)4,110m 仕上がり断面64m2 明かり土工区2,380m/工期:2004年12月〜2008年3月 (札幌支店JV施工) |
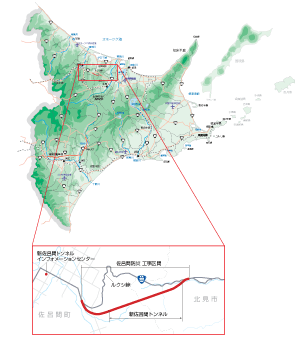 |
| クリックすると大きくなります |
| |
| |
| 住民の安全通行守る国道トンネル 女満別空港から車で約50分。丘陵地帯に囲まれた自然豊かな場所に現場はある。佐呂間町と北見市を結ぶ国道333号線の現場付近は地盤が緩く,2001年10月4日には土砂崩れで2人が亡くなっている。「事故のあった岩盤崩落箇所と同様の地質を持つ場所を避け,安全な道路を建設する防災事業の一環として整備されるのが新佐呂間トンネルです」と,現場の松木平恒美所長が説明してくれた。 国道333号線のルクシ峠(標高342m)越えは,急勾配,急カーブの多い道路でもあった。地盤の緩さから1時間に55ミリ以上の雨で峠は通れない。地域住民はその都度不便を強いられてきた。またこの道路は,主要産業品や資材の輸送ルートだけでなく,オホーツク圏唯一の高次医療機関・救命救急センターがある北見赤十字病院への救急搬送ルートでもある。新佐呂間トンネルが完成すると,勾配は2.6%,起点から終点にかけて緩やかに約100m登るだけとなり,カーブは28箇所から3箇所に減る。 一刻も早い完成を――。「地域住民の熱い願いと期待を受けて,24時間,休み無く稼動しています」と所長は言った。 |
| |
 |
 |
| |
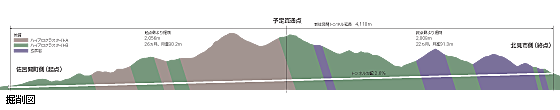 |
| クリックすると大きくなります |
| |
| 毎分3tの湧水と闘う 10月も終わり近くになると,朝晩の気温はマイナスになる。延長4,110mのトンネルを佐呂間町側(起点),北見市側(終点)両方向から同じ工法で掘り進む。 佐呂間町側のトンネル掘削先端(切羽)へ案内してもらった。 現場では,水抜孔から噴出する地下水を浴びながら装薬作業が進められていた。今年9月末に発生した切羽の湧水は毎分約3t。トンネル工事でこうした湧水は珍しいことではないが,これから迎える冬の外気はマイナス25℃にもなるという。北国での作業の厳しさは図り知れない。 湧水に伴い,起点のトンネル掘削は一時停止した。検討の結果,工事排水の濁水処理機の増設,坑内からの排水能力を増強するための排水管路を新設し,トンネル両側に水抜孔を設置。前面からの湧水を清濁分離させ,清流はそのまま放水できるようにした。またコンクリートではロックボルト(鋼棒)が地山にうまく固定しないため,水圧で固定するロックボルトを採用するなどの対応で,20日余りで掘削を再開した。 |
| |

| |
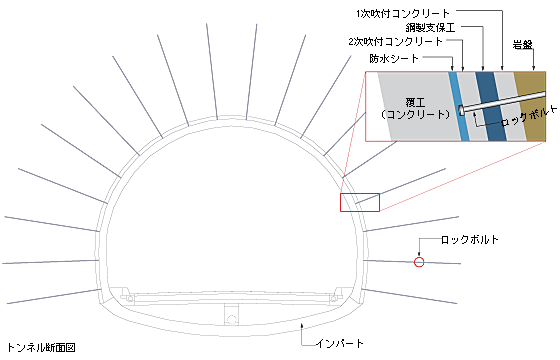
| |
| 安全と環境保全の技術駆使 現場では,複数の新技術・新工法が採用されているが,中でも多様な配慮が施されたのが安全と環境保全である。 発破で一面を真っ白にした粉塵は,わずか数分で消えて切羽がはっきりと見えてくる。大型集塵機「伸縮風管システム」の威力だ。このシステムでは,風管が切羽近くまで伸びるため,粉塵を逃さず吸い取ることができる。また,ズリ出しには連続ベルトコンベヤ方式を採用した。ダンプトラックが坑内を走らないことで,作業員の安全が図れるとともに,排気ガスと粉塵の舞い上がりによる坑内環境の悪化を防いだ。ズリ出し中も後方の覆工作業が行えるというメリットもある。 数々のトンネル現場を歴任してきた松木平所長が,その経験から導入したのが「微砂回収システム」である。トンネル工事ではコンクリートを洗い流すために大量の水を使うが,その際に取り出した脱水ケーキ(水とコンクリートを分離し固形分を脱水したもの)を,佐呂間側トンネル坑口と国道333号線を結ぶ道路の補修材に再利用した。 |
| |

| |

| |
 |
 |
| |
| 地域の人に見守られて この現場では,こうした最新技術を用いたトンネル工事を広く知ってもらおうと,現場見学会を随時開催しているほか,工事事務所敷地内にインフォメーションセンターを設置。ミニコミ誌「わかさ新聞」を月1回発行したり,ホームページを開設して,工事の進捗状況や現場で使われている技術などをわかりやすく説明している。現場の仮囲いを低くして,現場内の様子がわかる工夫をするなど,積極的な情報開示で,きめ細かく地元住民との交流を図っている。現場見学の来場者は10月末で約1,500人にのぼった。佐呂間町の人口は約6,000人。地元のトンネル建設への関心と期待の高さがうかがえる。 松木平所長は現場見学会に訪れる学生に「どうして蛇口をひねるといつも綺麗な水が出るのか,なぜ北海道や東京や沖縄で,同じジュースを同じ値段で買えるのか,もう一度考えて欲しい」と問い掛ける。生まれたときからインフラが整備され,便利で豊かな環境で育った若者にこそ,公共工事に対する誤解を解いてもらいたいとの思いがある。そして「この工事を無事完工させるために,昼夜を問わず常に約100人もの作業員が懸命に働いていることを知って欲しいのです」と語る。 所長は今年も10月4日に崩落事故の現場に花を手向けた。「二度とあのような悲劇が起きてはいけない。我々が作った安全で安心できるトンネルを地元の方々に使って欲しい。そして,長く親しまれるトンネルであって欲しい。そう願っています」。 新佐呂間トンネルの開通は2008年度の予定である。 |
| |
 |
 |
| |
 |
| |

| |
| |
|
| |
| |
| |