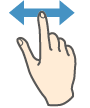世界各地で傑作を手がける,SANAA(妹島和世・西沢立衛両氏による建築家ユニット)の建築の特徴として,表層の操作と曲線のデザインが挙げられる。いずれもモダニズムの時代からなかったわけではない手法だが,かつてない独特な使い方によって,新しい効果をもたらした。こうした傾向は,SANAAの活動の初期にあたる1990年代から認められるが,21世紀を迎えると,もっと大胆になり,前衛化している。さらに起源を考察すると,妹島和世氏が1978年度の卒業論文で,ル・コルビュジエの全作品の曲線をトレースして分析したことまでたどれるかもしれない。 2021年,パリのど真ん中でサマリテーヌ百貨店が再生された。彼らは繋がった2棟のうち,アール・ヌーヴォーのポン・ヌフ館(1910年)の内部空間を明るく開放的にリノベーションしながら,外観は変更しなかったが,リヴォリ館の方では,細かいピッチで波打つガラスのファ第2回 表層16KAJIMA202405
世界各地で傑作を手がける,SANAA(妹島和世・西沢立衛両氏による建築家ユニット)の建築の特徴として,表層の操作と曲線のデザインが挙げられる。いずれもモダニズムの時代からなかったわけではない手法だが,かつてない独特な使い方によって,新しい効果をもたらした。こうした傾向は,SANAAの活動の初期にあたる1990年代から認められるが,21世紀を迎えると,もっと大胆になり,前衛化している。さらに起源を考察すると,妹島和世氏が1978年度の卒業論文で,ル・コルビュジエの全作品の曲線をトレースして分析したことまでたどれるかもしれない。 2021年,パリのど真ん中でサマリテーヌ百貨店が再生された。彼らは繋がった2棟のうち,アール・ヌーヴォーのポン・ヌフ館(1910年)の内部空間を明るく開放的にリノベーションしながら,外観は変更しなかったが,リヴォリ館の方では,細かいピッチで波打つガラスのファ第2回 表層16KAJIMA202405
 サードを与えている。これが東京の混沌とした街並みならば,そこまで驚くようなデザインではないが,古典主義の建築が連なるリヴォリ通りでは,ずば抜けて斬新な顔になるだろう。実際,計画時には地元の反対があったと聞く。だが,現地に足を運ぶと,なるほど格調高い通りに対しては,異形のかたちを挿入して,場を乱すのではなく,むしろうねるガラスで包むことで,かたちの存在感を消しつつ,ファサードにまわりの古典建築を幾重にも反復しながら映しだし,イメージを増幅させたことがわかる。かくして歴史的な街並みに新鮮な感覚をもたらすことに成功した。 2012年,フランスの地方都市,ランスの駅の近くにオープンしたのが,ルーブル美術館の別館である。この建築も,ガラスとアルミニウムの外壁に映り込む外の風景や,展示室における鏡面仕上げの内壁が,映像的な効果を生みだした。映像的というのは,鑑賞者が移動しながら表層を見ると,刻々と映り込みが変化したり,動くものの映り込みが興味深い,という意味である。またルーブル・ランスは,壁や床がまっすぐではなく,わずかにカーブしており,微妙なねじれをもつ。こうした曲線は,まわりの地形の高低差や引き込み線の土盛りなど,敷地の条件を踏まえたものだ。ちなみに,ランスはかつて炭鉱で栄えた街であり,敷地からはボタ山も見える。 これに対して,ロレックスラーニングセンターは,通常の平面図や断面図だけでは表現しにくい,はっきりと3次元的に曲がった造形である。これまでにない空間の体験を与えるものだ。が,広角レンズを使わずに撮影された今回の写真を見ると,うねる曲面が遠くのアルプスの山並み,あるいは向こうの木々といった風景と呼応していることに気づく。ユニークな造形に目を奪われがちだが,SANAAは建築とランドスケープの関係を大事にしている。写真 ― 鈴木久雄文 ― 五十嵐太郎2017年,ルーブル美術館ランス別館(ランス)。“時間のギャラリー”北面ファサード17KAJIMA202405
サードを与えている。これが東京の混沌とした街並みならば,そこまで驚くようなデザインではないが,古典主義の建築が連なるリヴォリ通りでは,ずば抜けて斬新な顔になるだろう。実際,計画時には地元の反対があったと聞く。だが,現地に足を運ぶと,なるほど格調高い通りに対しては,異形のかたちを挿入して,場を乱すのではなく,むしろうねるガラスで包むことで,かたちの存在感を消しつつ,ファサードにまわりの古典建築を幾重にも反復しながら映しだし,イメージを増幅させたことがわかる。かくして歴史的な街並みに新鮮な感覚をもたらすことに成功した。 2012年,フランスの地方都市,ランスの駅の近くにオープンしたのが,ルーブル美術館の別館である。この建築も,ガラスとアルミニウムの外壁に映り込む外の風景や,展示室における鏡面仕上げの内壁が,映像的な効果を生みだした。映像的というのは,鑑賞者が移動しながら表層を見ると,刻々と映り込みが変化したり,動くものの映り込みが興味深い,という意味である。またルーブル・ランスは,壁や床がまっすぐではなく,わずかにカーブしており,微妙なねじれをもつ。こうした曲線は,まわりの地形の高低差や引き込み線の土盛りなど,敷地の条件を踏まえたものだ。ちなみに,ランスはかつて炭鉱で栄えた街であり,敷地からはボタ山も見える。 これに対して,ロレックスラーニングセンターは,通常の平面図や断面図だけでは表現しにくい,はっきりと3次元的に曲がった造形である。これまでにない空間の体験を与えるものだ。が,広角レンズを使わずに撮影された今回の写真を見ると,うねる曲面が遠くのアルプスの山並み,あるいは向こうの木々といった風景と呼応していることに気づく。ユニークな造形に目を奪われがちだが,SANAAは建築とランドスケープの関係を大事にしている。写真 ― 鈴木久雄文 ― 五十嵐太郎2017年,ルーブル美術館ランス別館(ランス)。“時間のギャラリー”北面ファサード17KAJIMA202405
 18KAJIMA202405
18KAJIMA202405
 サマリテーヌ百貨店(パリ)。2022年, 北面(リヴォリ通り側)ファサードを リヴォリ通りとポン・ヌフ通り交差点より見る 2010年,スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) ロレックスラーニングセンター(ローザンヌ)。 北側ファサード中央図書館スペースを見る。 左部奥がモンブラン方向鈴木久雄 すずき・ひさお建築写真家。1957年生まれ。バルセロナ在住。1986年から現在まで,世界的な建築雑誌『ElCroquis(エル・クロッキー)』の専属カメラマンとして活躍。日本では1988年,鹿島出版会の雑誌『SD』「ガウディとその子弟たち」の撮影を行って以来,世界の著名建築家を撮影し続けている。ほかに『a+u』「ラ・ルース・マヒカ―写真家,鈴木久雄」504号,2012年,「スーパーモデル―鈴木久雄が写す建築模型」522号,2014年など。五十嵐太郎 いがらし・たろう建築史家,建築批評家。1967年生まれ。東北大学大学院教授。近現代建築・都市・建築デザイン,アートやサブカルチャーにも造詣が深く,多彩な評論・キュレーション活動,展覧会監修で知られる。これまでヴェネチアビエンナーレ国際建築展2008日本館コミッショナー,あいちトリエンナーレ2013芸術監督などを歴任。著書に『被災地を歩きながら考えたこと』『建築の東京』『現代日本建築家列伝』,編著『レム・コールハースは何を変えたのか』など多数。デザイン―江川拓未(鹿島出版会)19KAJIMA202405
サマリテーヌ百貨店(パリ)。2022年, 北面(リヴォリ通り側)ファサードを リヴォリ通りとポン・ヌフ通り交差点より見る 2010年,スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) ロレックスラーニングセンター(ローザンヌ)。 北側ファサード中央図書館スペースを見る。 左部奥がモンブラン方向鈴木久雄 すずき・ひさお建築写真家。1957年生まれ。バルセロナ在住。1986年から現在まで,世界的な建築雑誌『ElCroquis(エル・クロッキー)』の専属カメラマンとして活躍。日本では1988年,鹿島出版会の雑誌『SD』「ガウディとその子弟たち」の撮影を行って以来,世界の著名建築家を撮影し続けている。ほかに『a+u』「ラ・ルース・マヒカ―写真家,鈴木久雄」504号,2012年,「スーパーモデル―鈴木久雄が写す建築模型」522号,2014年など。五十嵐太郎 いがらし・たろう建築史家,建築批評家。1967年生まれ。東北大学大学院教授。近現代建築・都市・建築デザイン,アートやサブカルチャーにも造詣が深く,多彩な評論・キュレーション活動,展覧会監修で知られる。これまでヴェネチアビエンナーレ国際建築展2008日本館コミッショナー,あいちトリエンナーレ2013芸術監督などを歴任。著書に『被災地を歩きながら考えたこと』『建築の東京』『現代日本建築家列伝』,編著『レム・コールハースは何を変えたのか』など多数。デザイン―江川拓未(鹿島出版会)19KAJIMA202405