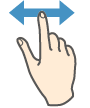数年前から、会議の研究をしている。建物にしろ、イベントにしろ、﹁つくる﹂の規模が大きくなればなるほど、関わる人の数もふえる。関わる人がふえれば、それだけ会議の数もふえる。ものやことをつくるためには人と人の関係をつくることが不可欠で、その意味で会議は第二のものづくりの現場ともいえる。 自分が出席者のひとりとして参加する会議はときに苦痛だが、観察者として参加する会議はとても面白い。暗黙のルールのようなものがあって、まるで演劇を見ているみたいだ。 ある月刊誌の編集会議では、司会の編集長が語尾を伸ばすと、みんなが意見を言い始める、という不思議なリズムがあった。﹁今日の4時に〇〇さんが来まーす﹂と言うと、それまで黙って聞いていた他のスタッフが﹁〇〇さんに会うなら△△の話をしておいたほうがいい﹂﹁△△については××さんが前に□□と言っていた﹂など、口々にしゃべり始めるのである。 また別の事業所の運営会議では、所長とAさんが、お互いを﹁山火事﹂と﹁消防車﹂と呼び合っていた。所長は面白そうなことがあると﹁やってみよう﹂とすぐに燃え上がるタイプ。それに対してAさんは﹁見切り発車はよくない﹂と冷や水を浴びせるタイプ。重要なのは、Aさんがいるからこそ、所長は安心して燃え上がることができる、ということだ。Aさんは所長を批判したいのではなく、所長の能力を発揮させるために、そばでホースを構えているのである。こうした﹁配役﹂も会議にはよく見られる。 ある福祉施設の会議では、合意することを徹底して避けていた。支援の計画が決まりそうになると必ずそれを否定したり、はぐらかしたりする人があらわれるのである。結論を出すこと、ひとつになることを徹底的に疑っている。 彼らの会議がそのようなスタイルをとる根本的な理由は、その施設が重度の知的障害がある人たちを相手にしていることが大きい。重度の知的障害がある人たちは、何を望んでいるのか、なぜそのような行動をとっているのか、分からないケースが多い。たとえばドアを叩いている人がいたら、﹁外に出たがっているんじゃないか﹂﹁ただ注目を浴びたいだけじゃないか﹂など解釈が複数出てくる。逆に言えば、解釈をひとつに決めてしまうことは、その人の意思をまわりのスタッフが勝手に代弁してしまうことになり、危険だ。毎回の会議は、彼らにとっては自分の価値観を疑う練習でもある。 ただ客観的に見て最善の選択をしたいだけなら、わざわざ集まって会議する必要はない。つくるのに会議が必要ということは、人間が合理だけでは動かない生き物であることの証拠のように思う。30KAJIMA202407いとう・あさ 美学者。東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長、リベラルアーツ研究教育院教授。MIT客員研究員(2019年)。もともと生物学者を目指していたが、大学3年次より文転。2010年に東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻美学芸術学専門分野博士課程を単位取得のうえ退学。同年、博士号を取得(文学)。主な著作に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『手の倫理』(講談社)。第13回(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞、第42回サントリー学芸賞、第19回日本学術振興会賞、日本学士院学術奨励賞受賞。vol.235
数年前から、会議の研究をしている。建物にしろ、イベントにしろ、﹁つくる﹂の規模が大きくなればなるほど、関わる人の数もふえる。関わる人がふえれば、それだけ会議の数もふえる。ものやことをつくるためには人と人の関係をつくることが不可欠で、その意味で会議は第二のものづくりの現場ともいえる。 自分が出席者のひとりとして参加する会議はときに苦痛だが、観察者として参加する会議はとても面白い。暗黙のルールのようなものがあって、まるで演劇を見ているみたいだ。 ある月刊誌の編集会議では、司会の編集長が語尾を伸ばすと、みんなが意見を言い始める、という不思議なリズムがあった。﹁今日の4時に〇〇さんが来まーす﹂と言うと、それまで黙って聞いていた他のスタッフが﹁〇〇さんに会うなら△△の話をしておいたほうがいい﹂﹁△△については××さんが前に□□と言っていた﹂など、口々にしゃべり始めるのである。 また別の事業所の運営会議では、所長とAさんが、お互いを﹁山火事﹂と﹁消防車﹂と呼び合っていた。所長は面白そうなことがあると﹁やってみよう﹂とすぐに燃え上がるタイプ。それに対してAさんは﹁見切り発車はよくない﹂と冷や水を浴びせるタイプ。重要なのは、Aさんがいるからこそ、所長は安心して燃え上がることができる、ということだ。Aさんは所長を批判したいのではなく、所長の能力を発揮させるために、そばでホースを構えているのである。こうした﹁配役﹂も会議にはよく見られる。 ある福祉施設の会議では、合意することを徹底して避けていた。支援の計画が決まりそうになると必ずそれを否定したり、はぐらかしたりする人があらわれるのである。結論を出すこと、ひとつになることを徹底的に疑っている。 彼らの会議がそのようなスタイルをとる根本的な理由は、その施設が重度の知的障害がある人たちを相手にしていることが大きい。重度の知的障害がある人たちは、何を望んでいるのか、なぜそのような行動をとっているのか、分からないケースが多い。たとえばドアを叩いている人がいたら、﹁外に出たがっているんじゃないか﹂﹁ただ注目を浴びたいだけじゃないか﹂など解釈が複数出てくる。逆に言えば、解釈をひとつに決めてしまうことは、その人の意思をまわりのスタッフが勝手に代弁してしまうことになり、危険だ。毎回の会議は、彼らにとっては自分の価値観を疑う練習でもある。 ただ客観的に見て最善の選択をしたいだけなら、わざわざ集まって会議する必要はない。つくるのに会議が必要ということは、人間が合理だけでは動かない生き物であることの証拠のように思う。30KAJIMA202407いとう・あさ 美学者。東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長、リベラルアーツ研究教育院教授。MIT客員研究員(2019年)。もともと生物学者を目指していたが、大学3年次より文転。2010年に東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻美学芸術学専門分野博士課程を単位取得のうえ退学。同年、博士号を取得(文学)。主な著作に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『手の倫理』(講談社)。第13回(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞、第42回サントリー学芸賞、第19回日本学術振興会賞、日本学士院学術奨励賞受賞。vol.235