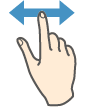04KAJIMA202408サステナブルコンクリートCO2で未来をつくる特集道路や橋,ダムやトンネルなどのインフラ,そしてマンションや商業施設,オフィスビルなど,様々な構造物に欠かすことのできないコンクリート。この材料は地球上で“水”に次いで使用量が多く,近代以降の私たちの生活基盤をつくりあげて来た。その一方で,コンクリートは製造時に大量のCO2を排出することから,地球温暖化を進行させる要因の一つとも言われている。世界規模でカーボンニュートラルへの取組みが本格化するなか,当社は世界で初めて,CO2排出量を実質ゼロ以下にできる,CO2を“吸収する”コンクリートの開発に成功。CO2を減らし,そして活かすことで,カーボンネガティブを達成した。“コンクリートをサステナブルへ。”CO2で私たちの未来をつくろう。
04KAJIMA202408サステナブルコンクリートCO2で未来をつくる特集道路や橋,ダムやトンネルなどのインフラ,そしてマンションや商業施設,オフィスビルなど,様々な構造物に欠かすことのできないコンクリート。この材料は地球上で“水”に次いで使用量が多く,近代以降の私たちの生活基盤をつくりあげて来た。その一方で,コンクリートは製造時に大量のCO2を排出することから,地球温暖化を進行させる要因の一つとも言われている。世界規模でカーボンニュートラルへの取組みが本格化するなか,当社は世界で初めて,CO2排出量を実質ゼロ以下にできる,CO2を“吸収する”コンクリートの開発に成功。CO2を減らし,そして活かすことで,カーボンネガティブを達成した。“コンクリートをサステナブルへ。”CO2で私たちの未来をつくろう。
 05KAJIMA202408
05KAJIMA202408
 質・経済性をバランスよく兼ね備え,脱炭素から『活炭素』へのステージ移行の促進,汎用性の高いカーボンネガティブコンクリートの実現と社会実装を目指した研究開発を進めています」。06KAJIMA202408ポイントは3つの技術 建設業で排出されるCO2は,全産業のCO2排出量の約4割を占め,建設資材の中ではコンクリート製造時に発生するCO2が最も大きな割合を占める。これはコンクリートの主要材料の一つであるセメントの製造に由来するもので,その製造過程において主原料である石灰石を高温で燃焼することから,CO2が大量に排出される。 当社はこれに着目し,セメントの使用量を低減するなど,いち早くサステナブルコンクリートの研究に取り組んだ。そして2008年,1万年コンクリート「EIEN®」のCO2吸収技術を応用し,世界で初めてCO2排出量を実質ゼロ以下にできる「CO2-SUICOM®※1」を開発した。 現在当社は,①セメントを“低減”する,②CO2を“固定”する,③CO2を“吸収”する3つの技術でCO2の削減に貢献するコンクリート技術を展開し,建設物の用途や特徴に合わせた,汎用性と適用の幅を,日進月歩で広げている。 当社技術研究所で,長年コンクリートの研究開発に携わる閑田徹志副所長は,当社のサステナブルコンクリートに関する研究の特長と汎用性を,土建の一体化にあるという。「土木は長期視野で基礎段階からの研究が得意であるのに対し,建築は実用化・汎用化を重視する傾向があります。当社は,土建の距離が近いからこそ,お互いの特長を活かすことができ,開発と実用化の両方を意識した研究へつなげることができています」。 今年5月,当社はサステナブルコンクリートの使用率を2030年までに40%(鹿島単体)とする目標を「鹿島環境ビジョン2050plus」で発表,さらなる技術開発と実用化へ向け,より一層力を注いでいる。CO2-SUICOMから発展。多業種・大学との連携で挑む「CUCO-SUICOM」 CO2-SUICOMの開発を契機に,サステナブルコンクリートのさらなる研究・開発と汎用性の向上を目的としたコンソーシアム「CUCO※2」が発足した。当社建築部門の開発責任者でもある閑田副所長は,CUCOについて次のように述べる。「CUCOは,当社・デンカ・竹中工務店の3社を幹事とするコンソーシアムで,NEDO※3の『グリーンイノベーション基金事業※4/CO2を用いたコンクリート等製造技術開発』のコンクリート分野における開発として共同提案を行った後,2022年に採択されました。CUCOの特長は,民間企業や大学など,合計55もの団体が集まっていること,そして研究開発のその先を見ていることです。環境・品※1CO2-StorageandUtilizationforInfrastructurebyCOncreteMaterials※2CarbonUtilizedConcreteの頭文字から生まれた造語※3国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構※4「2050年カーボンニュートラル」の目標達成に向け,NEDOに2兆円の基金を造成し,官民で野心的かつ具体的な目標を共有したうえで,これに経営課題として取り組む企業などに対して,10年間,研究開発・実証から社会実装までを継続して支援する事業~3つの技術を融合し,さらなるCO2排出量削減へ~鹿島のサステナブルコンクリート技術研究所 閑田徹志副所長コンクリートは,必要不可欠な存在であると同時に,環境への負荷も大きい。そこで当社は,CO2を減らす,そして活かすコンクリート技術を研究・開発し続けて来た。これからの未来を見据えた,当社のサステナブルコンクリートを紹介する。
質・経済性をバランスよく兼ね備え,脱炭素から『活炭素』へのステージ移行の促進,汎用性の高いカーボンネガティブコンクリートの実現と社会実装を目指した研究開発を進めています」。06KAJIMA202408ポイントは3つの技術 建設業で排出されるCO2は,全産業のCO2排出量の約4割を占め,建設資材の中ではコンクリート製造時に発生するCO2が最も大きな割合を占める。これはコンクリートの主要材料の一つであるセメントの製造に由来するもので,その製造過程において主原料である石灰石を高温で燃焼することから,CO2が大量に排出される。 当社はこれに着目し,セメントの使用量を低減するなど,いち早くサステナブルコンクリートの研究に取り組んだ。そして2008年,1万年コンクリート「EIEN®」のCO2吸収技術を応用し,世界で初めてCO2排出量を実質ゼロ以下にできる「CO2-SUICOM®※1」を開発した。 現在当社は,①セメントを“低減”する,②CO2を“固定”する,③CO2を“吸収”する3つの技術でCO2の削減に貢献するコンクリート技術を展開し,建設物の用途や特徴に合わせた,汎用性と適用の幅を,日進月歩で広げている。 当社技術研究所で,長年コンクリートの研究開発に携わる閑田徹志副所長は,当社のサステナブルコンクリートに関する研究の特長と汎用性を,土建の一体化にあるという。「土木は長期視野で基礎段階からの研究が得意であるのに対し,建築は実用化・汎用化を重視する傾向があります。当社は,土建の距離が近いからこそ,お互いの特長を活かすことができ,開発と実用化の両方を意識した研究へつなげることができています」。 今年5月,当社はサステナブルコンクリートの使用率を2030年までに40%(鹿島単体)とする目標を「鹿島環境ビジョン2050plus」で発表,さらなる技術開発と実用化へ向け,より一層力を注いでいる。CO2-SUICOMから発展。多業種・大学との連携で挑む「CUCO-SUICOM」 CO2-SUICOMの開発を契機に,サステナブルコンクリートのさらなる研究・開発と汎用性の向上を目的としたコンソーシアム「CUCO※2」が発足した。当社建築部門の開発責任者でもある閑田副所長は,CUCOについて次のように述べる。「CUCOは,当社・デンカ・竹中工務店の3社を幹事とするコンソーシアムで,NEDO※3の『グリーンイノベーション基金事業※4/CO2を用いたコンクリート等製造技術開発』のコンクリート分野における開発として共同提案を行った後,2022年に採択されました。CUCOの特長は,民間企業や大学など,合計55もの団体が集まっていること,そして研究開発のその先を見ていることです。環境・品※1CO2-StorageandUtilizationforInfrastructurebyCOncreteMaterials※2CarbonUtilizedConcreteの頭文字から生まれた造語※3国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構※4「2050年カーボンニュートラル」の目標達成に向け,NEDOに2兆円の基金を造成し,官民で野心的かつ具体的な目標を共有したうえで,これに経営課題として取り組む企業などに対して,10年間,研究開発・実証から社会実装までを継続して支援する事業~3つの技術を融合し,さらなるCO2排出量削減へ~鹿島のサステナブルコンクリート技術研究所 閑田徹志副所長コンクリートは,必要不可欠な存在であると同時に,環境への負荷も大きい。そこで当社は,CO2を減らす,そして活かすコンクリート技術を研究・開発し続けて来た。これからの未来を見据えた,当社のサステナブルコンクリートを紹介する。
 07KAJIMA202408特集 CO2で未来をつくる サステナブルコンクリートエコクリート®R3CO2でつくる,これからのコンクリート「CO2-SUICOM」世界初!CO2排出量を実質ゼロ以下へエコクリート®ECM・KKC・BLSCUCO-SUICOM製造過程一般的なコンクリートとCO2-SUICOMのCO2排出量の比較CUCO-SUICOMが目指すCO2削減量の目標値※5コンクリート工事では,注文したコンクリートの1∼2%がやむを得ない理由で使用されず,骨材を回収・再生したのち,残ったセメント分(スラッジ)は産業廃棄物として処分されている※6戻りコンクリートから骨材を除去・脱水・粉砕し,製造される※8鹿島,中国電力,デンカ,ランデスの4社※7鉄鋼製造の副産物で,セメントと同様,水との化学反応によって硬化する性質を持つFile.1セメントを低減するセメントの一部を再生セメントや産業副産物などに置き換えることで,セメントの使用量を減らし,CO2排出量を低減する。File.2File.3CO2を固定するCO2を吸収する廃コンクリートなどにCO2を反応・吸収させて骨材や粉末を製造し,それをコンクリートに材料として練り混ぜることで,CO2を固定する。コンクリート製造時に,大量のCO2を吸収して固まることで,コンクリート製造過程でのCO2排出量をゼロ以下にできる。 戻りコンクリート※5から製造される再生セメント「CemR3※6」を使用したコンクリート。CemR3は,通常のセメントとは異なり,CO2が直接合成される焼成過程を経ず,さらに低温で製造されるため製造時のCO2排出量を約1/8に抑えられる。 「CO2-SUICOM」は,2008年に当社ら※8が開発した,製造過程でCO2を吸収するコンクリート。セメントの半分以上を,産業副産物と,CO2との化学反応によってコンクリートを硬化させる「γガンマシーツ―エス-C2S」に置き換え,さらに炭酸化養生することでCO2を吸収させ,コンクリートに固定する。 CUCO-SUICOMでは,CO2-SUICOMのCO2を吸収する技術をベースに,CemR3やECMなどのセメントを低減する技術や,エコタンカルのようなCO2を固定する技術を組み合わせて,CO2削減量の最大化を図る。 セメントの一部置換えに加え,炭酸化養生によりCO2削減量を増大させることで,一般的なコンクリートと比較し,実質ゼロ以下(=▲18㎏/m3)を実現した。 他のサステナブルコンクリートにはない,CO2を吸収・固定する特長を持ち,現在は,CO2固定量に応じて,カーボンネガティブ型とカーボン低減型の2種類のグレードを展開している。 CO2を固定した炭酸カルシウム「エコタンカル®」は,CO2を固定化した炭酸カルシウムとして現在,唯一市販されているもので,当社と共同研究をしている日本コンクリート工業が開発した。プレキャストコンクリート工場内で発生するカルシウムを含んだ排水と,ボイラーの排ガスに含まれるCO2を反応させることで製造される。 セメントの一部を,微粉末状にした高炉スラグ※7に置き換えたコンクリートで,高炉スラグ微粉末の含有率によって下表のような異なる特長を持つ。セムアールスリー地上構造エコクリート®BLSCO2削減量,最大化へ「CUCO-SUICOM」CO2-SUICOM製造過程廃棄物とCO2から生成されたエコタンカル高炉セメントコンクリートの種類とCFT造建設物における適用部位への使用CemR3の製造とエコクリートR3の活用イメージ
07KAJIMA202408特集 CO2で未来をつくる サステナブルコンクリートエコクリート®R3CO2でつくる,これからのコンクリート「CO2-SUICOM」世界初!CO2排出量を実質ゼロ以下へエコクリート®ECM・KKC・BLSCUCO-SUICOM製造過程一般的なコンクリートとCO2-SUICOMのCO2排出量の比較CUCO-SUICOMが目指すCO2削減量の目標値※5コンクリート工事では,注文したコンクリートの1∼2%がやむを得ない理由で使用されず,骨材を回収・再生したのち,残ったセメント分(スラッジ)は産業廃棄物として処分されている※6戻りコンクリートから骨材を除去・脱水・粉砕し,製造される※8鹿島,中国電力,デンカ,ランデスの4社※7鉄鋼製造の副産物で,セメントと同様,水との化学反応によって硬化する性質を持つFile.1セメントを低減するセメントの一部を再生セメントや産業副産物などに置き換えることで,セメントの使用量を減らし,CO2排出量を低減する。File.2File.3CO2を固定するCO2を吸収する廃コンクリートなどにCO2を反応・吸収させて骨材や粉末を製造し,それをコンクリートに材料として練り混ぜることで,CO2を固定する。コンクリート製造時に,大量のCO2を吸収して固まることで,コンクリート製造過程でのCO2排出量をゼロ以下にできる。 戻りコンクリート※5から製造される再生セメント「CemR3※6」を使用したコンクリート。CemR3は,通常のセメントとは異なり,CO2が直接合成される焼成過程を経ず,さらに低温で製造されるため製造時のCO2排出量を約1/8に抑えられる。 「CO2-SUICOM」は,2008年に当社ら※8が開発した,製造過程でCO2を吸収するコンクリート。セメントの半分以上を,産業副産物と,CO2との化学反応によってコンクリートを硬化させる「γガンマシーツ―エス-C2S」に置き換え,さらに炭酸化養生することでCO2を吸収させ,コンクリートに固定する。 CUCO-SUICOMでは,CO2-SUICOMのCO2を吸収する技術をベースに,CemR3やECMなどのセメントを低減する技術や,エコタンカルのようなCO2を固定する技術を組み合わせて,CO2削減量の最大化を図る。 セメントの一部置換えに加え,炭酸化養生によりCO2削減量を増大させることで,一般的なコンクリートと比較し,実質ゼロ以下(=▲18㎏/m3)を実現した。 他のサステナブルコンクリートにはない,CO2を吸収・固定する特長を持ち,現在は,CO2固定量に応じて,カーボンネガティブ型とカーボン低減型の2種類のグレードを展開している。 CO2を固定した炭酸カルシウム「エコタンカル®」は,CO2を固定化した炭酸カルシウムとして現在,唯一市販されているもので,当社と共同研究をしている日本コンクリート工業が開発した。プレキャストコンクリート工場内で発生するカルシウムを含んだ排水と,ボイラーの排ガスに含まれるCO2を反応させることで製造される。 セメントの一部を,微粉末状にした高炉スラグ※7に置き換えたコンクリートで,高炉スラグ微粉末の含有率によって下表のような異なる特長を持つ。セムアールスリー地上構造エコクリート®BLSCO2削減量,最大化へ「CUCO-SUICOM」CO2-SUICOM製造過程廃棄物とCO2から生成されたエコタンカル高炉セメントコンクリートの種類とCFT造建設物における適用部位への使用CemR3の製造とエコクリートR3の活用イメージ
 社員寮「DOMMY南長崎アネックス」(東京都豊島区2022年竣工)では,2種類のセメントを低減するコンクリートを採用。地下構造に「エコクリートECM」を235m3,上部構造に「エコクリートBLS」を1,942m3採用した。これにより,「J-クレジット制度※1」において,181t-CO2のクレジットを取得した。 社有施設「鹿島テクニカルセンター」(横浜市鶴見区2022年竣工)では,エコクリートR3とCO2-SUICOMを採用。 高含有型エコクリートR3※2の生コンクリート(以下,生コン)を外構RC目隠し壁に,低含有型エコクリートR3※3の生コンを基礎躯体に採用した。建設現場で高含有型の現場打ちコンクリートを採用したのは初めてで,28.4tのCO2を削減した。また,CO2-SUICOMは,歩道のインターロッキングブロッ08KAJIMA202408KAJIMA未来へつなげる実適用section.1※1省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2などの排出削減量や,適切な森林管理によるCO2などの吸収量を「クレジット」として国が認証する制度※2CemR3をセメントの一部として50%程度使用し, CO2削減効果の高いもの※3CemR3をセメントの一部として20%程度使用したもの歩道のインターロッキングブロックにCO2-SUICOMを採用photo:エスエス島尾望高含有型のエコクリートR3を採用した外構RC目隠し壁エコクリートECMとエコクリートBLSを採用した社員寮「DOMMY南長崎アネックス」photo:エスエス島尾望当社のサステナブルコンクリートは様々な特長を持ち,建物・ダム・道路・橋など,構造物の用途や部位に応じて,採用するコンクリートや組合せなどを選定することができる。多様な選択肢が実工事適用への幅を広げている。File.1File.2鹿島テクニカルセンター社員寮「DOMMY南長崎アネックス」ク,駐車場の車止め,外構緑地システムDEWレインガーデン®の底板・側板に使用し,2.6tのCO2を削減,これによりトータル 2023年4月,当社技術研究所の西調布実験場内(東京都調布市)に開設された,「KAJIMACONCRETEBASE」。この展示施設では,CO2-SUICOMやセメント系3Dプリンティング(12~13ページ参照)をはじめ,当社のコンクリート技術を実際に,「見て・触れて・深く知る」ことができる。様々な技術の写真や実物の展示に加え,中央に配置されている大きなコンクリートテーブルではサステナブルコンクリートに関する動画が再生されるなど,見学者参加型の施設となっている。 本施設は,オンラインミュージアム※を設けてお「KAJIMACOCRETEBASE」内観。大きな円形のコンクリートテーブルが目を引くKAJIMACONCRETEBASEColumn1※一般の方は,オンラインミュージアムをご利用くださいり,特設サイト「KAJIMACONCRETEBASE」からオンライン見学も可能。当社のサステナブルコンクリートのビジョンムービーも視聴することができる。低減 吸収低減 固定 吸収低減 吸収低減 固定 吸収KAJIMACONCRETEBASEの特設サイトはこちらから。「CUCO」のHPにもアクセスできますで31tのCO2を削減した。施設入口前の歩道には,CO2-SUICOMで作製したブロックを敷設
社員寮「DOMMY南長崎アネックス」(東京都豊島区2022年竣工)では,2種類のセメントを低減するコンクリートを採用。地下構造に「エコクリートECM」を235m3,上部構造に「エコクリートBLS」を1,942m3採用した。これにより,「J-クレジット制度※1」において,181t-CO2のクレジットを取得した。 社有施設「鹿島テクニカルセンター」(横浜市鶴見区2022年竣工)では,エコクリートR3とCO2-SUICOMを採用。 高含有型エコクリートR3※2の生コンクリート(以下,生コン)を外構RC目隠し壁に,低含有型エコクリートR3※3の生コンを基礎躯体に採用した。建設現場で高含有型の現場打ちコンクリートを採用したのは初めてで,28.4tのCO2を削減した。また,CO2-SUICOMは,歩道のインターロッキングブロッ08KAJIMA202408KAJIMA未来へつなげる実適用section.1※1省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2などの排出削減量や,適切な森林管理によるCO2などの吸収量を「クレジット」として国が認証する制度※2CemR3をセメントの一部として50%程度使用し, CO2削減効果の高いもの※3CemR3をセメントの一部として20%程度使用したもの歩道のインターロッキングブロックにCO2-SUICOMを採用photo:エスエス島尾望高含有型のエコクリートR3を採用した外構RC目隠し壁エコクリートECMとエコクリートBLSを採用した社員寮「DOMMY南長崎アネックス」photo:エスエス島尾望当社のサステナブルコンクリートは様々な特長を持ち,建物・ダム・道路・橋など,構造物の用途や部位に応じて,採用するコンクリートや組合せなどを選定することができる。多様な選択肢が実工事適用への幅を広げている。File.1File.2鹿島テクニカルセンター社員寮「DOMMY南長崎アネックス」ク,駐車場の車止め,外構緑地システムDEWレインガーデン®の底板・側板に使用し,2.6tのCO2を削減,これによりトータル 2023年4月,当社技術研究所の西調布実験場内(東京都調布市)に開設された,「KAJIMACONCRETEBASE」。この展示施設では,CO2-SUICOMやセメント系3Dプリンティング(12~13ページ参照)をはじめ,当社のコンクリート技術を実際に,「見て・触れて・深く知る」ことができる。様々な技術の写真や実物の展示に加え,中央に配置されている大きなコンクリートテーブルではサステナブルコンクリートに関する動画が再生されるなど,見学者参加型の施設となっている。 本施設は,オンラインミュージアム※を設けてお「KAJIMACOCRETEBASE」内観。大きな円形のコンクリートテーブルが目を引くKAJIMACONCRETEBASEColumn1※一般の方は,オンラインミュージアムをご利用くださいり,特設サイト「KAJIMACONCRETEBASE」からオンライン見学も可能。当社のサステナブルコンクリートのビジョンムービーも視聴することができる。低減 吸収低減 固定 吸収低減 吸収低減 固定 吸収KAJIMACONCRETEBASEの特設サイトはこちらから。「CUCO」のHPにもアクセスできますで31tのCO2を削減した。施設入口前の歩道には,CO2-SUICOMで作製したブロックを敷設
 来年開幕する大阪・関西万博会場へのアクセスルートとなる海老江工区開削トンネル工事(大阪市福島区2025年3月竣工予定)では,海老江ジャンクション区間の橋梁下部工において,CO2-SUICOMを用いた埋設型枠を高速道路の橋脚工事に 当社は5月に,CO2-SUICOMの普及,展開を加速するため,2種類のグレードを設定した。コンクリート1m3あたりのCO2吸収・固定量が100kg以上となる従来の「CO2-SUICOM(P)PLEMIUM」に加え,100㎏未満となるものを「CO2-SUICOM(E)ECONOMY」とし,(E)タイプを用いた大型PCaコンクリート製品であるブロック擁壁を開発した。従来の(P)タイプでは舗装用PCaコンクリート製品などの小型ブロック製品を デザインオフィスnendo代表の佐藤オオキ氏デザインによる個人住宅(長野県軽井沢町2023年竣工)のブロック塀にCO2-SUICOMを採用。特徴的な敷地形状と目の前の道路からの視線を遮り,緑豊かな周辺環境を楽しむため,フィルターのような役割を持つグラデーション状のブロックデザインとし,高さ3mの塀を5列配置した。使用し09KAJIMA202408特集 CO2で未来をつくる サステナブルコンクリートFile.3File.4File.5海老江工区開削トンネル大型ブロック擁壁塀の家 当社は川崎重工業と,同社が保有する「DAC※」をCO2-SUICOMの製造に利用するための共同研究を開始した。 DACは,CO2の吸収に最適な多孔質材料とアミン化合物から成る固体吸収材によって,大気中のCO2を分離・回収することができる。 現在,CO2-SUICOM製造時における炭酸化養生で必要となるCO2は外部から購入しているが,川崎重工業が保有する最先端のDAC技術と組み合わせることでCO2を回収・利用することが可能となれば,必要な時に必要な場所でCO2を調達でき,カーボンDACで使用する固体吸収材のイメージCO2-SUICOM炭酸化養生槽川崎重工業との共同研究—CO2-SUICOM×DAC—Column2※DirectAirCapture大気中のCO2を直接回収する技術ニュートラル社会の実現に,大きく寄与することが期待される。初めて導入。埋設型枠で通常排出されるCO2は207㎏/m3であるのに対しCO2-SUICOMは229㎏/m3のCO2を吸収する。実質排出量は▲22㎏/m3となり,橋脚1基あたり59㎏のCO2を世の中から減らすことができた。展開してきたが,(E)タイプが新たに加わり,製品種類の拡充やインフラ建設市場に,より広く展開が可能となった。 また,CO2-SUICOM製造時の炭酸化養生でpHが中性域になることによる鉄筋腐食を考慮し,従来は無筋ブロックを展開していたが,用心鉄筋※4を有機系繊維の配合で代替したことで,現行の製品と比較し,1個あたり約72kgのCO2を削減した。CO2-SUICOM埋設型枠を採用した橋脚「塀の家」外観CO2-SUICOMを採用した大型ブロック擁壁CO2-SUICOMを採用したブロック塀「塀の家」内観※4ひび割れや破損を防ぐことを目的とした鉄筋低減 吸収低減 固定 吸収低減 吸収低減 固定 吸収低減 吸収低減 固定 吸収たブロックは約2,050個に及んだ。CO2-SUICOM埋設型枠123photo:1,2,3takumiota/masahiroohgami
来年開幕する大阪・関西万博会場へのアクセスルートとなる海老江工区開削トンネル工事(大阪市福島区2025年3月竣工予定)では,海老江ジャンクション区間の橋梁下部工において,CO2-SUICOMを用いた埋設型枠を高速道路の橋脚工事に 当社は5月に,CO2-SUICOMの普及,展開を加速するため,2種類のグレードを設定した。コンクリート1m3あたりのCO2吸収・固定量が100kg以上となる従来の「CO2-SUICOM(P)PLEMIUM」に加え,100㎏未満となるものを「CO2-SUICOM(E)ECONOMY」とし,(E)タイプを用いた大型PCaコンクリート製品であるブロック擁壁を開発した。従来の(P)タイプでは舗装用PCaコンクリート製品などの小型ブロック製品を デザインオフィスnendo代表の佐藤オオキ氏デザインによる個人住宅(長野県軽井沢町2023年竣工)のブロック塀にCO2-SUICOMを採用。特徴的な敷地形状と目の前の道路からの視線を遮り,緑豊かな周辺環境を楽しむため,フィルターのような役割を持つグラデーション状のブロックデザインとし,高さ3mの塀を5列配置した。使用し09KAJIMA202408特集 CO2で未来をつくる サステナブルコンクリートFile.3File.4File.5海老江工区開削トンネル大型ブロック擁壁塀の家 当社は川崎重工業と,同社が保有する「DAC※」をCO2-SUICOMの製造に利用するための共同研究を開始した。 DACは,CO2の吸収に最適な多孔質材料とアミン化合物から成る固体吸収材によって,大気中のCO2を分離・回収することができる。 現在,CO2-SUICOM製造時における炭酸化養生で必要となるCO2は外部から購入しているが,川崎重工業が保有する最先端のDAC技術と組み合わせることでCO2を回収・利用することが可能となれば,必要な時に必要な場所でCO2を調達でき,カーボンDACで使用する固体吸収材のイメージCO2-SUICOM炭酸化養生槽川崎重工業との共同研究—CO2-SUICOM×DAC—Column2※DirectAirCapture大気中のCO2を直接回収する技術ニュートラル社会の実現に,大きく寄与することが期待される。初めて導入。埋設型枠で通常排出されるCO2は207㎏/m3であるのに対しCO2-SUICOMは229㎏/m3のCO2を吸収する。実質排出量は▲22㎏/m3となり,橋脚1基あたり59㎏のCO2を世の中から減らすことができた。展開してきたが,(E)タイプが新たに加わり,製品種類の拡充やインフラ建設市場に,より広く展開が可能となった。 また,CO2-SUICOM製造時の炭酸化養生でpHが中性域になることによる鉄筋腐食を考慮し,従来は無筋ブロックを展開していたが,用心鉄筋※4を有機系繊維の配合で代替したことで,現行の製品と比較し,1個あたり約72kgのCO2を削減した。CO2-SUICOM埋設型枠を採用した橋脚「塀の家」外観CO2-SUICOMを採用した大型ブロック擁壁CO2-SUICOMを採用したブロック塀「塀の家」内観※4ひび割れや破損を防ぐことを目的とした鉄筋低減 吸収低減 固定 吸収低減 吸収低減 固定 吸収低減 吸収低減 固定 吸収たブロックは約2,050個に及んだ。CO2-SUICOM埋設型枠123photo:1,2,3takumiota/masahiroohgami
 10KAJIMA202408未来へつなげる実適用section.2CO2削減量の最大化と同時に,社会実装を目指すCUCO-SUICOM。土木から建築まで,その実適用は着々と進められ,CUCO-SUICOMドームでのRC造建築物への採用など,さらなる汎用性を追求し続けている。 4月に完成式が行われた新日下川放水路(高知県高岡郡日高村2023年竣工)のうち,当社はトンネル部分を施工し,「CUCO-SUICOM型枠」を埋設型枠として採用。本型枠は,建設現場に初適用したCUCOの技術開発成果の第一弾となった。 セメントの半分以上を高炉スラグ微粉末とγ-C2Sに置き換え,炭酸化養生によりCO2を吸収・固定化させる。さらにエコタンカルを組み合わせることで合計677kg/m3のCO2を削減した。従来の高強度パネル 静岡県熱海市の沿岸,道路全長6.1kmの熱海ビーチライン※1に今年から消波ブロック「CUCO-SUICOMテトラポッド※2」が設置されている。 当社とCUCOの参画メンバーであるゼネコンの不動テトラは,カーボンネガティブコンクリートを市中のレディーミクストコンクリート工場で製造,アジテータ車で運搬し,打設・脱型に加え,炭酸化養生を行う,完成までの全工程を現場で実施した。これまで炭酸化養生を行うコンクリートはPCaコンクリート工場で製造,出荷されていたが,全工程を現地で行ったのはこれが初めてとなる。 CUCO-SUICOMテトラポッドは,新日下川放水路管理道のCUCO-SUICOM型枠で得た知見をもとに発展させ,製造時にエコタンカルを大量に配合,炭酸化養生を行うことで,断面の大きい部材としては初めて,CUCO-SUICOM型枠の適用箇所(完成時)熱海ビーチラインCUCO-SUICOM型枠の適用箇所(施工時)File.1File.2新日下川放水路管理道熱海ビーチライン(615kg/m3のCO2排出)と比較し,実質排出量▲62kg/m3のカーボンネガティブを▲12%のカーボンネガティブを達成した。また,炭酸化養生によりコンクリートの表面が低アルカリ化することで,環境保全にも適したものになっている。低減 吸収低減 固定 吸収低減 吸収低減 固定 吸収達成した。(25ページに関連記事掲載)※12021年にグループ会社の鹿島道路と道路の維持補修や環境配慮技術の社会実証・実装を目的に設立した熱海インフラマネジメント合同会社が事業運営している※2「テトラポッド」は不動テトラの登録商標CUCO-SUICOMテトラポッド
10KAJIMA202408未来へつなげる実適用section.2CO2削減量の最大化と同時に,社会実装を目指すCUCO-SUICOM。土木から建築まで,その実適用は着々と進められ,CUCO-SUICOMドームでのRC造建築物への採用など,さらなる汎用性を追求し続けている。 4月に完成式が行われた新日下川放水路(高知県高岡郡日高村2023年竣工)のうち,当社はトンネル部分を施工し,「CUCO-SUICOM型枠」を埋設型枠として採用。本型枠は,建設現場に初適用したCUCOの技術開発成果の第一弾となった。 セメントの半分以上を高炉スラグ微粉末とγ-C2Sに置き換え,炭酸化養生によりCO2を吸収・固定化させる。さらにエコタンカルを組み合わせることで合計677kg/m3のCO2を削減した。従来の高強度パネル 静岡県熱海市の沿岸,道路全長6.1kmの熱海ビーチライン※1に今年から消波ブロック「CUCO-SUICOMテトラポッド※2」が設置されている。 当社とCUCOの参画メンバーであるゼネコンの不動テトラは,カーボンネガティブコンクリートを市中のレディーミクストコンクリート工場で製造,アジテータ車で運搬し,打設・脱型に加え,炭酸化養生を行う,完成までの全工程を現場で実施した。これまで炭酸化養生を行うコンクリートはPCaコンクリート工場で製造,出荷されていたが,全工程を現地で行ったのはこれが初めてとなる。 CUCO-SUICOMテトラポッドは,新日下川放水路管理道のCUCO-SUICOM型枠で得た知見をもとに発展させ,製造時にエコタンカルを大量に配合,炭酸化養生を行うことで,断面の大きい部材としては初めて,CUCO-SUICOM型枠の適用箇所(完成時)熱海ビーチラインCUCO-SUICOM型枠の適用箇所(施工時)File.1File.2新日下川放水路管理道熱海ビーチライン(615kg/m3のCO2排出)と比較し,実質排出量▲62kg/m3のカーボンネガティブを▲12%のカーボンネガティブを達成した。また,炭酸化養生によりコンクリートの表面が低アルカリ化することで,環境保全にも適したものになっている。低減 吸収低減 固定 吸収低減 吸収低減 固定 吸収達成した。(25ページに関連記事掲載)※12021年にグループ会社の鹿島道路と道路の維持補修や環境配慮技術の社会実証・実装を目的に設立した熱海インフラマネジメント合同会社が事業運営している※2「テトラポッド」は不動テトラの登録商標CUCO-SUICOMテトラポッド
 11KAJIMA202408特集 CO2で未来をつくる サステナブルコンクリート 2025年,日本国際博覧会(以下,大阪・関西万博)の開催が予定されている。当社は,大阪・関西万博のコンセプトである「People’sLivingLab(未来社会の実験場)」に基づき,短工期,低コストで大空間を構築する「KTドーム®」工法の技術とCO2を大量に低減するサステナブルコンクリートの2つの技術を組み合わせた「CUCO-SUICOMドーム」を建設する。ドームの大きさは,高さ5.45m,直径23m×18m,延べ面積263m2の楕円形となる。 使用するサステナブルコンクリートは2種大阪・関西万博でのCUCO-SUICOMドーム施工状況。PVC膜膨張完了(6月撮影)大阪・関西万博でのCUCO-SUICOMドームイメージパース炭酸化養生の仕組み。ドーム躯体を構築した後,内部に本体より若干小型のドーム(内膜)を膨らませ,本体と内膜の隙間のみにCO2を充填。これにより,CO2の使用量と充填に必要なエネルギーを減らすことが可能となるFile.3大阪・関西万博低減 吸収低減 固定 吸収CUCO-SUICOM型枠の適用箇所類。1つ目は「エコクリートECM」で,ドーム躯体の主要箇所に用いる。膨張したドーム内部に断熱材などを施工した後に鉄筋を配置し,その上から吹き付ける。2つ目は,「CUCO-SUICOMショット」で,ドーム躯体の一部,エコクリートECMを覆うように吹き付ける。両者とも当社が保有する知見とノウハウをもとに材料と調合を工夫し,当ドーム全体で70%(約18t)のCO2が削減可能となった。 両コンクリートの吹き付けによるドーム建設およびCUCO-SUICOMショットを鉄筋コンクリートとして建築構造躯体へ適用した世界で初めての試みとなる。 CUCO-SUICOMドームで採用している「KTドーム」工法は,米国ドーム・テクノロジーとの技術提携で開発した工法で,工場製作したドーム型のPVC膜に空気を送り込んで膨らませ,これを型枠として内側からコンクリートを吹き付け,躯体を構築していく。 PVC膜膨張後に内側から躯体工事を行うため,天候の影響を受けにくく,工期短縮や建設コストの低減が可能となる。ドーム内側に吹き付けた断熱材が外部の熱を効果的に遮断し,一年を通じて安定した室内温度を保持するなどの特長も持つ。「KTドーム」工法Tips 当社の自動化施工システム「Aクワッドアクセル4CSEL®」の技術開発を目的とした社有施設西湘実験フィールド(神奈川県小田原市2020年竣工)に,本工法によるドーム型事務所棟を建設した。現在では,A4CSELの遠隔管制室をドーム内に設置し,ITパイロットたちが,約400km離れた成瀬ダム(秋田県雄勝郡東成瀬村)の工事現場へ作業指示を行っている。 また,トクヤマ南陽工場(山口県周南市)に,1万t貯蔵サイロを建設した(2022年竣工)。西湘実験フィールドのKTドームphoto:daiciano
11KAJIMA202408特集 CO2で未来をつくる サステナブルコンクリート 2025年,日本国際博覧会(以下,大阪・関西万博)の開催が予定されている。当社は,大阪・関西万博のコンセプトである「People’sLivingLab(未来社会の実験場)」に基づき,短工期,低コストで大空間を構築する「KTドーム®」工法の技術とCO2を大量に低減するサステナブルコンクリートの2つの技術を組み合わせた「CUCO-SUICOMドーム」を建設する。ドームの大きさは,高さ5.45m,直径23m×18m,延べ面積263m2の楕円形となる。 使用するサステナブルコンクリートは2種大阪・関西万博でのCUCO-SUICOMドーム施工状況。PVC膜膨張完了(6月撮影)大阪・関西万博でのCUCO-SUICOMドームイメージパース炭酸化養生の仕組み。ドーム躯体を構築した後,内部に本体より若干小型のドーム(内膜)を膨らませ,本体と内膜の隙間のみにCO2を充填。これにより,CO2の使用量と充填に必要なエネルギーを減らすことが可能となるFile.3大阪・関西万博低減 吸収低減 固定 吸収CUCO-SUICOM型枠の適用箇所類。1つ目は「エコクリートECM」で,ドーム躯体の主要箇所に用いる。膨張したドーム内部に断熱材などを施工した後に鉄筋を配置し,その上から吹き付ける。2つ目は,「CUCO-SUICOMショット」で,ドーム躯体の一部,エコクリートECMを覆うように吹き付ける。両者とも当社が保有する知見とノウハウをもとに材料と調合を工夫し,当ドーム全体で70%(約18t)のCO2が削減可能となった。 両コンクリートの吹き付けによるドーム建設およびCUCO-SUICOMショットを鉄筋コンクリートとして建築構造躯体へ適用した世界で初めての試みとなる。 CUCO-SUICOMドームで採用している「KTドーム」工法は,米国ドーム・テクノロジーとの技術提携で開発した工法で,工場製作したドーム型のPVC膜に空気を送り込んで膨らませ,これを型枠として内側からコンクリートを吹き付け,躯体を構築していく。 PVC膜膨張後に内側から躯体工事を行うため,天候の影響を受けにくく,工期短縮や建設コストの低減が可能となる。ドーム内側に吹き付けた断熱材が外部の熱を効果的に遮断し,一年を通じて安定した室内温度を保持するなどの特長も持つ。「KTドーム」工法Tips 当社の自動化施工システム「Aクワッドアクセル4CSEL®」の技術開発を目的とした社有施設西湘実験フィールド(神奈川県小田原市2020年竣工)に,本工法によるドーム型事務所棟を建設した。現在では,A4CSELの遠隔管制室をドーム内に設置し,ITパイロットたちが,約400km離れた成瀬ダム(秋田県雄勝郡東成瀬村)の工事現場へ作業指示を行っている。 また,トクヤマ南陽工場(山口県周南市)に,1万t貯蔵サイロを建設した(2022年竣工)。西湘実験フィールドのKTドームphoto:daiciano
 12KAJIMA202408世代・学科・職種を横断した産学によるプロジェクト 3Dプリンターの研究に力を入れる金沢工業大学(以下,金工大)と,建設業のDXを推進する当社は,セメント系3Dプリンターを使った共同研究を開始し,2022年にラボを設立,プロジェクトが始動した。「社会課題の解決」を目的に,金沢市の協力を得て産官学一体で研究から社会実装までを目指したこのプロジェクトは,土木・建築・機械・ロボティクス・応用化学・心理・メディア情報・電気・数学など幅広い学科を代表する教員・学生と,当社の技術者が集まる,世代・学科・職種を横断した取組みだ。 ラボの所長を務める工学部環境土木工学科の宮里心一教授は,「研究題材,材CO2-SUICOMでつくる3Dプリンティングベンチ鹿島×金沢工業大学未来をつくる共同研究今年3月,石川県金沢市内の公園に,特徴的なデザインのベンチが設置された。建設分野向けのセメント系3Dプリンターで製作したCO2-SUICOMベンチ。金沢城と尾山神社の間に位置するこの公園に調和するデザインだ。本取組みは,金沢工業大学と当社の共同研究開発拠点「KIT×KAJIMA3DPrintingLab(以下,ラボ)」による研究成果の第一弾となった。全長4mのロボットアーム式3Dプリンター。ロボットアームの先端からセメント材料を吐出し,それを積層していくことで構造物を製作する公園に設置されたベンチ。座面は金沢の伝統工芸品「加賀友禅」の工程である友禅流しをモチーフにしている料,製作物など,プラン全体を構想するところから始まりました。ここまで幅広く学科を横断したプロジェクトは前代未聞。そうした状況の中で産官学一体で取組むことを軸とした,CO2-SUICOMで製作したベンチは,このラボだからこそ実現できた」と語る。 金沢工業大学と当社は,建設業におけるDXと脱炭素に向けた最新の取組みについて学ぶことのできる「KITコーオプ教育プログラム」を2022年度から開始している。当プログラムでは,企業の第一線で活躍する技術者を「実務家教員」として招き,寄付講座を開講して最先端の技術を実践的に学ぶ。また,受講者の中から選抜された数名の学生が,当社技術研究所や機械部にて約4ヵ月間勤務し,実務を経験する取組みであるコーオプ教育も行っている。KITコーオプ教育プログラムColumn 2024年度は,7人の当社社員が講師となって,それぞれの専門領域の最新技術について講義を行っている。坂井主席研究員は主任教員として,当社のサステナブルコンクリートについて講義を行った。 また,浦上研究員は,金工大在籍時に当プログラムを受講したうちの一人。プログラム内で初めて3Dプリンターに触れたことをきっかけにラボに参加した。大学内の講義では学ぶ機会が少ない社会実装の重要性を,当プログラムとラボを通して学んだ。炭酸化養生槽を前に,坂井主席研究員から講義を受ける受講生photo:teruhikoirie
12KAJIMA202408世代・学科・職種を横断した産学によるプロジェクト 3Dプリンターの研究に力を入れる金沢工業大学(以下,金工大)と,建設業のDXを推進する当社は,セメント系3Dプリンターを使った共同研究を開始し,2022年にラボを設立,プロジェクトが始動した。「社会課題の解決」を目的に,金沢市の協力を得て産官学一体で研究から社会実装までを目指したこのプロジェクトは,土木・建築・機械・ロボティクス・応用化学・心理・メディア情報・電気・数学など幅広い学科を代表する教員・学生と,当社の技術者が集まる,世代・学科・職種を横断した取組みだ。 ラボの所長を務める工学部環境土木工学科の宮里心一教授は,「研究題材,材CO2-SUICOMでつくる3Dプリンティングベンチ鹿島×金沢工業大学未来をつくる共同研究今年3月,石川県金沢市内の公園に,特徴的なデザインのベンチが設置された。建設分野向けのセメント系3Dプリンターで製作したCO2-SUICOMベンチ。金沢城と尾山神社の間に位置するこの公園に調和するデザインだ。本取組みは,金沢工業大学と当社の共同研究開発拠点「KIT×KAJIMA3DPrintingLab(以下,ラボ)」による研究成果の第一弾となった。全長4mのロボットアーム式3Dプリンター。ロボットアームの先端からセメント材料を吐出し,それを積層していくことで構造物を製作する公園に設置されたベンチ。座面は金沢の伝統工芸品「加賀友禅」の工程である友禅流しをモチーフにしている料,製作物など,プラン全体を構想するところから始まりました。ここまで幅広く学科を横断したプロジェクトは前代未聞。そうした状況の中で産官学一体で取組むことを軸とした,CO2-SUICOMで製作したベンチは,このラボだからこそ実現できた」と語る。 金沢工業大学と当社は,建設業におけるDXと脱炭素に向けた最新の取組みについて学ぶことのできる「KITコーオプ教育プログラム」を2022年度から開始している。当プログラムでは,企業の第一線で活躍する技術者を「実務家教員」として招き,寄付講座を開講して最先端の技術を実践的に学ぶ。また,受講者の中から選抜された数名の学生が,当社技術研究所や機械部にて約4ヵ月間勤務し,実務を経験する取組みであるコーオプ教育も行っている。KITコーオプ教育プログラムColumn 2024年度は,7人の当社社員が講師となって,それぞれの専門領域の最新技術について講義を行っている。坂井主席研究員は主任教員として,当社のサステナブルコンクリートについて講義を行った。 また,浦上研究員は,金工大在籍時に当プログラムを受講したうちの一人。プログラム内で初めて3Dプリンターに触れたことをきっかけにラボに参加した。大学内の講義では学ぶ機会が少ない社会実装の重要性を,当プログラムとラボを通して学んだ。炭酸化養生槽を前に,坂井主席研究員から講義を受ける受講生photo:teruhikoirie
 13KAJIMA202408特集 CO2で未来をつくる サステナブルコンクリートCO2の吸収効率を最大限引き出すデザイン セメント系3Dプリンターは型枠無しで複雑な形状の造形物を製作できるという特長がある。一方で,材料が柔らかすぎると崩れて形状が保てず,硬すぎると積層した材料が一体化できないという難しさがある。また,CO2-SUICOMは,部材の表面からCO2を吸収して固まる。形状を保ちつつ,CO2との接触面積を増やすため,材料の調合や3Dプリンターの動作,意匠・構造など,最適解を求め何度も検証を重ねた。その結果,学生主体でベンチ脚部をヒダ形状にするデザインへたどり着いた。一般的な隙間がない脚部と比較し,表面積を1.7倍に増大,CO2吸収割合が2倍以上に向上したことで,CO2排出量▲9.7㎏/m3を達成した。主体性と学生のバイタリティが開発スピードを加速 様々な観点からの課題解決と試行錯誤を重ね,全長5m×幅0.7mのベンチが完成,今年3月に公園への設置が完了した。 金工大在籍時にラボに参加し,現在は当社の技術研究所に新入社員として配属になった浦上和也研究員は,ラボでの活動を通じ,課題への解決策として物事を異なる視点から見ることの大切さを学んだという。「積層の際,環境土木工学科の学生は材料の品質に注目し,機械工学科の学生は機械の制御に注目していました。各々に役割がありましたが,課題解決には双方向からのアプローチが必要だった」と,経験を通してさらに勉強する意欲が掻き立てられたと話す。 また,プロジェクト始動からわずか2年足らずで社会実装まで完遂したこのスピード感に,当社側の開発実務の責任者である技術研究所の坂井吾郎主席研究員は,次のように述べる。「当初,3Dプリンターで線を引けるようになるまで1年はかかるのではと考えていました。それが,2年も待たずにベンチ完成までたどり着きました。参加者全員が主体性を持って取り組んだこと,自分の担当分野で他の担当者を待たせないようにする意識の高さや,学生さんたちのトライアンドエラーを恐れず諦めない姿勢,バイタリティがこのスピード感を生み出したと肌で感じました。『考えすぎず,とにかくやってみよう!』という精神に,技術者として良い刺激をもらいました」。多角的な知見と専門性の一体化で可能性を広げる プロジェクトメンバーの多角的な知見や専門性,世代を超えた構成メンバーが,多岐にわたる検討を可能にした。 現在,本校4年生で建築学部建築学科に在籍し,ラボのメンバーでもある鍋嶋宏誓さんは,「活動の一環である意匠・構造ワーキングでは,他の学科の人と様々な意見交換が行われ,現在,別の対象物のデザインを検討しています。自分たちの研究開発した製作物が学内で終わらずに,学外の一般の人たちの目に映る機会があるのは,とてもやりがいを感じます」と研究への思いを語る。 「『社会の役に立つにはどうしたらいいの参画メンバー。宮里教授(中央左),坂井主席研究員(中央右),浦上研究員(右),鍋島さん(左)か』。この価値観を全員が共有し,尊重しあって研究に取り組んだことが,この成果に結びつきました。本校と鹿島建設さんの持つ文化や考え方が近いからこそ,このスピード感で実装までたどり着いたと実感しています。人,技術など色々な側面からも,3Dプリンター×CO2-SUICOMの掛け合わせは,両者の強みを活かしたベストマッチングでしたね。今後も技術をアップデートし,挑戦していきたいです」(宮里教授)。 当社はサステナブルコンクリートについて,金沢工業大学をはじめ,東洋大学との共同研究や,東北大学とのCO2排出量低減を実現する建設材料の研究開発など,サステナブルな社会を目指し,大学との共同研究を活発化していく。ベンチ脚部のデザイン検討状況炭酸化養生装置は,長さ6m×幅2.4mの密閉式。養生槽内部の温度・湿度・CO2濃度を適切に管理することで,部材内にCO2を効率的に吸収させるベンチ脚部の造形の違いによる表面積とCO2吸収割合の比較ヒダ形状に積層された脚部photo:teruhikoiriephoto:teruhikoirie
13KAJIMA202408特集 CO2で未来をつくる サステナブルコンクリートCO2の吸収効率を最大限引き出すデザイン セメント系3Dプリンターは型枠無しで複雑な形状の造形物を製作できるという特長がある。一方で,材料が柔らかすぎると崩れて形状が保てず,硬すぎると積層した材料が一体化できないという難しさがある。また,CO2-SUICOMは,部材の表面からCO2を吸収して固まる。形状を保ちつつ,CO2との接触面積を増やすため,材料の調合や3Dプリンターの動作,意匠・構造など,最適解を求め何度も検証を重ねた。その結果,学生主体でベンチ脚部をヒダ形状にするデザインへたどり着いた。一般的な隙間がない脚部と比較し,表面積を1.7倍に増大,CO2吸収割合が2倍以上に向上したことで,CO2排出量▲9.7㎏/m3を達成した。主体性と学生のバイタリティが開発スピードを加速 様々な観点からの課題解決と試行錯誤を重ね,全長5m×幅0.7mのベンチが完成,今年3月に公園への設置が完了した。 金工大在籍時にラボに参加し,現在は当社の技術研究所に新入社員として配属になった浦上和也研究員は,ラボでの活動を通じ,課題への解決策として物事を異なる視点から見ることの大切さを学んだという。「積層の際,環境土木工学科の学生は材料の品質に注目し,機械工学科の学生は機械の制御に注目していました。各々に役割がありましたが,課題解決には双方向からのアプローチが必要だった」と,経験を通してさらに勉強する意欲が掻き立てられたと話す。 また,プロジェクト始動からわずか2年足らずで社会実装まで完遂したこのスピード感に,当社側の開発実務の責任者である技術研究所の坂井吾郎主席研究員は,次のように述べる。「当初,3Dプリンターで線を引けるようになるまで1年はかかるのではと考えていました。それが,2年も待たずにベンチ完成までたどり着きました。参加者全員が主体性を持って取り組んだこと,自分の担当分野で他の担当者を待たせないようにする意識の高さや,学生さんたちのトライアンドエラーを恐れず諦めない姿勢,バイタリティがこのスピード感を生み出したと肌で感じました。『考えすぎず,とにかくやってみよう!』という精神に,技術者として良い刺激をもらいました」。多角的な知見と専門性の一体化で可能性を広げる プロジェクトメンバーの多角的な知見や専門性,世代を超えた構成メンバーが,多岐にわたる検討を可能にした。 現在,本校4年生で建築学部建築学科に在籍し,ラボのメンバーでもある鍋嶋宏誓さんは,「活動の一環である意匠・構造ワーキングでは,他の学科の人と様々な意見交換が行われ,現在,別の対象物のデザインを検討しています。自分たちの研究開発した製作物が学内で終わらずに,学外の一般の人たちの目に映る機会があるのは,とてもやりがいを感じます」と研究への思いを語る。 「『社会の役に立つにはどうしたらいいの参画メンバー。宮里教授(中央左),坂井主席研究員(中央右),浦上研究員(右),鍋島さん(左)か』。この価値観を全員が共有し,尊重しあって研究に取り組んだことが,この成果に結びつきました。本校と鹿島建設さんの持つ文化や考え方が近いからこそ,このスピード感で実装までたどり着いたと実感しています。人,技術など色々な側面からも,3Dプリンター×CO2-SUICOMの掛け合わせは,両者の強みを活かしたベストマッチングでしたね。今後も技術をアップデートし,挑戦していきたいです」(宮里教授)。 当社はサステナブルコンクリートについて,金沢工業大学をはじめ,東洋大学との共同研究や,東北大学とのCO2排出量低減を実現する建設材料の研究開発など,サステナブルな社会を目指し,大学との共同研究を活発化していく。ベンチ脚部のデザイン検討状況炭酸化養生装置は,長さ6m×幅2.4mの密閉式。養生槽内部の温度・湿度・CO2濃度を適切に管理することで,部材内にCO2を効率的に吸収させるベンチ脚部の造形の違いによる表面積とCO2吸収割合の比較ヒダ形状に積層された脚部photo:teruhikoiriephoto:teruhikoirie