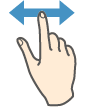モンジュイックの丘は,バルセロナにおいて特別な場所である。近代以前には要塞が築かれた場所であり,20世紀に入ると,1929年の万博と1992年のオリンピックという国際的なイベントが開催された。またフランコの独裁時代には,政治犯が処刑されたり,牢獄が設置されている。そうした暗い記憶を払拭したのが,おそらくバルセロナ・オリンピックであり,その施設として建てられたのが,磯崎新によるパラウ・サン・ジョルディ(1990年)だった。万博は都市開発とセットになるが,このエリアもレガシーが数多く残り,文化や運動施設が集中している。例えば,旧政府館はカタロニア美術館としてリノベーションされたほか,万博時に集めたコレクションをもとに設立された考古学博物館や民族学博物館,スペイン村,改造してオリンピックで再利用した競技場,そして再現されたミース・ファン・デル・ローエの傑作バルセロナ・パビリオンなどだ。小高い丘だが,随所に屋外エスカレーターが設けられ,思いのほか楽に上ることができる。さて,国際招待コンペ案で選ばれた磯崎の当初案は,放物線のアーチによって屋根を吊る構造を計画していた。空中に架けられた2つのアーチのかたちには,ガウディも用いたカタロニア・ヴォールトを採用し,祝祭的な雰囲気を意識したという。だが,工期やコスト,合理性,安全性などを考慮して,構造家の川口衞まもるが考案したパンタ・ドーム構法を採用し,それが特徴的な屋根の輪郭を形成した。すなわち,地表近くで折りたたんだ状態でスペース・フレームを組み立てた後,垂直にリフトアップし,最終的な屋根のかたちに変形させているのだ。興味深いのは,このプロセスそのものがスペクタクルとなり,新聞などで連日報道され,しばしば一面に掲載されたという。バルセロナの市民は,建設途中の印象的な姿を目撃する祭礼的なイベントを通じて,自分たちの街の建築だと受け入れた。竣工後の一般公開では,三日間で約30万人が来場し,単純計算すると,市民の6分の1が訪れたことになるという。まさに建築の誕生が祝福されたのである。その結果,磯崎はスペインで有名になった。実際,筆者が関わったTOTOギャラリー・間(東京都港区)の磯崎展「アンビルトUNBUILT/反建築史」(2001年)でも,わざわざスペインからメディアが取材に来ていたことで,その人気を実感した。ちなみに,屋根は新しい実験的な構法だが,基壇において反復する矩形のフレームは,クラシックなテイストであり,磯崎らしいデザインだろう。ところで,隣の絶妙なバランスでたつ白い塔,モンジュイック・タワーはサンティアゴ・カラトラバが設計したものだ。ここではスポーツだけではなく,建築家の競演を楽しむこともできる。第5回 祭典と日常のあいだ写真 ― 鈴木久雄文 ― 五十嵐太郎14KAJIMA202408
モンジュイックの丘は,バルセロナにおいて特別な場所である。近代以前には要塞が築かれた場所であり,20世紀に入ると,1929年の万博と1992年のオリンピックという国際的なイベントが開催された。またフランコの独裁時代には,政治犯が処刑されたり,牢獄が設置されている。そうした暗い記憶を払拭したのが,おそらくバルセロナ・オリンピックであり,その施設として建てられたのが,磯崎新によるパラウ・サン・ジョルディ(1990年)だった。万博は都市開発とセットになるが,このエリアもレガシーが数多く残り,文化や運動施設が集中している。例えば,旧政府館はカタロニア美術館としてリノベーションされたほか,万博時に集めたコレクションをもとに設立された考古学博物館や民族学博物館,スペイン村,改造してオリンピックで再利用した競技場,そして再現されたミース・ファン・デル・ローエの傑作バルセロナ・パビリオンなどだ。小高い丘だが,随所に屋外エスカレーターが設けられ,思いのほか楽に上ることができる。さて,国際招待コンペ案で選ばれた磯崎の当初案は,放物線のアーチによって屋根を吊る構造を計画していた。空中に架けられた2つのアーチのかたちには,ガウディも用いたカタロニア・ヴォールトを採用し,祝祭的な雰囲気を意識したという。だが,工期やコスト,合理性,安全性などを考慮して,構造家の川口衞まもるが考案したパンタ・ドーム構法を採用し,それが特徴的な屋根の輪郭を形成した。すなわち,地表近くで折りたたんだ状態でスペース・フレームを組み立てた後,垂直にリフトアップし,最終的な屋根のかたちに変形させているのだ。興味深いのは,このプロセスそのものがスペクタクルとなり,新聞などで連日報道され,しばしば一面に掲載されたという。バルセロナの市民は,建設途中の印象的な姿を目撃する祭礼的なイベントを通じて,自分たちの街の建築だと受け入れた。竣工後の一般公開では,三日間で約30万人が来場し,単純計算すると,市民の6分の1が訪れたことになるという。まさに建築の誕生が祝福されたのである。その結果,磯崎はスペインで有名になった。実際,筆者が関わったTOTOギャラリー・間(東京都港区)の磯崎展「アンビルトUNBUILT/反建築史」(2001年)でも,わざわざスペインからメディアが取材に来ていたことで,その人気を実感した。ちなみに,屋根は新しい実験的な構法だが,基壇において反復する矩形のフレームは,クラシックなテイストであり,磯崎らしいデザインだろう。ところで,隣の絶妙なバランスでたつ白い塔,モンジュイック・タワーはサンティアゴ・カラトラバが設計したものだ。ここではスポーツだけではなく,建築家の競演を楽しむこともできる。第5回 祭典と日常のあいだ写真 ― 鈴木久雄文 ― 五十嵐太郎14KAJIMA202408
 モンジュイックの丘とパラウ・サン・ジョルディ(バルセロナ)15KAJIMA202408
モンジュイックの丘とパラウ・サン・ジョルディ(バルセロナ)15KAJIMA202408
 建設中のパラウ・サン・ジョルディ16KAJIMA202408
建設中のパラウ・サン・ジョルディ16KAJIMA202408
 鈴木久雄 すずき・ひさお建築写真家。1957年生まれ。バルセロナ在住。1986年から現在まで,世界的な建築雑誌『ElCroquis(エル・クロッキー)』の専属カメラマンとして活躍。日本では1988年,鹿島出版会の雑誌『SD』「ガウディとその子弟たち」の撮影を行って以来,世界の著名建築家を撮影し続けている。ほかに『a+u』「ラ・ルース・マヒカ―写真家,鈴木久雄」504号,2012年,「スーパーモデル―鈴木久雄が写す建築模型」522号,2014年など。五十嵐太郎 いがらし・たろう建築史家,建築批評家。1967年生まれ。東北大学大学院教授。近現代建築・都市・建築デザイン,アートやサブカルチャーにも造詣が深く,多彩な評論・キュレーション活動,展覧会監修で知られる。これまでヴェネチアビエンナーレ国際建築展2008日本館コミッショナー,あいちトリエンナーレ2013芸術監督などを歴任。著書に『被災地を歩きながら考えたこと』『建築の東京』『現代日本建築家列伝』,編著『レム・コールハースは何を変えたのか』など多数。デザイン―江川拓未(鹿島出版会)17KAJIMA202408
鈴木久雄 すずき・ひさお建築写真家。1957年生まれ。バルセロナ在住。1986年から現在まで,世界的な建築雑誌『ElCroquis(エル・クロッキー)』の専属カメラマンとして活躍。日本では1988年,鹿島出版会の雑誌『SD』「ガウディとその子弟たち」の撮影を行って以来,世界の著名建築家を撮影し続けている。ほかに『a+u』「ラ・ルース・マヒカ―写真家,鈴木久雄」504号,2012年,「スーパーモデル―鈴木久雄が写す建築模型」522号,2014年など。五十嵐太郎 いがらし・たろう建築史家,建築批評家。1967年生まれ。東北大学大学院教授。近現代建築・都市・建築デザイン,アートやサブカルチャーにも造詣が深く,多彩な評論・キュレーション活動,展覧会監修で知られる。これまでヴェネチアビエンナーレ国際建築展2008日本館コミッショナー,あいちトリエンナーレ2013芸術監督などを歴任。著書に『被災地を歩きながら考えたこと』『建築の東京』『現代日本建築家列伝』,編著『レム・コールハースは何を変えたのか』など多数。デザイン―江川拓未(鹿島出版会)17KAJIMA202408