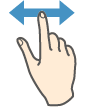北海道新幹線は,2016年に新青森∼新函館北斗までの区間(約149km)が開業し,現在は新函館北斗から札幌までの路線延長約212kmを整備している。当社JVは札幌駅から苗穂駅までの約1.3kmにわたり,整備新幹線では初めてとなる高架式の車両基地の施工を担当する。 現場は市街地の中で約1.3kmと細長い形状かつ,営業線が近接する狭隘地で,冬季は施工ができないなど制約も多い難工事だ。課題解決に向けて 当現場では4月から建設業にも適用された時間外労働時間の上限規制への対策が必要ななか,ICTツールの導入を現場の限られた人員で行わなければならなかった。 ICTツールは,最初の仕組みづくりや軌道に乗せるまでには相応の労力がかかる。この課題解決に向けて,土木管理本部に在籍していた数理系※1の新入社員(配属当時,1年目の12月)であった山田大樹担当の現場常駐配属が決まった。 「最初はどう協働すればいいのか正直不安でしたが,現場の二子石さんがICT化リストを準備して待ってくれていたので,まずは現場の要望に応えようと尽力しました」と配属当時の状況を話す。ICTツール導入を一気に加速 山田担当は学生時代,土木専攻で,ドローンとAIを用いて鉄筋コンクリート構造物の性能評価を行う研究をしていた。土木の知識も活かした機械・IT系の仕事に従事できる職種があることに魅力を感じて当社に入社。土木を学んできたからこそ,入社1年目の途中での配属という条件でも現場に馴染むのは早かった。 山田担当は配属早々に,現場全体をWi-Fi化することで通信環境を整備し,リアルタイムでの分散朝礼や発注者の遠隔臨場検査の安定化を実現。現場内での移動距離は全長約1.3kmに及ぶため時短効果は大きい。また,場所打ち杭進捗管理システムでは,Office365標準ツールのPowerAutomateでの自動処理機能を加え,現場用にカスタマイズした。そのほか,時間外労働時間や現場見学会などの情報をJV社員が一目でわかるようにSharePoint上での現場ポータルサイト作成やRPAによる自動処理,デキスパートの導入とFormsを絡めた効率化など,現場のニーズにより良いかたちで応えていった。「効率化が図れることを積極的に見つけな20KAJIMA202409[工事概要]北海道新幹線,札幌車両基地高架橋工事場所:札幌市中央区発注者:鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線建設局設計:土木―日本交通技術/建築―安井建築設計事務所規模:延長1,344m コンクリート41,553m3 杭(φ1,500∼2,000)374本工期:2023年6月∼2028年3月(予定)(北海道支店JV施工)現場業務のICT化は,もはや建設業界における生産性や魅力向上に欠かせない一方で,ツールの多様化や導入にかかる労力が障壁となることも少なくない。当現場では配置された数理系若手社員と現場社員が共鳴し,次々とICTツールを現場に浸透させた。キラリと輝く社員の活躍でさらなる効率化を見据える現場をリポートする。怒涛のICTツール導入第9回新幹線札幌車両基地高架橋JV工事事務所杉本亮輔工事課長山田大樹担当二子石秀哉工事主任 (写真左から)私たちの働き方※1建設プロジェクトや企業経営におけるIT活用の戦略企画,推進,およびサービス・システムの構築と研究開発
北海道新幹線は,2016年に新青森∼新函館北斗までの区間(約149km)が開業し,現在は新函館北斗から札幌までの路線延長約212kmを整備している。当社JVは札幌駅から苗穂駅までの約1.3kmにわたり,整備新幹線では初めてとなる高架式の車両基地の施工を担当する。 現場は市街地の中で約1.3kmと細長い形状かつ,営業線が近接する狭隘地で,冬季は施工ができないなど制約も多い難工事だ。課題解決に向けて 当現場では4月から建設業にも適用された時間外労働時間の上限規制への対策が必要ななか,ICTツールの導入を現場の限られた人員で行わなければならなかった。 ICTツールは,最初の仕組みづくりや軌道に乗せるまでには相応の労力がかかる。この課題解決に向けて,土木管理本部に在籍していた数理系※1の新入社員(配属当時,1年目の12月)であった山田大樹担当の現場常駐配属が決まった。 「最初はどう協働すればいいのか正直不安でしたが,現場の二子石さんがICT化リストを準備して待ってくれていたので,まずは現場の要望に応えようと尽力しました」と配属当時の状況を話す。ICTツール導入を一気に加速 山田担当は学生時代,土木専攻で,ドローンとAIを用いて鉄筋コンクリート構造物の性能評価を行う研究をしていた。土木の知識も活かした機械・IT系の仕事に従事できる職種があることに魅力を感じて当社に入社。土木を学んできたからこそ,入社1年目の途中での配属という条件でも現場に馴染むのは早かった。 山田担当は配属早々に,現場全体をWi-Fi化することで通信環境を整備し,リアルタイムでの分散朝礼や発注者の遠隔臨場検査の安定化を実現。現場内での移動距離は全長約1.3kmに及ぶため時短効果は大きい。また,場所打ち杭進捗管理システムでは,Office365標準ツールのPowerAutomateでの自動処理機能を加え,現場用にカスタマイズした。そのほか,時間外労働時間や現場見学会などの情報をJV社員が一目でわかるようにSharePoint上での現場ポータルサイト作成やRPAによる自動処理,デキスパートの導入とFormsを絡めた効率化など,現場のニーズにより良いかたちで応えていった。「効率化が図れることを積極的に見つけな20KAJIMA202409[工事概要]北海道新幹線,札幌車両基地高架橋工事場所:札幌市中央区発注者:鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線建設局設計:土木―日本交通技術/建築―安井建築設計事務所規模:延長1,344m コンクリート41,553m3 杭(φ1,500∼2,000)374本工期:2023年6月∼2028年3月(予定)(北海道支店JV施工)現場業務のICT化は,もはや建設業界における生産性や魅力向上に欠かせない一方で,ツールの多様化や導入にかかる労力が障壁となることも少なくない。当現場では配置された数理系若手社員と現場社員が共鳴し,次々とICTツールを現場に浸透させた。キラリと輝く社員の活躍でさらなる効率化を見据える現場をリポートする。怒涛のICTツール導入第9回新幹線札幌車両基地高架橋JV工事事務所杉本亮輔工事課長山田大樹担当二子石秀哉工事主任 (写真左から)私たちの働き方※1建設プロジェクトや企業経営におけるIT活用の戦略企画,推進,およびサービス・システムの構築と研究開発
 21KAJIMA202409山本信也所長ITソリューション部企画管理グループ角川友隆グループ長がら,所員が少しでも簡単に,かつ使いやすいシステムとなるよう心がけています」と山田担当は生き生きと語る。ITリテラシーの高い現場へ 会社が推奨するICTツールは数多く整備されているものの,社員全員が使いこなせるわけではない。JV社員をはじめ,所員全員に鹿島仕様の主要ツールの使い方を理解してもらう必要があった。二子石秀哉工事主任は山田担当に,工程管理ツール「工程’s」,出来形管理ツール「デキスパート」の所員への説明を任せたところ,「資料作成・プレゼンから質疑応答まで,新入社員とは思えない対応でした。この時,山田さんとならICTツールの導入を一気に進めることができ,現場全体のITリテラシーが高まると確信しました」と当時の印象と手応えを振り返る。品質管理の独自体制を確立 当現場では品質管理業務における施工担当者の負荷軽減を検討した。まず,場所打ち杭の品質管理体制の改革を図った。 通常,品質検査の業務は発注者の検査立会い準備,現地検査立会い,立会い結果の報告書作成・写真整理など,一連の流れをすべて施工担当者が行う。そのうち,報告書作成・写真整理などの事務作業をIA(InspectionAssistant,現場独自で命名)という検査補助者が行うことで,施工担当者の業務を軽減する体制を構築した。IAを統括している杉本亮輔工事課長は,「山田さんが関連するICTツールのカスタマイズをはじめ,この体制の肝であるIAへの教育や北海道支店のIT系部門との連携など,使いやすい環境を整備してくれたので,労働時間削減につながりました」と現場への貢献度の高さを語る。 現在は,場所打ち杭は半分以上完了しており,このスキームによって生産性が向上する体制であることが実証された。今後の躯体構築のフェーズでも活用し効率化を図る。 このほか,車両運行管理システム「G-Safe®」を現場で導入し,現在「AI配筋検査システム」などの導入も山田担当が中心となり着々と進めている。今後,ICTツールはさらに高度化し,導入が増えていくことは明白だ。数理系社員と施工系社員が協調し互いに高め合うことで,さらなる生産性向上が期待できる。 竣工に向け,現場のチャレンジは続く。検査補助業務を担うIAの角田担当(右)と杉本工事課長現場での数理系社員の活躍についてMessage札幌車両基地での経験を通じて,現場が本質的に何を求めているか,真の課題を理解し,現場に寄り添った改善策を見つける洞察力を養うことができました。この経験は,今後のITツールの開発や展開に大いに役立つと考えています。山田さんのように,数理系社員が現場の実態を知ることを通して,生産性向上と生産革命をともに実現する存在になっていければと思います。山田さんが来てくれたことで,現場のICT化は劇的に進みました。また,現場での直接的なコミュニケーションを通じて,IT管理部門と現場間のギャップを感じながら業務を学ぶことは,本人にとっても良い経験になっていると思います。現場におけるIT活用に関する知識と応用力を高めていただき,今後,当社全体のICT普及に貢献してくれる人材になってほしいですね。AI配筋検査端末。撮影するだけで鉄筋径・鉄筋間隔を自動計測することができる。当現場では,発注者との立会検査で試行中である札幌駅側からの全景(2024年8月撮影)札幌車両基地高架橋延長約1.3km創成川通新幹線札幌駅
21KAJIMA202409山本信也所長ITソリューション部企画管理グループ角川友隆グループ長がら,所員が少しでも簡単に,かつ使いやすいシステムとなるよう心がけています」と山田担当は生き生きと語る。ITリテラシーの高い現場へ 会社が推奨するICTツールは数多く整備されているものの,社員全員が使いこなせるわけではない。JV社員をはじめ,所員全員に鹿島仕様の主要ツールの使い方を理解してもらう必要があった。二子石秀哉工事主任は山田担当に,工程管理ツール「工程’s」,出来形管理ツール「デキスパート」の所員への説明を任せたところ,「資料作成・プレゼンから質疑応答まで,新入社員とは思えない対応でした。この時,山田さんとならICTツールの導入を一気に進めることができ,現場全体のITリテラシーが高まると確信しました」と当時の印象と手応えを振り返る。品質管理の独自体制を確立 当現場では品質管理業務における施工担当者の負荷軽減を検討した。まず,場所打ち杭の品質管理体制の改革を図った。 通常,品質検査の業務は発注者の検査立会い準備,現地検査立会い,立会い結果の報告書作成・写真整理など,一連の流れをすべて施工担当者が行う。そのうち,報告書作成・写真整理などの事務作業をIA(InspectionAssistant,現場独自で命名)という検査補助者が行うことで,施工担当者の業務を軽減する体制を構築した。IAを統括している杉本亮輔工事課長は,「山田さんが関連するICTツールのカスタマイズをはじめ,この体制の肝であるIAへの教育や北海道支店のIT系部門との連携など,使いやすい環境を整備してくれたので,労働時間削減につながりました」と現場への貢献度の高さを語る。 現在は,場所打ち杭は半分以上完了しており,このスキームによって生産性が向上する体制であることが実証された。今後の躯体構築のフェーズでも活用し効率化を図る。 このほか,車両運行管理システム「G-Safe®」を現場で導入し,現在「AI配筋検査システム」などの導入も山田担当が中心となり着々と進めている。今後,ICTツールはさらに高度化し,導入が増えていくことは明白だ。数理系社員と施工系社員が協調し互いに高め合うことで,さらなる生産性向上が期待できる。 竣工に向け,現場のチャレンジは続く。検査補助業務を担うIAの角田担当(右)と杉本工事課長現場での数理系社員の活躍についてMessage札幌車両基地での経験を通じて,現場が本質的に何を求めているか,真の課題を理解し,現場に寄り添った改善策を見つける洞察力を養うことができました。この経験は,今後のITツールの開発や展開に大いに役立つと考えています。山田さんのように,数理系社員が現場の実態を知ることを通して,生産性向上と生産革命をともに実現する存在になっていければと思います。山田さんが来てくれたことで,現場のICT化は劇的に進みました。また,現場での直接的なコミュニケーションを通じて,IT管理部門と現場間のギャップを感じながら業務を学ぶことは,本人にとっても良い経験になっていると思います。現場におけるIT活用に関する知識と応用力を高めていただき,今後,当社全体のICT普及に貢献してくれる人材になってほしいですね。AI配筋検査端末。撮影するだけで鉄筋径・鉄筋間隔を自動計測することができる。当現場では,発注者との立会検査で試行中である札幌駅側からの全景(2024年8月撮影)札幌車両基地高架橋延長約1.3km創成川通新幹線札幌駅