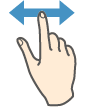KAJIMA20240926Kboard「新桂沢ダム」が竣工 6月9日,当社JVが施工を進めてきた「新桂沢ダム堤体建設工事」(北海道三笠市)の修祓式・竣工式が行われた。修祓式では,現地で玉串奉奠などを行い,三笠市民会館に場所を移した竣工式では,斉藤鉄夫国土交通大臣ほか,国土交通省関係者,来賓,工事関係者,地元関係者ら約200名が出席するなか,くす玉開披などが行われ,竣工を盛大に祝った。 本工事は,当社が1957年に施工した桂沢ダムを嵩上げする再開発工事で,幾春別川総合開発事業の一環として整備したもの。近年,国内では新設ダムの適地が限られる一方,各地での洪水の頻発などにより,既設ダムを有効活用する,ダム再開発の重要性が高まっている。こうした背景から本工事は,既設ダムを運用しながら堤体を嵩上げし,総貯水容量を増大することでダムの機能を向上する「ダム再生」事業のひとつとして全国的に注目を集めた。 2016年8月に工事着手。積雪寒冷地のため,1年の約半分を豪雪と闘いながら施工を進め,2024年3月に無事完成した。既設堤体の堤高63.6mから11.9m嵩上げしたことで,総貯水容量はこれまでの約1.6倍となった。ダム機能の向上により,これまで度々洪水被害を受けてきた流域の安全を守るとともに,灌漑,発電,工業用水,飲料水などの安定した供給が期待される。完成した新桂沢ダム子 5月23日,当社JVが施工を担当する「松山自動車道双海橋工事」(愛媛県伊予市)の連結式が現地にて挙行され,来賓や工事関係者ら約40名が参列し,橋の連結を祝った。 本工事は,西日本高速道路が進める松山自動車道(伊予ICから中山スマートIC間約6.3km)の4車線化事業の一部で,橋長232.3mのPC4径間連続バランスドアーチ橋を,上下部工一体で建設するもの。暫定2車線で供用中のⅠ期線アーチ橋に隣接して,Ⅱ期線となる本橋を架設し,4車線に拡幅することで,災害時の交通機能の確保や渋滞緩和が期待されている。 当社JVは,2020年8月から施工を開始。下部工は橋脚3基,橋台2基を構築し,上部工はトラス張出し架設により施工した。建設「松山自動車道双海橋」が連結双海橋全景(8月2日撮影)金色のシャベルを手に最終コンクリートを打設。右から2人目が尾崎四国支店長地は急峻な谷間で,地すべりブロック(地すべりを起こす可能性のある土塊)とI期線に近接しているため,施工ヤードの確保が困難だった。アーチリブの施工では,専用のアーチリブ移動作業車を新たに開発することで,効率的かつ安全に構築することができた。 現在(8月2日時点),別途工事となる舗装工事への橋面引き渡しを完了し,仮設桟橋撤去の準備中である。修祓式で玉串奉奠を行う風間副社長(中央)
KAJIMA20240926Kboard「新桂沢ダム」が竣工 6月9日,当社JVが施工を進めてきた「新桂沢ダム堤体建設工事」(北海道三笠市)の修祓式・竣工式が行われた。修祓式では,現地で玉串奉奠などを行い,三笠市民会館に場所を移した竣工式では,斉藤鉄夫国土交通大臣ほか,国土交通省関係者,来賓,工事関係者,地元関係者ら約200名が出席するなか,くす玉開披などが行われ,竣工を盛大に祝った。 本工事は,当社が1957年に施工した桂沢ダムを嵩上げする再開発工事で,幾春別川総合開発事業の一環として整備したもの。近年,国内では新設ダムの適地が限られる一方,各地での洪水の頻発などにより,既設ダムを有効活用する,ダム再開発の重要性が高まっている。こうした背景から本工事は,既設ダムを運用しながら堤体を嵩上げし,総貯水容量を増大することでダムの機能を向上する「ダム再生」事業のひとつとして全国的に注目を集めた。 2016年8月に工事着手。積雪寒冷地のため,1年の約半分を豪雪と闘いながら施工を進め,2024年3月に無事完成した。既設堤体の堤高63.6mから11.9m嵩上げしたことで,総貯水容量はこれまでの約1.6倍となった。ダム機能の向上により,これまで度々洪水被害を受けてきた流域の安全を守るとともに,灌漑,発電,工業用水,飲料水などの安定した供給が期待される。完成した新桂沢ダム子 5月23日,当社JVが施工を担当する「松山自動車道双海橋工事」(愛媛県伊予市)の連結式が現地にて挙行され,来賓や工事関係者ら約40名が参列し,橋の連結を祝った。 本工事は,西日本高速道路が進める松山自動車道(伊予ICから中山スマートIC間約6.3km)の4車線化事業の一部で,橋長232.3mのPC4径間連続バランスドアーチ橋を,上下部工一体で建設するもの。暫定2車線で供用中のⅠ期線アーチ橋に隣接して,Ⅱ期線となる本橋を架設し,4車線に拡幅することで,災害時の交通機能の確保や渋滞緩和が期待されている。 当社JVは,2020年8月から施工を開始。下部工は橋脚3基,橋台2基を構築し,上部工はトラス張出し架設により施工した。建設「松山自動車道双海橋」が連結双海橋全景(8月2日撮影)金色のシャベルを手に最終コンクリートを打設。右から2人目が尾崎四国支店長地は急峻な谷間で,地すべりブロック(地すべりを起こす可能性のある土塊)とI期線に近接しているため,施工ヤードの確保が困難だった。アーチリブの施工では,専用のアーチリブ移動作業車を新たに開発することで,効率的かつ安全に構築することができた。 現在(8月2日時点),別途工事となる舗装工事への橋面引き渡しを完了し,仮設桟橋撤去の準備中である。修祓式で玉串奉奠を行う風間副社長(中央)
 27KAJIMA202409第50回東京建築賞授賞式の様子新旧が融合したレトロモダンな九段会館テラス第25回日本免震構造協会賞表彰式。受賞者による記念撮影 6月14日,日本建設機械施工協会主催「令和6年度日本建設機械施工大賞」の表彰式が機械振興会館(東京都港区)で行われ,大賞部門において当社の「超高層建物における吊取り解体工法の開発」が最優秀賞,「遠隔操作システムを用いた,現場オペレータのテレワークシステム」が優秀賞※を受賞した。 この賞は,建設機械および建設施工に関して,有意な技術の向上または地域の建設事業の課題解消に,顕著な功績をあげた業績を表彰するもの。今年度は大賞部門7件,地域賞部門4件が選ばれた。 最優秀賞の技術は,超高層建物の地上躯体の解体工事で課題となっているガラの飛来・落下や粉塵の飛散,工期とコストの増加に対応する解体工法。スラブを斜めに切断した後の仮設支保工を不要「令和6年度日本建設機械施工大賞最優秀賞,優秀賞」を受賞とすることで,工程短縮とコスト低減を図った。本工法の開発にあたりスラブ斜め切断カッターのほか,ノロ水脱水装置,4点自動吊上げ装置も新たに開発した(鹿島スラッシュカット工法®)。この技術を適用した,最高高さ162mの世界貿易センタービルディング(東京都港区)の解体工事では,ガラ・粉塵が飛散することなく,従来に比べ約17%の工程短縮を実現した。 優秀賞は,油圧ショベルの遠隔操作システム(K-DIVE®)を用いた, 当社と東急不動産が担当した九段会館テラスが,「第25回日本免震構造協会賞作品賞」と「第50回東京建築賞東京都知事賞」を受賞した。 九段会館テラスは,登録有形文化財である旧九段会館の再生(保存・復原)と,新しいワーキングプレイスの創出をテーマに計画された再開発事業。旧九段会館の外装を保存,貴賓室・宴会場・玄関ホールなど内部を再生し,創建時の意匠に復原した保存棟と,地上17階,地下3階のオフィスビルを新たに建設した新築棟からなる。歴史建造物を永続的に使用し続けるため,保存棟は地下1階に免震レトロフィット工法※を採用し,安全性を最大限確保した。 日本免震構造協会賞(主催:日本免震構造協会)では,基礎上免震を採用し,エキスパンションジョイ九段会館テラスが「日本免震構造協会賞」と「東京建築賞」をダブル受賞ント部のレベルを巧みに変えて目立たないよう工夫することで,外観の保存に配慮しながら,免震の保存棟と制震の新築棟をつなぎ,耐震性能を向上させた点が評価された。 東京建築賞(主催:東京都建築士事務所協会)では,レガシーを長く使い続けるために長寿命化を図っている点や,空間的・意匠的なつながりがスムーズで,新旧の建築的な魅力が融合し新たな価値を生み出している点,外部空間に現場改善ソリューション。1台のコックピットから複数重機の切替え遠隔操作を実現し,実機の振動や傾き,音など現場にいる感覚で操作することを可能とした。赤谷地区上流渓流保全工他工事(奈良県五條市)では特定期間に1台を運用し,従来の遠隔操縦と比較して10∼20%の生産性が向上した。超高層ビル解体に用いられた「スラブ斜め切断カッター」現場オペレータの働き方を変革した「遠隔操作システム(K-DIVE)」※既存の建物の基礎などに免震装置を新たに設け,建物のデザインや機能を損なうことなく地震に対する安全性を確保する補強方法最優秀賞を受賞した左から,技術研究所中村隆寛主任研究員,機械部石田武志グループ長,東京建築支店機械部藤原健弥主任優秀賞を受賞した左から,コベルコ建機佐々木均担当,佐伯誠司部長,関西支店赤谷工事事務所森田真幸所長,冨島建設木村公彰所長都心の新たな憩いの場を作り出した点などが評価された。 当社は今後も魅力ある建築と都市の建設に貢献し,免震構造など建築技術の進歩や普及発展に寄与していく。※当社・冨島建設・コベルコ建機の共同受賞
27KAJIMA202409第50回東京建築賞授賞式の様子新旧が融合したレトロモダンな九段会館テラス第25回日本免震構造協会賞表彰式。受賞者による記念撮影 6月14日,日本建設機械施工協会主催「令和6年度日本建設機械施工大賞」の表彰式が機械振興会館(東京都港区)で行われ,大賞部門において当社の「超高層建物における吊取り解体工法の開発」が最優秀賞,「遠隔操作システムを用いた,現場オペレータのテレワークシステム」が優秀賞※を受賞した。 この賞は,建設機械および建設施工に関して,有意な技術の向上または地域の建設事業の課題解消に,顕著な功績をあげた業績を表彰するもの。今年度は大賞部門7件,地域賞部門4件が選ばれた。 最優秀賞の技術は,超高層建物の地上躯体の解体工事で課題となっているガラの飛来・落下や粉塵の飛散,工期とコストの増加に対応する解体工法。スラブを斜めに切断した後の仮設支保工を不要「令和6年度日本建設機械施工大賞最優秀賞,優秀賞」を受賞とすることで,工程短縮とコスト低減を図った。本工法の開発にあたりスラブ斜め切断カッターのほか,ノロ水脱水装置,4点自動吊上げ装置も新たに開発した(鹿島スラッシュカット工法®)。この技術を適用した,最高高さ162mの世界貿易センタービルディング(東京都港区)の解体工事では,ガラ・粉塵が飛散することなく,従来に比べ約17%の工程短縮を実現した。 優秀賞は,油圧ショベルの遠隔操作システム(K-DIVE®)を用いた, 当社と東急不動産が担当した九段会館テラスが,「第25回日本免震構造協会賞作品賞」と「第50回東京建築賞東京都知事賞」を受賞した。 九段会館テラスは,登録有形文化財である旧九段会館の再生(保存・復原)と,新しいワーキングプレイスの創出をテーマに計画された再開発事業。旧九段会館の外装を保存,貴賓室・宴会場・玄関ホールなど内部を再生し,創建時の意匠に復原した保存棟と,地上17階,地下3階のオフィスビルを新たに建設した新築棟からなる。歴史建造物を永続的に使用し続けるため,保存棟は地下1階に免震レトロフィット工法※を採用し,安全性を最大限確保した。 日本免震構造協会賞(主催:日本免震構造協会)では,基礎上免震を採用し,エキスパンションジョイ九段会館テラスが「日本免震構造協会賞」と「東京建築賞」をダブル受賞ント部のレベルを巧みに変えて目立たないよう工夫することで,外観の保存に配慮しながら,免震の保存棟と制震の新築棟をつなぎ,耐震性能を向上させた点が評価された。 東京建築賞(主催:東京都建築士事務所協会)では,レガシーを長く使い続けるために長寿命化を図っている点や,空間的・意匠的なつながりがスムーズで,新旧の建築的な魅力が融合し新たな価値を生み出している点,外部空間に現場改善ソリューション。1台のコックピットから複数重機の切替え遠隔操作を実現し,実機の振動や傾き,音など現場にいる感覚で操作することを可能とした。赤谷地区上流渓流保全工他工事(奈良県五條市)では特定期間に1台を運用し,従来の遠隔操縦と比較して10∼20%の生産性が向上した。超高層ビル解体に用いられた「スラブ斜め切断カッター」現場オペレータの働き方を変革した「遠隔操作システム(K-DIVE)」※既存の建物の基礎などに免震装置を新たに設け,建物のデザインや機能を損なうことなく地震に対する安全性を確保する補強方法最優秀賞を受賞した左から,技術研究所中村隆寛主任研究員,機械部石田武志グループ長,東京建築支店機械部藤原健弥主任優秀賞を受賞した左から,コベルコ建機佐々木均担当,佐伯誠司部長,関西支店赤谷工事事務所森田真幸所長,冨島建設木村公彰所長都心の新たな憩いの場を作り出した点などが評価された。 当社は今後も魅力ある建築と都市の建設に貢献し,免震構造など建築技術の進歩や普及発展に寄与していく。※当社・冨島建設・コベルコ建機の共同受賞
 KAJIMA20240928令和6年度「安全衛生・厚生労働大臣表彰優良賞・奨励賞」を受賞 7月1日,令和6年度「安全衛生に係る優良事業場,団体又は功労者に対する厚生労働大臣表彰」の中央表彰式が東京會舘(東京都千代田区)で行われた。この表彰は,安全衛生に関する水準が特に優秀で,他の模範となる優良事業場や,安全衛生水準の向上に貢献した功労者などを讃えるもの。今年度は23事業場,33名が表彰された。 優良賞を受賞した中国支店JV施工の「出雲市新体育館建設JV工事」(島根県出雲市)は,職長・技能者への「鹿島の安全ルール」の周知徹底とともに,職長会の活性化で現場運営の主体は職長と意識付ける試みや,外国人技能実習生への複数言語を併記した安全看板の掲示,保護具の元請支給による着装の徹底など,他現場の優良な活動を多数取り込んだ。 関西支店施工の「西日本高速道路株式会社受託淀川東高架橋(P2-P4鋼上部工)工事」(大阪府枚方市)は奨励賞を受賞。橋梁上部での施工が多いため,緻密な設計と入念な架設計画のもと制作後の記念撮影。オブジェは今治市に寄贈し,同市伯方開発総合センターのロビーに設置された新川河口自然排水樋門建設工事が「全国土地改良優良工事等学術技術最優秀賞」を受賞 当社が施工を進めている新川河口自然排水樋門建設工事(新潟県新潟市)が,「2023年度全国土地改良優良工事等学術技術最優秀賞」を受賞し,6月28日,学士会館(東京都千代田区)にて表彰式が行われた。 本表彰は,土地改良事業に関わる新技術の開発,導入を促進するために設けられ,農業と農村の発展に寄与する学術団体「農業農村工学会」が主催し,農林水産省が後援。革新的な新技術の提案,導入などを行い,学術的,技術的に優れた工事などを表彰する。 本工事は,農林水産省北陸農政局が新川流域二期農業水利事業の一環として進めるもので,新潟市を流れる新川に50年以上前から設置されている自然排水樋門を更新する。住宅地に隣接し十分な施工ヤードの確保が厳しい状況下で,樋門の機能を維持しながら施工を行う半川締切※工法を採用するなど,技術的難易度が高い工事のため,土地改良事業では初めてECI方式を適用し,右岸側の樋門は昨年3月に完成した。また,仮締切工では,濁度の高さや流れの強さから構造を陸上でユニット化し,クレーンで沈設することで,水中での作業を60%低減。さらに樋門の基礎杭の施工に防音装置工事関係者による記念撮影様々なリスクに対し,本社・支店と連携した安全対策を行い,安全設備の設置や点検を徹底した。また,IoTを積極的に活用した安全活動や,技能者のやりがいと安全意識向上を目的とした様々な取組みを行い,安全レベルの向上を図った。 両現場は,これらの創意工夫を凝らした様々な安全活動が模範となるものとして高く評価された。 5月18日,今治市大三島で,「しまなみテクノロジー市民大学講座(しまテク)」の1周年イベントが開催された。 本講座は,東京大学大学院工愛媛県大三島で開催された「しまテク」1周年記念イベントに参加学系研究科・工学部と日本アイ・ビー・エムが主体となり,産・官・学・地域が連携し,未来の地域・街を考え実践することを目的としたプロジェクト「コグニティブ・デザイニング・エクセレンス」の取組みのひとつで,当社は社会貢献活動の一環として参画している。 当日は,建築・ものづくりの楽しさを知ってもらうことを目的に,今治市とも連携し,「建築ものづくり体験会」を実施。シンガポールのSuperstructure社と当社が共同パーツを組み立てる子どもたちでデザイン・制作した32個の木造パーツを子どもたちが組み立て,高さ150cmの32面体オブジェが完成した。このオブジェは「しまなみともしびボール」と名付けられ,今治市の3つの島である大三島,伯方島,大島がかたどられている。子どもたちは中に入って遊んだり,写真撮影をしたりと,作った作品を心赴くままに楽しんだ。を導入し,騒音を30%低減するなどの技術的な取組みが高く評価され,今回の受賞に至った。 左岸側を含めた全体の工事完了は2026年3月を予定。※川を半分ずつ締め切る関西支店受賞者よる記念撮影(左から関西支店都築辰夫安全環境部長,橋本和晃所長,茅野支店長)中国支店受賞者による記念撮影(左から中国支店佐々木学安全環境部長,岡本寛司所長,竹川専務,建築管理本部石井陽一安全推進部長)FromEhime&Singapore
KAJIMA20240928令和6年度「安全衛生・厚生労働大臣表彰優良賞・奨励賞」を受賞 7月1日,令和6年度「安全衛生に係る優良事業場,団体又は功労者に対する厚生労働大臣表彰」の中央表彰式が東京會舘(東京都千代田区)で行われた。この表彰は,安全衛生に関する水準が特に優秀で,他の模範となる優良事業場や,安全衛生水準の向上に貢献した功労者などを讃えるもの。今年度は23事業場,33名が表彰された。 優良賞を受賞した中国支店JV施工の「出雲市新体育館建設JV工事」(島根県出雲市)は,職長・技能者への「鹿島の安全ルール」の周知徹底とともに,職長会の活性化で現場運営の主体は職長と意識付ける試みや,外国人技能実習生への複数言語を併記した安全看板の掲示,保護具の元請支給による着装の徹底など,他現場の優良な活動を多数取り込んだ。 関西支店施工の「西日本高速道路株式会社受託淀川東高架橋(P2-P4鋼上部工)工事」(大阪府枚方市)は奨励賞を受賞。橋梁上部での施工が多いため,緻密な設計と入念な架設計画のもと制作後の記念撮影。オブジェは今治市に寄贈し,同市伯方開発総合センターのロビーに設置された新川河口自然排水樋門建設工事が「全国土地改良優良工事等学術技術最優秀賞」を受賞 当社が施工を進めている新川河口自然排水樋門建設工事(新潟県新潟市)が,「2023年度全国土地改良優良工事等学術技術最優秀賞」を受賞し,6月28日,学士会館(東京都千代田区)にて表彰式が行われた。 本表彰は,土地改良事業に関わる新技術の開発,導入を促進するために設けられ,農業と農村の発展に寄与する学術団体「農業農村工学会」が主催し,農林水産省が後援。革新的な新技術の提案,導入などを行い,学術的,技術的に優れた工事などを表彰する。 本工事は,農林水産省北陸農政局が新川流域二期農業水利事業の一環として進めるもので,新潟市を流れる新川に50年以上前から設置されている自然排水樋門を更新する。住宅地に隣接し十分な施工ヤードの確保が厳しい状況下で,樋門の機能を維持しながら施工を行う半川締切※工法を採用するなど,技術的難易度が高い工事のため,土地改良事業では初めてECI方式を適用し,右岸側の樋門は昨年3月に完成した。また,仮締切工では,濁度の高さや流れの強さから構造を陸上でユニット化し,クレーンで沈設することで,水中での作業を60%低減。さらに樋門の基礎杭の施工に防音装置工事関係者による記念撮影様々なリスクに対し,本社・支店と連携した安全対策を行い,安全設備の設置や点検を徹底した。また,IoTを積極的に活用した安全活動や,技能者のやりがいと安全意識向上を目的とした様々な取組みを行い,安全レベルの向上を図った。 両現場は,これらの創意工夫を凝らした様々な安全活動が模範となるものとして高く評価された。 5月18日,今治市大三島で,「しまなみテクノロジー市民大学講座(しまテク)」の1周年イベントが開催された。 本講座は,東京大学大学院工愛媛県大三島で開催された「しまテク」1周年記念イベントに参加学系研究科・工学部と日本アイ・ビー・エムが主体となり,産・官・学・地域が連携し,未来の地域・街を考え実践することを目的としたプロジェクト「コグニティブ・デザイニング・エクセレンス」の取組みのひとつで,当社は社会貢献活動の一環として参画している。 当日は,建築・ものづくりの楽しさを知ってもらうことを目的に,今治市とも連携し,「建築ものづくり体験会」を実施。シンガポールのSuperstructure社と当社が共同パーツを組み立てる子どもたちでデザイン・制作した32個の木造パーツを子どもたちが組み立て,高さ150cmの32面体オブジェが完成した。このオブジェは「しまなみともしびボール」と名付けられ,今治市の3つの島である大三島,伯方島,大島がかたどられている。子どもたちは中に入って遊んだり,写真撮影をしたりと,作った作品を心赴くままに楽しんだ。を導入し,騒音を30%低減するなどの技術的な取組みが高く評価され,今回の受賞に至った。 左岸側を含めた全体の工事完了は2026年3月を予定。※川を半分ずつ締め切る関西支店受賞者よる記念撮影(左から関西支店都築辰夫安全環境部長,橋本和晃所長,茅野支店長)中国支店受賞者による記念撮影(左から中国支店佐々木学安全環境部長,岡本寛司所長,竹川専務,建築管理本部石井陽一安全推進部長)FromEhime&Singapore
 BOOKS29KAJIMA202409 7月3日,当社が幹事会社として参画する,建設施工ロボットやIoT分野での技術連携を目的とした「建設RXコンソーシアム」(以下,RXコンソ)の2024年度通常総会が開催された。 2021年9月に当社をはじめとする16社で発足したRXコンソは,ゼネコン大手5社を含む正会員29社,協力会員233社の計262社(6月30日現在)にまで拡大。個社だけでは実現が難しい業界全体の生産性向上のため,会員 当社東北支店は,6月5・6日の2日間,夢メッセみやぎ(仙台市宮城野区)で開催された「EE※東北’24」に出展した。このイベントはEE東北実行委員会(委員長:東北地方整備局企画部長)が主催する展示会で,建設事業に係わる新材料,新工法のほか時代のニーズに対応して開発された新技術を公開し,その普及を図ることにより,さらなる技術開発の促進と,良質な社会資本の整備を通じて,社会に寄与することを目的としている。「建設RXコンソーシアム」2024年度通常総会を開催「EE東北’24」に出展企業間の協働を推し進めている。なお,今年度からは当社の小林常務が副会長に就任した。 本総会では,技術開発に目途がつき,実用化の検証に進む段階にある技術の普及展開を支援する「実用化推進委員会」の活動方針,スケジュールなどが決議された。技術開発のみならず,その技術を建設業に広く普及展開し,実用化を推進するというフェーズへ,着々とステップアップしてきている。 6月7日,86社,約300人のMicrosoftユーザーが集結し,東軍(東京虎ノ門)西軍(大阪梅田)に分かれてPowerPlatform※1を使った合戦「パワプラ関ヶ原」が開催され,当社デジタル推進室中川康子さんなどが参戦した。 この催しは,「NipponPPEC※2」参加企業2社が発起人となり実施された。「NipponPPEC」は日本マイクロソフトが活動を支援するPowerPlatformユーザー会で,参加企業の交流と情報交換を促し,各社の市民開発や社内コミュニティパワプラ関ヶ原に参加!の活性化を目的に活動しており,当社もオープンイノベーション推進のため積極的に参加している。 当社が武将として東西両軍から参戦した,制限時間わずか15分の「アプリ早づくり対決(テーマ:名刺読み取りアプリ)」では,当社関西支店建築部今井桃子さんのグループが見事1位を獲得した。各種イベントは大いに盛り上がり,最終的には西軍が優勝。東軍大将から次回へのリベンジを誓うコメントがあり,会場は新たな熱気に包まれた。「様式なき様式」を追求堀口捨己の評伝お問合せ鹿島出版会tel:03-6264-2301RXコンソのロゴを手に,参加会員全員で集合写真当社ブースの様子屋内展示棟の様子 33回目の開催となる本展示会には,378の出展者による958の技術が集結。来場者は2日間で過去最多の計1万7,000人超を記録した。当社ブースでは,「山岳トンネル自動化施工システム」や,先端ICT・各種ロボットの活用と現場管理手法の革新で,より魅力的な建築生産プロセスを目指す「鹿島スマート生産」に関する取組みを紹介。両日とも多くの来場者が担当者の説明に耳を傾けた。『SD選書275堀口捨己の世界』藤岡洋保/著,四六判・278頁,定価2,640円(税込み)新刊のSD選書(中央)と,これまでに鹿島出版会で刊行してきた堀口捨己の著書の数々。『堀口捨己作品・家と庭の空間構成』,『建築論叢』など(現在,品切れ)の赤い函(はこ)の装丁は堀口によるデザイン SD選書の最新刊は,日本のモダニズムを牽引した建築家,堀口捨己(1895-1984)のモノグラフ。建築史家,庭園史家,茶の湯研究者,歌人……と多彩な顔を持ち,和風建築の大家としても知られました。合目的の美を目指す「様式なき様式」という言葉を残した堀口の営みを,建築史家・藤岡洋保氏(東京工業大学名誉教授)がひもときます。 本書は,国立近現代建築資料館にて開催中の企画展「建築家・堀口捨己の探求モダニズム・利休・庭園・和歌」(10月27日まで)に合わせて刊行。建築における美のあり方を追求した,堀口の世界を堪能できる一冊です。東軍の様子※EngineeringExhibition※1Microsoftが提供するローコード開発ツール※2PowerPlatformEnterpriseCommunity
BOOKS29KAJIMA202409 7月3日,当社が幹事会社として参画する,建設施工ロボットやIoT分野での技術連携を目的とした「建設RXコンソーシアム」(以下,RXコンソ)の2024年度通常総会が開催された。 2021年9月に当社をはじめとする16社で発足したRXコンソは,ゼネコン大手5社を含む正会員29社,協力会員233社の計262社(6月30日現在)にまで拡大。個社だけでは実現が難しい業界全体の生産性向上のため,会員 当社東北支店は,6月5・6日の2日間,夢メッセみやぎ(仙台市宮城野区)で開催された「EE※東北’24」に出展した。このイベントはEE東北実行委員会(委員長:東北地方整備局企画部長)が主催する展示会で,建設事業に係わる新材料,新工法のほか時代のニーズに対応して開発された新技術を公開し,その普及を図ることにより,さらなる技術開発の促進と,良質な社会資本の整備を通じて,社会に寄与することを目的としている。「建設RXコンソーシアム」2024年度通常総会を開催「EE東北’24」に出展企業間の協働を推し進めている。なお,今年度からは当社の小林常務が副会長に就任した。 本総会では,技術開発に目途がつき,実用化の検証に進む段階にある技術の普及展開を支援する「実用化推進委員会」の活動方針,スケジュールなどが決議された。技術開発のみならず,その技術を建設業に広く普及展開し,実用化を推進するというフェーズへ,着々とステップアップしてきている。 6月7日,86社,約300人のMicrosoftユーザーが集結し,東軍(東京虎ノ門)西軍(大阪梅田)に分かれてPowerPlatform※1を使った合戦「パワプラ関ヶ原」が開催され,当社デジタル推進室中川康子さんなどが参戦した。 この催しは,「NipponPPEC※2」参加企業2社が発起人となり実施された。「NipponPPEC」は日本マイクロソフトが活動を支援するPowerPlatformユーザー会で,参加企業の交流と情報交換を促し,各社の市民開発や社内コミュニティパワプラ関ヶ原に参加!の活性化を目的に活動しており,当社もオープンイノベーション推進のため積極的に参加している。 当社が武将として東西両軍から参戦した,制限時間わずか15分の「アプリ早づくり対決(テーマ:名刺読み取りアプリ)」では,当社関西支店建築部今井桃子さんのグループが見事1位を獲得した。各種イベントは大いに盛り上がり,最終的には西軍が優勝。東軍大将から次回へのリベンジを誓うコメントがあり,会場は新たな熱気に包まれた。「様式なき様式」を追求堀口捨己の評伝お問合せ鹿島出版会tel:03-6264-2301RXコンソのロゴを手に,参加会員全員で集合写真当社ブースの様子屋内展示棟の様子 33回目の開催となる本展示会には,378の出展者による958の技術が集結。来場者は2日間で過去最多の計1万7,000人超を記録した。当社ブースでは,「山岳トンネル自動化施工システム」や,先端ICT・各種ロボットの活用と現場管理手法の革新で,より魅力的な建築生産プロセスを目指す「鹿島スマート生産」に関する取組みを紹介。両日とも多くの来場者が担当者の説明に耳を傾けた。『SD選書275堀口捨己の世界』藤岡洋保/著,四六判・278頁,定価2,640円(税込み)新刊のSD選書(中央)と,これまでに鹿島出版会で刊行してきた堀口捨己の著書の数々。『堀口捨己作品・家と庭の空間構成』,『建築論叢』など(現在,品切れ)の赤い函(はこ)の装丁は堀口によるデザイン SD選書の最新刊は,日本のモダニズムを牽引した建築家,堀口捨己(1895-1984)のモノグラフ。建築史家,庭園史家,茶の湯研究者,歌人……と多彩な顔を持ち,和風建築の大家としても知られました。合目的の美を目指す「様式なき様式」という言葉を残した堀口の営みを,建築史家・藤岡洋保氏(東京工業大学名誉教授)がひもときます。 本書は,国立近現代建築資料館にて開催中の企画展「建築家・堀口捨己の探求モダニズム・利休・庭園・和歌」(10月27日まで)に合わせて刊行。建築における美のあり方を追求した,堀口の世界を堪能できる一冊です。東軍の様子※EngineeringExhibition※1Microsoftが提供するローコード開発ツール※2PowerPlatformEnterpriseCommunity