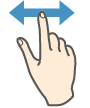セルガスカーノ/メリダ・ファクトリー・ユース・ムーヴメント(スペイン,メリダ)14KAJIMA202410
セルガスカーノ/メリダ・ファクトリー・ユース・ムーヴメント(スペイン,メリダ)14KAJIMA202410
 第7回 現代を反映するマテリアル写真 ― 鈴木久雄文 ― 五十嵐太郎15KAJIMA202410
第7回 現代を反映するマテリアル写真 ― 鈴木久雄文 ― 五十嵐太郎15KAJIMA202410
 ヘルツォーク&ド・ムーロン/シグナル・ボックス(スイス,バーゼル)16KAJIMA202410
ヘルツォーク&ド・ムーロン/シグナル・ボックス(スイス,バーゼル)16KAJIMA202410
 デザイン―江川拓未(鹿島出版会)パリのオリンピックは開会式と競技において都市空間を積極的に活用したことで注目を集め,コンコルド広場では,スケートボード,ブレイキン,自転車BMXフリースタイルなどが開催された。もちろん,このときは仮設の会場がつくられたが,スペインのメリダ・ファクトリー・ユース・ムーヴメント(2011年)は,もし恒常的な施設を構想するならば,かくあるべきという建築だろう。これは都市の中の開かれた大きなキャノピーの下で,スケートパークやクライミング・ウォールからヒップホップ・ダンスまで,さまざまなアクティビティを許容する。メリダは古代ローマの遺跡が数多く残る街だが,オレンジのほか,黄,赤,緑など,驚くほどカラフルに彩られた現代的な空間だ。 設計は,マドリッドに拠点を置く男女の建築家ユニット,セルガスカーノによる。彼らは明るく鮮やかなデザインを得意とし,特に色や素材の使い方が圧倒的にユニークだ。ゆえに,色がついた皮膜を通過する光が美しい。一方で夜になると,透明な外皮を通じて,内部から発光する効果をもたらす。カタルヘナの文化センター(2011年)やプラセンシアのオーディトリアムと会議場(2016年)もそうだが,かつてこれほど大胆にオレンジの色と光を導入した建築が存在しただろうかと思わせる。また,メリダのプロジェクトがポリカーボネートのパネルでスチールの骨格を覆うように,彼らは人工的に製造された高分子化合物,すなわちプラスチック系マテリアルを積極的に用いる。ほかの建築でもETFE膜,フィルム,テープ,アクリルなどが使われた。 建築界では,ポストモダンの波が収束し,ミニマリズムに転回した1990年代から,マテリアルの表現を重視する傾向が登場した。その牽引役となったのはスイスの建築家たちであり,シンプルなかたちに対し,石,木,ガラス,金属などで包み,表層の素材の特性をいかしたデザインを生みだした。ヘルツォーク&ド・ムーロンはその代表格であり,とりわけバーゼルのシグナル・ボックス(1995年)が有名だろう。これは鉄道の信号所という,通常ならば建築作品になりにくいビルディングタイプであり,かたちもおおむね箱形である。だが,外部の環境が内部の電子機器に影響しないように,シールドとして幅20cmの銅の帯を躯体に巻く。しかも,すべて均質ではなく,一部にねじれを与えることで,見る角度によって微細に表情が変化する。かくして無表情になるであろう施設が,オブジェ的な性格を獲得した。シグナル・ボックスは銅の鎧をまとうことで,その内側に大事なものを秘めていることを示唆し,建物の見えない性格を可視化している。鈴木久雄 すずき・ひさお建築写真家。1957年生まれ。バルセロナ在住。1986年から現在まで,世界的な建築雑誌『ElCroquis(エル・クロッキー)』の専属カメラマンとして活躍。日本では1988年,鹿島出版会の雑誌『SD』「ガウディとその子弟たち」の撮影を行って以来,世界の著名建築家を撮影し続けている。ほかに『a+u』「ラ・ルース・マヒカ―写真家,鈴木久雄」504号,2012年,「スーパーモデル―鈴木久雄が写す建築模型」522号,2014年など。五十嵐太郎 いがらし・たろう建築史家,建築批評家。1967年生まれ。東北大学大学院教授。近現代建築・都市・建築デザイン,アートやサブカルチャーにも造詣が深く,多彩な評論・キュレーション活動,展覧会監修で知られる。これまでヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2008日本館コミッショナー,あいちトリエンナーレ2013芸術監督などを歴任。著書に『被災地を歩きながら考えたこと』『建築の東京』『現代日本建築家列伝』,編著『レム・コールハースは何を変えたのか』など多数。17KAJIMA202410
デザイン―江川拓未(鹿島出版会)パリのオリンピックは開会式と競技において都市空間を積極的に活用したことで注目を集め,コンコルド広場では,スケートボード,ブレイキン,自転車BMXフリースタイルなどが開催された。もちろん,このときは仮設の会場がつくられたが,スペインのメリダ・ファクトリー・ユース・ムーヴメント(2011年)は,もし恒常的な施設を構想するならば,かくあるべきという建築だろう。これは都市の中の開かれた大きなキャノピーの下で,スケートパークやクライミング・ウォールからヒップホップ・ダンスまで,さまざまなアクティビティを許容する。メリダは古代ローマの遺跡が数多く残る街だが,オレンジのほか,黄,赤,緑など,驚くほどカラフルに彩られた現代的な空間だ。 設計は,マドリッドに拠点を置く男女の建築家ユニット,セルガスカーノによる。彼らは明るく鮮やかなデザインを得意とし,特に色や素材の使い方が圧倒的にユニークだ。ゆえに,色がついた皮膜を通過する光が美しい。一方で夜になると,透明な外皮を通じて,内部から発光する効果をもたらす。カタルヘナの文化センター(2011年)やプラセンシアのオーディトリアムと会議場(2016年)もそうだが,かつてこれほど大胆にオレンジの色と光を導入した建築が存在しただろうかと思わせる。また,メリダのプロジェクトがポリカーボネートのパネルでスチールの骨格を覆うように,彼らは人工的に製造された高分子化合物,すなわちプラスチック系マテリアルを積極的に用いる。ほかの建築でもETFE膜,フィルム,テープ,アクリルなどが使われた。 建築界では,ポストモダンの波が収束し,ミニマリズムに転回した1990年代から,マテリアルの表現を重視する傾向が登場した。その牽引役となったのはスイスの建築家たちであり,シンプルなかたちに対し,石,木,ガラス,金属などで包み,表層の素材の特性をいかしたデザインを生みだした。ヘルツォーク&ド・ムーロンはその代表格であり,とりわけバーゼルのシグナル・ボックス(1995年)が有名だろう。これは鉄道の信号所という,通常ならば建築作品になりにくいビルディングタイプであり,かたちもおおむね箱形である。だが,外部の環境が内部の電子機器に影響しないように,シールドとして幅20cmの銅の帯を躯体に巻く。しかも,すべて均質ではなく,一部にねじれを与えることで,見る角度によって微細に表情が変化する。かくして無表情になるであろう施設が,オブジェ的な性格を獲得した。シグナル・ボックスは銅の鎧をまとうことで,その内側に大事なものを秘めていることを示唆し,建物の見えない性格を可視化している。鈴木久雄 すずき・ひさお建築写真家。1957年生まれ。バルセロナ在住。1986年から現在まで,世界的な建築雑誌『ElCroquis(エル・クロッキー)』の専属カメラマンとして活躍。日本では1988年,鹿島出版会の雑誌『SD』「ガウディとその子弟たち」の撮影を行って以来,世界の著名建築家を撮影し続けている。ほかに『a+u』「ラ・ルース・マヒカ―写真家,鈴木久雄」504号,2012年,「スーパーモデル―鈴木久雄が写す建築模型」522号,2014年など。五十嵐太郎 いがらし・たろう建築史家,建築批評家。1967年生まれ。東北大学大学院教授。近現代建築・都市・建築デザイン,アートやサブカルチャーにも造詣が深く,多彩な評論・キュレーション活動,展覧会監修で知られる。これまでヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2008日本館コミッショナー,あいちトリエンナーレ2013芸術監督などを歴任。著書に『被災地を歩きながら考えたこと』『建築の東京』『現代日本建築家列伝』,編著『レム・コールハースは何を変えたのか』など多数。17KAJIMA202410