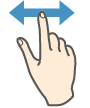18KAJIMA202410 ロボットコンテスト(ロボコン)は,競技課題に従い,チームでロボットを製作しアイデアや技術力を競う。機械・電気・制御などの知識だけではなく,チームワークや戦略も重要となる。 様々なロボコンの中でも,NHK学生ロボコンは,規模の大きさや,優勝すると日本代表として世界大会「ABU※1ロボコン」に出場できることから,特に注目を集める大会だ。 若く未来あるエンジニアたちがしのぎを削るロボコンは,土木分野で「現場の工場化」,建築分野で「作業の半分はロボットと」を掲げる当社にとっても親和性が高い。競技テーマ「HarvestDay」 今大会では,ABUロボコン2024が開催されるベトナムの棚田からインスピレーションを得たフィールドが設けられ,苗を植えて稲を収穫するまでを模した課題が与えられた。フィールドでロボットが扱う対象物は3種類。塩ビパイプで見立てた「苗」,赤または青のボールで見立てた「籾」,紫のボールの「空籾」である。 競技は,12本の苗をラックからプランティングゾーンに植える「プラント」,ハーベスティングゾーンから12個の籾と空籾を収穫してルール概要(一部抜粋)●大会に出場できるのはチームメンバー3名とピットクルー上限3名まで●【ロボット1(R1)】エリア1,2に進入可。手動ロボット,自動ロボットどちらでもOK。手動ロボットは無線でチームメンバーが操作する。自動ロボットはチームメンバーの操作なしで動く●【ロボット2(R2)】エリア1,2,3に進入できる。自動ロボットでなければならない当社は2024年からNHK学生ロボコン(主催:NHK,NHKエンタープライズ)に協賛する。6月9日に開催された本大会では,「鹿島建設特別賞」(以下,鹿島賞)を設け,ロボットづくりに情熱を注ぐ学生たちを応援した。今回は,鹿島賞を受賞した「新潟大学科学技術研究部」の皆さんへの取材をとおして,ロボコンの魅力を探る。プランティングゾーンサイロゾーンストレージゾーンハーベスティングゾーン#KAJIMA#kajimaステキシェアいいね!#NHK学生ロボコン2024アイデアを形に!夢は現実に!大会の様子。新潟大学メンバー(フィールド手前)が奮闘中※1アジア太平洋放送連合ストレージゾーンに入れる「ハーベスト」,ストレージゾーンの籾をサイロに貯蔵する「ストア」の3つのタスクがある。 今大会では,自動ロボットの導入が必須となり,より高度な技術が必要とされた。豊橋技術科学大学が大会初の3連覇 エントリー総数は42チーム。この中から書類確認と二度にわたるビデオ審査を通過した18チームが本大会に出場した。 本大会では3チーム毎,6グループに分かれてリーグ戦を戦い,各グループの1位と2位の得点上位2チームを加えた計8チームが決勝トーナメントに進んだ。 決勝では,豊橋技術科学大学が熱戦を制し,同大会では初めてとなる3連覇を成し遂げ,ABUロボコン2024への出場を決めた。 鹿島賞には見事ベスト4に進出した新潟大学(科学技術研究部)を選出。特にR1の苗を植える動作が美しく,実践的な点を高く評価した。籾と空籾エリア1エリア2エリア3R1技能タイプ:手動ロボット特徴:苗を4本同時に保持でき,常に同じ方向を向いたまま,植える動作を行う。回収した籾を投げ入れる際は,ローラーを上側だけ内向きに低速回転させることでバックスピンをかける。ココに自信アリ!:苗の設置速度。計3動作,約30∼40秒でエリア1のタスクを完了させられる。R1の一次機体苗鹿島賞に輝いた新潟大学チームメンバーとピットクルーの皆さん
18KAJIMA202410 ロボットコンテスト(ロボコン)は,競技課題に従い,チームでロボットを製作しアイデアや技術力を競う。機械・電気・制御などの知識だけではなく,チームワークや戦略も重要となる。 様々なロボコンの中でも,NHK学生ロボコンは,規模の大きさや,優勝すると日本代表として世界大会「ABU※1ロボコン」に出場できることから,特に注目を集める大会だ。 若く未来あるエンジニアたちがしのぎを削るロボコンは,土木分野で「現場の工場化」,建築分野で「作業の半分はロボットと」を掲げる当社にとっても親和性が高い。競技テーマ「HarvestDay」 今大会では,ABUロボコン2024が開催されるベトナムの棚田からインスピレーションを得たフィールドが設けられ,苗を植えて稲を収穫するまでを模した課題が与えられた。フィールドでロボットが扱う対象物は3種類。塩ビパイプで見立てた「苗」,赤または青のボールで見立てた「籾」,紫のボールの「空籾」である。 競技は,12本の苗をラックからプランティングゾーンに植える「プラント」,ハーベスティングゾーンから12個の籾と空籾を収穫してルール概要(一部抜粋)●大会に出場できるのはチームメンバー3名とピットクルー上限3名まで●【ロボット1(R1)】エリア1,2に進入可。手動ロボット,自動ロボットどちらでもOK。手動ロボットは無線でチームメンバーが操作する。自動ロボットはチームメンバーの操作なしで動く●【ロボット2(R2)】エリア1,2,3に進入できる。自動ロボットでなければならない当社は2024年からNHK学生ロボコン(主催:NHK,NHKエンタープライズ)に協賛する。6月9日に開催された本大会では,「鹿島建設特別賞」(以下,鹿島賞)を設け,ロボットづくりに情熱を注ぐ学生たちを応援した。今回は,鹿島賞を受賞した「新潟大学科学技術研究部」の皆さんへの取材をとおして,ロボコンの魅力を探る。プランティングゾーンサイロゾーンストレージゾーンハーベスティングゾーン#KAJIMA#kajimaステキシェアいいね!#NHK学生ロボコン2024アイデアを形に!夢は現実に!大会の様子。新潟大学メンバー(フィールド手前)が奮闘中※1アジア太平洋放送連合ストレージゾーンに入れる「ハーベスト」,ストレージゾーンの籾をサイロに貯蔵する「ストア」の3つのタスクがある。 今大会では,自動ロボットの導入が必須となり,より高度な技術が必要とされた。豊橋技術科学大学が大会初の3連覇 エントリー総数は42チーム。この中から書類確認と二度にわたるビデオ審査を通過した18チームが本大会に出場した。 本大会では3チーム毎,6グループに分かれてリーグ戦を戦い,各グループの1位と2位の得点上位2チームを加えた計8チームが決勝トーナメントに進んだ。 決勝では,豊橋技術科学大学が熱戦を制し,同大会では初めてとなる3連覇を成し遂げ,ABUロボコン2024への出場を決めた。 鹿島賞には見事ベスト4に進出した新潟大学(科学技術研究部)を選出。特にR1の苗を植える動作が美しく,実践的な点を高く評価した。籾と空籾エリア1エリア2エリア3R1技能タイプ:手動ロボット特徴:苗を4本同時に保持でき,常に同じ方向を向いたまま,植える動作を行う。回収した籾を投げ入れる際は,ローラーを上側だけ内向きに低速回転させることでバックスピンをかける。ココに自信アリ!:苗の設置速度。計3動作,約30∼40秒でエリア1のタスクを完了させられる。R1の一次機体苗鹿島賞に輝いた新潟大学チームメンバーとピットクルーの皆さん
 19KAJIMA202410 8月7日,当社は鹿島賞受賞をご縁として,新潟大学科学技術部などの学生と関係者を,大河津分水路新第二床固改築Ⅰ期工事(新潟県長岡市)の現場見学会に招待した。 大河津分水路は,日本一の長さを誇る信濃川を越後平野中央部で分岐することにより一部を日本海へ流し,信濃川下流部の洪水被害の低減を目的としてつくられた全長9.1kmの人工河川。本工事は「令和の大改修」と呼ばれる分水路の改修事業のうち,老朽化の進む現在の第二床固下流220mの位置に,新第二床固を新たに建設する。当日は工事のPR施設「にとこみえ∼る館」や,鋼殻ケーソンのコンクリート打設作業などを見学台より見学した。 ―科学技術研究部について松田 2006年創部で,現在部員数は約30名です。うちNHK学生ロボコンに参加する上級生が10名。1・2年生は下級生用の大会に出て学んでもらい,NHK学生ロボコンを目指します。週5日ほど活動しています。部員はマイペースで,色々な考えを持った人がいます。自分のつくりたいものがある人,制御などの知識を増やしたい人,単位が取れる特殊な部活なので,単位が欲しい人もいます(笑)。高橋 単位が取れるので軽い気持ちで入りましたが,1・2年生にも大会があるので,やってみたら結構面白かったです。―今大会用ロボットの製作スケジュールは?松田 昨年9月にルール発表があり,6月の大会までロボットをつくり込みました。初めに製作期間を長く取る年もありますが,今年はつくって直してを繰り返し,3回ロボットを製作しました。細沼 一次機体(初号機)のアイデア出しは,なかなか形にならず時間がかかりました。R1はタスクが明確だったので,これなら強いだろうという機能を盛り込み,そこから不要なものを削っていきました。松田 逆にR2は最終の機体に比べると一次機体はシンプルです。自動ロボットだったので,最低限の機能を搭載し,思い通り動くのかというところに着目していました。昨年は予選敗退だったので,とにかく1勝することを目標に取り組みました。―製作だけではなく,練習も大変そうですね松田 例年は毎日フィールドを設置・撤去しながら練習していました。今年は段差が2段あり,フィールドの出来が自動ロボットの動きに影響するので,ルール発表から約1ヵ月後には大学施設の一部に常設させてもらい,毎日練習できる環境を準備しました。細沼 本番前2ヵ月間はGW返上で色々な想定をしながらみっちり練習しましたね。―本番は練習どおりだった?細沼 R1は練習で動かしていたときより本番の方が正確な動きができました。本番用のフィールドの正確さのおかげなのかも。松田 R2は本番にセンサーなどが不具合を起こしていました。練習環境の段差を甘めにつくったせいか,坂でひっかかってしまった…でも本番で不具合が起きたときには,これまでの経験則をたよりに,修正できた試合もありました。―次回への意気込み,後輩への期待を教えてください高橋 自動化では,機体がどこにいるか認識することや,固定のcolumn#ムアバン(MuaVang/HarvestGlory) #米どころ新潟 #鹿島はつなぐ棚田遺産のオフィシャルサポーターinterview祝鹿島賞受賞!新潟大学科学技術研究部にロボコン期間を振り返ってもらいました 見学応対したのは関原真之介機電課長代理と加賀山智機電担当。見学後には両機電担当者が現場で主導した生産性向上を目指す取組み,「バックホウ台船による河川の掘削工事において河床形状をリアルタイムに可視化する技術」と「AIとドローンを組み合わせた資機材管理」を紹介した。参加した学生からは,解析ソナーの精度や,AIシステム,新しい技術の導入による生産性向上への効果など,各々専攻分野に関する視点も絡めながら,鋭い質問や意見が飛び交った。見学後,松田さんに話を聞くと,「工事現場の見学は初めてでした。先輩はメーカーなどに就職する方が多く,建設業になじみが無かったので,今日のお話は新鮮でした」と感想を教えてくれた。新潟大学の学生さんを現場見学会に招待!現場を一望できる見学台にて現場見学後の質疑タイム今大会のチームメンバー。左から松田拓未さん(部代表・4年生),細沼舞都さん(4年生),高橋優輔さん(次期部代表・3年生)位置を動くことが上手くいった。今回の経験を活かし,新しいものは積極的に取り入れて,より良いものをつくりたいです。細沼 これまでの技術を今後も継承してどんどん強くなってほしいです。松田 自動化の指定が無かった頃から,強いチームは自動ロボットで参戦していました。その技術力に先輩方は悔しさを感じると同時に,自動化の可能性に注目し,私たちに自動化に応用可能な技術を教えてくれました。そして私たちの代で自動化がルールになった。その巡り合わせから,教育も大切だと考えるようになりました。技術継承を大切に,勝てる部になってほしいと思います。R2技能タイプ:自動ロボット特徴:正方形内部の籾の並びや,サイロの配置は最初にカメラで認識する。その後は動的な経路生成にはたよらずに,固定動作で最初に組まれた経路で動く。ココに自信アリ!:エリア3の最初に設置された「6球」を認識してストアする速度。R2の一次機体
19KAJIMA202410 8月7日,当社は鹿島賞受賞をご縁として,新潟大学科学技術部などの学生と関係者を,大河津分水路新第二床固改築Ⅰ期工事(新潟県長岡市)の現場見学会に招待した。 大河津分水路は,日本一の長さを誇る信濃川を越後平野中央部で分岐することにより一部を日本海へ流し,信濃川下流部の洪水被害の低減を目的としてつくられた全長9.1kmの人工河川。本工事は「令和の大改修」と呼ばれる分水路の改修事業のうち,老朽化の進む現在の第二床固下流220mの位置に,新第二床固を新たに建設する。当日は工事のPR施設「にとこみえ∼る館」や,鋼殻ケーソンのコンクリート打設作業などを見学台より見学した。 ―科学技術研究部について松田 2006年創部で,現在部員数は約30名です。うちNHK学生ロボコンに参加する上級生が10名。1・2年生は下級生用の大会に出て学んでもらい,NHK学生ロボコンを目指します。週5日ほど活動しています。部員はマイペースで,色々な考えを持った人がいます。自分のつくりたいものがある人,制御などの知識を増やしたい人,単位が取れる特殊な部活なので,単位が欲しい人もいます(笑)。高橋 単位が取れるので軽い気持ちで入りましたが,1・2年生にも大会があるので,やってみたら結構面白かったです。―今大会用ロボットの製作スケジュールは?松田 昨年9月にルール発表があり,6月の大会までロボットをつくり込みました。初めに製作期間を長く取る年もありますが,今年はつくって直してを繰り返し,3回ロボットを製作しました。細沼 一次機体(初号機)のアイデア出しは,なかなか形にならず時間がかかりました。R1はタスクが明確だったので,これなら強いだろうという機能を盛り込み,そこから不要なものを削っていきました。松田 逆にR2は最終の機体に比べると一次機体はシンプルです。自動ロボットだったので,最低限の機能を搭載し,思い通り動くのかというところに着目していました。昨年は予選敗退だったので,とにかく1勝することを目標に取り組みました。―製作だけではなく,練習も大変そうですね松田 例年は毎日フィールドを設置・撤去しながら練習していました。今年は段差が2段あり,フィールドの出来が自動ロボットの動きに影響するので,ルール発表から約1ヵ月後には大学施設の一部に常設させてもらい,毎日練習できる環境を準備しました。細沼 本番前2ヵ月間はGW返上で色々な想定をしながらみっちり練習しましたね。―本番は練習どおりだった?細沼 R1は練習で動かしていたときより本番の方が正確な動きができました。本番用のフィールドの正確さのおかげなのかも。松田 R2は本番にセンサーなどが不具合を起こしていました。練習環境の段差を甘めにつくったせいか,坂でひっかかってしまった…でも本番で不具合が起きたときには,これまでの経験則をたよりに,修正できた試合もありました。―次回への意気込み,後輩への期待を教えてください高橋 自動化では,機体がどこにいるか認識することや,固定のcolumn#ムアバン(MuaVang/HarvestGlory) #米どころ新潟 #鹿島はつなぐ棚田遺産のオフィシャルサポーターinterview祝鹿島賞受賞!新潟大学科学技術研究部にロボコン期間を振り返ってもらいました 見学応対したのは関原真之介機電課長代理と加賀山智機電担当。見学後には両機電担当者が現場で主導した生産性向上を目指す取組み,「バックホウ台船による河川の掘削工事において河床形状をリアルタイムに可視化する技術」と「AIとドローンを組み合わせた資機材管理」を紹介した。参加した学生からは,解析ソナーの精度や,AIシステム,新しい技術の導入による生産性向上への効果など,各々専攻分野に関する視点も絡めながら,鋭い質問や意見が飛び交った。見学後,松田さんに話を聞くと,「工事現場の見学は初めてでした。先輩はメーカーなどに就職する方が多く,建設業になじみが無かったので,今日のお話は新鮮でした」と感想を教えてくれた。新潟大学の学生さんを現場見学会に招待!現場を一望できる見学台にて現場見学後の質疑タイム今大会のチームメンバー。左から松田拓未さん(部代表・4年生),細沼舞都さん(4年生),高橋優輔さん(次期部代表・3年生)位置を動くことが上手くいった。今回の経験を活かし,新しいものは積極的に取り入れて,より良いものをつくりたいです。細沼 これまでの技術を今後も継承してどんどん強くなってほしいです。松田 自動化の指定が無かった頃から,強いチームは自動ロボットで参戦していました。その技術力に先輩方は悔しさを感じると同時に,自動化の可能性に注目し,私たちに自動化に応用可能な技術を教えてくれました。そして私たちの代で自動化がルールになった。その巡り合わせから,教育も大切だと考えるようになりました。技術継承を大切に,勝てる部になってほしいと思います。R2技能タイプ:自動ロボット特徴:正方形内部の籾の並びや,サイロの配置は最初にカメラで認識する。その後は動的な経路生成にはたよらずに,固定動作で最初に組まれた経路で動く。ココに自信アリ!:エリア3の最初に設置された「6球」を認識してストアする速度。R2の一次機体