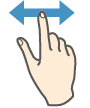写真 ― 鈴木久雄文 ― 五十嵐太郎いまやドラマ「魔法のリノベ」(2022年)が,フジテレビで月曜日の夜に放映されるほど,リノベーションという言葉は市民権を得ているが,日本においてこの言葉が普及したのは,21世紀になってからである。建築界では『SD』(鹿島出版会)1999年10月号の特集「東京リノベーション」が注目を集める大きなきっかけとなり,筆者も2000年代初頭に「リノベーション・スタディーズ」という連続シンポジウムを企画した(LIXIL出版から2003年に書籍化)。戦後の高度経済成長からバブル期まで,激しいスクラップ・アンド・ビルドが続いた状況がいったん落ち着き,リノベーションの選択肢が重要視されたわけだが,ヨーロッパでは必ずしもめずらしいものではない。 バルセロナには,ニノト市場,サン・アントニ市場,旧ボルン市場など,リノベーションされた市場がいくつか存在するが,特に有名なのは,サンタ・カテリナ市場(2005年)だろう。地元の建築家,エンリク・ミラーレスが手がけ,彼が45歳という若さで2000年に亡くなったため,EMBTという事務所を共同主宰していた妻のベネデッタ・タグリアブエが完成させたプロジェクトである。19世紀に建設されたバルセロナで最初の屋根付き市場のペディメント(三角破風)をもち,アーチを反復するクラシックな外壁はおおむね残しながら,その上部にうねる屋根を架けたり,イレギュラーな形のヴォリュームを挿入したものだ。高い位置からカラフルなモザイク・タイルに覆われた屋根を見下ろすと,軽やかなファブリックのドレープのようであり,異なる分野のパラレルな関係を提示した「スキン+ボーンズ 1980年代以降の建築とファッション」展(国立新美術館,2007年)でも紹介されている。なお,光沢のある六角形の陶製タイルは,野菜や果物のイメージを抽象化したグラフィックのパターンで配列された。 ヘルツォーク&ド・ムーロンは,ロンドンで試みたリノベーション,すなわちテート・モダン(2000年)で知られるが,マドリッドやブルックリンでも発電所を改造している。一般的に産業施設を転用する際,スケールの大きさから,現代アートとの相性が良い。マドリッドの文化センター,カイシャ・フォーラムは,瓦造の外壁を残しつつ,その上に赤茶色の鉄さびのファサードを継ぎ足し,内部は現代的な空間につくりかえたものだ。もっとも,構造と切り離された瓦の壁は,一階レベルをガラスの開口とし,重いヴォリュームが宙に浮いたような印象を与える。また発電所がもつ三角屋根のシルエットと,増築部分における凸凹のスカイラインによる新旧の組み合わせも,好対照をなし,視覚的なインパクトをもたらす。第10回 リノベーションという手法26KAJIMA202501
写真 ― 鈴木久雄文 ― 五十嵐太郎いまやドラマ「魔法のリノベ」(2022年)が,フジテレビで月曜日の夜に放映されるほど,リノベーションという言葉は市民権を得ているが,日本においてこの言葉が普及したのは,21世紀になってからである。建築界では『SD』(鹿島出版会)1999年10月号の特集「東京リノベーション」が注目を集める大きなきっかけとなり,筆者も2000年代初頭に「リノベーション・スタディーズ」という連続シンポジウムを企画した(LIXIL出版から2003年に書籍化)。戦後の高度経済成長からバブル期まで,激しいスクラップ・アンド・ビルドが続いた状況がいったん落ち着き,リノベーションの選択肢が重要視されたわけだが,ヨーロッパでは必ずしもめずらしいものではない。 バルセロナには,ニノト市場,サン・アントニ市場,旧ボルン市場など,リノベーションされた市場がいくつか存在するが,特に有名なのは,サンタ・カテリナ市場(2005年)だろう。地元の建築家,エンリク・ミラーレスが手がけ,彼が45歳という若さで2000年に亡くなったため,EMBTという事務所を共同主宰していた妻のベネデッタ・タグリアブエが完成させたプロジェクトである。19世紀に建設されたバルセロナで最初の屋根付き市場のペディメント(三角破風)をもち,アーチを反復するクラシックな外壁はおおむね残しながら,その上部にうねる屋根を架けたり,イレギュラーな形のヴォリュームを挿入したものだ。高い位置からカラフルなモザイク・タイルに覆われた屋根を見下ろすと,軽やかなファブリックのドレープのようであり,異なる分野のパラレルな関係を提示した「スキン+ボーンズ 1980年代以降の建築とファッション」展(国立新美術館,2007年)でも紹介されている。なお,光沢のある六角形の陶製タイルは,野菜や果物のイメージを抽象化したグラフィックのパターンで配列された。 ヘルツォーク&ド・ムーロンは,ロンドンで試みたリノベーション,すなわちテート・モダン(2000年)で知られるが,マドリッドやブルックリンでも発電所を改造している。一般的に産業施設を転用する際,スケールの大きさから,現代アートとの相性が良い。マドリッドの文化センター,カイシャ・フォーラムは,瓦造の外壁を残しつつ,その上に赤茶色の鉄さびのファサードを継ぎ足し,内部は現代的な空間につくりかえたものだ。もっとも,構造と切り離された瓦の壁は,一階レベルをガラスの開口とし,重いヴォリュームが宙に浮いたような印象を与える。また発電所がもつ三角屋根のシルエットと,増築部分における凸凹のスカイラインによる新旧の組み合わせも,好対照をなし,視覚的なインパクトをもたらす。第10回 リノベーションという手法26KAJIMA202501
 サンタ・カテリナ市場(バルセロナ)27KAJIMA202501
サンタ・カテリナ市場(バルセロナ)27KAJIMA202501
 カイシャ・フォーラム(マドリッド)28KAJIMA202501
カイシャ・フォーラム(マドリッド)28KAJIMA202501
 デザイン―江川拓未(鹿島出版会)鈴木久雄 すずき・ひさお建築写真家。1957年生まれ。バルセロナ在住。1986年から現在まで,世界的な建築雑誌『ElCroquis(エル・クロッキー)』の専属カメラマンとして活躍。日本では1988年,鹿島出版会の雑誌『SD』「ガウディとその子弟たち」の撮影を行って以来,世界の著名建築家を撮影し続けている。ほかに『a+u』「ラ・ルース・マヒカ―写真家,鈴木久雄」504号,2012年,「スーパーモデル―鈴木久雄が写す建築模型」522号,2014年など。五十嵐太郎 いがらし・たろう建築史家,建築批評家。1967年生まれ。東北大学大学院教授。近現代建築・都市・建築デザイン,アートやサブカルチャーにも造詣が深く,多彩な評論・キュレーション活動,展覧会監修で知られる。これまでヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2008日本館コミッショナー,あいちトリエンナーレ2013芸術監督などを歴任。著書に『被災地を歩きながら考えたこと』『建築の東京』『現代日本建築家列伝』,編著『レム・コールハースは何を変えたのか』など多数。29KAJIMA202501
デザイン―江川拓未(鹿島出版会)鈴木久雄 すずき・ひさお建築写真家。1957年生まれ。バルセロナ在住。1986年から現在まで,世界的な建築雑誌『ElCroquis(エル・クロッキー)』の専属カメラマンとして活躍。日本では1988年,鹿島出版会の雑誌『SD』「ガウディとその子弟たち」の撮影を行って以来,世界の著名建築家を撮影し続けている。ほかに『a+u』「ラ・ルース・マヒカ―写真家,鈴木久雄」504号,2012年,「スーパーモデル―鈴木久雄が写す建築模型」522号,2014年など。五十嵐太郎 いがらし・たろう建築史家,建築批評家。1967年生まれ。東北大学大学院教授。近現代建築・都市・建築デザイン,アートやサブカルチャーにも造詣が深く,多彩な評論・キュレーション活動,展覧会監修で知られる。これまでヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2008日本館コミッショナー,あいちトリエンナーレ2013芸術監督などを歴任。著書に『被災地を歩きながら考えたこと』『建築の東京』『現代日本建築家列伝』,編著『レム・コールハースは何を変えたのか』など多数。29KAJIMA202501