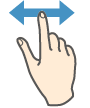04KAJIMA202502鹿島建設中興の祖とたたえられる鹿島守之助会長。実業家・政治家・学者という3つの顔を持ち,国内外に数多くの業績を残している。本年は1975年の逝去から50年を迎える。若き日に海外の文学や哲学に親しみ,国際関係や外交史の分野における研究で深めた広範な視点と見識,さらには政治家として自らの理想の実現に向けた努力と経験をもとに,当社の経営の舵を取り,建設業の近代化にも貢献した。今月の特集では,鹿島守之助会長の歩みと功績をあらためて振り返り,現在も当社に引き継がれているその思想と哲学を確認する。鹿島守之助没後50年特集実業家政治家学者
04KAJIMA202502鹿島建設中興の祖とたたえられる鹿島守之助会長。実業家・政治家・学者という3つの顔を持ち,国内外に数多くの業績を残している。本年は1975年の逝去から50年を迎える。若き日に海外の文学や哲学に親しみ,国際関係や外交史の分野における研究で深めた広範な視点と見識,さらには政治家として自らの理想の実現に向けた努力と経験をもとに,当社の経営の舵を取り,建設業の近代化にも貢献した。今月の特集では,鹿島守之助会長の歩みと功績をあらためて振り返り,現在も当社に引き継がれているその思想と哲学を確認する。鹿島守之助没後50年特集実業家政治家学者
 05KAJIMA202502没後50年の「追懐の会」が催された 昨年12月3日,「鹿島守之助会長没後50年追懐の会」がホテルイースト21「永代の間」(東京都江東区)で開かれ,鹿島家関係者,当社役員,顧問ら111人が出席した。 会のはじめに施主である鹿島顧問の挨拶,続いて天野社長より鹿島守之助会長の功績について紹介があった。献杯の後は,逝去の3年後(1978年)に制作された映像「鹿島守之助創造の生涯」(短縮版)や1958年にラジオ岩手で放送された「春及廬随談」に映像をのせた「鹿島守之助『事業成功の秘 父鹿島守之助が亡くなりましてから50年,半世紀を経過してなお,会社経営理念の支柱として,その存在感は生き続けております。 鹿島建設には,家族的な雰囲気の中で皆が会社を想い,誠実に仕事に向き合う独特な社風が培われております。会社経営には,技術革新や経営手法も重要ではありますが,それにも増して,この一朝一夕には醸成できない企業風土を,役員・社員の皆様が次世代に引き継ぎ,かけがえのない鹿島の企業文化を育み,会社をさらに発展させていくことを心から願っております。 鹿島昭一最高相談役も,その社風を守るという創業家としての責務を,両親から受け継ぎ,終生,強い自覚と使命感をもって全ういたしました。 会社にはこれから先,幾多の変遷があるかと思いますが,鹿島守之助会長の五十回忌に当たり,改めて,今後とも鹿島創業家としての責務を果たして参りたいと存じております。訣二十ヵ条を語る』」が上映され,南谷元副社長より追懐談が語られた。会の締めとして押味会長より閉会の辞が述べられた。 会場向かいに設けられた展示室には,生前鹿島守之助会長が使用していた机や数々の思い出の品が並べられ,写真パネルとともに,勲記・勲章が飾られた。大型陶板の立像や卯女名誉会長と並んだ胸像には,とくにOBの方々から往時を懐かしむ声が聞かれた。 また,出席者には鹿島守之助会長の事績をまとめた記念冊子『鹿島守之助』が配られた。※本特集は,記念冊子『鹿島守之助』の内容を抜粋,要約したものです鹿島守之助会長五十回忌を迎えて施主 鹿島公子顧問記念冊子『鹿島守之助』の表紙。題字は小野左鵞氏による(問い合わせ先:本社資料センター)
05KAJIMA202502没後50年の「追懐の会」が催された 昨年12月3日,「鹿島守之助会長没後50年追懐の会」がホテルイースト21「永代の間」(東京都江東区)で開かれ,鹿島家関係者,当社役員,顧問ら111人が出席した。 会のはじめに施主である鹿島顧問の挨拶,続いて天野社長より鹿島守之助会長の功績について紹介があった。献杯の後は,逝去の3年後(1978年)に制作された映像「鹿島守之助創造の生涯」(短縮版)や1958年にラジオ岩手で放送された「春及廬随談」に映像をのせた「鹿島守之助『事業成功の秘 父鹿島守之助が亡くなりましてから50年,半世紀を経過してなお,会社経営理念の支柱として,その存在感は生き続けております。 鹿島建設には,家族的な雰囲気の中で皆が会社を想い,誠実に仕事に向き合う独特な社風が培われております。会社経営には,技術革新や経営手法も重要ではありますが,それにも増して,この一朝一夕には醸成できない企業風土を,役員・社員の皆様が次世代に引き継ぎ,かけがえのない鹿島の企業文化を育み,会社をさらに発展させていくことを心から願っております。 鹿島昭一最高相談役も,その社風を守るという創業家としての責務を,両親から受け継ぎ,終生,強い自覚と使命感をもって全ういたしました。 会社にはこれから先,幾多の変遷があるかと思いますが,鹿島守之助会長の五十回忌に当たり,改めて,今後とも鹿島創業家としての責務を果たして参りたいと存じております。訣二十ヵ条を語る』」が上映され,南谷元副社長より追懐談が語られた。会の締めとして押味会長より閉会の辞が述べられた。 会場向かいに設けられた展示室には,生前鹿島守之助会長が使用していた机や数々の思い出の品が並べられ,写真パネルとともに,勲記・勲章が飾られた。大型陶板の立像や卯女名誉会長と並んだ胸像には,とくにOBの方々から往時を懐かしむ声が聞かれた。 また,出席者には鹿島守之助会長の事績をまとめた記念冊子『鹿島守之助』が配られた。※本特集は,記念冊子『鹿島守之助』の内容を抜粋,要約したものです鹿島守之助会長五十回忌を迎えて施主 鹿島公子顧問記念冊子『鹿島守之助』の表紙。題字は小野左鵞氏による(問い合わせ先:本社資料センター)
 鹿島守之助略年譜06KAJIMA2025021896年(明治29年)2月2日,兵庫県揖保郡半田村(現・たつの市揖保川町)新在家,永富敏夫・くわんの四男に生まれる1920年(大正9年)東京帝国大学法学部政治学科卒業,高等文官試験外交科合格,外務省に入り通商局第二課勤務1922年(大正11年)ドイツ国在勤を命ぜられる/在ベルリン日本大使館勤務1925年(大正14年)ドイツより帰朝,欧米局勤務1926年(昭和元年)イタリア国在勤を命ぜられる1927年(昭和2年)鹿島精一長女卯女と結婚,鹿島家の養嗣子となる/在ローマ日本大使館勤務1930年(昭和5年)依願退官/衆議院選挙に敗れる1934年(昭和9年)東京帝国大学より「世界大戦原因の研究」により法学博士の学位を受ける1936年(昭和11年)鹿島組取締役に就任/「事業成功の秘訣二十ヵ条」作成1938年(昭和13年)鹿島組社長に就任1940年(昭和15年)満州鹿島組設立1941年(昭和16年)かたばみ商事(現・かたばみ)を設立1946年(昭和21年)日本最大のアースダム・山王海ダム着工1947年(昭和22年)養父精一病没/「株式会社鹿島組」の社名を「鹿島建設株式会社」と変更/東京を救った利根川決潰緊急締切工事(内務省より特命,後に建設大臣から感謝状が贈られる)/大興物産を設立1949年(昭和24年)鹿島建設技術研究所設立,所長に就任/旧軽井沢ゴルフ倶楽部設立,再開場1950年(昭和25年)米国・モリソン・クヌードセン社と提携1951年(昭和26年)土木工業協会初代会長に就任/拓殖大学教授に就任1952年(昭和27年)電力建設協会初代会長,発電水力協会設立にあたり副会長に就任,全国建設業協会常任理事,日本経営者団体連盟財務理事,経済団体連合会理事に就任/日本初のアーチダム・上椎葉ダム着工/米軍発注工事のクレーム問題が承認される1953年(昭和28年)参議院議員に当選(全国区4位)1954年(昭和29年)列国議会同盟会議(ウィーン)に出席,日本代表として演説/欧米視察/全国社会保険協会連合会会長に就任/戦後初の海外工事・ビルマ(現・ミャンマー)・バルーチャン発電所着工1955年(昭和30年)社団法人海外建設協力会(現・海外建設協会)設立1956年(昭和31年)財団法人鹿島育英会設立/日本初の原子炉・日本原子力研究所第一号原子炉着工1957年(昭和32年)国務大臣北海道開発庁長官に就任/鹿島建設社長をはじめ会社・団体等の役職を辞任/夫人鹿島卯女鹿島建設社長に就任/鹿島建設会長に就任/鹿島研究所創設/藍綬褒章を受章1959年(昭和34年)著書『日英外交史』『日本外交政策の史的考察』に対し日本学士院賞受賞/参議院議員に再選(全国区2位),参議院外務委員長に就任1960年(昭和35年)自民党対外経済協力特別委員長に就任/列国議会同盟会議(東京)に出席,日本代表として演説1961年(昭和36年)自民党外交調査会会長に就任(4期務める)/米国,南米,欧州各国の外交調査活動視察/株式を東京店頭市場に公開1962年(昭和37年)自民党経済調査会会長に就任1963年(昭和38年)八千代エンジニヤリング,ケミカルグラウト,鹿島研究所出版会 (現・鹿島出版会),日本技術映画社(現・Kプロビジョン)設立/年間受注高世界第1位となる1964年(昭和39年)紺綬褒章を受章/ロサンゼルスにKII社を設立/新宮殿着工1965年(昭和40年)参議院議員に3選(全国区1位)/日本初の超高層ビル・霞が関ビル着工1966年(昭和41年)夫人鹿島卯女副会長に就任,渥美健夫社長に就任/財団法人鹿島平和研究所設立/勲一等に叙せられ瑞宝章を受章勲一等瑞宝章親授式を終えて,卯女夫人とともに(1966年)
鹿島守之助略年譜06KAJIMA2025021896年(明治29年)2月2日,兵庫県揖保郡半田村(現・たつの市揖保川町)新在家,永富敏夫・くわんの四男に生まれる1920年(大正9年)東京帝国大学法学部政治学科卒業,高等文官試験外交科合格,外務省に入り通商局第二課勤務1922年(大正11年)ドイツ国在勤を命ぜられる/在ベルリン日本大使館勤務1925年(大正14年)ドイツより帰朝,欧米局勤務1926年(昭和元年)イタリア国在勤を命ぜられる1927年(昭和2年)鹿島精一長女卯女と結婚,鹿島家の養嗣子となる/在ローマ日本大使館勤務1930年(昭和5年)依願退官/衆議院選挙に敗れる1934年(昭和9年)東京帝国大学より「世界大戦原因の研究」により法学博士の学位を受ける1936年(昭和11年)鹿島組取締役に就任/「事業成功の秘訣二十ヵ条」作成1938年(昭和13年)鹿島組社長に就任1940年(昭和15年)満州鹿島組設立1941年(昭和16年)かたばみ商事(現・かたばみ)を設立1946年(昭和21年)日本最大のアースダム・山王海ダム着工1947年(昭和22年)養父精一病没/「株式会社鹿島組」の社名を「鹿島建設株式会社」と変更/東京を救った利根川決潰緊急締切工事(内務省より特命,後に建設大臣から感謝状が贈られる)/大興物産を設立1949年(昭和24年)鹿島建設技術研究所設立,所長に就任/旧軽井沢ゴルフ倶楽部設立,再開場1950年(昭和25年)米国・モリソン・クヌードセン社と提携1951年(昭和26年)土木工業協会初代会長に就任/拓殖大学教授に就任1952年(昭和27年)電力建設協会初代会長,発電水力協会設立にあたり副会長に就任,全国建設業協会常任理事,日本経営者団体連盟財務理事,経済団体連合会理事に就任/日本初のアーチダム・上椎葉ダム着工/米軍発注工事のクレーム問題が承認される1953年(昭和28年)参議院議員に当選(全国区4位)1954年(昭和29年)列国議会同盟会議(ウィーン)に出席,日本代表として演説/欧米視察/全国社会保険協会連合会会長に就任/戦後初の海外工事・ビルマ(現・ミャンマー)・バルーチャン発電所着工1955年(昭和30年)社団法人海外建設協力会(現・海外建設協会)設立1956年(昭和31年)財団法人鹿島育英会設立/日本初の原子炉・日本原子力研究所第一号原子炉着工1957年(昭和32年)国務大臣北海道開発庁長官に就任/鹿島建設社長をはじめ会社・団体等の役職を辞任/夫人鹿島卯女鹿島建設社長に就任/鹿島建設会長に就任/鹿島研究所創設/藍綬褒章を受章1959年(昭和34年)著書『日英外交史』『日本外交政策の史的考察』に対し日本学士院賞受賞/参議院議員に再選(全国区2位),参議院外務委員長に就任1960年(昭和35年)自民党対外経済協力特別委員長に就任/列国議会同盟会議(東京)に出席,日本代表として演説1961年(昭和36年)自民党外交調査会会長に就任(4期務める)/米国,南米,欧州各国の外交調査活動視察/株式を東京店頭市場に公開1962年(昭和37年)自民党経済調査会会長に就任1963年(昭和38年)八千代エンジニヤリング,ケミカルグラウト,鹿島研究所出版会 (現・鹿島出版会),日本技術映画社(現・Kプロビジョン)設立/年間受注高世界第1位となる1964年(昭和39年)紺綬褒章を受章/ロサンゼルスにKII社を設立/新宮殿着工1965年(昭和40年)参議院議員に3選(全国区1位)/日本初の超高層ビル・霞が関ビル着工1966年(昭和41年)夫人鹿島卯女副会長に就任,渥美健夫社長に就任/財団法人鹿島平和研究所設立/勲一等に叙せられ瑞宝章を受章勲一等瑞宝章親授式を終えて,卯女夫人とともに(1966年)
 07KAJIMA202502特集 鹿島守之助没後50年1967年(昭和42年)第1回鹿島平和賞をクーデンホーフ・カレルギー伯爵に授与する (第9回まで実施)1968年(昭和43年)本社を八重洲から元赤坂に移転/チリ共和国フレイ大統領よりオルデン・アル・メリト・グラン・クルス勲章を受章1969年(昭和44年)インドネシア共和国スハルト大統領より功労勲章を受章1970年(昭和45年)列国議会同盟会議(ハーグ)に出席,日本代表として演説/欧米視察1971年(昭和46年)ポルトガル共和国トーマス大統領よりインファンテ・ドン・エンリケ勲章大十字章を受章/最高裁判所新庁舎着工1972年(昭和47年)ドイツ連邦共和国ハイネマン大統領より大綬附大功労十字星章を受章1973年(昭和48年)大平外務大臣より『日本外交史』本巻34巻,別巻4巻刊行に対し表彰状を受彰/文化功労者として顕彰される1975年(昭和50年)イタリア共和国レオーネ大統領よりイタリア共和国有功勲章大十字章を受章12月3日逝去,隆徳院殿済国守道大居士/正三位勲一等旭日大綬章を贈られる1976年(昭和51年)財団法人鹿島学術振興財団設立1977年(昭和52年)八重洲ブックセンター設立授与された勲章一覧勲章オルデン・アル・メリト・グラン・クルス勲章功労章第三級インファンテ・ドン・エンリケ勲章大十字章(最高勲章)大功労十字星章有功勲章大十字章日本学士院賞勲一等瑞宝章文化功労者顕彰正三位勲一等旭日大綬章追贈授与年月日・国1968年11月29日チリ共和国1969年8月17日インドネシア共和国1971年10月28日ポルトガル共和国1972年10月26日ドイツ連邦共和国1975年5月21日イタリア共和国1959年5月6日1966年4月29日1973年11月13日1975年12月3日授与理由汎亜細亜,世界平和促進への努力がラテン・アメリカの連帯政策を提言しているチリ国フレイ大統領の構想と符合したことによる。日本人初。汎亜細亜理念に基づく平和と繁栄の国際協力関係を推進せんとする高邁な精神のもとに鹿島平和研究所を設置してその発揚に努め,(財)日本インドネシア協会会長として日イ両国間の友好親善に寄与したことによる。ポルトガル文化に関する世界の関心を深めるための努力に対して。ドイツに関する諸問題に対する日本国民一般の理解を増進し,世界平和の確立のため献身的努力をささげた。日伊両国の文化関係進展の活動がイタリア政府の人々の注意を喚起したことによる。『日英外交史』『日本外交政策の史的考察』に対して。多年にわたる政界,実業界,および学界における功績に対して。『日本外交史』本巻34巻,別巻4巻の刊行に対して。外交史学界に対する大きな貢献であるのみならず,わが国の外交の推進に資するところが少なくない。生前の功に照らして。インファンテ・ドン・エンリケ勲章大十字章受章(1971年)大綬附大功労十字星章受章(1972年)日本学士院賞賞状文化功労者顕彰状「追懐の会」で展示された勲章
07KAJIMA202502特集 鹿島守之助没後50年1967年(昭和42年)第1回鹿島平和賞をクーデンホーフ・カレルギー伯爵に授与する (第9回まで実施)1968年(昭和43年)本社を八重洲から元赤坂に移転/チリ共和国フレイ大統領よりオルデン・アル・メリト・グラン・クルス勲章を受章1969年(昭和44年)インドネシア共和国スハルト大統領より功労勲章を受章1970年(昭和45年)列国議会同盟会議(ハーグ)に出席,日本代表として演説/欧米視察1971年(昭和46年)ポルトガル共和国トーマス大統領よりインファンテ・ドン・エンリケ勲章大十字章を受章/最高裁判所新庁舎着工1972年(昭和47年)ドイツ連邦共和国ハイネマン大統領より大綬附大功労十字星章を受章1973年(昭和48年)大平外務大臣より『日本外交史』本巻34巻,別巻4巻刊行に対し表彰状を受彰/文化功労者として顕彰される1975年(昭和50年)イタリア共和国レオーネ大統領よりイタリア共和国有功勲章大十字章を受章12月3日逝去,隆徳院殿済国守道大居士/正三位勲一等旭日大綬章を贈られる1976年(昭和51年)財団法人鹿島学術振興財団設立1977年(昭和52年)八重洲ブックセンター設立授与された勲章一覧勲章オルデン・アル・メリト・グラン・クルス勲章功労章第三級インファンテ・ドン・エンリケ勲章大十字章(最高勲章)大功労十字星章有功勲章大十字章日本学士院賞勲一等瑞宝章文化功労者顕彰正三位勲一等旭日大綬章追贈授与年月日・国1968年11月29日チリ共和国1969年8月17日インドネシア共和国1971年10月28日ポルトガル共和国1972年10月26日ドイツ連邦共和国1975年5月21日イタリア共和国1959年5月6日1966年4月29日1973年11月13日1975年12月3日授与理由汎亜細亜,世界平和促進への努力がラテン・アメリカの連帯政策を提言しているチリ国フレイ大統領の構想と符合したことによる。日本人初。汎亜細亜理念に基づく平和と繁栄の国際協力関係を推進せんとする高邁な精神のもとに鹿島平和研究所を設置してその発揚に努め,(財)日本インドネシア協会会長として日イ両国間の友好親善に寄与したことによる。ポルトガル文化に関する世界の関心を深めるための努力に対して。ドイツに関する諸問題に対する日本国民一般の理解を増進し,世界平和の確立のため献身的努力をささげた。日伊両国の文化関係進展の活動がイタリア政府の人々の注意を喚起したことによる。『日英外交史』『日本外交政策の史的考察』に対して。多年にわたる政界,実業界,および学界における功績に対して。『日本外交史』本巻34巻,別巻4巻の刊行に対して。外交史学界に対する大きな貢献であるのみならず,わが国の外交の推進に資するところが少なくない。生前の功に照らして。インファンテ・ドン・エンリケ勲章大十字章受章(1971年)大綬附大功労十字星章受章(1972年)日本学士院賞賞状文化功労者顕彰状「追懐の会」で展示された勲章
 08KAJIMA202502不振の時代に 創立50周年*を迎えた鹿島組にとって,1929(昭和4)年はひとつの頂点だった。というのは,この後業績が下り坂へ向かうからである。鉄道と水力のほか事業の多角化として始めた建築工事でも特色のある建物を施工していたが,採算の合うものばかりではなかった。 この状況下で,1934(昭和9)年丹那トンネル(静岡県)完成後は安定した収入源もなくなり,ついに1936(昭和11)年,鹿島組は資本金を300万円から250万円に減資せざるを得なくなった。 鹿島守之助が社長として鹿島組の陣頭に立ったのは,このような時だった。副社長就任後に行う大改革 守之助が鹿島組の経営に直接関係したのは,会社が不況のどん底にあった1936年,取締役として就任してからである。この年,当時の社内報「鹿島組月報10月号」誌上で提示した「事業成功の秘訣二十ヵ条」は,彼の経営における思想・哲学をよく表している(p.11)。 翌1937年,副社長に就任,施工能力の増強と科学的管理の二大原則を強く提唱し,実践していく。科学的管理の骨子は予算統制と経営比較であり,施工能力の増強は大量生産によるコストダウンが可能になる。従来腹づもりや勘で運営されてきた請負業に,科学的管理法を導入することで立て直しを行った。マーケットリサーチの結果,それまで事業の従だった建築工事の分野にもっと積極的に進出するよう,将来性のある市場を対象に工事受注方針を大きく変換させた。 1938年7月,鹿島精一社長が会長に退き,守之助が社長に就任すると,改革した経営方針を一層推し進めていった。1936年度年間請負高1,000万円,取下高500万円だった鹿島組の業績は,1938年度請負高4,700万円,取下高2,600万円と大きく飛躍した。さらに,1940年度請負高1億3,000万円,1941年度は戦争の影響もあるが請負高1億9,000万円,取下高6,000万円となり,業績は急速に回復していった。資本金も1939年350万円,1941年550万円と増加した。戦後の混乱期を率いる 終戦を迎えた1945(昭和20)年8月15日の翌日,社長の守之助は「終戦処理要綱」を発表。今後の経営方針を示すとともに,戦後対策に関する訓示を行った。「土木建築業の使命は平時も戦時も同様に重要であるから,わが国復興のため常にその第一線に立つ気迫と自覚が必要である」と述べ,将来の建設に向け社の総力を傾けるよう示した。しかし,終戦後,鹿島組の手持ち工事が継続できたのは4分の1,さらに軍需補償の打ち切りで軍工事関係の未収金が取下げ不能に追い込まれる。鹿島組を含む建設業者の受けた打撃は大きく,産業復興の目途が立つまでの苦労は並大抵ではなかった。 全館焼失した八重洲(当時,京橋区槇町)の本店ビルを修理し,11月にそれまで軽井沢や松濤に移していた本店機構を戻すと,そこに海外からの引揚社員や軍隊から復員してきた社員が続々戻ってきた。しかし,守之助は社員の首を切らなかった。本店の復帰に際して「全員雇傭を押し通すことは私の誇りであり,また戦時中苦しみを共にしたみなさ空襲に遭った八重洲本店ビル(中央左上)(1945年) 利根川決潰緊急締切工事にて。前列左から,松尾梅雄所長,高橋嘉一郎常務,守之助社長,鹿島忠夫土木第二部長(1947年) 鹿島組人事部から「鹿島組外地在勤社員留守宅各位」へ向けて連絡を求める旨の公告が新聞各紙に何度か出された(1945年12月)社長就任の頃(1938年頃)鹿島組不振の時代や戦後の混乱期に経営の陣頭指揮をとり,建設業の近代化の礎を築いた鹿島守之助。その先見の明と実践は,日本で初めてJVを導入し根付かせ,クレーム問題によって建設業界の地位向上を成し遂げた。そして日本初の超高層ビル「霞が関ビル」の建設など,常に新しい時代のニーズに応え,将来の社の方針を示し続けた。鹿島守之助3つの顔実業家1*1840(天保11)年,鹿島岩吉が江戸中橋正木町で創業1880(明治13)年,鹿島組創立。東京京橋木挽町に本店を構え,鹿島岩蔵が初代組長となる
08KAJIMA202502不振の時代に 創立50周年*を迎えた鹿島組にとって,1929(昭和4)年はひとつの頂点だった。というのは,この後業績が下り坂へ向かうからである。鉄道と水力のほか事業の多角化として始めた建築工事でも特色のある建物を施工していたが,採算の合うものばかりではなかった。 この状況下で,1934(昭和9)年丹那トンネル(静岡県)完成後は安定した収入源もなくなり,ついに1936(昭和11)年,鹿島組は資本金を300万円から250万円に減資せざるを得なくなった。 鹿島守之助が社長として鹿島組の陣頭に立ったのは,このような時だった。副社長就任後に行う大改革 守之助が鹿島組の経営に直接関係したのは,会社が不況のどん底にあった1936年,取締役として就任してからである。この年,当時の社内報「鹿島組月報10月号」誌上で提示した「事業成功の秘訣二十ヵ条」は,彼の経営における思想・哲学をよく表している(p.11)。 翌1937年,副社長に就任,施工能力の増強と科学的管理の二大原則を強く提唱し,実践していく。科学的管理の骨子は予算統制と経営比較であり,施工能力の増強は大量生産によるコストダウンが可能になる。従来腹づもりや勘で運営されてきた請負業に,科学的管理法を導入することで立て直しを行った。マーケットリサーチの結果,それまで事業の従だった建築工事の分野にもっと積極的に進出するよう,将来性のある市場を対象に工事受注方針を大きく変換させた。 1938年7月,鹿島精一社長が会長に退き,守之助が社長に就任すると,改革した経営方針を一層推し進めていった。1936年度年間請負高1,000万円,取下高500万円だった鹿島組の業績は,1938年度請負高4,700万円,取下高2,600万円と大きく飛躍した。さらに,1940年度請負高1億3,000万円,1941年度は戦争の影響もあるが請負高1億9,000万円,取下高6,000万円となり,業績は急速に回復していった。資本金も1939年350万円,1941年550万円と増加した。戦後の混乱期を率いる 終戦を迎えた1945(昭和20)年8月15日の翌日,社長の守之助は「終戦処理要綱」を発表。今後の経営方針を示すとともに,戦後対策に関する訓示を行った。「土木建築業の使命は平時も戦時も同様に重要であるから,わが国復興のため常にその第一線に立つ気迫と自覚が必要である」と述べ,将来の建設に向け社の総力を傾けるよう示した。しかし,終戦後,鹿島組の手持ち工事が継続できたのは4分の1,さらに軍需補償の打ち切りで軍工事関係の未収金が取下げ不能に追い込まれる。鹿島組を含む建設業者の受けた打撃は大きく,産業復興の目途が立つまでの苦労は並大抵ではなかった。 全館焼失した八重洲(当時,京橋区槇町)の本店ビルを修理し,11月にそれまで軽井沢や松濤に移していた本店機構を戻すと,そこに海外からの引揚社員や軍隊から復員してきた社員が続々戻ってきた。しかし,守之助は社員の首を切らなかった。本店の復帰に際して「全員雇傭を押し通すことは私の誇りであり,また戦時中苦しみを共にしたみなさ空襲に遭った八重洲本店ビル(中央左上)(1945年) 利根川決潰緊急締切工事にて。前列左から,松尾梅雄所長,高橋嘉一郎常務,守之助社長,鹿島忠夫土木第二部長(1947年) 鹿島組人事部から「鹿島組外地在勤社員留守宅各位」へ向けて連絡を求める旨の公告が新聞各紙に何度か出された(1945年12月)社長就任の頃(1938年頃)鹿島組不振の時代や戦後の混乱期に経営の陣頭指揮をとり,建設業の近代化の礎を築いた鹿島守之助。その先見の明と実践は,日本で初めてJVを導入し根付かせ,クレーム問題によって建設業界の地位向上を成し遂げた。そして日本初の超高層ビル「霞が関ビル」の建設など,常に新しい時代のニーズに応え,将来の社の方針を示し続けた。鹿島守之助3つの顔実業家1*1840(天保11)年,鹿島岩吉が江戸中橋正木町で創業1880(明治13)年,鹿島組創立。東京京橋木挽町に本店を構え,鹿島岩蔵が初代組長となる
 09KAJIMA202502特集 鹿島守之助没後50年んに対する義務であると考える」と声明を発表し,12月には「全員雇傭制度確立に関する件」の通達を出した。近代化に導く 1947(昭和22)年2月6日,前年秋から体調を崩していた精一会長が73歳で逝去。鹿島組は名実ともに社長である守之助の時代に入る。 この年の9月16日夜,関東を襲ったキャサリン台風により利根川の堤防が崩れて東京下町の大半が水浸しになり,罹災者約100万人という大災害が起こる。内務省の直轄工事では間に合わず,鹿島組と間組に緊急締切工事が特命された。直ちに社長の守之助が自ら現場に駆けつけて総指揮にあたり,わずか20日間で復旧工事を完成させた。その後,会社をあげた昼夜通しての突貫工事に対し,建設大臣から感謝状が贈られた。 また同年12月26日,「株式会社鹿島組」は定款を変更し,社名を「鹿島建設株式会社」とした。 業界に先立ち,鹿島が初めて技術研究所を設けたのは1949(昭和24)年。戦時中財団法人として設立されたものだったが,戦後の経済混乱で経営が成り立たず,これを守之助が引き取り,鹿島の技術研究所として再発足させた。この技術研究所がその後の建設技術の向上,とくに超高層ビルの建設に非常に大きな役割を果たした。JVを初めて日本に導入 今でこそ複数の建設業者がJV(ジョイント・ベンチャー,共同企業体)を組むことは当たり前のように行われているが,1949(昭和24)年頃に,業者間でもその意味を理解している人はほとんどいなかった。 日本でもJVを導入しようと考えた守之助は,当時米軍軍政下だった沖縄の米軍施設工事で,日米業者によるJV構想を立て,米国のモリソン・クヌードセン社と交渉を始めた。同社は1930年フーバーダムで米国初のJVを実施した会社である。勝手がわからない状況で施工するリスクの分散という目的だったが,米国の一流業者との提携で,そのノウハウを吸収できるという狙いもあった。 この計画は,1950(昭和25)年モリソン・クヌードセン社が落札した工事に日本の業者3社(鹿島・竹中工務店・大林組)の連合が10%の割合で参加するという変則的な形で実現したが,その影響は非常に大きかった。とくに,大規模工事はJVを組織して請け負うという考えを日本の業者に植え付けたことである。この後,日本業者4社(鹿島を含む先の3社と大成建設)がJVを組み那覇飛行場の工事を落札したのをはじめ,内地でもさまざまな工事でJVが行われるようになっていった。鹿島が国に先駆けJVを推進したが,最初は導入に消極的だった建設省もその効果を認め,JVの普及を図るよう通達を出すに至った。 現在,JVが当たり前のように行われているのは,守之助の先見の明と実践によるものといえる。「鹿島建設」と看板が架け替えられた本社ビル(1947年) 中央区新川の技術研究所(1949年)仕事始め式にて(1965年) モリソン・クヌードセン本社入口前にて(1954年)八重洲本店ビル屋上にて(1938年)家族と正月を迎える(1935年)
09KAJIMA202502特集 鹿島守之助没後50年んに対する義務であると考える」と声明を発表し,12月には「全員雇傭制度確立に関する件」の通達を出した。近代化に導く 1947(昭和22)年2月6日,前年秋から体調を崩していた精一会長が73歳で逝去。鹿島組は名実ともに社長である守之助の時代に入る。 この年の9月16日夜,関東を襲ったキャサリン台風により利根川の堤防が崩れて東京下町の大半が水浸しになり,罹災者約100万人という大災害が起こる。内務省の直轄工事では間に合わず,鹿島組と間組に緊急締切工事が特命された。直ちに社長の守之助が自ら現場に駆けつけて総指揮にあたり,わずか20日間で復旧工事を完成させた。その後,会社をあげた昼夜通しての突貫工事に対し,建設大臣から感謝状が贈られた。 また同年12月26日,「株式会社鹿島組」は定款を変更し,社名を「鹿島建設株式会社」とした。 業界に先立ち,鹿島が初めて技術研究所を設けたのは1949(昭和24)年。戦時中財団法人として設立されたものだったが,戦後の経済混乱で経営が成り立たず,これを守之助が引き取り,鹿島の技術研究所として再発足させた。この技術研究所がその後の建設技術の向上,とくに超高層ビルの建設に非常に大きな役割を果たした。JVを初めて日本に導入 今でこそ複数の建設業者がJV(ジョイント・ベンチャー,共同企業体)を組むことは当たり前のように行われているが,1949(昭和24)年頃に,業者間でもその意味を理解している人はほとんどいなかった。 日本でもJVを導入しようと考えた守之助は,当時米軍軍政下だった沖縄の米軍施設工事で,日米業者によるJV構想を立て,米国のモリソン・クヌードセン社と交渉を始めた。同社は1930年フーバーダムで米国初のJVを実施した会社である。勝手がわからない状況で施工するリスクの分散という目的だったが,米国の一流業者との提携で,そのノウハウを吸収できるという狙いもあった。 この計画は,1950(昭和25)年モリソン・クヌードセン社が落札した工事に日本の業者3社(鹿島・竹中工務店・大林組)の連合が10%の割合で参加するという変則的な形で実現したが,その影響は非常に大きかった。とくに,大規模工事はJVを組織して請け負うという考えを日本の業者に植え付けたことである。この後,日本業者4社(鹿島を含む先の3社と大成建設)がJVを組み那覇飛行場の工事を落札したのをはじめ,内地でもさまざまな工事でJVが行われるようになっていった。鹿島が国に先駆けJVを推進したが,最初は導入に消極的だった建設省もその効果を認め,JVの普及を図るよう通達を出すに至った。 現在,JVが当たり前のように行われているのは,守之助の先見の明と実践によるものといえる。「鹿島建設」と看板が架け替えられた本社ビル(1947年) 中央区新川の技術研究所(1949年)仕事始め式にて(1965年) モリソン・クヌードセン本社入口前にて(1954年)八重洲本店ビル屋上にて(1938年)家族と正月を迎える(1935年)
 10KAJIMA202502かたばみの取組みScene2:完成した霞が関ビル(1968年)創業130年記念パーティ(ホテルオークラ)(1969年)霞が関ビル上棟式にて(1967年)クレーム問題と建設業の地位向上 戦後,日本の建設業は進駐軍関係の工事で生きられたといってもよい状態だった。しかし,材料の規格から施工の方法・慣習など,それまでの日本のやり方とは大きく異なり,さらに言葉の違いから契約を巡ってはさまざまなトラブルが発生した。また,そのような場合は,ほとんど例外なく日本側が譲歩させられていた。 鹿島でも進駐軍工事での紛争は尽きなかったが,その中でとくに重要となったのは,1950(昭和25)年に発生したクレーム問題だった。この年の6月,名古屋の米第5空軍司令部から日本各地の飛行場・レーダー基地など20数件の工事がわずか1ヵ月の間に次々と発注。その中で,鹿島は厚木(神奈川県)と松島(宮城県)の飛行場工事を落札した。実際の工事では仕様書や図面に不備があったにもかかわらず,米軍監督官は英文仕様書を盾に,日本の実情に合わない要求を押し通してきた。 守之助は監督官の不当措置撤回を申し入れるなど対抗措置を講じ一応の決着を見たものの,厚木と松島両工事の莫大な損失はそのままとなった。ちょうどこの時期,沖縄でモリソン・クヌードセン社とのJVが成立していたことから同社の技師に相談したところ,こうした場合,米国ではクレームを提起して補償を求めるとの助言を得た。たしかに契約書の紛争条項にはクレームに関する規定があったが,日本の業者はその権利を活用することなど考えていなかった。最終的にこのクレーム問題は,鹿島が最終判定の権限を持つ極東空軍司令官に上訴し,1951(昭和26)年に事実審理が行われた。その結果,公正に判断され,鹿島の申立理由が十分に認められることになり,厚木工事で4割,松島工事で9割以上の要求が通った。 この後,次第に日本の請負業者の権利が認められ,建設業全体の地位が向上していった。クレームを提起した守之助の決断は特筆に値するものといえる。「超高層のあけぼの」 守之助は,1953(昭和28)年に参議院議員に初当選,1957(昭和32)年国務大臣北海道開発庁長官に就任し,会社の役職を退いた時期以外は,社長を譲った卯女夫人とともに会長として熱心に社の業務にあたった。鹿島は昭和30年代の高度成長の波にも乗って業績を伸ばし,1963(昭和38)年には年間受注高世界第1位となった。 鹿島の建築において燦然と輝く功績は,日本初の超高層ビル「霞が関ビル」の建設である。守之助は,当時耐震構造研究の権威だった武藤清を招へい,社内プロジェクトチームを起ち上げて,従来の建物構造を変えるまったく新しい発想の「柔構造理論」を確立した。そして1965(昭和40)年に起工式が行われ,1968(昭和43)年36階147メートルの超高層ビルが完成した。新しい時代に将来の社の方針を示す 霞が関ビルが完成した直後の1968年,港区元赤坂の新本社ビルが落成,八重洲にあった本社を移転した。そして翌1969(昭和44)年,鹿島は創業130年を迎えた。 創立記念日にあたる2月22日に会長の守之助は,全役員・社員に向けて次のようなメッセージを送った。 「会社の発展にとって,経営の進むべき方向を見定めることは非常に大切なことである。最近の急速な科学技術の進歩に伴って,建設プロジェクトはますます巨大化し,複雑化している。このような今日の複雑かつ多様な要求に,より良く応えるため,多くの場合設計と施工の調和によって仕事が進められるが,米国その他の先進国では,そうした設計施工の協調関係はさらに発展して,最近では双方の能力を同時に発揮する単一体,すなわちエンジニア・コンストラクターという形態へと発展しつつある。 われわれの理想もエンジニア・コンストラクターたることである。鹿島は霞が関超高層ビルを建設し,千葉や坂出において50万トン巨大ドックが完成し,また先日は最高裁判所設計のコンペに最優秀賞や優秀賞を獲得するなど,わが社がエンジニア・コンストラクターとして十分なる資格と能力を備えていることを実証したのである。 このエンジニア・コンストラクターとしての活動は,日本では今まさに開始されんとするものである。かくしてわが社は,受注業務の内容や受注対象を絶えず多様化し,拡大して前例のない業績と繁栄の時代を築かんとするものである」。 新しい時代のニーズに応え,また激しい競争の中で生き残り,繁栄を継続するため,将来の社の方針を明確に示したのである。(小野一成『鹿島建設の歩み人が事業であった頃』より抜粋)
10KAJIMA202502かたばみの取組みScene2:完成した霞が関ビル(1968年)創業130年記念パーティ(ホテルオークラ)(1969年)霞が関ビル上棟式にて(1967年)クレーム問題と建設業の地位向上 戦後,日本の建設業は進駐軍関係の工事で生きられたといってもよい状態だった。しかし,材料の規格から施工の方法・慣習など,それまでの日本のやり方とは大きく異なり,さらに言葉の違いから契約を巡ってはさまざまなトラブルが発生した。また,そのような場合は,ほとんど例外なく日本側が譲歩させられていた。 鹿島でも進駐軍工事での紛争は尽きなかったが,その中でとくに重要となったのは,1950(昭和25)年に発生したクレーム問題だった。この年の6月,名古屋の米第5空軍司令部から日本各地の飛行場・レーダー基地など20数件の工事がわずか1ヵ月の間に次々と発注。その中で,鹿島は厚木(神奈川県)と松島(宮城県)の飛行場工事を落札した。実際の工事では仕様書や図面に不備があったにもかかわらず,米軍監督官は英文仕様書を盾に,日本の実情に合わない要求を押し通してきた。 守之助は監督官の不当措置撤回を申し入れるなど対抗措置を講じ一応の決着を見たものの,厚木と松島両工事の莫大な損失はそのままとなった。ちょうどこの時期,沖縄でモリソン・クヌードセン社とのJVが成立していたことから同社の技師に相談したところ,こうした場合,米国ではクレームを提起して補償を求めるとの助言を得た。たしかに契約書の紛争条項にはクレームに関する規定があったが,日本の業者はその権利を活用することなど考えていなかった。最終的にこのクレーム問題は,鹿島が最終判定の権限を持つ極東空軍司令官に上訴し,1951(昭和26)年に事実審理が行われた。その結果,公正に判断され,鹿島の申立理由が十分に認められることになり,厚木工事で4割,松島工事で9割以上の要求が通った。 この後,次第に日本の請負業者の権利が認められ,建設業全体の地位が向上していった。クレームを提起した守之助の決断は特筆に値するものといえる。「超高層のあけぼの」 守之助は,1953(昭和28)年に参議院議員に初当選,1957(昭和32)年国務大臣北海道開発庁長官に就任し,会社の役職を退いた時期以外は,社長を譲った卯女夫人とともに会長として熱心に社の業務にあたった。鹿島は昭和30年代の高度成長の波にも乗って業績を伸ばし,1963(昭和38)年には年間受注高世界第1位となった。 鹿島の建築において燦然と輝く功績は,日本初の超高層ビル「霞が関ビル」の建設である。守之助は,当時耐震構造研究の権威だった武藤清を招へい,社内プロジェクトチームを起ち上げて,従来の建物構造を変えるまったく新しい発想の「柔構造理論」を確立した。そして1965(昭和40)年に起工式が行われ,1968(昭和43)年36階147メートルの超高層ビルが完成した。新しい時代に将来の社の方針を示す 霞が関ビルが完成した直後の1968年,港区元赤坂の新本社ビルが落成,八重洲にあった本社を移転した。そして翌1969(昭和44)年,鹿島は創業130年を迎えた。 創立記念日にあたる2月22日に会長の守之助は,全役員・社員に向けて次のようなメッセージを送った。 「会社の発展にとって,経営の進むべき方向を見定めることは非常に大切なことである。最近の急速な科学技術の進歩に伴って,建設プロジェクトはますます巨大化し,複雑化している。このような今日の複雑かつ多様な要求に,より良く応えるため,多くの場合設計と施工の調和によって仕事が進められるが,米国その他の先進国では,そうした設計施工の協調関係はさらに発展して,最近では双方の能力を同時に発揮する単一体,すなわちエンジニア・コンストラクターという形態へと発展しつつある。 われわれの理想もエンジニア・コンストラクターたることである。鹿島は霞が関超高層ビルを建設し,千葉や坂出において50万トン巨大ドックが完成し,また先日は最高裁判所設計のコンペに最優秀賞や優秀賞を獲得するなど,わが社がエンジニア・コンストラクターとして十分なる資格と能力を備えていることを実証したのである。 このエンジニア・コンストラクターとしての活動は,日本では今まさに開始されんとするものである。かくしてわが社は,受注業務の内容や受注対象を絶えず多様化し,拡大して前例のない業績と繁栄の時代を築かんとするものである」。 新しい時代のニーズに応え,また激しい競争の中で生き残り,繁栄を継続するため,将来の社の方針を明確に示したのである。(小野一成『鹿島建設の歩み人が事業であった頃』より抜粋)
 11KAJIMA202502特集 鹿島守之助没後50年 1935年頃の鹿島組は,いまだ封建的制度から脱しきれずにいた。取締役に就任した守之助は,まず徹底的に赤字経営の原因と鹿島組の病弊を探った。日本だけでなく,欧米各国から土建事業と会社経営に関する書物を集め,専門家の意見を聞いた。 そこで導き出した帰結が「事業が古くなるとその5割は失敗する」であり,「失敗するのは内部要因による場合が多い」との分析だった。これを自らの信条と結び合わせて生まれたのが「事業成功の秘訣二十ヵ条」だ。取締役就任から約半年後,守之助40歳の時である。 「事業成功の秘訣二十ヵ条」の根底に流れている「絶えざる拡大と発展の中に安定を見出す“動的安定”こそ,鹿島の生きる道である」という経営方針は,業績をみるみる向上させていった。 守之助は高い理想と固い信念のもと,1938年社長に就任。その後,施工能力の増強と科学的管理の二大原則による経営管理の革新を断行し,社運隆昌の道を開いていく。事業成功の秘訣ニ十ヵ条に流れる“動的安定”という経営方針当社社員は誰もが目にしたことがある「事業成功の秘訣二十ヵ条」。1936(昭和11)年10月,鹿島守之助が鹿島組取締役就任後に発表したもので,ここに込められた思想と哲学は,当社が業績不振から脱却し飛躍的に発展する原動力となった。そして約90年経った現在も,その精神は当社の中に受け継がれている。寄稿 事業成功の秘訣二十ヵ条 鹿島守之助 はしがき 事業が古くなると,その5割までは失敗するといわれている。なぜ,かれらは失敗するのであろうか。外部からの原因で失敗するものは割合に少ない。むしろかれらが正しいと思ってやっていることが,事業失敗の原因になっていることが多いのである。 一般的見地より事業成功の秘訣と思わるるもの二十ヵ条をあげてみよう。これらはわかりきったことであるかもしれない。しかしわかりきったことだといって馬鹿にしたり無視してはならない。真理はきわめて平凡である。わかりきったことがなかなか実行できない世の中である。この中の一ヵ条でも適用せられ,ただ一人の社員にでも感化を与えることができれば筆者の労は報いられる次第である。第一条 「旧来の方法が一番いい」という考えを捨てよ古い設備,古い方法で満足しようとする心は慢性病のように恐ろしい。絶えざる改良を試みずして事業の発展するはずがない。第二条 絶えず改良を試みよ,「できない」と言わずにやってみよ「今までこれで成功してきたのだ」ということを盾にとって改善しようとしない支配人はその会社を亡ぼすものである。第三条 有能な指導者をつくれ自然界は適者生存の世界である。有能なる指導者のいる会社は繁昌する。第四条 人をつくらぬ事業は亡ぶ「何事もオレでなくては」と思って万事を一人で切りまわすのもよかろう。しかしそういう人は寿命よりも二十年も早く死ぬ。そして事業もその人とともに亡びる。第五条 「どうなるか」を研究せよ「どうにかなる」と考えるよりは「どうなるか」を研究して「どうするか」の計画を樹立すべきである。第六条 本を読む時間をもて研究するには本を読まなければならぬ。自分の独特の考えだと思っていることも,その実,たいていは本からきている。第七条 給料は高くせよ給料や設備にかけた金はかならず戻る。けっして経費ではない投資である。第八条 よく働かせる人たれ本当に偉い主任は,人を働かせることを本職と心得,きまった仕事を人に与えて働かせるばかりでなく,これは少しむずかしいなと思われる仕事でも,これを部下にやらせてみる。第九条 賞罰を明らかにせよ働く者も怠ける者も,一律同様の俸給であり,また,儲ける者と,損をかける者との取扱い上たいした差異がないならば,経済活動は枯死する危険がある。第十条 なるべく機械を使うこと機械は生産原価を下げる。しかして,生産高を増すものである。第十一条 部下の協力一致を計れ会社は身体のようなものである。身体はたんに指や胃や腸が集まったものではない。これらが協同して組織をつくっているところに生命があるのである。第十二条 事業は大きさよりも釣り合いが肝心物大なるをもって尊しとせず,小なりといえども釣合いのとれていることが肝心である。第十三条 なによりもまず計画まず計画,つぎに実施,最後に統制,これは能率方法の定石である。第十四条 新しい考え,新しい方法の採用を怠るな常に時勢に後れてはならない。上に立つ者の一番恐ろしいことは自分の無知を知らずにいることである。第十五条 一人よがりは事を損ず専門家の説を聞かず,これまでの方法に執着ばかりしているとかならず失敗する。第十六条 イエスマンに取巻かるるなかれ反対論は聞いてみて損になるものではない。むしろ自説の土台を固める上に役立つものである。第十七条 欠陥は改良せよ欠陥に直面し,虚心坦懐なことが必要である。第十八条 人をうらまず突進せよ成績のあがらない場合にはまず自分を非難して,方法を変えるのが一番である。競争者を非難するのはくだらないことである。第十九条 ムダを見つける目を開けムダというものは何人にも利益しない。第二十条 仕事を道楽とせよ四六時中経営のために浮身をやつして,しかも余裕綽々たるためには,仕事を道楽化することが必要である。寄稿として掲載された「鹿島組月報昭和11年10月号」の表紙と本文。事業成功の秘訣二十ヵ条は守之助が40歳の時に書かれた若手技術系社員を対象とした実務体験型研修施設「鹿島テクニカルセンター」(横浜市鶴見区)のエントランスホールの壁には,「企業理念」と「事業成功の秘訣二十ヵ条」の短冊がデザインされている※初出は「鹿島組月報昭和11年10月号」。本誌に掲載するにあたり,『わが経営を語る―理解と創造―』に掲載のものより,旧仮名遣い,一部の漢字や表現を修正した。説明部分は一部抜粋している原文は鹿島イントラネット―[会社情報]―[トップメッセージ]より読むことができる
11KAJIMA202502特集 鹿島守之助没後50年 1935年頃の鹿島組は,いまだ封建的制度から脱しきれずにいた。取締役に就任した守之助は,まず徹底的に赤字経営の原因と鹿島組の病弊を探った。日本だけでなく,欧米各国から土建事業と会社経営に関する書物を集め,専門家の意見を聞いた。 そこで導き出した帰結が「事業が古くなるとその5割は失敗する」であり,「失敗するのは内部要因による場合が多い」との分析だった。これを自らの信条と結び合わせて生まれたのが「事業成功の秘訣二十ヵ条」だ。取締役就任から約半年後,守之助40歳の時である。 「事業成功の秘訣二十ヵ条」の根底に流れている「絶えざる拡大と発展の中に安定を見出す“動的安定”こそ,鹿島の生きる道である」という経営方針は,業績をみるみる向上させていった。 守之助は高い理想と固い信念のもと,1938年社長に就任。その後,施工能力の増強と科学的管理の二大原則による経営管理の革新を断行し,社運隆昌の道を開いていく。事業成功の秘訣ニ十ヵ条に流れる“動的安定”という経営方針当社社員は誰もが目にしたことがある「事業成功の秘訣二十ヵ条」。1936(昭和11)年10月,鹿島守之助が鹿島組取締役就任後に発表したもので,ここに込められた思想と哲学は,当社が業績不振から脱却し飛躍的に発展する原動力となった。そして約90年経った現在も,その精神は当社の中に受け継がれている。寄稿 事業成功の秘訣二十ヵ条 鹿島守之助 はしがき 事業が古くなると,その5割までは失敗するといわれている。なぜ,かれらは失敗するのであろうか。外部からの原因で失敗するものは割合に少ない。むしろかれらが正しいと思ってやっていることが,事業失敗の原因になっていることが多いのである。 一般的見地より事業成功の秘訣と思わるるもの二十ヵ条をあげてみよう。これらはわかりきったことであるかもしれない。しかしわかりきったことだといって馬鹿にしたり無視してはならない。真理はきわめて平凡である。わかりきったことがなかなか実行できない世の中である。この中の一ヵ条でも適用せられ,ただ一人の社員にでも感化を与えることができれば筆者の労は報いられる次第である。第一条 「旧来の方法が一番いい」という考えを捨てよ古い設備,古い方法で満足しようとする心は慢性病のように恐ろしい。絶えざる改良を試みずして事業の発展するはずがない。第二条 絶えず改良を試みよ,「できない」と言わずにやってみよ「今までこれで成功してきたのだ」ということを盾にとって改善しようとしない支配人はその会社を亡ぼすものである。第三条 有能な指導者をつくれ自然界は適者生存の世界である。有能なる指導者のいる会社は繁昌する。第四条 人をつくらぬ事業は亡ぶ「何事もオレでなくては」と思って万事を一人で切りまわすのもよかろう。しかしそういう人は寿命よりも二十年も早く死ぬ。そして事業もその人とともに亡びる。第五条 「どうなるか」を研究せよ「どうにかなる」と考えるよりは「どうなるか」を研究して「どうするか」の計画を樹立すべきである。第六条 本を読む時間をもて研究するには本を読まなければならぬ。自分の独特の考えだと思っていることも,その実,たいていは本からきている。第七条 給料は高くせよ給料や設備にかけた金はかならず戻る。けっして経費ではない投資である。第八条 よく働かせる人たれ本当に偉い主任は,人を働かせることを本職と心得,きまった仕事を人に与えて働かせるばかりでなく,これは少しむずかしいなと思われる仕事でも,これを部下にやらせてみる。第九条 賞罰を明らかにせよ働く者も怠ける者も,一律同様の俸給であり,また,儲ける者と,損をかける者との取扱い上たいした差異がないならば,経済活動は枯死する危険がある。第十条 なるべく機械を使うこと機械は生産原価を下げる。しかして,生産高を増すものである。第十一条 部下の協力一致を計れ会社は身体のようなものである。身体はたんに指や胃や腸が集まったものではない。これらが協同して組織をつくっているところに生命があるのである。第十二条 事業は大きさよりも釣り合いが肝心物大なるをもって尊しとせず,小なりといえども釣合いのとれていることが肝心である。第十三条 なによりもまず計画まず計画,つぎに実施,最後に統制,これは能率方法の定石である。第十四条 新しい考え,新しい方法の採用を怠るな常に時勢に後れてはならない。上に立つ者の一番恐ろしいことは自分の無知を知らずにいることである。第十五条 一人よがりは事を損ず専門家の説を聞かず,これまでの方法に執着ばかりしているとかならず失敗する。第十六条 イエスマンに取巻かるるなかれ反対論は聞いてみて損になるものではない。むしろ自説の土台を固める上に役立つものである。第十七条 欠陥は改良せよ欠陥に直面し,虚心坦懐なことが必要である。第十八条 人をうらまず突進せよ成績のあがらない場合にはまず自分を非難して,方法を変えるのが一番である。競争者を非難するのはくだらないことである。第十九条 ムダを見つける目を開けムダというものは何人にも利益しない。第二十条 仕事を道楽とせよ四六時中経営のために浮身をやつして,しかも余裕綽々たるためには,仕事を道楽化することが必要である。寄稿として掲載された「鹿島組月報昭和11年10月号」の表紙と本文。事業成功の秘訣二十ヵ条は守之助が40歳の時に書かれた若手技術系社員を対象とした実務体験型研修施設「鹿島テクニカルセンター」(横浜市鶴見区)のエントランスホールの壁には,「企業理念」と「事業成功の秘訣二十ヵ条」の短冊がデザインされている※初出は「鹿島組月報昭和11年10月号」。本誌に掲載するにあたり,『わが経営を語る―理解と創造―』に掲載のものより,旧仮名遣い,一部の漢字や表現を修正した。説明部分は一部抜粋している原文は鹿島イントラネット―[会社情報]―[トップメッセージ]より読むことができる
 12KAJIMA202502初選挙は落選 1930(昭和5)年1月15日,衆議院議員に立候補するため,守之助は急遽イタリアから帰国し,外務省を依願退職した。議会は同月21日に解散,2月20日を投票日とする第17回総選挙戦に入った。どの党からも公認を受けず,兵庫県第4区に中立で立候補し,華々しく選挙戦を展開したが,結果は落選に終わった。 その後,学究生活に入った守之助は,精一の求めに応じ,1936(昭和11)年取締役として鹿島の経営に参画,以来経営に邁進する。 終戦後,再度衆議院選挙に立候補する準備をしていたが,精一が貴族院議員に勅選されたこともあり,引き続き社業に専念した。初当選から第1期参議院議員時代 1953(昭和28)年4月,第3回参議院通常選挙に自由党から全国区で立候補。前年の衆議院選挙に立候補する話もあったが,自分は参議院のほうが適しており,冷静な批判を主にした政治を行うべきと判断した結果だった。 参議院全国区の選挙は,全国の有権者に呼びかける必要がある。鹿島の全組織網や同業者の人々の強力な支援,全国建設業協会の職域代表としての推薦などがあり,守之助は東奔西走し,次のような立候補演説を行った。 「(前略)日本の経済自立を確立し,国民の生活水準を絶えず向上させる道は,眠れる資源の開発,食糧の増産,年々繰り返す災害の防除等を目的とする国土の総合開発です。総合開発はわが国においても広く知られ,20世紀の奇跡といわれています。私は皆さまとともに,この20世紀の奇跡の実現に努力いたしたく存じます(後略)」。 選挙は大量票を獲得し,全国区4位で当選。政界入りという積年の念願は,ついに果たされた。 守之助は,当初外務委員を希望していたが,選挙に際し鹿島や同業者から多大な支援を受けたため,それに報いようと1年ほど建設委員を務めた。業界を代表した立場から,要求を貫徹するために活動し,成果を挙げた。その後,自由党外交調査会副会長に就任,また参議院自由党審議会の外交部長を務め,参議院外務委員会で外務委員長にもなった。 1954(昭和29)年,オーストリア・ウィーンで開催された列国議会同盟会議に代表団の一員として列席。これは各国の議会連合による会議で,国際平和と相互理解のための活動増進を目的としたものである。守之助はこの会議の安全保障および軍縮委員会で,一般軍縮の必要性,とくに核実験の中止を訴え,やむを得ずして実験を行う場合は生じた損害の補償を要求するという演説を行った。この演説は,スイス代表が提出した軍備縮小および安全保障問題に関する決議案に対する賛成演説のかたちで行われ,世界唯一の被爆国の代表演説として注目を浴びた。 なおこの会議の日本代表団では,守之助のほかに夫婦同伴がいなかった。夜会では卯女夫人の着物姿を珍しがって周囲に多くの人が集まり,夫人は英,仏,伊語でなごやかに対応し,注目の的となったという。国務大臣北海道開発庁長官として 1957(昭和32)年,岸内閣が成立,その第5回参議院選挙で選挙カーに乗りアピール(1959年)参議院初当選時(1953年)参議院本会議での代表質問(1965年)1929(昭和4)年,外交官だった鹿島守之助は,スイス・ジュネーブで開かれた国際連盟総会に出席,ヨーロッパの政治家の演説を聴き,自分の理想を実現するには政治家になる以外ないと決意を新たにしたという。豊かな国際感覚と外交経験を持った政治家・守之助の軌跡をたどる。鹿島守之助3つの顔政治家2
12KAJIMA202502初選挙は落選 1930(昭和5)年1月15日,衆議院議員に立候補するため,守之助は急遽イタリアから帰国し,外務省を依願退職した。議会は同月21日に解散,2月20日を投票日とする第17回総選挙戦に入った。どの党からも公認を受けず,兵庫県第4区に中立で立候補し,華々しく選挙戦を展開したが,結果は落選に終わった。 その後,学究生活に入った守之助は,精一の求めに応じ,1936(昭和11)年取締役として鹿島の経営に参画,以来経営に邁進する。 終戦後,再度衆議院選挙に立候補する準備をしていたが,精一が貴族院議員に勅選されたこともあり,引き続き社業に専念した。初当選から第1期参議院議員時代 1953(昭和28)年4月,第3回参議院通常選挙に自由党から全国区で立候補。前年の衆議院選挙に立候補する話もあったが,自分は参議院のほうが適しており,冷静な批判を主にした政治を行うべきと判断した結果だった。 参議院全国区の選挙は,全国の有権者に呼びかける必要がある。鹿島の全組織網や同業者の人々の強力な支援,全国建設業協会の職域代表としての推薦などがあり,守之助は東奔西走し,次のような立候補演説を行った。 「(前略)日本の経済自立を確立し,国民の生活水準を絶えず向上させる道は,眠れる資源の開発,食糧の増産,年々繰り返す災害の防除等を目的とする国土の総合開発です。総合開発はわが国においても広く知られ,20世紀の奇跡といわれています。私は皆さまとともに,この20世紀の奇跡の実現に努力いたしたく存じます(後略)」。 選挙は大量票を獲得し,全国区4位で当選。政界入りという積年の念願は,ついに果たされた。 守之助は,当初外務委員を希望していたが,選挙に際し鹿島や同業者から多大な支援を受けたため,それに報いようと1年ほど建設委員を務めた。業界を代表した立場から,要求を貫徹するために活動し,成果を挙げた。その後,自由党外交調査会副会長に就任,また参議院自由党審議会の外交部長を務め,参議院外務委員会で外務委員長にもなった。 1954(昭和29)年,オーストリア・ウィーンで開催された列国議会同盟会議に代表団の一員として列席。これは各国の議会連合による会議で,国際平和と相互理解のための活動増進を目的としたものである。守之助はこの会議の安全保障および軍縮委員会で,一般軍縮の必要性,とくに核実験の中止を訴え,やむを得ずして実験を行う場合は生じた損害の補償を要求するという演説を行った。この演説は,スイス代表が提出した軍備縮小および安全保障問題に関する決議案に対する賛成演説のかたちで行われ,世界唯一の被爆国の代表演説として注目を浴びた。 なおこの会議の日本代表団では,守之助のほかに夫婦同伴がいなかった。夜会では卯女夫人の着物姿を珍しがって周囲に多くの人が集まり,夫人は英,仏,伊語でなごやかに対応し,注目の的となったという。国務大臣北海道開発庁長官として 1957(昭和32)年,岸内閣が成立,その第5回参議院選挙で選挙カーに乗りアピール(1959年)参議院初当選時(1953年)参議院本会議での代表質問(1965年)1929(昭和4)年,外交官だった鹿島守之助は,スイス・ジュネーブで開かれた国際連盟総会に出席,ヨーロッパの政治家の演説を聴き,自分の理想を実現するには政治家になる以外ないと決意を新たにしたという。豊かな国際感覚と外交経験を持った政治家・守之助の軌跡をたどる。鹿島守之助3つの顔政治家2
 13KAJIMA202502特集 鹿島守之助没後50年第7回参議院選挙に当選。左から卯女,守之助,平泉渉(同時当選),三枝子(1965年)代表質問をする守之助(1965年)第58回列国議会同盟会議。オランダ大会開会式にて(1970年)国務大臣認証式を終えて。岸信介総理大臣と(1957年)第7回参議院選挙で当選御礼挨拶(八重洲本社前)(1965年)第7回参議院選挙の際,佐藤栄作総理大臣と(1965年)ときの北海道開発庁長官が病気で辞職したため,守之助がその後任として入閣することになった。ちょうど1952年からの第一次5カ年計画に続き,第二次5カ年計画に移ろうとしたころで,北海道の産業開発の原動力となる電源開発,道路,港湾,河川の整備拡充,食糧の増産,開発の基本調査などに重点が置かれていた。就任後なによりもまず北海道の現実を見るべきと,数度にわたって現地視察を行い,基本的な調査と研究を徹底的に行った。 守之助は長官就任時に国務専念のため,社長をはじめ,土木工業協会会長その他20あまりの役職をすべて辞め,卯女夫人に社長を譲った。また,長官として公明正大に行うことが必要だと考え,守之助は鹿島に対し,北海道開発局関係の請負工事の指名を一切停止した。後に大臣を辞めたとき,いちばん喜んだのは鹿島の札幌支店長だったという。国会議員生活に終止符 1959(昭和34)年6月の第5回参議院通常選挙では大量票を獲得し,全国区2位で当選。第32回国会で守之助は参議院外務委員長に選任され,その後も外務委員として活躍した。また自民党の対外経済協力特別委員長,外交調査会長,経済調査会長を引き受け,主として経済と外交問題に取り組んだ。 1965(昭和40)年7月,第7回参議院通常選挙は,自民党から3度目となる全国区に立候補。結果は全国区1位当選だった。この選挙では,同時に女婿である平泉渉も初当選している。 1970年,第58回列国議会同盟会議がオランダ・ハーグで開催,守之助は卯女夫人を伴い,日本議団の一員として出席した。ここで日本を代表し,「1970年代の日本経済の課題」として,日本の対外援助と地域協力について英語で経済演説を行った。近年,地域共同体の機運が急速に高まり,東南アジア開発閣僚会議,アジア・太平洋協議会,東南アジア諸国連合などが組織,結成され,活発に活動していること,わが国を含むアジア諸国が相互に利益ある経済発展を導き出す旨の演説が終わると,会場全体から拍手が起こった。自席に戻るときには,東南アジア諸国の代表が席を立って彼を迎え,感謝の意を表したという。 1971(昭和46)年の第9回参議院議員通常選挙が近づくと,守之助は1953年以来3期18年間にわたる国会議員生活に終止符を打ち,参議院議員・平泉渉の大成に期待するとともに,そのすべてを若い世代の活動と責任に引き継ぐ決心をした。そうして任期を全うし,いさぎよく政治家としての人生を引退したのである。
13KAJIMA202502特集 鹿島守之助没後50年第7回参議院選挙に当選。左から卯女,守之助,平泉渉(同時当選),三枝子(1965年)代表質問をする守之助(1965年)第58回列国議会同盟会議。オランダ大会開会式にて(1970年)国務大臣認証式を終えて。岸信介総理大臣と(1957年)第7回参議院選挙で当選御礼挨拶(八重洲本社前)(1965年)第7回参議院選挙の際,佐藤栄作総理大臣と(1965年)ときの北海道開発庁長官が病気で辞職したため,守之助がその後任として入閣することになった。ちょうど1952年からの第一次5カ年計画に続き,第二次5カ年計画に移ろうとしたころで,北海道の産業開発の原動力となる電源開発,道路,港湾,河川の整備拡充,食糧の増産,開発の基本調査などに重点が置かれていた。就任後なによりもまず北海道の現実を見るべきと,数度にわたって現地視察を行い,基本的な調査と研究を徹底的に行った。 守之助は長官就任時に国務専念のため,社長をはじめ,土木工業協会会長その他20あまりの役職をすべて辞め,卯女夫人に社長を譲った。また,長官として公明正大に行うことが必要だと考え,守之助は鹿島に対し,北海道開発局関係の請負工事の指名を一切停止した。後に大臣を辞めたとき,いちばん喜んだのは鹿島の札幌支店長だったという。国会議員生活に終止符 1959(昭和34)年6月の第5回参議院通常選挙では大量票を獲得し,全国区2位で当選。第32回国会で守之助は参議院外務委員長に選任され,その後も外務委員として活躍した。また自民党の対外経済協力特別委員長,外交調査会長,経済調査会長を引き受け,主として経済と外交問題に取り組んだ。 1965(昭和40)年7月,第7回参議院通常選挙は,自民党から3度目となる全国区に立候補。結果は全国区1位当選だった。この選挙では,同時に女婿である平泉渉も初当選している。 1970年,第58回列国議会同盟会議がオランダ・ハーグで開催,守之助は卯女夫人を伴い,日本議団の一員として出席した。ここで日本を代表し,「1970年代の日本経済の課題」として,日本の対外援助と地域協力について英語で経済演説を行った。近年,地域共同体の機運が急速に高まり,東南アジア開発閣僚会議,アジア・太平洋協議会,東南アジア諸国連合などが組織,結成され,活発に活動していること,わが国を含むアジア諸国が相互に利益ある経済発展を導き出す旨の演説が終わると,会場全体から拍手が起こった。自席に戻るときには,東南アジア諸国の代表が席を立って彼を迎え,感謝の意を表したという。 1971(昭和46)年の第9回参議院議員通常選挙が近づくと,守之助は1953年以来3期18年間にわたる国会議員生活に終止符を打ち,参議院議員・平泉渉の大成に期待するとともに,そのすべてを若い世代の活動と責任に引き継ぐ決心をした。そうして任期を全うし,いさぎよく政治家としての人生を引退したのである。
 外交官生活を約10年送った後,学究生活に入った鹿島守之助は,論文「世界大戦原因の研究」を提出して法学博士となる。著書『日英外交史』および『日本外交の史的考察』によって学界最高の栄誉である日本学士院賞を受賞。守之助は外交史や国際問題の研究により,やがて文化功労者として顕彰される。14KAJIMA202502第1回鹿島平和賞授賞式(1967年)。クーデンホーフ・カレルギー伯爵に鹿島平和賞を贈る1974年6月に完結した『日本外交史』本巻34巻,別巻4巻若き外交評論家 外交官としてドイツ・ベルリンに赴任中の守之助は,大使館勤務の余暇に日本の「外交時報」や「国際知識」,そのほか新聞・雑誌に,ヨーロッパとドイツの情勢について原稿を送り,すでに新進外交評論家として注目されていたという。 在独中の1924(大正13)年,これまで執筆してきたヨーロッパの政治問題について公表可能なものをまとめ,最初の著書である『欧州の現勢と其将来』(北文館)を刊行した。 この在ドイツ大使館時代,オーストリア貴族リヒャルト・クーデンホーフ・カレルギー伯爵との出会いは,守之助の生涯の思想に決定的な影響を与えた。彼のパン・ヨーロッパ論(欧州統合主義)に感動し,自分もまたパン・アジアの形成を生涯の理想とするに至った。 その後,守之助は在イタリア大使館勤務となり,1926年に『汎亜細亜運動と汎欧羅巴運動』(北文館)を刊行,パン・アジア運動に関する彼の主張とパン・ヨーロッパ運動の進展を述べている。ドイツの事情に関しては先の本の続編で,在ドイツ大使館勤務中に同国の文献をもとに起草したものである。 また,クーデンホーフ・カレルギー伯爵とは,ローマ着任以来,旧交を温めていた。以前に翻訳を依頼されていた彼の著書『パン・ヨーロッパ』の訳書は,1927(昭和2)年日本で『汎ヨーロッパ』(国際連盟協会)として刊行され,ローマ着任早々に出版の通知を受け取り,クーデンホーフ・カレルギー伯爵も喜んだという。4年にわたる学究生活 1930(昭和5)年,初めての選挙に敗れた守之助は,その後4年間,東京郊外の調布町に引きこもり外交と国際問題の研究に没頭した。ベルリンやローマでの大使館時代に,ドイツやそのほかの国の外交文書,研究書などを大量に蒐集し,くわえて約10年間の外交官生活は,外交実務を習得するだけでなく,英,独,仏,伊の4ヵ国語に通じさせていた。その結果,諸国の外交文書を閲覧することに困難を感じることなく,正確に解読することができた。 「世界大戦原因の研究」は,守之助が1933(昭和8)年に母校東京帝国大学法学部に提出した学位論文である。当時公表されていた各国の外交文書を基礎に,最新の資料を網羅,駆使して,第一次世界大戦の原因を究明しようとした。この問題は,欧米では賠償問題に絡むため,ドイツやその反対の立場のイギリス・フランスでも,冷静な判断からの客観的,歴史的,学術的研究が困難だった。守之助は,日本のような比較的中立の立場にある国,遠い極東の我々が研究すべき問題と考え,在ドイツ大使館勤務当時から資料を集めていた。 この論文は提出後,世界的水準を抜くものとして翌1934年に法学博士の学位が授与された。これは同年,『世界大戦原因の研究』(岩波書店)として刊行されたが,後年『日本外交史別巻2世界大戦原因の研究』の序文で述懐しているように,本書は守之助の生涯において最も心血を注いだ最大の力作となった。 1938(昭和13)年,『帝国外交の基本政策』(巌松堂書店)を出版。これは三国干渉から日露国交の回復まで,1895(明治28)年から1925(大正14)年までの30余年間における外交の基本政策の研究であ調布時代(1930年頃)鹿島守之助3つの顔学者3
外交官生活を約10年送った後,学究生活に入った鹿島守之助は,論文「世界大戦原因の研究」を提出して法学博士となる。著書『日英外交史』および『日本外交の史的考察』によって学界最高の栄誉である日本学士院賞を受賞。守之助は外交史や国際問題の研究により,やがて文化功労者として顕彰される。14KAJIMA202502第1回鹿島平和賞授賞式(1967年)。クーデンホーフ・カレルギー伯爵に鹿島平和賞を贈る1974年6月に完結した『日本外交史』本巻34巻,別巻4巻若き外交評論家 外交官としてドイツ・ベルリンに赴任中の守之助は,大使館勤務の余暇に日本の「外交時報」や「国際知識」,そのほか新聞・雑誌に,ヨーロッパとドイツの情勢について原稿を送り,すでに新進外交評論家として注目されていたという。 在独中の1924(大正13)年,これまで執筆してきたヨーロッパの政治問題について公表可能なものをまとめ,最初の著書である『欧州の現勢と其将来』(北文館)を刊行した。 この在ドイツ大使館時代,オーストリア貴族リヒャルト・クーデンホーフ・カレルギー伯爵との出会いは,守之助の生涯の思想に決定的な影響を与えた。彼のパン・ヨーロッパ論(欧州統合主義)に感動し,自分もまたパン・アジアの形成を生涯の理想とするに至った。 その後,守之助は在イタリア大使館勤務となり,1926年に『汎亜細亜運動と汎欧羅巴運動』(北文館)を刊行,パン・アジア運動に関する彼の主張とパン・ヨーロッパ運動の進展を述べている。ドイツの事情に関しては先の本の続編で,在ドイツ大使館勤務中に同国の文献をもとに起草したものである。 また,クーデンホーフ・カレルギー伯爵とは,ローマ着任以来,旧交を温めていた。以前に翻訳を依頼されていた彼の著書『パン・ヨーロッパ』の訳書は,1927(昭和2)年日本で『汎ヨーロッパ』(国際連盟協会)として刊行され,ローマ着任早々に出版の通知を受け取り,クーデンホーフ・カレルギー伯爵も喜んだという。4年にわたる学究生活 1930(昭和5)年,初めての選挙に敗れた守之助は,その後4年間,東京郊外の調布町に引きこもり外交と国際問題の研究に没頭した。ベルリンやローマでの大使館時代に,ドイツやそのほかの国の外交文書,研究書などを大量に蒐集し,くわえて約10年間の外交官生活は,外交実務を習得するだけでなく,英,独,仏,伊の4ヵ国語に通じさせていた。その結果,諸国の外交文書を閲覧することに困難を感じることなく,正確に解読することができた。 「世界大戦原因の研究」は,守之助が1933(昭和8)年に母校東京帝国大学法学部に提出した学位論文である。当時公表されていた各国の外交文書を基礎に,最新の資料を網羅,駆使して,第一次世界大戦の原因を究明しようとした。この問題は,欧米では賠償問題に絡むため,ドイツやその反対の立場のイギリス・フランスでも,冷静な判断からの客観的,歴史的,学術的研究が困難だった。守之助は,日本のような比較的中立の立場にある国,遠い極東の我々が研究すべき問題と考え,在ドイツ大使館勤務当時から資料を集めていた。 この論文は提出後,世界的水準を抜くものとして翌1934年に法学博士の学位が授与された。これは同年,『世界大戦原因の研究』(岩波書店)として刊行されたが,後年『日本外交史別巻2世界大戦原因の研究』の序文で述懐しているように,本書は守之助の生涯において最も心血を注いだ最大の力作となった。 1938(昭和13)年,『帝国外交の基本政策』(巌松堂書店)を出版。これは三国干渉から日露国交の回復まで,1895(明治28)年から1925(大正14)年までの30余年間における外交の基本政策の研究であ調布時代(1930年頃)鹿島守之助3つの顔学者3
 15KAJIMA202502特集 鹿島守之助没後50年本社資料センターにある鹿島記念室。ここには守之助のすべての著作(著書88冊,訳書56冊,計144冊)を初版本(一部再版)で揃えた「鹿島記念文庫」が設置されているる。戦前にまとめられたこの本は1958(昭和33)年に『日本外交政策の史的考察』(鹿島研究所)と改題し,刊行された。日本学士院賞と文化功労者顕彰 1957(昭和32)年『日英外交史』,翌年『日米外交史』(ともに鹿島研究所)を刊行。1959(昭和34)年,『日英外交史』と『日本外交政策の史的考察』により,学界最高の権威ある賞である日本学士院賞が授与された。 鹿島平和研究所は,守之助の提唱により明治百年記念事業として,『日本外交史』本巻34巻,別巻4巻の編集・刊行を計画。1968(昭和43)年から本格的に着手し,鹿島研究所出版会(現・鹿島出版会)より1970(昭和45)年3月から毎月刊行を続け,1974(昭和49)年6月に完結した。近代日本の外交を振り返り,公平,かつ客観的,専門的標準によって起草し,正確な史実を後世に伝えるとともに,国際的地位が向上しつつある日本の外交に,新しい活力を吹き込むことを期した。 『鹿島守之助外交論選集』本巻12巻別巻3巻は,1971(昭和46)年12月から1973(昭和48)年2月にかけて逐次刊行された。守之助は生涯を通じて,日本および世界外交史の研究に没頭し,時局問題やそのほかの著書を多数出版,各種の論文を新聞・雑誌に発表してきた。論選集は,これらの著書と論文をまとめ,別巻3巻にはコンラッド・アデナウアーの伝記を含めた第二次世界大戦後の西ドイツの事情に関する著書を収録,ブラント政権成立以後,とくにその東方政策について新たに書き加えられている。 1973(昭和48)年,『日本外交史』『鹿島守之助外交論選集』の刊行が完結したことから,記念祝賀会が盛大に開催された。会場には,政界,官界,財界,学界,外交団などの要人および令夫人約1,000人が集まった。この記念祝賀会は,守之助の外交史および国際問題研究に有終の美を飾る盛事となった。 この祝賀会では,大平正芳外務大臣(当時)から次のような賛辞を受けた。 「鹿島博士はわが外務省の大先輩ですが,終始外交界にとどまらなかった。また,政界に進出され,内閣に列せられたこともありながら,組織する立場にはならなかった。多くの学術的な研鑽を重ねられましたが,ついに象牙の塔にこもることもされませんでした。外交官としてもできないこと,宰相の権威をもってしてもできないこと,学者としてもできないことを,国家のためになしていただいたわけです」。 同年,主として『日本外交史』の刊行による業績により,文部省から文化功労者として顕彰される。国立教育会館で顕彰式が挙行され,守之助は卯女夫人を伴って出席した。その後「天皇陛下が文化功労者のお話を聞く会」に出席,さらに別室で陛下を囲んで歓談したという。当社に引き継がれている思想と哲学 当時,鹿島邸に隣接する鹿島新館(東京都文京区)の2階には,守之助の執筆活動,読書など思索の場としての書斎があった。 守之助は,実業家として「鹿島中興の祖」「建設業界近代化の父」とたたえられる功績を残しただけでなく,政治家として参議院議員を3期18年にわたり務め,さらには外交官生活約10年の経験を活かし,実践的平和主義者として外交・国際問題に関する幅広い研究業績を世に遺した。戦後,会社経営の難しい舵取りをしながら,これほどの学術書を多数執筆出版した経営者は例がない。 守之助亡き後,その著訳編書,勲章・勲記,遺品などがこの部屋に集められ,書斎はいつしか「鹿島記念室」と呼ばれるようになった。現在,鹿島記念室は赤坂別館2階の本社資料センターに移設されている。 守之助の思想と哲学は,現在でもなお当社に連綿と引き継がれている。葉山別荘にて(1957年)軽井沢別荘にてラジオ岩手『春及廬随談』の録音(1958年)文化功労者顕彰を受け,夫妻で宮中へ参内(1973年)
15KAJIMA202502特集 鹿島守之助没後50年本社資料センターにある鹿島記念室。ここには守之助のすべての著作(著書88冊,訳書56冊,計144冊)を初版本(一部再版)で揃えた「鹿島記念文庫」が設置されているる。戦前にまとめられたこの本は1958(昭和33)年に『日本外交政策の史的考察』(鹿島研究所)と改題し,刊行された。日本学士院賞と文化功労者顕彰 1957(昭和32)年『日英外交史』,翌年『日米外交史』(ともに鹿島研究所)を刊行。1959(昭和34)年,『日英外交史』と『日本外交政策の史的考察』により,学界最高の権威ある賞である日本学士院賞が授与された。 鹿島平和研究所は,守之助の提唱により明治百年記念事業として,『日本外交史』本巻34巻,別巻4巻の編集・刊行を計画。1968(昭和43)年から本格的に着手し,鹿島研究所出版会(現・鹿島出版会)より1970(昭和45)年3月から毎月刊行を続け,1974(昭和49)年6月に完結した。近代日本の外交を振り返り,公平,かつ客観的,専門的標準によって起草し,正確な史実を後世に伝えるとともに,国際的地位が向上しつつある日本の外交に,新しい活力を吹き込むことを期した。 『鹿島守之助外交論選集』本巻12巻別巻3巻は,1971(昭和46)年12月から1973(昭和48)年2月にかけて逐次刊行された。守之助は生涯を通じて,日本および世界外交史の研究に没頭し,時局問題やそのほかの著書を多数出版,各種の論文を新聞・雑誌に発表してきた。論選集は,これらの著書と論文をまとめ,別巻3巻にはコンラッド・アデナウアーの伝記を含めた第二次世界大戦後の西ドイツの事情に関する著書を収録,ブラント政権成立以後,とくにその東方政策について新たに書き加えられている。 1973(昭和48)年,『日本外交史』『鹿島守之助外交論選集』の刊行が完結したことから,記念祝賀会が盛大に開催された。会場には,政界,官界,財界,学界,外交団などの要人および令夫人約1,000人が集まった。この記念祝賀会は,守之助の外交史および国際問題研究に有終の美を飾る盛事となった。 この祝賀会では,大平正芳外務大臣(当時)から次のような賛辞を受けた。 「鹿島博士はわが外務省の大先輩ですが,終始外交界にとどまらなかった。また,政界に進出され,内閣に列せられたこともありながら,組織する立場にはならなかった。多くの学術的な研鑽を重ねられましたが,ついに象牙の塔にこもることもされませんでした。外交官としてもできないこと,宰相の権威をもってしてもできないこと,学者としてもできないことを,国家のためになしていただいたわけです」。 同年,主として『日本外交史』の刊行による業績により,文部省から文化功労者として顕彰される。国立教育会館で顕彰式が挙行され,守之助は卯女夫人を伴って出席した。その後「天皇陛下が文化功労者のお話を聞く会」に出席,さらに別室で陛下を囲んで歓談したという。当社に引き継がれている思想と哲学 当時,鹿島邸に隣接する鹿島新館(東京都文京区)の2階には,守之助の執筆活動,読書など思索の場としての書斎があった。 守之助は,実業家として「鹿島中興の祖」「建設業界近代化の父」とたたえられる功績を残しただけでなく,政治家として参議院議員を3期18年にわたり務め,さらには外交官生活約10年の経験を活かし,実践的平和主義者として外交・国際問題に関する幅広い研究業績を世に遺した。戦後,会社経営の難しい舵取りをしながら,これほどの学術書を多数執筆出版した経営者は例がない。 守之助亡き後,その著訳編書,勲章・勲記,遺品などがこの部屋に集められ,書斎はいつしか「鹿島記念室」と呼ばれるようになった。現在,鹿島記念室は赤坂別館2階の本社資料センターに移設されている。 守之助の思想と哲学は,現在でもなお当社に連綿と引き継がれている。葉山別荘にて(1957年)軽井沢別荘にてラジオ岩手『春及廬随談』の録音(1958年)文化功労者顕彰を受け,夫妻で宮中へ参内(1973年)