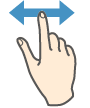ある日、私は、靴を履いたまま、一人暮らしをしている都内のアパートの玄関に倒れていた。目を覚まして時間を見ると遅刻ギリギリで、そのまま玄関を飛び出した。駅まで走り電車に乗ってふと思った。﹁自分は何をしているのだろう﹂と。 どうしてこんなことになっているのか。器械体操のケガで一時期車いす生活をしたこと、実家が介護の会社であったことから、大学は社会福祉学科に。ミッション系の大学で福祉を学んだ結果、なぜか﹁お金持ちになりたい﹂と思い、外資系コンサル会社に就職。20代で年収1000万円を目標に、ひたすら働いていた。10時に出社して一息つくのが夜の10時。退社するのは午前2時で、タクシーで帰宅するのは午前3時。体育会系で鍛えた若い20代でも限界を超えたのか、玄関で倒れてしまったのだった。 飛び乗った電車の中でモヤモヤと考えていたら、気付けば会社の自席に座っていた。あまりにも疲れていて仕事にならない。上司に﹁体調が悪いので﹂と言って早退した。帰宅してゆっくり考えてみた。そもそも、自分は何がしたかったのか。高校生の時、車いすの自分が乗り込めるスペースが空いておらず、何度もエレベーターをやり過ごした。﹁こんな辛い想いをする人を減らしたい﹂と強く思い、決死の覚悟で受験勉強し大学にたどり着いたのだった。﹁やはり人を支える仕事がしたい﹂と思い返し、すぐに退職届を出した。 介護の仕事を始めて20年ほど経ったが、﹁人を支える意味﹂を未だ言語化できていない。自宅で寝たきりの方の入浴をお手伝いする﹁訪問入浴﹂で、懸命な介護の末に家族を虐待してしまう場面を、何度も目の当たりにした。もっと早く支援を届ければ、家族による虐待を防げるのではと考え、企業にアウトリーチして、介護セミナーや個別相談をする事業を立ち上げた。今では年700件以上の相談を受けるようになり﹁〝支える〟とは〝与えてもらう〟こと﹂ではないかと気付いた。高齢者を支援する目的は﹁高齢者の生き様から学ぶこと﹂ではないか。 先日もデイサービスに通う高齢女性に﹁90年以上生きてきて、朝起きが面倒になりませんか?﹂とぶしつけに聞くと、その女性は苦笑いしながら﹁そんなことあるわけないでしょ。生きてるんだから﹂とパシッと頬を叩かれるような返答だった。戦火や貧しい時代を生き抜いたからこその率直な言葉から、やはり私は〝与えていただいた〟のだった。﹁そうですよね。勉強になります﹂と言うと、ニッコリ嬉しそうな表情だった。 私は、相談者の悩みごとを聞きながら、高齢者のその人らしい生き方を想像し、一つひとつの体験を学ばせていただくことが、よりよい介護を目指す礎になると信じている。これが自分にとっての﹁創る﹂なのだろう。32KAJIMA202502かわうち・じゅん 1980年生まれ。上智大学文学部社会福祉学科卒業。老人ホーム紹介事業、外資系コンサル会社、在宅・施設介護職員を経て、2008年に市民団体「となりのかいご」設立。2014年に「となりのかいご」をNPO法人化、代表理事に就任。厚生労働省「令和2年度仕事と介護の両立支援カリキュラム事業」委員、育児・介護休業法改正では国会に参考人として出席。著書に『親不孝介護 距離を取るからうまくいく』(共著)、『わたしたちの親不孝介護 「親孝行の呪い」から自由になろう』(ともに日経BP)、近著に『親の介護の「やってはいけない」』(青春出版社)など。vol.242
ある日、私は、靴を履いたまま、一人暮らしをしている都内のアパートの玄関に倒れていた。目を覚まして時間を見ると遅刻ギリギリで、そのまま玄関を飛び出した。駅まで走り電車に乗ってふと思った。﹁自分は何をしているのだろう﹂と。 どうしてこんなことになっているのか。器械体操のケガで一時期車いす生活をしたこと、実家が介護の会社であったことから、大学は社会福祉学科に。ミッション系の大学で福祉を学んだ結果、なぜか﹁お金持ちになりたい﹂と思い、外資系コンサル会社に就職。20代で年収1000万円を目標に、ひたすら働いていた。10時に出社して一息つくのが夜の10時。退社するのは午前2時で、タクシーで帰宅するのは午前3時。体育会系で鍛えた若い20代でも限界を超えたのか、玄関で倒れてしまったのだった。 飛び乗った電車の中でモヤモヤと考えていたら、気付けば会社の自席に座っていた。あまりにも疲れていて仕事にならない。上司に﹁体調が悪いので﹂と言って早退した。帰宅してゆっくり考えてみた。そもそも、自分は何がしたかったのか。高校生の時、車いすの自分が乗り込めるスペースが空いておらず、何度もエレベーターをやり過ごした。﹁こんな辛い想いをする人を減らしたい﹂と強く思い、決死の覚悟で受験勉強し大学にたどり着いたのだった。﹁やはり人を支える仕事がしたい﹂と思い返し、すぐに退職届を出した。 介護の仕事を始めて20年ほど経ったが、﹁人を支える意味﹂を未だ言語化できていない。自宅で寝たきりの方の入浴をお手伝いする﹁訪問入浴﹂で、懸命な介護の末に家族を虐待してしまう場面を、何度も目の当たりにした。もっと早く支援を届ければ、家族による虐待を防げるのではと考え、企業にアウトリーチして、介護セミナーや個別相談をする事業を立ち上げた。今では年700件以上の相談を受けるようになり﹁〝支える〟とは〝与えてもらう〟こと﹂ではないかと気付いた。高齢者を支援する目的は﹁高齢者の生き様から学ぶこと﹂ではないか。 先日もデイサービスに通う高齢女性に﹁90年以上生きてきて、朝起きが面倒になりませんか?﹂とぶしつけに聞くと、その女性は苦笑いしながら﹁そんなことあるわけないでしょ。生きてるんだから﹂とパシッと頬を叩かれるような返答だった。戦火や貧しい時代を生き抜いたからこその率直な言葉から、やはり私は〝与えていただいた〟のだった。﹁そうですよね。勉強になります﹂と言うと、ニッコリ嬉しそうな表情だった。 私は、相談者の悩みごとを聞きながら、高齢者のその人らしい生き方を想像し、一つひとつの体験を学ばせていただくことが、よりよい介護を目指す礎になると信じている。これが自分にとっての﹁創る﹂なのだろう。32KAJIMA202502かわうち・じゅん 1980年生まれ。上智大学文学部社会福祉学科卒業。老人ホーム紹介事業、外資系コンサル会社、在宅・施設介護職員を経て、2008年に市民団体「となりのかいご」設立。2014年に「となりのかいご」をNPO法人化、代表理事に就任。厚生労働省「令和2年度仕事と介護の両立支援カリキュラム事業」委員、育児・介護休業法改正では国会に参考人として出席。著書に『親不孝介護 距離を取るからうまくいく』(共著)、『わたしたちの親不孝介護 「親孝行の呪い」から自由になろう』(ともに日経BP)、近著に『親の介護の「やってはいけない」』(青春出版社)など。vol.242