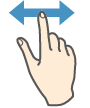1 ゲラルドゥス・メルカトルの世界地図(1569年)GerardMercator,Novaetauctaorbisterraedescriptioadusumnavigantiumemendateaccomodata:illustriss..principi..WilhelmoDucijuliae,ClivorumetMontiOpushoc..eiusauspiciisinchoatum../GerardusMercatordedicabat,1569図版提供:BibliothèquenationaledeFrance#1どこでもない世界の眺め
1 ゲラルドゥス・メルカトルの世界地図(1569年)GerardMercator,Novaetauctaorbisterraedescriptioadusumnavigantiumemendateaccomodata:illustriss..principi..WilhelmoDucijuliae,ClivorumetMontiOpushoc..eiusauspiciisinchoatum../GerardusMercatordedicabat,1569図版提供:BibliothèquenationaledeFrance#1どこでもない世界の眺め
 2 ニコラ・サンソンの円形地図(1658年)NicolasSanson,Cartesgeneralesdetouteslespartiesdumonde,oulesempires,monarchies,republiques,estats,peuples,&c.del’Asie,del’Afrique,del’Europe,&del’Americque,tantanciensquenouveaux,sontexactementremarqués,&distinguéssuivantleurestendue.ParleSieurSansond’Abbeville,GeographeordinaireduRoy,1658図版提供:BibliothèquenationaledeFrance3 バックミンスター・フラーのダイマクション地図(1952年)R.BuckminsterFuller&ShojiSadao,TheDymaxionAiroceanWorldMap,StudentPublicationsoftheSchoolofDesign,1952図版提供:TheEstateofR.BuckminsterFullerカトルに由来する。彼は16世紀のフランドルで活動した地理学者で地図製作者だった。前頁はメルカトルによる1569年の世界地図だ1。天のほうにラテン語で「航海の用途に適した全世界の新しくいっそう完全な描写」という意味のタイトルが記されている。世界に未知の地域が残っていた時代のこと,探検や航海から戻った人びとの報告や各種の情報と想像を総合してこうした地図も作られていた。それだけに現在の眼からは奇妙に見える箇所も少なくない。 さて,この地図でメルカトルは航海する人たちに便利なようにと,経緯線を方眼紙のように直交する直線で描いてみせた。こうすれば,どこにいても目的地への角度を正確に把握できるし,航程を地図の上で直線として扱えて便利というわけだ。 ただし,この工夫には犠牲が伴う。なにしろ緯線は,球体上では赤道を最大と世界地図はなんだか不思議でおもしろい。あまりにも見慣れていると,そんなふうには感じないかもしれないが,世界地図を目にするつど,私たちは現実にはあり得ないどこかへ連れてゆかれる。 ちょっと想像してみよう。もし空を自由に飛び回れたら,この地図のようにものが見える場所に行けるだろうか。地上を後にして高度を上げてゆく。それまで見下ろせば視野いっぱいに大地が広がっていたところ,地球の輪郭が見えはじめ,やがて円となり,徐々に小さくなってゆくだろう。このとき地球の表面には,世界の一部だけが見えているはずだ。もしそうだとしたら,世界地図を眺めるとき,私たちはなにを目にしていることになるのか。 お馴染みの地図作成法の一つにメルカトル図法がある。製作者ゲルハルト・クレメルのラテン語名ゲラルドゥス・メル214KAJIMA202504
2 ニコラ・サンソンの円形地図(1658年)NicolasSanson,Cartesgeneralesdetouteslespartiesdumonde,oulesempires,monarchies,republiques,estats,peuples,&c.del’Asie,del’Afrique,del’Europe,&del’Americque,tantanciensquenouveaux,sontexactementremarqués,&distinguéssuivantleurestendue.ParleSieurSansond’Abbeville,GeographeordinaireduRoy,1658図版提供:BibliothèquenationaledeFrance3 バックミンスター・フラーのダイマクション地図(1952年)R.BuckminsterFuller&ShojiSadao,TheDymaxionAiroceanWorldMap,StudentPublicationsoftheSchoolofDesign,1952図版提供:TheEstateofR.BuckminsterFullerカトルに由来する。彼は16世紀のフランドルで活動した地理学者で地図製作者だった。前頁はメルカトルによる1569年の世界地図だ1。天のほうにラテン語で「航海の用途に適した全世界の新しくいっそう完全な描写」という意味のタイトルが記されている。世界に未知の地域が残っていた時代のこと,探検や航海から戻った人びとの報告や各種の情報と想像を総合してこうした地図も作られていた。それだけに現在の眼からは奇妙に見える箇所も少なくない。 さて,この地図でメルカトルは航海する人たちに便利なようにと,経緯線を方眼紙のように直交する直線で描いてみせた。こうすれば,どこにいても目的地への角度を正確に把握できるし,航程を地図の上で直線として扱えて便利というわけだ。 ただし,この工夫には犠牲が伴う。なにしろ緯線は,球体上では赤道を最大と世界地図はなんだか不思議でおもしろい。あまりにも見慣れていると,そんなふうには感じないかもしれないが,世界地図を目にするつど,私たちは現実にはあり得ないどこかへ連れてゆかれる。 ちょっと想像してみよう。もし空を自由に飛び回れたら,この地図のようにものが見える場所に行けるだろうか。地上を後にして高度を上げてゆく。それまで見下ろせば視野いっぱいに大地が広がっていたところ,地球の輪郭が見えはじめ,やがて円となり,徐々に小さくなってゆくだろう。このとき地球の表面には,世界の一部だけが見えているはずだ。もしそうだとしたら,世界地図を眺めるとき,私たちはなにを目にしていることになるのか。 お馴染みの地図作成法の一つにメルカトル図法がある。製作者ゲルハルト・クレメルのラテン語名ゲラルドゥス・メル214KAJIMA202504
 デザイン―江川拓未(鹿島出版会)して極に向かうにつれて小さくなってゆく円である。これをすべて同じ長さの直線にして並べようというのだから無理もない。理屈はともかく結果はご覧の通りで,赤道を上下に離れるにつれて大陸や島が実際より大きくなっている。極に至っては,地図の天と地に帯のように果てのない場所として広がってしまっている。もちろんメルカトルもそれは先刻承知で,北極付近はうまく描けないからと,左下に別途北極の地図を載せている。 球体を平面に変換するには,なにかを選んでなにかを捨てねばならない。その取捨選択は,地図を作る人の目的による。メルカトルのように船乗りたちのためにと面積の正確さは捨てて角度を採る人もあれば,ともかく面積や縮尺を適切に比べたいという用途もある。古来そうしたさまざまな技法が工夫されており,それだけで何冊もの本になるほど。ここでは見比べる参考に17世紀フランスの地図製作者ニコラ・サンソンの円形地図2 と,バックミンスター・フラーが地球を多面体に仕立てたダイマクション地図3 を並べてみた。それぞれの狙いはいずこに,と考える楽しみは読者にとっておこう。 いずれにしても世界地図には,誰もそのように見たことがない,どこからでもない世界の見方が表されている。他方でこれを眺める私たちは,知らず識らずのうちに「世界とはこういうものだ」と思い込んだりするのだからおもしろい。山本貴光 TakamitsuYAMAMOTO文筆家,ゲーム作家,大学教員。著書に『文学のエコロジー』『記憶のデザイン』『マルジナリアでつかまえて』『文学問題(F+f)+』『「百学連環」を読む』他。共著に『図書館を建てる,図書館で暮らす』(橋本麻里と),『高校生のためのゲームで考える人工知能』(三宅陽一郎と),『人文的,あまりに人文的』(吉川浩満と)他。2021年から東京科学大学(旧東京工業大学)リベラルアーツ研究教育院教授。315KAJIMA202504
デザイン―江川拓未(鹿島出版会)して極に向かうにつれて小さくなってゆく円である。これをすべて同じ長さの直線にして並べようというのだから無理もない。理屈はともかく結果はご覧の通りで,赤道を上下に離れるにつれて大陸や島が実際より大きくなっている。極に至っては,地図の天と地に帯のように果てのない場所として広がってしまっている。もちろんメルカトルもそれは先刻承知で,北極付近はうまく描けないからと,左下に別途北極の地図を載せている。 球体を平面に変換するには,なにかを選んでなにかを捨てねばならない。その取捨選択は,地図を作る人の目的による。メルカトルのように船乗りたちのためにと面積の正確さは捨てて角度を採る人もあれば,ともかく面積や縮尺を適切に比べたいという用途もある。古来そうしたさまざまな技法が工夫されており,それだけで何冊もの本になるほど。ここでは見比べる参考に17世紀フランスの地図製作者ニコラ・サンソンの円形地図2 と,バックミンスター・フラーが地球を多面体に仕立てたダイマクション地図3 を並べてみた。それぞれの狙いはいずこに,と考える楽しみは読者にとっておこう。 いずれにしても世界地図には,誰もそのように見たことがない,どこからでもない世界の見方が表されている。他方でこれを眺める私たちは,知らず識らずのうちに「世界とはこういうものだ」と思い込んだりするのだからおもしろい。山本貴光 TakamitsuYAMAMOTO文筆家,ゲーム作家,大学教員。著書に『文学のエコロジー』『記憶のデザイン』『マルジナリアでつかまえて』『文学問題(F+f)+』『「百学連環」を読む』他。共著に『図書館を建てる,図書館で暮らす』(橋本麻里と),『高校生のためのゲームで考える人工知能』(三宅陽一郎と),『人文的,あまりに人文的』(吉川浩満と)他。2021年から東京科学大学(旧東京工業大学)リベラルアーツ研究教育院教授。315KAJIMA202504