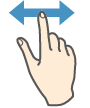21KAJIMA202504永富家の歴史 兵庫県姫路市から西へ約15キロ,播磨平野西部を流れる一級河川・揖保川の下流域に位置する揖保郡半田村(現・たつの市揖保川町)の新在家にある永富家。守之助は永富家19代当主・敏夫の四男として1896(明治29)年に生まれ,17歳で京都の第三高等学校(三高)に入学するまでこの家に育った。 永富家は室町時代初期にこの地に居を構え,江戸時代には代々庄屋を務めた。地帳(土地台帳)に基づき,田ごとの年貢を集め,龍野藩の藩主へ納めた。江戸時代中期以降には,藩内で重要な位置を占めるに至り,藩主・脇坂家より「在郷家臣」として上級武士の待遇を受け,名字帯刀を許された。 南北朝・室町時代,永富左衛門六郎の娘は,能楽の祖・観阿弥清次の妻であり,世阿弥元清の母である。後に世阿弥の曽孫にあたる元定は,永富家に5代目当主として入っている。また,武将である楠木正成の父・正遠の娘(正成の妹)が観阿弥の母だったことから,永富家にとって楠木家は身近な縁戚のひとつだった。 江戸文化成熟時代の永富家当主・六郎兵衛定村(定群)(1798-1861)は,和歌,茶道,生け花をたしなみ,34年間に22冊にわたる「高関堂日記」を残した。これは後にまとめられ,鹿島出版会から出版されている。 永富家住宅の大改修は,文政年間(1818-30)に行われた。周囲に土塀を巡らした古式ゆかしい武家屋敷風に造られており,特異な家格を示している。守之助を囲む人びと 守之助の父・永富敏夫(1863-1913)は「撫松山人」と号し,名利や世俗に恬淡で,孤高を愛する漢詩人として関西詩壇に名を響かせていた。陶淵明※に私淑し,晩年の居所を「春及廬」と名付けた。この名は雅号と同様,陶淵明の「帰去来時」に由来している。 母・くわん(通称・とよ)は,播州相生(現在の兵庫県南西部)の岡田家出身。兄・太郎は大地主で,那波銀行を創立し,塩田や植林などの事業にも熱心だった。※陶淵明(365-427)は,中国の魏晋南北朝時代(六朝期)の東晋末から南朝宋頃の文学者。郷里の田園に隠遁後は,自ら農作業に従事しつつ,日常生活に即した詩文を多く残し,「隠逸詩人」「田園詩人」と呼ばれた*永富家住宅は一般公開されているが,本年7月末から耐震改修のため一時閉館予定(再開時期未定)龍野中学時代の守之助タイトルバック:長屋門鹿島守之助会長没後50年という節目の年を迎え,2月号の特集に続く特別連載(隔月)として,その事跡を振り返っていく。第1回は守之助を形作ってきた背景となる生家,永富家を紹介する。守之助は,家族や従兄,友人たちに囲まれ,さまざまな影響を受けながら,中学時代まで生まれ育ったこの地で過ごした。第1回守之助揺籃の地と永富家 守之助は少年時代,父から『論語』や『十八史略』などの素読を受け,父を模範とし,よく学んだ。1908(明治41)年,龍野中学に入学すると,京都帝国大学文学部に在学する長兄・勝質の文学書や哲学書を学校で仲間と回覧し,同人雑誌を作った。そこから成功した中に,三木哲学の三木清がいる。文学愛好の同人には,後に医学博士になった沢野哲三もいた。また,従兄の内藤吉之助は,文学雑誌の懸賞小説によく入選するなど文才に優れ,後に京城帝国大学の法制史の教授となった。このほか,後に理学博士,東京帝国大学理学部長,国立科学博物館館長となる従兄の岡田要とは,夏休みになると2人で揖保川へアユやフナを捕りにいった。 家族や従兄,友人たちからさまざまな影響を受けて育った守之助は,1913(大正2)年,第三高等学校に入学すると哲学に傾倒するようになり,とくにベルクソン哲学の「創造的進化論」に大きな影響を受けた。この思想は守之助の一生を貫いていくものとなる。 [第2回(6月号)に続く]父・永富敏夫長兄・永富勝質主屋。左から玄関(藩主専用),中玄関(藩主以外の客人と主人),大戸口(家族、使用人)を設け,身分によって使い分けた秋恵園。6月には池の周囲に花菖蒲が咲く 永富家住宅の敷地面積は2,670m2。主屋は1822(文政5)年に完成したもので,建築面積478m2,延べ506m2,屋根は入母屋造・本瓦葺となっている。主屋をはじめ,長屋門,籾納屋,大蔵,乾蔵,内蔵,味噌蔵,東蔵の8棟は,ほぼ同時期に建てられたもので「播州平野における江戸末期豪農の家としてとくにすぐれるもの」(文化庁「国指定文化財等データベース」)として,1967(昭和42)年,国の重要文化財に指定された。また,建築当時の設計図「板絵図」と「永重要文化財「永富家住宅」と付属庭園「秋恵園」column富家住宅普請張」13冊も重要文化財である。 永富家住宅の付属庭園「秋恵園」には,2,425m2の庭内に,鹿島家寄せ書の碑,撫松山人詩碑,パン・アジアの碑,定群歌碑,世阿弥の母の像などが設けられ,錦鯉が泳ぐ大きな池のまわりは花菖蒲や藤棚など季節の花々が楽しめるしつらえになっている。鹿島守之助没後50年特別連載(全5回)
21KAJIMA202504永富家の歴史 兵庫県姫路市から西へ約15キロ,播磨平野西部を流れる一級河川・揖保川の下流域に位置する揖保郡半田村(現・たつの市揖保川町)の新在家にある永富家。守之助は永富家19代当主・敏夫の四男として1896(明治29)年に生まれ,17歳で京都の第三高等学校(三高)に入学するまでこの家に育った。 永富家は室町時代初期にこの地に居を構え,江戸時代には代々庄屋を務めた。地帳(土地台帳)に基づき,田ごとの年貢を集め,龍野藩の藩主へ納めた。江戸時代中期以降には,藩内で重要な位置を占めるに至り,藩主・脇坂家より「在郷家臣」として上級武士の待遇を受け,名字帯刀を許された。 南北朝・室町時代,永富左衛門六郎の娘は,能楽の祖・観阿弥清次の妻であり,世阿弥元清の母である。後に世阿弥の曽孫にあたる元定は,永富家に5代目当主として入っている。また,武将である楠木正成の父・正遠の娘(正成の妹)が観阿弥の母だったことから,永富家にとって楠木家は身近な縁戚のひとつだった。 江戸文化成熟時代の永富家当主・六郎兵衛定村(定群)(1798-1861)は,和歌,茶道,生け花をたしなみ,34年間に22冊にわたる「高関堂日記」を残した。これは後にまとめられ,鹿島出版会から出版されている。 永富家住宅の大改修は,文政年間(1818-30)に行われた。周囲に土塀を巡らした古式ゆかしい武家屋敷風に造られており,特異な家格を示している。守之助を囲む人びと 守之助の父・永富敏夫(1863-1913)は「撫松山人」と号し,名利や世俗に恬淡で,孤高を愛する漢詩人として関西詩壇に名を響かせていた。陶淵明※に私淑し,晩年の居所を「春及廬」と名付けた。この名は雅号と同様,陶淵明の「帰去来時」に由来している。 母・くわん(通称・とよ)は,播州相生(現在の兵庫県南西部)の岡田家出身。兄・太郎は大地主で,那波銀行を創立し,塩田や植林などの事業にも熱心だった。※陶淵明(365-427)は,中国の魏晋南北朝時代(六朝期)の東晋末から南朝宋頃の文学者。郷里の田園に隠遁後は,自ら農作業に従事しつつ,日常生活に即した詩文を多く残し,「隠逸詩人」「田園詩人」と呼ばれた*永富家住宅は一般公開されているが,本年7月末から耐震改修のため一時閉館予定(再開時期未定)龍野中学時代の守之助タイトルバック:長屋門鹿島守之助会長没後50年という節目の年を迎え,2月号の特集に続く特別連載(隔月)として,その事跡を振り返っていく。第1回は守之助を形作ってきた背景となる生家,永富家を紹介する。守之助は,家族や従兄,友人たちに囲まれ,さまざまな影響を受けながら,中学時代まで生まれ育ったこの地で過ごした。第1回守之助揺籃の地と永富家 守之助は少年時代,父から『論語』や『十八史略』などの素読を受け,父を模範とし,よく学んだ。1908(明治41)年,龍野中学に入学すると,京都帝国大学文学部に在学する長兄・勝質の文学書や哲学書を学校で仲間と回覧し,同人雑誌を作った。そこから成功した中に,三木哲学の三木清がいる。文学愛好の同人には,後に医学博士になった沢野哲三もいた。また,従兄の内藤吉之助は,文学雑誌の懸賞小説によく入選するなど文才に優れ,後に京城帝国大学の法制史の教授となった。このほか,後に理学博士,東京帝国大学理学部長,国立科学博物館館長となる従兄の岡田要とは,夏休みになると2人で揖保川へアユやフナを捕りにいった。 家族や従兄,友人たちからさまざまな影響を受けて育った守之助は,1913(大正2)年,第三高等学校に入学すると哲学に傾倒するようになり,とくにベルクソン哲学の「創造的進化論」に大きな影響を受けた。この思想は守之助の一生を貫いていくものとなる。 [第2回(6月号)に続く]父・永富敏夫長兄・永富勝質主屋。左から玄関(藩主専用),中玄関(藩主以外の客人と主人),大戸口(家族、使用人)を設け,身分によって使い分けた秋恵園。6月には池の周囲に花菖蒲が咲く 永富家住宅の敷地面積は2,670m2。主屋は1822(文政5)年に完成したもので,建築面積478m2,延べ506m2,屋根は入母屋造・本瓦葺となっている。主屋をはじめ,長屋門,籾納屋,大蔵,乾蔵,内蔵,味噌蔵,東蔵の8棟は,ほぼ同時期に建てられたもので「播州平野における江戸末期豪農の家としてとくにすぐれるもの」(文化庁「国指定文化財等データベース」)として,1967(昭和42)年,国の重要文化財に指定された。また,建築当時の設計図「板絵図」と「永重要文化財「永富家住宅」と付属庭園「秋恵園」column富家住宅普請張」13冊も重要文化財である。 永富家住宅の付属庭園「秋恵園」には,2,425m2の庭内に,鹿島家寄せ書の碑,撫松山人詩碑,パン・アジアの碑,定群歌碑,世阿弥の母の像などが設けられ,錦鯉が泳ぐ大きな池のまわりは花菖蒲や藤棚など季節の花々が楽しめるしつらえになっている。鹿島守之助没後50年特別連載(全5回)