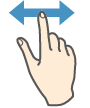絵を描くことが幼魚︵こども︶の頃から大好きです。ものギョころ︵物心︶つく頃には、ダンプカーやゴミ収集車などの働く車をわくわくしながら見ては描いていました。とくに! お気に入りの角度は斜め45度。お魚もその角度から見て描くと、両目が見え、表情や姿形の全体もよく捉えられます。人は挨拶する時に顔と顔を合わせますが、お魚とのギョミュニケーションも一緒。正面を見た時﹁こんなお顔をしていたんだ!﹂と発見があります。 お魚は観察がすギョく大事。一つひとつのお魚の形や色、模様の細部までじっくり見ます。時にはまな板に載せ、鰭や鱗の数まで数えて描きます。さかなクンの描いた絵を観て下さっているのか、最近では全国各地のお子さんの描くお魚の絵には、両目が向いた正面のお顔もあり、嬉しくなります。 小学生の時、友達が描いたタコちゃんの絵に感激し、夢中になって図鑑で調べるうちに生きた姿を見たくなり、ついに海に出かけるようになりました。﹁うわあ、こんなところにいた!﹂﹁何この力!ひきずりこまれそう!﹂。海で生き物に出会い、その感動冷めやらぬうちに絵に描く。漁師さんのお船に乗せていただいたり、釣りをしたり、海に潜ったりするようになった今も毎日、お魚に夢中です。自分の目で見て、手で触れ、耳で聞き、鼻で嗅ぎ、舌で味わう﹁ギョ︵五︶感﹂で得た情報こそが、生きた学びでギョざいます。 世界に約3万種、日本に4千種以上も知られるお魚のそれぞれに、固有の特徴や魅力があります。たとえば、名前の通り箱形の体をしたハコフグちゃんは、触ってみるとカチカチに硬い。よく見ると、ギョ角形や六角形をした鱗の一枚一枚が、ジグソーパズルのように繋ぎ合わさり、ハチの巣のようなハニカム構造をしているのです。それでも敵から食べられそうになると、パフトキシンという毒を体表から放出します。でもそれはあくまで防御のため。それぞれの厳しい生存競争の中で、お魚たちはいろんな手段を使って生き抜いています。 テレビ番組の撮影で五島列島の海に潜ったある時には、洋上風力発電が立つはるか沖合で、タワーの周囲に海藻が繁り、サンゴがくっつき、なんと岸近くの海にいるはずのイソギンチャクとクマノミちゃんが共生する光景がありました。﹁あなたたちはどうやってここまできたの?﹂。卵のうちに沖まで流れたとして、付着できる場所が沖合にあったから奇跡のように生き延びた!!お魚たちはどんな場所でも懸命に生きているのです。 地球温暖化により、獲れるお魚の種類や場所、時期などが変化しています。このままの状況が続くと、2048年には食卓から食用魚が消えるという説もあります。でも、たくましいお魚たちは、変化する環境にあわせ、臨機応変にライフスタイルを変えて生きています。じつは私たちの起源もお魚。そのお魚たちが、身をもって私たちに教えてくれることもしっかり伝えていきたいです。26KAJIMA202504さかなクン 東京都出身、千葉県館山市在住。画家。東京海洋大学名誉博士・客員教授。様々なお魚の情報や知識・美味しい食べ方や環境問題などについて全国各地で講演を行う。2010年には絶滅したと思われていたクニマスの生息確認に貢献。さらに海洋に関する普及・啓発活動の功績が認められ、2012年「海洋立国推進功労者」として内閣総理大臣賞を受賞。2021年外務省「海とさかなの親善大使」、2021年環境省「サステナビリティ広報大使」。2022年には自叙伝『さかなクンの一魚一会∼まいにち夢中な人生』(講談社、2016年)を原作とした映画「さかなのこ」が公開。『朝日小学生新聞』にて「おしえてさかなクン」コラムを連載中。NHKEテレにて出演番組『ギョギョッとサカナ★スター』が放映中。vol.244
絵を描くことが幼魚︵こども︶の頃から大好きです。ものギョころ︵物心︶つく頃には、ダンプカーやゴミ収集車などの働く車をわくわくしながら見ては描いていました。とくに! お気に入りの角度は斜め45度。お魚もその角度から見て描くと、両目が見え、表情や姿形の全体もよく捉えられます。人は挨拶する時に顔と顔を合わせますが、お魚とのギョミュニケーションも一緒。正面を見た時﹁こんなお顔をしていたんだ!﹂と発見があります。 お魚は観察がすギョく大事。一つひとつのお魚の形や色、模様の細部までじっくり見ます。時にはまな板に載せ、鰭や鱗の数まで数えて描きます。さかなクンの描いた絵を観て下さっているのか、最近では全国各地のお子さんの描くお魚の絵には、両目が向いた正面のお顔もあり、嬉しくなります。 小学生の時、友達が描いたタコちゃんの絵に感激し、夢中になって図鑑で調べるうちに生きた姿を見たくなり、ついに海に出かけるようになりました。﹁うわあ、こんなところにいた!﹂﹁何この力!ひきずりこまれそう!﹂。海で生き物に出会い、その感動冷めやらぬうちに絵に描く。漁師さんのお船に乗せていただいたり、釣りをしたり、海に潜ったりするようになった今も毎日、お魚に夢中です。自分の目で見て、手で触れ、耳で聞き、鼻で嗅ぎ、舌で味わう﹁ギョ︵五︶感﹂で得た情報こそが、生きた学びでギョざいます。 世界に約3万種、日本に4千種以上も知られるお魚のそれぞれに、固有の特徴や魅力があります。たとえば、名前の通り箱形の体をしたハコフグちゃんは、触ってみるとカチカチに硬い。よく見ると、ギョ角形や六角形をした鱗の一枚一枚が、ジグソーパズルのように繋ぎ合わさり、ハチの巣のようなハニカム構造をしているのです。それでも敵から食べられそうになると、パフトキシンという毒を体表から放出します。でもそれはあくまで防御のため。それぞれの厳しい生存競争の中で、お魚たちはいろんな手段を使って生き抜いています。 テレビ番組の撮影で五島列島の海に潜ったある時には、洋上風力発電が立つはるか沖合で、タワーの周囲に海藻が繁り、サンゴがくっつき、なんと岸近くの海にいるはずのイソギンチャクとクマノミちゃんが共生する光景がありました。﹁あなたたちはどうやってここまできたの?﹂。卵のうちに沖まで流れたとして、付着できる場所が沖合にあったから奇跡のように生き延びた!!お魚たちはどんな場所でも懸命に生きているのです。 地球温暖化により、獲れるお魚の種類や場所、時期などが変化しています。このままの状況が続くと、2048年には食卓から食用魚が消えるという説もあります。でも、たくましいお魚たちは、変化する環境にあわせ、臨機応変にライフスタイルを変えて生きています。じつは私たちの起源もお魚。そのお魚たちが、身をもって私たちに教えてくれることもしっかり伝えていきたいです。26KAJIMA202504さかなクン 東京都出身、千葉県館山市在住。画家。東京海洋大学名誉博士・客員教授。様々なお魚の情報や知識・美味しい食べ方や環境問題などについて全国各地で講演を行う。2010年には絶滅したと思われていたクニマスの生息確認に貢献。さらに海洋に関する普及・啓発活動の功績が認められ、2012年「海洋立国推進功労者」として内閣総理大臣賞を受賞。2021年外務省「海とさかなの親善大使」、2021年環境省「サステナビリティ広報大使」。2022年には自叙伝『さかなクンの一魚一会∼まいにち夢中な人生』(講談社、2016年)を原作とした映画「さかなのこ」が公開。『朝日小学生新聞』にて「おしえてさかなクン」コラムを連載中。NHKEテレにて出演番組『ギョギョッとサカナ★スター』が放映中。vol.244