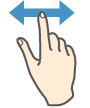KAJIMA20251120Kboard宮城県で「県民会館・NPOプラザ複合施設新築工事」が着工2025年度期央経営総合会議開催 10月3日,当社KIビル(東京都港区)で,2025年度期央経営総合会議が開催された。 天野社長は会議冒頭の訓示で,期首に掲げた目標の達成に向け業績が順調に推移していることに関し,社員の日々の努力に謝意を述べた。また,こうした時こそ「良質な危機感」をもってリスクに備える必要があると呼び掛け,当社事業の根幹である安全・品質の確保の重要性について改めて強調した。特に安全に関しては,過去の事例を記憶に残し,社員個々の危険感受性を高めることが重要 7月30日,宮城県が整備する「県民会館・NPOプラザ複合施設新築工事」の起工式が仙台市宮城野区の現地で行われ,事業・工事関係者が工事の安全を祈願した。 当プロジェクトは,老朽化が進む県民会館とみやぎNPOプラザを旧仙台医療センターの跡地約5.3haに移転・集約し,文化芸術と市民活動の融合による交流・協働・創造の拠点を整備するもの。施設は地上4階,地下1階建てで,観客の臨場感と快適性を重視し,東北最大級の規模となる2,147席の大ホール,多様な芸術表現に対応可能なスタジオシアター(578席,スタンディング時最大約1,600人収容)のほか,交流サロンや会議室などからなるNPOであると述べた。 会議では,本社各部門から今年度の経営目標達成状況と重点施策の取組み状況について説明があり,下期の課題と取組みの方向性を共有した。続いて,各部門からナレッジの整備・活用状況エリア,ギャラリーなどで構成。和歌にも詠まれた宮城野の風景に調和する伸びやかな大屋根のもと,人々の活動をつなぐ「交流ひろば」を中心に各種機能が配置される。 建築工事を担当する当社は,電気・空調・衛生・舞台設備工事を担当する各社と連携し,無事故・無災害で精度の高い施工を目受賞者集合写真西側外観イメージ県民会館・NPOプラザ複合施設新築工事場所:仙台市宮城野区発注者:宮城県設計・監理:石本建築事務所規模:複合施設棟̶SRC造一部RC・S造(免震構造) B1,4F 付属棟(屋外便所棟,屋外通路棟,駐車場通路棟)ほか 総延べ32,308m2工期:2025年7月∼2028年11月(東北支店JV施工)会議の様子および,安全・コンプライアンス・DE&Iに関する取組み状況等について,動画を交え報告された。 このほか,「2024年度社長賞(2025年度期央表彰)」の受賞案件も紹介された。(2025年度期央表彰)2024年度社長賞【工事表彰(土木)】日本原子力発電日本原電防潮堤工事(関東支店)京浜急行電鉄大師線連続立体交差事業第1期第3工区土木工事(横浜支店)阪神高速道路海老江工区開削トンネル工事(関西支店)【工事表彰(建築)】ベルーナ(仮称)札幌ホテル計画新築工事(北海道支店)(仮称)三井リンクラボ新木場3新築工事(東京建築支店)日揮中外藤枝FJ3計画(横浜支店)2025年大阪・関西万博福岡館建設工事(関西支店)日立ハイテク笠戸製造新棟建設工事(中国支店)(仮称)杉乃井ホテルスタンダード新棟新築工事(九州支店)【開発事業表彰】浜松町二丁目地区市街地再開発事業(開発事業本部)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦指す。竣工は2028年11月を予定している。
KAJIMA20251120Kboard宮城県で「県民会館・NPOプラザ複合施設新築工事」が着工2025年度期央経営総合会議開催 10月3日,当社KIビル(東京都港区)で,2025年度期央経営総合会議が開催された。 天野社長は会議冒頭の訓示で,期首に掲げた目標の達成に向け業績が順調に推移していることに関し,社員の日々の努力に謝意を述べた。また,こうした時こそ「良質な危機感」をもってリスクに備える必要があると呼び掛け,当社事業の根幹である安全・品質の確保の重要性について改めて強調した。特に安全に関しては,過去の事例を記憶に残し,社員個々の危険感受性を高めることが重要 7月30日,宮城県が整備する「県民会館・NPOプラザ複合施設新築工事」の起工式が仙台市宮城野区の現地で行われ,事業・工事関係者が工事の安全を祈願した。 当プロジェクトは,老朽化が進む県民会館とみやぎNPOプラザを旧仙台医療センターの跡地約5.3haに移転・集約し,文化芸術と市民活動の融合による交流・協働・創造の拠点を整備するもの。施設は地上4階,地下1階建てで,観客の臨場感と快適性を重視し,東北最大級の規模となる2,147席の大ホール,多様な芸術表現に対応可能なスタジオシアター(578席,スタンディング時最大約1,600人収容)のほか,交流サロンや会議室などからなるNPOであると述べた。 会議では,本社各部門から今年度の経営目標達成状況と重点施策の取組み状況について説明があり,下期の課題と取組みの方向性を共有した。続いて,各部門からナレッジの整備・活用状況エリア,ギャラリーなどで構成。和歌にも詠まれた宮城野の風景に調和する伸びやかな大屋根のもと,人々の活動をつなぐ「交流ひろば」を中心に各種機能が配置される。 建築工事を担当する当社は,電気・空調・衛生・舞台設備工事を担当する各社と連携し,無事故・無災害で精度の高い施工を目受賞者集合写真西側外観イメージ県民会館・NPOプラザ複合施設新築工事場所:仙台市宮城野区発注者:宮城県設計・監理:石本建築事務所規模:複合施設棟̶SRC造一部RC・S造(免震構造) B1,4F 付属棟(屋外便所棟,屋外通路棟,駐車場通路棟)ほか 総延べ32,308m2工期:2025年7月∼2028年11月(東北支店JV施工)会議の様子および,安全・コンプライアンス・DE&Iに関する取組み状況等について,動画を交え報告された。 このほか,「2024年度社長賞(2025年度期央表彰)」の受賞案件も紹介された。(2025年度期央表彰)2024年度社長賞【工事表彰(土木)】日本原子力発電日本原電防潮堤工事(関東支店)京浜急行電鉄大師線連続立体交差事業第1期第3工区土木工事(横浜支店)阪神高速道路海老江工区開削トンネル工事(関西支店)【工事表彰(建築)】ベルーナ(仮称)札幌ホテル計画新築工事(北海道支店)(仮称)三井リンクラボ新木場3新築工事(東京建築支店)日揮中外藤枝FJ3計画(横浜支店)2025年大阪・関西万博福岡館建設工事(関西支店)日立ハイテク笠戸製造新棟建設工事(中国支店)(仮称)杉乃井ホテルスタンダード新棟新築工事(九州支店)【開発事業表彰】浜松町二丁目地区市街地再開発事業(開発事業本部)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦指す。竣工は2028年11月を予定している。
 21KAJIMA202511「芝御成門タワー」が竣工「パナソニックHVACチェコ新P1棟」が竣工「北九州ニッスイ本社工場計画」が起工 8月29日,「パナソニックHVACチェコ新P1棟」(チェコ共和国ピルゼン市)の竣工式が現地で行われ,事業・工事関係者が多数参列し,工事の無事完成を祝った。 パナソニックHVACチェコは欧州で主流のヒートポンプ式温水給湯暖房機※の増産体制の構築を目的に新棟を建設。規模は,RC造,地上2階一部3階,延床面積10万2,433m2,設計は当社建築設計本部とカジマ・チェコ,施工はカジマ・チェコが担当した。 当社が設計・施工を担当する「北九州ニッスイ本社工場計画」(北九州市戸畑区)の起工式が,8月7日に現地で行われた。 このプロジェクトは,水産大手ニッスイが国内食品事業の成長に向け,グループ企業である北九州ニッスイの新たな本社工場を建設するもの。ニッスイグループでは,これからの国内食品工場の基本思想を,ものづくりを通じて,環境・社会・人財・経済の4つの価値を創造する「ニッスイスマートファクトリー」と定義。新工場はニッスイの企業 当社が企画・設計・施工を一貫して担い,開発を進めてきた「芝御成門タワー」(東京都港区)が完成した。7月28日,現地で事業・工事関係者が完成を祝った。 本計画では,都営三田線「御 新棟の完成で需要に合わせた製造ライン増設に加え,現在80台導入しているロボットの活用による自動化で,生産能力を年間15万台から最大約70万台まで拡張可能とする。 建物には1MWの太陽光発電システムや採光を促進する天窓を導入し,2025年中のCO2排出量ゼロ化に取り組み,環境に配慮した製品開発と事業活動でカーボンニュートラルの実現を推進していく。価値を高める象徴として,そのモデル工場となる。 新工場では,AIなどの最先端技術を活用することで,最大限に自動化した効率化ラインを構築するほか,省エネ対策,再生可能エネルギー活用に加えて非化石化証書※の入手により,カーボンニュートラルを実現する。成門」駅から徒歩2分の好立地に,S造(制振構造),地上19階,地下2階,塔屋2階,延床面積2万4,436m2の大規模オフィスビルを建設。「歴史と気品ある街並みの伝統を受け継ぐ新たなビジネス拠点」をコンセプトに,賃貸オフィスや港区最大級の規模となる認可外保育所,店舗,駐車場で構成されている。設計は当社とプランテック,建築設備設計研究所が担当した。 オフィスフロアは柱の少ない開放的な空間とグリッドシステム天井により,自由度の高いレイアウト変更がオープンスペースには四季を彩る植栽を配置し,街の賑わいづくりに貢献する可能となっている。さらに制振構造や2回線受電システムを採用し,非常時のBCP支援も行う。 環境配慮面では,高性能Low-E複層ガラスや高効率な空調室外機,加湿機能付きの全熱交換機の採用など様々な取組みを行い,BELS認証「ZEBReady」を取得。緑豊かなオープンスペースと自然との連続性の確保が評価され,生物多様性への貢献度や達成状況を評価する環境認証制度「JHEP」Aランクを取得した。完成予想図新棟外観北九州ニッスイ本社工場計画 場所:北九州市戸畑区/発注者:北九州ニッスイ設計:当社九州支店建築設計部/用途:工場/規模:S造 4F 延べ23,871m2工期:2025年4月∼2026年12月(九州支店施工)※再生可能エネルギーをはじめとする,CO2を排出しない非化石電源から発電された電力の環境価値部分を証書化したもの。再エネ由来の非化石証書であれば,通常の電力を使いながら,実質的な再エネ電力を導入できる仕組み※大気中の熱を利用して温水をつくり,建物に循環させて暖房を行う空調システムで,化石燃料を用いた暖房機器に比べCO2排出量を抑え,環境への負荷が少ない建物外観(日比谷通りから)
21KAJIMA202511「芝御成門タワー」が竣工「パナソニックHVACチェコ新P1棟」が竣工「北九州ニッスイ本社工場計画」が起工 8月29日,「パナソニックHVACチェコ新P1棟」(チェコ共和国ピルゼン市)の竣工式が現地で行われ,事業・工事関係者が多数参列し,工事の無事完成を祝った。 パナソニックHVACチェコは欧州で主流のヒートポンプ式温水給湯暖房機※の増産体制の構築を目的に新棟を建設。規模は,RC造,地上2階一部3階,延床面積10万2,433m2,設計は当社建築設計本部とカジマ・チェコ,施工はカジマ・チェコが担当した。 当社が設計・施工を担当する「北九州ニッスイ本社工場計画」(北九州市戸畑区)の起工式が,8月7日に現地で行われた。 このプロジェクトは,水産大手ニッスイが国内食品事業の成長に向け,グループ企業である北九州ニッスイの新たな本社工場を建設するもの。ニッスイグループでは,これからの国内食品工場の基本思想を,ものづくりを通じて,環境・社会・人財・経済の4つの価値を創造する「ニッスイスマートファクトリー」と定義。新工場はニッスイの企業 当社が企画・設計・施工を一貫して担い,開発を進めてきた「芝御成門タワー」(東京都港区)が完成した。7月28日,現地で事業・工事関係者が完成を祝った。 本計画では,都営三田線「御 新棟の完成で需要に合わせた製造ライン増設に加え,現在80台導入しているロボットの活用による自動化で,生産能力を年間15万台から最大約70万台まで拡張可能とする。 建物には1MWの太陽光発電システムや採光を促進する天窓を導入し,2025年中のCO2排出量ゼロ化に取り組み,環境に配慮した製品開発と事業活動でカーボンニュートラルの実現を推進していく。価値を高める象徴として,そのモデル工場となる。 新工場では,AIなどの最先端技術を活用することで,最大限に自動化した効率化ラインを構築するほか,省エネ対策,再生可能エネルギー活用に加えて非化石化証書※の入手により,カーボンニュートラルを実現する。成門」駅から徒歩2分の好立地に,S造(制振構造),地上19階,地下2階,塔屋2階,延床面積2万4,436m2の大規模オフィスビルを建設。「歴史と気品ある街並みの伝統を受け継ぐ新たなビジネス拠点」をコンセプトに,賃貸オフィスや港区最大級の規模となる認可外保育所,店舗,駐車場で構成されている。設計は当社とプランテック,建築設備設計研究所が担当した。 オフィスフロアは柱の少ない開放的な空間とグリッドシステム天井により,自由度の高いレイアウト変更がオープンスペースには四季を彩る植栽を配置し,街の賑わいづくりに貢献する可能となっている。さらに制振構造や2回線受電システムを採用し,非常時のBCP支援も行う。 環境配慮面では,高性能Low-E複層ガラスや高効率な空調室外機,加湿機能付きの全熱交換機の採用など様々な取組みを行い,BELS認証「ZEBReady」を取得。緑豊かなオープンスペースと自然との連続性の確保が評価され,生物多様性への貢献度や達成状況を評価する環境認証制度「JHEP」Aランクを取得した。完成予想図新棟外観北九州ニッスイ本社工場計画 場所:北九州市戸畑区/発注者:北九州ニッスイ設計:当社九州支店建築設計部/用途:工場/規模:S造 4F 延べ23,871m2工期:2025年4月∼2026年12月(九州支店施工)※再生可能エネルギーをはじめとする,CO2を排出しない非化石電源から発電された電力の環境価値部分を証書化したもの。再エネ由来の非化石証書であれば,通常の電力を使いながら,実質的な再エネ電力を導入できる仕組み※大気中の熱を利用して温水をつくり,建物に循環させて暖房を行う空調システムで,化石燃料を用いた暖房機器に比べCO2排出量を抑え,環境への負荷が少ない建物外観(日比谷通りから)
 22KAJIMA202511広島呉道路天応トンネルが無事に貫通TheGEARが「JAPANコンストラクション国際賞」を受賞阿知和地区工業団地跨道橋の架設工事を一晩で完了 9月9日,国土交通省主催の第8回JAPANコンストラクション国際賞の表彰式が三田共用会議所(東京都港区)で行われ,「TheGEAR」が建設・プロジェクト部門で受賞した。 同賞は,我が国の建設・不動産業の競争力の強化を図り,日系企業のさらなる海外進出を後押しするため,「質の高いインフラ」を実現する海外建設プロジェクトおよび海外において先導的に活躍してい 7月12日,当社JVが施工を担当する「岡崎市阿知和地区工業団地造成事業」(愛知県岡崎市)において,東名高速道路に跨道橋を架設する工事を一晩で実施した。 岡崎市が進める同事業では,愛知県の中央部,岡崎市の北西に位置する約63haの敷地に,新しい工業団地を整備する。今回実 当社が広島県呉市で施工を進めている「広島呉道路小屋浦トンネル他1トンネル工事」のうち,天応トンネルの貫通式が,7月30日,同トンネル内の貫通点付近で行われた。式典には,来賓をはじめ,発注者や工事関係者らが出席した。 本工事は,西日本高速道路が進める広島呉道路・坂北IC∼呉IC(約12.2km)の4車線化事業の一部。広島呉道路は平成30年7月豪雨により道路の一部が崩落し,約3ヵ月間,通行止めが続いたことから,道路ネットワークの強化を目的に,2車線から4車線に拡幅さる中堅・中小建設関連企業などを表彰するもので,2017年度に創設された。 2023年,シンガポールに開設したTheGEARは,当社のアジア本社,R&Dセンター(当社技術研究所のシンガポールオフィス「KaTRIS」),オープンイノベーションハブ機能をもつアジアの統括事業拠点である。 今回の表彰では,日本で培った多数の環境配慮技術をシンガポー施した跨道橋の架替工事は,工業団地に直結する(仮称)岡崎阿知和スマートインターチェンジを構築するための工事の一環で,2024年9月に高速道路を跨ぐ2つの橋(幅員約4m)を2夜連続で撤去。今回新たに跨道橋を架設した。 当日は,東名高速道路の岡崎IC∼豊田JCT間を夜8時から翌朝6時まで,全線通行止めにして工事を実施。新設する橋長43.5m,幅員約10m,重量約80tの鋼単純少数主桁橋は,スマートインターチェンジ敷地内のヤードで組み立てれることになった。このうち当社は,供用中の安芸郡坂町小屋浦から呉市天応西条の区間に,供用中の一期線に近接して小屋浦トンネル633m,天応トンネル391m,橋梁下部工および切盛土工の総延長2,710mを施工する工事を担当している。 天応トンネルは,2024年9月からNATM工法により掘削を開始。近接する供用中の一期線に影響を与えないよう,振動や騒音を抑制する制御発破を採用し,振動などを常時計測しながら掘削を進め,約10ヵ月をかけて無事に貫通を迎えた。ルに初導入し,新技術のショーケースとして活用した点や,建物内の人のバイタルデータ,位置情報,た。連結させた2台の多軸式特殊台車を用いて,組立ヤードから架設位置まで,橋桁を運搬して据付。限られた作業時間のなか,綿密な施工計画と入念な準備により,架設工事は無事完了した。 スマートインターチェンジと直結する阿知和地区工業団地および周辺道路の整備により,地域経済の一層の発展が期待されている。工業団地造成の完了は,2027年3月末の予定。 今後は,覆工コンクリート工事や橋梁下部工などの工事を進め,続く小屋浦トンネルの掘削に着手する。80tにもおよぶ橋桁を多軸式特殊台車を用いて運搬した表彰式にて関係者による記念撮影。左から,中野洋昌国土交通大臣(当時),カジマ・デベロップメント大石社長,森地茂政策研究大学院大学名誉教授(審査委員長)貫通時の坑内にて職員による記念撮影一晩で架設された跨道橋環境情報などのデータを収集・解析し,ウェルネスに寄与する空間を創出した点などが高く評価された。
22KAJIMA202511広島呉道路天応トンネルが無事に貫通TheGEARが「JAPANコンストラクション国際賞」を受賞阿知和地区工業団地跨道橋の架設工事を一晩で完了 9月9日,国土交通省主催の第8回JAPANコンストラクション国際賞の表彰式が三田共用会議所(東京都港区)で行われ,「TheGEAR」が建設・プロジェクト部門で受賞した。 同賞は,我が国の建設・不動産業の競争力の強化を図り,日系企業のさらなる海外進出を後押しするため,「質の高いインフラ」を実現する海外建設プロジェクトおよび海外において先導的に活躍してい 7月12日,当社JVが施工を担当する「岡崎市阿知和地区工業団地造成事業」(愛知県岡崎市)において,東名高速道路に跨道橋を架設する工事を一晩で実施した。 岡崎市が進める同事業では,愛知県の中央部,岡崎市の北西に位置する約63haの敷地に,新しい工業団地を整備する。今回実 当社が広島県呉市で施工を進めている「広島呉道路小屋浦トンネル他1トンネル工事」のうち,天応トンネルの貫通式が,7月30日,同トンネル内の貫通点付近で行われた。式典には,来賓をはじめ,発注者や工事関係者らが出席した。 本工事は,西日本高速道路が進める広島呉道路・坂北IC∼呉IC(約12.2km)の4車線化事業の一部。広島呉道路は平成30年7月豪雨により道路の一部が崩落し,約3ヵ月間,通行止めが続いたことから,道路ネットワークの強化を目的に,2車線から4車線に拡幅さる中堅・中小建設関連企業などを表彰するもので,2017年度に創設された。 2023年,シンガポールに開設したTheGEARは,当社のアジア本社,R&Dセンター(当社技術研究所のシンガポールオフィス「KaTRIS」),オープンイノベーションハブ機能をもつアジアの統括事業拠点である。 今回の表彰では,日本で培った多数の環境配慮技術をシンガポー施した跨道橋の架替工事は,工業団地に直結する(仮称)岡崎阿知和スマートインターチェンジを構築するための工事の一環で,2024年9月に高速道路を跨ぐ2つの橋(幅員約4m)を2夜連続で撤去。今回新たに跨道橋を架設した。 当日は,東名高速道路の岡崎IC∼豊田JCT間を夜8時から翌朝6時まで,全線通行止めにして工事を実施。新設する橋長43.5m,幅員約10m,重量約80tの鋼単純少数主桁橋は,スマートインターチェンジ敷地内のヤードで組み立てれることになった。このうち当社は,供用中の安芸郡坂町小屋浦から呉市天応西条の区間に,供用中の一期線に近接して小屋浦トンネル633m,天応トンネル391m,橋梁下部工および切盛土工の総延長2,710mを施工する工事を担当している。 天応トンネルは,2024年9月からNATM工法により掘削を開始。近接する供用中の一期線に影響を与えないよう,振動や騒音を抑制する制御発破を採用し,振動などを常時計測しながら掘削を進め,約10ヵ月をかけて無事に貫通を迎えた。ルに初導入し,新技術のショーケースとして活用した点や,建物内の人のバイタルデータ,位置情報,た。連結させた2台の多軸式特殊台車を用いて,組立ヤードから架設位置まで,橋桁を運搬して据付。限られた作業時間のなか,綿密な施工計画と入念な準備により,架設工事は無事完了した。 スマートインターチェンジと直結する阿知和地区工業団地および周辺道路の整備により,地域経済の一層の発展が期待されている。工業団地造成の完了は,2027年3月末の予定。 今後は,覆工コンクリート工事や橋梁下部工などの工事を進め,続く小屋浦トンネルの掘削に着手する。80tにもおよぶ橋桁を多軸式特殊台車を用いて運搬した表彰式にて関係者による記念撮影。左から,中野洋昌国土交通大臣(当時),カジマ・デベロップメント大石社長,森地茂政策研究大学院大学名誉教授(審査委員長)貫通時の坑内にて職員による記念撮影一晩で架設された跨道橋環境情報などのデータを収集・解析し,ウェルネスに寄与する空間を創出した点などが高く評価された。
 23KAJIMA202511イノベーション推進室が社外講師を招いた講演会を開催 当社イノベーション推進室は,社外講師を招き,当社施設において2つの講演会を,会場とオンラインのハイブリッドで開催した。 8月5日は,米国マサチューセッツ工科大学MediaLab※1の新進気鋭の若手のPaulLiang教授が「人間とAIの共生を目指して:マルチセンサリー(多感覚)AIの可能性」をテーマに,AIの基礎やがん予後予測,ロボット制御の事例などに加え,産学連携の取組みをプレゼン。社員260名が参加し,参加者からは「AIを用いた人間の知覚評価は,技能者の作業環境の評価のために有用な技術で,より活用が進んでほしい」などの声が寄せられた。 また,9月1∼3日には,NEXCO-WestUSA※2の松本正人CEOが,「米国におけるインフラ技術での事業展開と世界に通用する人材の育成」をテーマに講演。米国でのクライアントの信頼獲得の道のりやPPP事業の事例と今後の戦略,世界に通用する人材の育成制度などについて紹介した。432名の社員が参加し,「自国での強みは必ずしも他国での強みにならない」「誰もがファーストペンギンになりたがらないが,挑戦しなければ始まらない」な※1同大学建築・計画学科内に設立され,様々な分野の研究を組み合わせたイノベーションを推進している研究所※2西日本高速道路の米国現地法人Focus 当社デジタル推進室主催の「デジタル業務改善コンテスト2024」の受賞者が決定した。昨年に続く2回目の開催となった今回は,応募総数52件の中から,14件が選ばれ,6月30日には授賞式が行われた。受賞は以下の通り。※所属は受賞当時受賞者一覧【優秀賞 】 [PowerPlatform]運転日誌&アルコールチェックアプリの作成&導入宮前新さん・大沢駿輔さん・風間亮祐さん・椎名昭仁さん(東京土木支店)KAJIMAChatAIを活用した業務効率化~プロンプト作成ツール・アプリ~今井桃子さん(関西支店)撮ってすぐ描けるんです!森本征晃さん(中部支店)お手製オンライン測量野帳佐藤慎祐さん・丸山深直さん・池元康彦さん・植田康平さん(関東支店)・坂口未由希さん(関西支店)「デジタル業務改善コンテスト2024」の受賞者が決定!【コンテスト概要】応募対象:全社員応募期間:2025年1月6日~2月28日テーマ:デジタルを活用した業務改善の取組み(原則,1年以内に実施したもの)審査基準:汎用性・新規性・挑戦度・改善度・適用度どの意見が挙がるなど,両講演会とも大盛況のうちに幕を閉じた。質問に答えるPaulLiang教授(左)松本正人CEOによる講演の様子グランプリ受賞の山田さん(左),高嶺さん(中央)と真下英邦デジタル推進室長の記念撮影授賞式での集合写真AI朝礼松川修啓さん(関東支店)コンクリート品質管理の効率化―受入検査アプリ開発と帳票自動入力―勝山沙織さん・森永英里さん・菅原拓也さん・加藤恵介さん(横浜支店)RPAを活用した社外人材における時間外労働管理の効率化本多慶宇さん・石黒豪さん・角田遼太さん・小川美樹さん・佐藤一博さん・吉橋悟さん・鎌田朋子さん・永井琴花さん・小林咲桜里さん(横浜支店)【チャレンジ賞 】360度カメラの活用による検査の効率化/若手の悩みの早期解決和田淳さん・柳寺良昭さん・本多彩乃さん・明石勇介さん・吉澤裕也さん・森田洋平さん・坂上將大さん(東京建築支店)【特別賞 】実行予算の入力スピードアップ!中村将吾さん・本谷恵里さん・大嶋葵さん(中部支店)[クリックのみでグラフ作成]分析により多くの時間を使えるように!藤原健弥さん・南田宏典さん・岡崎隼也さん(東京建築支店)現場行事・休日予定等共有アプリの活用について堀江晃之介さん・鈴木猛丸さん・吉田雄二さん・佐藤雄紀さん・新田翔さん・山田直樹さん(東北支店)生成AIを活用した議事録作成の業務効率化大守亮輔さん(四国支店)コンクリート品質管理の効率化―受入検査アプリ開発と帳票自動入力―勝山沙織さん・森永英里さん・菅原拓也さん・加藤恵介さん(横浜支店)取組み概要:現場での隙間時間にFormsへ作業内容を入力することで,工事帳票の自動作成ができる仕組みを構築。三笠ぽんべつダムJV工事(北海道三笠市)では,この取組みにより,若手社員が施工計画や工程・コスト管理などに挑戦する時間を作ることができたと同時に,アウトソーシングも不要となり費用削減も達成した。【グランプリ 】スマホのFormsアプリで工事帳票を自動作成しよう!高嶺周平さん(北海道支店)・山田大樹さん(土木管理本部)
23KAJIMA202511イノベーション推進室が社外講師を招いた講演会を開催 当社イノベーション推進室は,社外講師を招き,当社施設において2つの講演会を,会場とオンラインのハイブリッドで開催した。 8月5日は,米国マサチューセッツ工科大学MediaLab※1の新進気鋭の若手のPaulLiang教授が「人間とAIの共生を目指して:マルチセンサリー(多感覚)AIの可能性」をテーマに,AIの基礎やがん予後予測,ロボット制御の事例などに加え,産学連携の取組みをプレゼン。社員260名が参加し,参加者からは「AIを用いた人間の知覚評価は,技能者の作業環境の評価のために有用な技術で,より活用が進んでほしい」などの声が寄せられた。 また,9月1∼3日には,NEXCO-WestUSA※2の松本正人CEOが,「米国におけるインフラ技術での事業展開と世界に通用する人材の育成」をテーマに講演。米国でのクライアントの信頼獲得の道のりやPPP事業の事例と今後の戦略,世界に通用する人材の育成制度などについて紹介した。432名の社員が参加し,「自国での強みは必ずしも他国での強みにならない」「誰もがファーストペンギンになりたがらないが,挑戦しなければ始まらない」な※1同大学建築・計画学科内に設立され,様々な分野の研究を組み合わせたイノベーションを推進している研究所※2西日本高速道路の米国現地法人Focus 当社デジタル推進室主催の「デジタル業務改善コンテスト2024」の受賞者が決定した。昨年に続く2回目の開催となった今回は,応募総数52件の中から,14件が選ばれ,6月30日には授賞式が行われた。受賞は以下の通り。※所属は受賞当時受賞者一覧【優秀賞 】 [PowerPlatform]運転日誌&アルコールチェックアプリの作成&導入宮前新さん・大沢駿輔さん・風間亮祐さん・椎名昭仁さん(東京土木支店)KAJIMAChatAIを活用した業務効率化~プロンプト作成ツール・アプリ~今井桃子さん(関西支店)撮ってすぐ描けるんです!森本征晃さん(中部支店)お手製オンライン測量野帳佐藤慎祐さん・丸山深直さん・池元康彦さん・植田康平さん(関東支店)・坂口未由希さん(関西支店)「デジタル業務改善コンテスト2024」の受賞者が決定!【コンテスト概要】応募対象:全社員応募期間:2025年1月6日~2月28日テーマ:デジタルを活用した業務改善の取組み(原則,1年以内に実施したもの)審査基準:汎用性・新規性・挑戦度・改善度・適用度どの意見が挙がるなど,両講演会とも大盛況のうちに幕を閉じた。質問に答えるPaulLiang教授(左)松本正人CEOによる講演の様子グランプリ受賞の山田さん(左),高嶺さん(中央)と真下英邦デジタル推進室長の記念撮影授賞式での集合写真AI朝礼松川修啓さん(関東支店)コンクリート品質管理の効率化―受入検査アプリ開発と帳票自動入力―勝山沙織さん・森永英里さん・菅原拓也さん・加藤恵介さん(横浜支店)RPAを活用した社外人材における時間外労働管理の効率化本多慶宇さん・石黒豪さん・角田遼太さん・小川美樹さん・佐藤一博さん・吉橋悟さん・鎌田朋子さん・永井琴花さん・小林咲桜里さん(横浜支店)【チャレンジ賞 】360度カメラの活用による検査の効率化/若手の悩みの早期解決和田淳さん・柳寺良昭さん・本多彩乃さん・明石勇介さん・吉澤裕也さん・森田洋平さん・坂上將大さん(東京建築支店)【特別賞 】実行予算の入力スピードアップ!中村将吾さん・本谷恵里さん・大嶋葵さん(中部支店)[クリックのみでグラフ作成]分析により多くの時間を使えるように!藤原健弥さん・南田宏典さん・岡崎隼也さん(東京建築支店)現場行事・休日予定等共有アプリの活用について堀江晃之介さん・鈴木猛丸さん・吉田雄二さん・佐藤雄紀さん・新田翔さん・山田直樹さん(東北支店)生成AIを活用した議事録作成の業務効率化大守亮輔さん(四国支店)コンクリート品質管理の効率化―受入検査アプリ開発と帳票自動入力―勝山沙織さん・森永英里さん・菅原拓也さん・加藤恵介さん(横浜支店)取組み概要:現場での隙間時間にFormsへ作業内容を入力することで,工事帳票の自動作成ができる仕組みを構築。三笠ぽんべつダムJV工事(北海道三笠市)では,この取組みにより,若手社員が施工計画や工程・コスト管理などに挑戦する時間を作ることができたと同時に,アウトソーシングも不要となり費用削減も達成した。【グランプリ 】スマホのFormsアプリで工事帳票を自動作成しよう!高嶺周平さん(北海道支店)・山田大樹さん(土木管理本部)
 24KAJIMA202511スタートアップのプレゼンテーションスタートアップ各社とのネットワーキングミーティング実習を行う参加者 9月24・25日の2日間,当社イノベーション推進室が主催する「鹿島イノベーションDAY」が当社技術研究所(東京都調布市)と赤坂別館(東京都港区)で開催された。イベントには両日で,社員235名(オンライン含む)が出席した。 このイベントは,世界30ヵ所に拠点を持つ,世界最大のテクノロジー・アクセラレータ(スタートアップ支援)企業PlugandPlayの協力により開催。当社の事業に親和性がある分野から,世界各国のスタートアップ10社が集結した。 各社のプレゼンテーションでは, 当社は,一般職などを対象に,各人の持てる能力を最大限に発揮し,長期的に活躍してもらうことを目的として,各種研修を行っている。 その一環として今夏,3日間にわたる「選抜研修」を実施。環境の変化に伴うキャリアマネジメントや,マネージャーとして必要になるスキルの取得向上,職種を超えた参加者同士のネットワーク構築などを狙いとしている。研修には,本社・各支店の推薦をもとに対象者の中から選出された20名が参加した。 1日目は,社外研修機関の講師が,チームコミュニケーションや成果につなげるファシリテーションスキル「鹿島イノベーションDAY」を開催一般職などを対象に「選抜研修」を開催などについて講義を実施。2・3日目は,参加者が自身の業務課題をチーム内で共有し,解決策を導くミーティングやプレゼン実習を行った。最後に,リーダーシップの能力診断と今後の自己啓発の計画を立て,本研修を締めくくった。 参加者からは,「どの研修も自身のキャリアアップにつながる重要な内容だと思った」「事前情報の共有が,より質の高いミーティングにつながると実感した」「リーダーとして必要なスキルや知識を学ぶと同時に,メンバーへの側面支援の必要性を学んだ」などの意見が挙がった。スマートフォンで撮影した動画や音声による現場レポートの自動作成や,宇宙線の一種である「ミュー粒子」を用いて構造物を可視化する非破壊探査など,様々なソリューションやビジネスモデルが披露された。また,昨年当イベントに参加したスタートアップからは,当社の現場とのコラボレーションが実現した事例などが紹介された。 その後行われたネットワーキングでは,各社が個別ブースを設け,当社とのコラボレーションの可能性などについて社員とコミュニケーションを図った。Person 11月15∼26日,第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025が開催される。日本での開催は初となる。デフリンピックは,耳が聞こえない(Deaf),聞こえにくいアスリートを対象としたオリンピック。国際ろう者スポーツ委員会が主催し,通常のオリンピック同様4年毎に開催され,今年で100周年を迎える。 今大会に,当社グループ「鹿島道路」に所属する親松直人選手が,デフテニス日本代表として選出された。デフテニス日本ランキング1位の戦歴を持ち,デフリンピックは2大会ぶり2度目の出場となる。シングルス,ダブルス,ミックスダブルスで戦う予定だ。 鹿島道路は,多様な人材が個々の強みや可能性を活かすことを目指し,その一環として障がい者雇用に積極的に取り組んでいる。その取組みを知った親松選手が同鹿島道路社員がデフリンピックに日本代表として出場!社へ応募,2021年に入社した。 親松選手は学生時代まで,補聴器を付けながらプレーしていたが,大学卒業後にデフテニスへ転身。ルールは通常のテニスと同じだが,補聴器を使用せず,音が聞こえない中でプレーすることが大きな特徴だ。そのため,特にダブルスではペア選手とのコミュニケーションが勝敗を左右すると言っても過言ではない。通常,どちらがボールを打つかは,音と目から得るペアの動きと掛け声で瞬時に決めるが,デフテニスでは,お互いの動きを事前に決め,プレーに入ることが多いそうだ。「私は読唇術を使い,ペア選手と試合前に入念な作戦会議を行っています」と話す。 来たるデフリンピックに向け「試合での勝利も大事ですが,まずはデフスポーツ・デフリンピックを知ってもらいたい。そのためにも今大会では,メダル獲得を目指して頑張ります!」と大きな目標を胸に,満面の笑みで意気込みを語ってくれた。 デフリンピックは間もなく開催。皆さん,親松選手を応援しよう!東京2025デフリンピック(デフテニス)日時:11月15日∼26日会場:有明テニスの森(東京都江東区)第3回世界デフテニス選手権ミックスダブルスで銅メダルを獲得!Profile1992年7月22日生まれ, 埼玉県出身,日本体育大学卒業。デフテニス日本ランキング1位(過去最高)。同世界ランキングシングルス15位,ダブルス4位(過去最高)。第3回世界デフテニス選手権ミックスダブルス3位,団体戦3位。東京2025デフリンピックテニス日本代表。得意ショットはサーブ。選手として活動する傍ら,デフテニスの普及のため,SNSでの発信にも力を注ぐ鹿島道路親松直人選手 インスタグラムで活動発信中!
24KAJIMA202511スタートアップのプレゼンテーションスタートアップ各社とのネットワーキングミーティング実習を行う参加者 9月24・25日の2日間,当社イノベーション推進室が主催する「鹿島イノベーションDAY」が当社技術研究所(東京都調布市)と赤坂別館(東京都港区)で開催された。イベントには両日で,社員235名(オンライン含む)が出席した。 このイベントは,世界30ヵ所に拠点を持つ,世界最大のテクノロジー・アクセラレータ(スタートアップ支援)企業PlugandPlayの協力により開催。当社の事業に親和性がある分野から,世界各国のスタートアップ10社が集結した。 各社のプレゼンテーションでは, 当社は,一般職などを対象に,各人の持てる能力を最大限に発揮し,長期的に活躍してもらうことを目的として,各種研修を行っている。 その一環として今夏,3日間にわたる「選抜研修」を実施。環境の変化に伴うキャリアマネジメントや,マネージャーとして必要になるスキルの取得向上,職種を超えた参加者同士のネットワーク構築などを狙いとしている。研修には,本社・各支店の推薦をもとに対象者の中から選出された20名が参加した。 1日目は,社外研修機関の講師が,チームコミュニケーションや成果につなげるファシリテーションスキル「鹿島イノベーションDAY」を開催一般職などを対象に「選抜研修」を開催などについて講義を実施。2・3日目は,参加者が自身の業務課題をチーム内で共有し,解決策を導くミーティングやプレゼン実習を行った。最後に,リーダーシップの能力診断と今後の自己啓発の計画を立て,本研修を締めくくった。 参加者からは,「どの研修も自身のキャリアアップにつながる重要な内容だと思った」「事前情報の共有が,より質の高いミーティングにつながると実感した」「リーダーとして必要なスキルや知識を学ぶと同時に,メンバーへの側面支援の必要性を学んだ」などの意見が挙がった。スマートフォンで撮影した動画や音声による現場レポートの自動作成や,宇宙線の一種である「ミュー粒子」を用いて構造物を可視化する非破壊探査など,様々なソリューションやビジネスモデルが披露された。また,昨年当イベントに参加したスタートアップからは,当社の現場とのコラボレーションが実現した事例などが紹介された。 その後行われたネットワーキングでは,各社が個別ブースを設け,当社とのコラボレーションの可能性などについて社員とコミュニケーションを図った。Person 11月15∼26日,第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025が開催される。日本での開催は初となる。デフリンピックは,耳が聞こえない(Deaf),聞こえにくいアスリートを対象としたオリンピック。国際ろう者スポーツ委員会が主催し,通常のオリンピック同様4年毎に開催され,今年で100周年を迎える。 今大会に,当社グループ「鹿島道路」に所属する親松直人選手が,デフテニス日本代表として選出された。デフテニス日本ランキング1位の戦歴を持ち,デフリンピックは2大会ぶり2度目の出場となる。シングルス,ダブルス,ミックスダブルスで戦う予定だ。 鹿島道路は,多様な人材が個々の強みや可能性を活かすことを目指し,その一環として障がい者雇用に積極的に取り組んでいる。その取組みを知った親松選手が同鹿島道路社員がデフリンピックに日本代表として出場!社へ応募,2021年に入社した。 親松選手は学生時代まで,補聴器を付けながらプレーしていたが,大学卒業後にデフテニスへ転身。ルールは通常のテニスと同じだが,補聴器を使用せず,音が聞こえない中でプレーすることが大きな特徴だ。そのため,特にダブルスではペア選手とのコミュニケーションが勝敗を左右すると言っても過言ではない。通常,どちらがボールを打つかは,音と目から得るペアの動きと掛け声で瞬時に決めるが,デフテニスでは,お互いの動きを事前に決め,プレーに入ることが多いそうだ。「私は読唇術を使い,ペア選手と試合前に入念な作戦会議を行っています」と話す。 来たるデフリンピックに向け「試合での勝利も大事ですが,まずはデフスポーツ・デフリンピックを知ってもらいたい。そのためにも今大会では,メダル獲得を目指して頑張ります!」と大きな目標を胸に,満面の笑みで意気込みを語ってくれた。 デフリンピックは間もなく開催。皆さん,親松選手を応援しよう!東京2025デフリンピック(デフテニス)日時:11月15日∼26日会場:有明テニスの森(東京都江東区)第3回世界デフテニス選手権ミックスダブルスで銅メダルを獲得!Profile1992年7月22日生まれ, 埼玉県出身,日本体育大学卒業。デフテニス日本ランキング1位(過去最高)。同世界ランキングシングルス15位,ダブルス4位(過去最高)。第3回世界デフテニス選手権ミックスダブルス3位,団体戦3位。東京2025デフリンピックテニス日本代表。得意ショットはサーブ。選手として活動する傍ら,デフテニスの普及のため,SNSでの発信にも力を注ぐ鹿島道路親松直人選手 インスタグラムで活動発信中!
 BOOKS25KAJIMA202511ロングセラー教科書が新版化でさらに充実お問合せ鹿島出版会tel:03-6264-2301 今月の新刊をご紹介します。木造からS造,RC造まで様々なバリエーションによる造形の魅力を体系的に整理し,完全図解した一冊。空間と構造の融合を創造する技法と,部材断面の設定といったスキルを具体的に示しており,学生から設計者まで,あらためて建築造形の奥深さと愉しさに触れることができます。 「建築とは本質的に空間の造形であり,同時に構造の造形である」という考え方をそのままに,2008年刊行の初版本から2回の増補改訂を経て,さらに内容を充実させた待望の新版です。ほぼ全ページに入った豊富な図版が見やすくなるよう,本の開きがよく工夫された造本となっています。ぜひ机上に置きたい一冊です。参加者集合写真日本橋橋洗いに参加した社員とその家族放水の様子『[新版]建築デザインの構造と造形』富岡義人・小野徹郎/編著B5判・208頁,3,300円(税込)杉本副主任研究員の講義風景「ニューヨーク×カリブ音楽」を紹介した連載第1回の誌面。多様な人や物が交差する都市と,文化が溶け合い発展する音楽をつづります 当社は,子どもたちの夏休み期間に「鹿島サマースクール∼本物の建設現場を見に行こう∼」を開催した。このイベントは,当社の社会貢献活動の一環として2017年から実施。小・中学生を対象に,現場見学や作業体験を通して,建設業に対する興味や理解を深めてもらうことを目的としている。 今年は東京,神奈川,新潟,愛知,兵庫の1都4県で,超高層ビルやダム,橋梁,河口部の水門 7月27日,「日本橋橋洗い」(主催:名橋「日本橋」保存会)が東京都中央区で行われ,当社東京建築支店や営業本部の社員とその家族ら45名が参加した。 このイベントは,国の重要文化財で五街道の起点である「日本橋」の美しさを後世に伝えようと1971年から行われており,今年で53回目を数える。当日は9時から日本橋を通行止めにし,オープニングセレモニーが開催された。その後,橋洗いが始まると日本橋消防署,地「鹿島サマースクール2025」を開催「日本橋橋洗い」に参加元消防団が放水し,地域住民や企業関係者など約1,800名の参加者たちが橋の路面や欄干を磨き上げた。当社社員も半纏姿にたわしやデッキブラシを使い,丁寧に1年の汚れを洗い流した。リニューアルの工事現場を公開し,親子合わせて82名が参加した。イベントでは,事業・工事概要の説明後,現場見学を実施。子どもたちは構造物や建設機械の迫力に目を輝かせながら,工事関係者の説明に耳を傾けた。作業体験では,測量作業や停止中のクレーンなどに試乗した。子どもたちからは,「工事の車に乗れて嬉しかった」「普段できないお仕事体験ができた」「まちにとって大切な仕事だとわかった」などの声が寄せられた。近大附属広島高校東広島校で当社社員が講義を実施 7月22日,近畿大学附属広島高等学校東広島校(広島県東広島市)にて開催された特別授業で,当社社員が講義を行った。 この特別授業は,生徒たちがカーボンニュートラルやまちづくりについて理解を深めるとともに,自己のキャリア形成を考える機会とするもの。当日は建築・建設や環境,まちづくりに興味のある生徒約40名が参加した。講師は広島県の職員と,当社技術研究所・建築生産グループの杉本裕紀副主任研究員の2名が担当。当社中国支店のカーボンニュートラル対応チーム「CNP42」もオブザーバーとして参加した。 杉本副主任研究員は当社開発のCO2を吸収するコンクリートをテーマに,コンクリートの成分や仕組み,CO2削減効果について実例を交え解説した。その後行われたグループワークでは,生徒たちが講義を踏まえ環境に優しいまちづくりについてディスカッションし,様々なアイデアを発表した。
BOOKS25KAJIMA202511ロングセラー教科書が新版化でさらに充実お問合せ鹿島出版会tel:03-6264-2301 今月の新刊をご紹介します。木造からS造,RC造まで様々なバリエーションによる造形の魅力を体系的に整理し,完全図解した一冊。空間と構造の融合を創造する技法と,部材断面の設定といったスキルを具体的に示しており,学生から設計者まで,あらためて建築造形の奥深さと愉しさに触れることができます。 「建築とは本質的に空間の造形であり,同時に構造の造形である」という考え方をそのままに,2008年刊行の初版本から2回の増補改訂を経て,さらに内容を充実させた待望の新版です。ほぼ全ページに入った豊富な図版が見やすくなるよう,本の開きがよく工夫された造本となっています。ぜひ机上に置きたい一冊です。参加者集合写真日本橋橋洗いに参加した社員とその家族放水の様子『[新版]建築デザインの構造と造形』富岡義人・小野徹郎/編著B5判・208頁,3,300円(税込)杉本副主任研究員の講義風景「ニューヨーク×カリブ音楽」を紹介した連載第1回の誌面。多様な人や物が交差する都市と,文化が溶け合い発展する音楽をつづります 当社は,子どもたちの夏休み期間に「鹿島サマースクール∼本物の建設現場を見に行こう∼」を開催した。このイベントは,当社の社会貢献活動の一環として2017年から実施。小・中学生を対象に,現場見学や作業体験を通して,建設業に対する興味や理解を深めてもらうことを目的としている。 今年は東京,神奈川,新潟,愛知,兵庫の1都4県で,超高層ビルやダム,橋梁,河口部の水門 7月27日,「日本橋橋洗い」(主催:名橋「日本橋」保存会)が東京都中央区で行われ,当社東京建築支店や営業本部の社員とその家族ら45名が参加した。 このイベントは,国の重要文化財で五街道の起点である「日本橋」の美しさを後世に伝えようと1971年から行われており,今年で53回目を数える。当日は9時から日本橋を通行止めにし,オープニングセレモニーが開催された。その後,橋洗いが始まると日本橋消防署,地「鹿島サマースクール2025」を開催「日本橋橋洗い」に参加元消防団が放水し,地域住民や企業関係者など約1,800名の参加者たちが橋の路面や欄干を磨き上げた。当社社員も半纏姿にたわしやデッキブラシを使い,丁寧に1年の汚れを洗い流した。リニューアルの工事現場を公開し,親子合わせて82名が参加した。イベントでは,事業・工事概要の説明後,現場見学を実施。子どもたちは構造物や建設機械の迫力に目を輝かせながら,工事関係者の説明に耳を傾けた。作業体験では,測量作業や停止中のクレーンなどに試乗した。子どもたちからは,「工事の車に乗れて嬉しかった」「普段できないお仕事体験ができた」「まちにとって大切な仕事だとわかった」などの声が寄せられた。近大附属広島高校東広島校で当社社員が講義を実施 7月22日,近畿大学附属広島高等学校東広島校(広島県東広島市)にて開催された特別授業で,当社社員が講義を行った。 この特別授業は,生徒たちがカーボンニュートラルやまちづくりについて理解を深めるとともに,自己のキャリア形成を考える機会とするもの。当日は建築・建設や環境,まちづくりに興味のある生徒約40名が参加した。講師は広島県の職員と,当社技術研究所・建築生産グループの杉本裕紀副主任研究員の2名が担当。当社中国支店のカーボンニュートラル対応チーム「CNP42」もオブザーバーとして参加した。 杉本副主任研究員は当社開発のCO2を吸収するコンクリートをテーマに,コンクリートの成分や仕組み,CO2削減効果について実例を交え解説した。その後行われたグループワークでは,生徒たちが講義を踏まえ環境に優しいまちづくりについてディスカッションし,様々なアイデアを発表した。