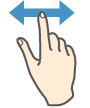﹁旅のつばくろ淋しかないか﹂。作詞は西条八十。つばくろとはツバメのこと。一九三三︵昭和八︶年の流行歌﹃サーカスの唄﹄の歌い出しだ。﹁俺もさびしいサーカス暮らし﹂と続く。ツバメは渡り鳥。サーカス団も旅回り。浮草稼業とツバメのイメージを上手に掛けた歌である。 ﹁燕来る時になりぬと雁がねは 本郷思ひつつ雲隠り鳴く﹂。こちらは﹃万葉集﹄。大伴家持の歌。雁は冬の渡り鳥。雁が北に帰る春に、ツバメは南からやってくる。季節の移ろいを渡り鳥で知る。北の大地と南の島々に挟まれる日本列島。そこに生きる者の自然な感覚だろう。それから、旧国鉄が新幹線開業以前、東海道本線に走らせていた特急の名前が﹁つばめ﹂だった。速いからである。旧国鉄が持ったプロ野球チームもスワローズだった。その伝統を汲むのが東京ヤクルトスワローズである。 私も日本人として、ツバメについてそのくらいのイメージは持っていた。でも高度成長期に都会で育った人間なので、本物のツバメに親しんで暮らす機会はなかった。我が家の軒先にツバメが巣をかけていることは一度もなかった。﹁柳青める日 ツバメが銀座に飛ぶ日﹂と歌い出す、サトウハチロー作詞の一九四七︵昭和二二︶年の流行歌﹃夢淡き東京﹄のような光景を実感したこともない。 そうしているうちに大人になり、壮年になり、二十年ほど前に、必要に迫られて、田舎の茅屋に引っ越したら、初めてなるほどと思った。日本人とツバメの近しさをようやく実感した。とにかく春になると殺到してくる。凸凹に富んだ我が家のあちこちに、多い年は七か所も八か所も巣をかける。しかも、元々間違っていたのだろうが、ツバメについて常識のつもりで知っていたこととは、様子がだいぶん異なる。短命と聞いていたが、六年も七年もやってくる大柄のツバメがいる。毎年、巣をかけかえるのが普通と人に教えられた気もするのだが、実際には全壊していない限り、ほとんどの巣を修繕して使っている。二十年住んで分かることだが、ツバメの巣とは思えない巨大な巣を築いて、毎年崩れた箇所を泥や藁で付け足して使い続けているツバメの一家もある。二十年間、同じ巣が子々孫々に受け継がれているように観察されるのだ。 ツバメの巣作りというが、ゼロからはあまり作りたがらぬものらしい。クリエートとか創造するとかいう観念はツバメの世界では縁遠いようである。少なくとも我が家のツバメたちにとって作るとは、補修することであり、付け足すことである。作ると付けるは語源的には別というけれど、私のつたないツバメ観察からは、どうも似た言葉に思えてくる。ツバメを長年の友として生きてきた日本人には、創造することよりも執念深く補修して付け足してゆくことをよしとする価値観が備わっているのではないだろうか。ツバメに感化されての、ひとつの妄想です。26KAJIMA202511かたやま・もりひで 評論家、政治学者。1963年、宮城県仙台市で生まれ、東京で育つ。幼少期から音楽と映画と演劇に親しむ。2008年から慶應義塾大学に勤め、現在、法学部教授、教養研究センター所長。専攻は政治思想史。90年代からコラムニスト、種々の分野の評論家として様々な媒体に執筆。次第に音楽評論の仕事が多くなる。2012年からNHKFM『クラシックの迷宮』の構成と出演。20年から三原市芸術文化センター館長、24年から水戸芸術館館長。08年『音盤考現学』と『音盤博物誌』で吉田秀和賞、サントリー学芸賞、12年『未完のファシズム』で司馬遼太郎賞、25年『大楽必易』で芸術選奨文部科学大臣賞受賞。その他著書多数。vol.251
﹁旅のつばくろ淋しかないか﹂。作詞は西条八十。つばくろとはツバメのこと。一九三三︵昭和八︶年の流行歌﹃サーカスの唄﹄の歌い出しだ。﹁俺もさびしいサーカス暮らし﹂と続く。ツバメは渡り鳥。サーカス団も旅回り。浮草稼業とツバメのイメージを上手に掛けた歌である。 ﹁燕来る時になりぬと雁がねは 本郷思ひつつ雲隠り鳴く﹂。こちらは﹃万葉集﹄。大伴家持の歌。雁は冬の渡り鳥。雁が北に帰る春に、ツバメは南からやってくる。季節の移ろいを渡り鳥で知る。北の大地と南の島々に挟まれる日本列島。そこに生きる者の自然な感覚だろう。それから、旧国鉄が新幹線開業以前、東海道本線に走らせていた特急の名前が﹁つばめ﹂だった。速いからである。旧国鉄が持ったプロ野球チームもスワローズだった。その伝統を汲むのが東京ヤクルトスワローズである。 私も日本人として、ツバメについてそのくらいのイメージは持っていた。でも高度成長期に都会で育った人間なので、本物のツバメに親しんで暮らす機会はなかった。我が家の軒先にツバメが巣をかけていることは一度もなかった。﹁柳青める日 ツバメが銀座に飛ぶ日﹂と歌い出す、サトウハチロー作詞の一九四七︵昭和二二︶年の流行歌﹃夢淡き東京﹄のような光景を実感したこともない。 そうしているうちに大人になり、壮年になり、二十年ほど前に、必要に迫られて、田舎の茅屋に引っ越したら、初めてなるほどと思った。日本人とツバメの近しさをようやく実感した。とにかく春になると殺到してくる。凸凹に富んだ我が家のあちこちに、多い年は七か所も八か所も巣をかける。しかも、元々間違っていたのだろうが、ツバメについて常識のつもりで知っていたこととは、様子がだいぶん異なる。短命と聞いていたが、六年も七年もやってくる大柄のツバメがいる。毎年、巣をかけかえるのが普通と人に教えられた気もするのだが、実際には全壊していない限り、ほとんどの巣を修繕して使っている。二十年住んで分かることだが、ツバメの巣とは思えない巨大な巣を築いて、毎年崩れた箇所を泥や藁で付け足して使い続けているツバメの一家もある。二十年間、同じ巣が子々孫々に受け継がれているように観察されるのだ。 ツバメの巣作りというが、ゼロからはあまり作りたがらぬものらしい。クリエートとか創造するとかいう観念はツバメの世界では縁遠いようである。少なくとも我が家のツバメたちにとって作るとは、補修することであり、付け足すことである。作ると付けるは語源的には別というけれど、私のつたないツバメ観察からは、どうも似た言葉に思えてくる。ツバメを長年の友として生きてきた日本人には、創造することよりも執念深く補修して付け足してゆくことをよしとする価値観が備わっているのではないだろうか。ツバメに感化されての、ひとつの妄想です。26KAJIMA202511かたやま・もりひで 評論家、政治学者。1963年、宮城県仙台市で生まれ、東京で育つ。幼少期から音楽と映画と演劇に親しむ。2008年から慶應義塾大学に勤め、現在、法学部教授、教養研究センター所長。専攻は政治思想史。90年代からコラムニスト、種々の分野の評論家として様々な媒体に執筆。次第に音楽評論の仕事が多くなる。2012年からNHKFM『クラシックの迷宮』の構成と出演。20年から三原市芸術文化センター館長、24年から水戸芸術館館長。08年『音盤考現学』と『音盤博物誌』で吉田秀和賞、サントリー学芸賞、12年『未完のファシズム』で司馬遼太郎賞、25年『大楽必易』で芸術選奨文部科学大臣賞受賞。その他著書多数。vol.251