|
KAJIMAエコプラザ |
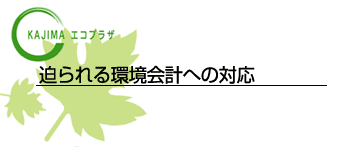 |
| 近年,環境会計を導入する企業が急激に増加しています。2000年に20社程度であったのが,2001年には160社以上,建設会社でも大手5社をはじめ11社が既に導入しています。 この背景には,環境問題の多様化・複雑化に伴い,企業の環境に関するリスクが増大していることが挙げられます。国などによる環境規制は年々強化され,その対策にかかる投資は増加の一途にあります。そのため,企業は費用対効果をできるだけ明確にして,経営の効率化を進めることが迫られています。また,社会から積極的な環境保全活動が求められるにつれ,活動内容を開示して企業としての信頼性の向上を図っています。 環境会計は,動き出したばかりの制度でまだ確立されたルールが存在しません。そこで2000年5月に環境省(旧環境庁)より,「環境庁ガイドライン」が示され,多くの企業はこれに沿ったかたちで運営しています。建設業については,生産メーカーとは異なる個別の現場生産という事情があります。日本建設業団体連合会(日建連)は,これを踏まえて業界の実情に即したガイドラインを現在作成しており,来春発表する予定です。当社をはじめとする数社は,既に積極的な取組みを始めています。 なお,環境庁ガイドラインでは,「企業が環境保全のために支出したコストとその活動により得られた効果を定量的に把握し,分析,公表する仕組み」と環境会計システムを定義しています。 当社における環境会計への取組みは,1999年度から施工部門の環境コストに限定して試行しました。2000年度からは,全社の設計,施工,研究開発の部門,及びオフィスを含む全業務を対象に,環境庁ガイドラインに準じて六つの活動に整理し,コストと効果・成果を集計しています。 六つの活動は,主に現場などの施工部門と本社・支店といったオフィスでの環境負荷を抑制する「事業エリア内活動」,設計部門での取組みやグリーン購入(KAJIMAエコプラザ11月),解体処理といった事業エリアの上流,下流で行われる「上・下流活動」などに分けられます。 当社の具体的な取組み内容については,環境保全コストの総額は230.5億円となっています。これに対し,社会全体が享受する効果・成果は,アイドリングストップ活動やエネルギー消費量のCO2削減量,熱帯材の型枠削減量,産業廃棄物のリサイクル率,グリーン購入額など,さらには当社における経済効果まで,広範囲にわたって集計しています。(下図参照) また,活動結果を判断するために四つの指標を算定しています。(環境コスト比率,産業廃棄物処理コスト比率,環境関連研究開発コスト比率,環境関連研究開発効率) これらの詳細は,2001年の鹿島環境保全活動報告書の中に記載されていますので,そちらをご覧下さい。また当社のホームページからもアクセスできます。 最後に,当社の今後の課題は,環境保全活動の効果をより明確にし,インターネットの活用により全社情報を効率的に把握することです。そして企業の経営管理指標ともなる内部管理への積極的な活用を促すことにあります。 |
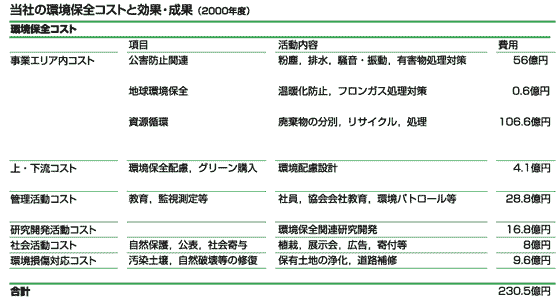
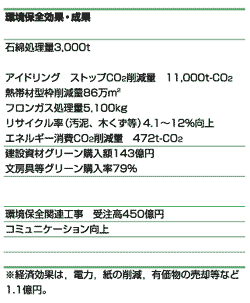 |