| 極める |
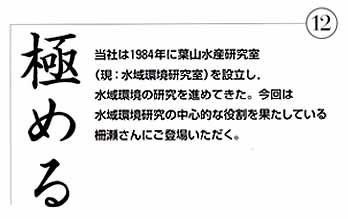 |
「水域環境の達人」 環境本部 地域環境計画グループ 柵瀬信夫(さくらい のぶお)さん |
 |
|
|
 柵瀬さんは1982年に水産施設の研究者として鹿島に入社。学生時代は神奈川県・江ノ島海岸で8年ものあいだ漁師を手伝いながら,ウナギの稚魚であるシラスウナギの生態を追いかけ学位論文を完成させたという,面白い経歴を持つ河口や干潟の専門家。入社後は,葉山水産研究室の責任者として,海洋研究・水産施設の計画設計,環境保全のための調査や商品開発,発展途上国の研究生の水産技術指導から地元での調査を兼ねたハゼ釣り大会や子供の環境教室の開催にいたるまで,実に多彩な業務をこなしてきた。現在は環境本部で自ら開発した商品を営業しながら全国を飛び回っている。
柵瀬さんは1982年に水産施設の研究者として鹿島に入社。学生時代は神奈川県・江ノ島海岸で8年ものあいだ漁師を手伝いながら,ウナギの稚魚であるシラスウナギの生態を追いかけ学位論文を完成させたという,面白い経歴を持つ河口や干潟の専門家。入社後は,葉山水産研究室の責任者として,海洋研究・水産施設の計画設計,環境保全のための調査や商品開発,発展途上国の研究生の水産技術指導から地元での調査を兼ねたハゼ釣り大会や子供の環境教室の開催にいたるまで,実に多彩な業務をこなしてきた。現在は環境本部で自ら開発した商品を営業しながら全国を飛び回っている。柵瀬さんは自らの役割は通訳だと説明する。「環境意識が高まった今,動植物を保護しない無謀な計画は途中でつぶれてしまいます。私は開発計画関係者に対して,水産学の専門家として最適な方法を提示することもできるし,市民にも『こうすれば動植物を守りながら工事ができる』と説明することもできるからです」と理由を語った。 |
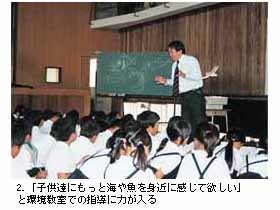 柵瀬さんは現場第一主義であり,雨や雪や炎天下といった人の嫌がる日にこそ海に出て沿岸を見て歩くという。コンクリートの護岸にカニがいなくなったと聞いた時は,それを確かめに川や海に向かい,あらゆるタイプの護岸を回り,カニの生息する条件を調べた。調査を続けると,新しいコンクリート護岸は白くつるつるとして,日の照り返しもきつく眩しくてカニが近寄らないが,コンクリートが経年化していくうちに色がつき,目地が抜けカニの歩ける穴があいた石垣のようになったところにカニが多数生息しているのを確認した。
「ならば,初めからその条件を整えればいい」という発想で完成したのが『カニ護岸パネル』。これは,コンクリートを初めから暗い色で着色し,凸凹を付け,カニが歩けるような穴を開けた。新品のコンクリート製品としてはデコボコで穴だらけの不良品のようだが,生き物にとっては居心地が良く,設置後すぐにカニが護岸に戻った。カニが戻ってくれば食物連鎖の修復になり,カニを餌としているハゼ,ハゼを餌にしているウナギやカレイなど,内湾の生物資源の復活に役立つのだ。コンクリートの最新技術を研究している専門家にはこのような発想は浮かばない。
柵瀬さんは現場第一主義であり,雨や雪や炎天下といった人の嫌がる日にこそ海に出て沿岸を見て歩くという。コンクリートの護岸にカニがいなくなったと聞いた時は,それを確かめに川や海に向かい,あらゆるタイプの護岸を回り,カニの生息する条件を調べた。調査を続けると,新しいコンクリート護岸は白くつるつるとして,日の照り返しもきつく眩しくてカニが近寄らないが,コンクリートが経年化していくうちに色がつき,目地が抜けカニの歩ける穴があいた石垣のようになったところにカニが多数生息しているのを確認した。
「ならば,初めからその条件を整えればいい」という発想で完成したのが『カニ護岸パネル』。これは,コンクリートを初めから暗い色で着色し,凸凹を付け,カニが歩けるような穴を開けた。新品のコンクリート製品としてはデコボコで穴だらけの不良品のようだが,生き物にとっては居心地が良く,設置後すぐにカニが護岸に戻った。カニが戻ってくれば食物連鎖の修復になり,カニを餌としているハゼ,ハゼを餌にしているウナギやカレイなど,内湾の生物資源の復活に役立つのだ。コンクリートの最新技術を研究している専門家にはこのような発想は浮かばない。
 柵瀬さんは生物とコンクリートの専門家との間でも通訳の役割を果たしたといえよう。「コンクリートはマイナス面ばかりが強調されるが,コストやリサイクルを考えれば,非常に優れた素材。生き物が好む環境はコンクリートでいくらでも作ることが出来る」と,現在は土と同じように保水するコンクリートの開発を熱心に進めている。
柵瀬さんは生物とコンクリートの専門家との間でも通訳の役割を果たしたといえよう。「コンクリートはマイナス面ばかりが強調されるが,コストやリサイクルを考えれば,非常に優れた素材。生き物が好む環境はコンクリートでいくらでも作ることが出来る」と,現在は土と同じように保水するコンクリートの開発を熱心に進めている。「建設会社は環境を壊したと言われるが,逆に再生できるのも建設会社だと思う。今まで美しいとされてきた護岸は人の勝手な主観であったのではないか。これからは,生き物全体としての主観で,本当に必要なものは何かを見極め,目先のことではなく将来を,部分ではなく全体を考えて事業を進めていくことが重要」と最後に語った。 |