テクノプラザ: ゆく河の流れは清くして
河川の水質浄化技術
下水道や浄化槽の整備が進んでも,河川の水質は,それに正比例して良くなってきているとは,必ずしもいい難い。とりわけ都市部における中小河川の水質汚濁は,依然深刻な問題として,解決されずに残されたままである。今月号では,河川の水質改善に関連する当社の取組みや技術について紹介する。


水路に擬岩の蓋をして景観を損なわないようにしてある
●進まない河川の浄化
これは,側溝などから直接川に流れ込む雑排水が,相当量にのぼること,河川の岸辺から植物が消え,生態系の破壊が進んだことなどが主な原因と考えられる。
●多自然化技術による浄化
河川の水質を改善するにあたり,これまで最も一般的だったのは礫間浄化である。河床や河川敷に礫(小石)を敷き並べて,礫に付着した微生物による生物濾過を行い,浄化された水を川に戻すという方法である。
この多自然化技術と呼ばれる方法では,いずれも自然の持つ自浄作用に頼るもので,景観や生態系を保存・再生できる反面,浄化効率が低く水質が良くなるまでに時間がかかり,広大なスペースも必要であった。
●直接浄化技術による浄化
これに対する直接浄化技術は,浄化プラントを設置して水質を改善する。効果は早く現れるものの,水処理の過程で発生する汚泥や土砂などを適切に処理しなければならない。また,比較的小さな敷地でも設置が可能な反面,建設コストがかかり,施設構造物が自然の景観を損なうおそれがある。
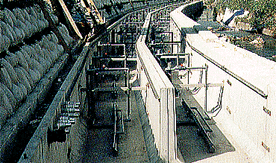 |
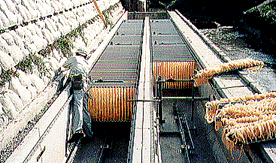 |
水路の長さは約70m、深さ約1m、幅約1mのものが2列。
配管は攪拌のために空気を送る散気管。 |
ユニット化したリングレースは軽量で設置作業も容易 |
●東生駒川の浄化の場合
当社は,東生駒川(奈良県生駒市)の水質改善計画の推進にあたり,浄化施設の施工,エンジニアリング支援を行った。
ここでは,左岸の河道に長さ約70mにわたって高水敷部を作り,そこに幅約1m,深さ約1mの水路を2列設けている。河川水の一部を取水してこの水路を通す。水路の中には,リングレース(ひも状接触材)を設置し,リングレースに付着した微生物と,水路を流れる水が接触を繰り返す。水路の底から空気を送って攪拌し,水と微生物との接触効率を高める。水質汚濁の原因である水中の有機物を,水と二酸化炭素に分解することで,川の水を浄化する。
水流に対する抵抗が少なく,処理性能が安定しており,施工性にすぐれ,点検や清掃なども容易である。施設も半地下式にして景観を損なわないようにしている。しかも,発生する汚泥を比較的少なくできる生物処理を行い,消費電力もわずかという特長を持っている。
当社では、今後も研究開発を進め、それぞれの河川の条件に合わせて水環境再生のプランを提案していく。 |