| ザ・フォアフロント |
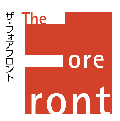
|
ユニバーサルデザインが目指す優しいかたち より多くの人々が利用できるデザインを目指すユニバーサルデザイン。 昨年11月にはわが国で初めて「国際ユニバーサルデザイン会議2002」が開催されるなどますますその重要性が注目されている。今月のザ・フォアフロントではユニバーサルデザインの意義をあらためて考え,当社の取組みと姿勢を紹介する。 |
|
|
|
|
| ユニバーサルデザインの精神 ユニバーサルデザイン(UD)を語る際,しばしばバリアフリーと比較される。双方ともに,何らかの障害を抱える人々が社会で出会う様々な障壁の除去・低減を目指したものだが,両者の大きな違いは,バリアフリーが「特定の障害」を想定しているのに対し,UDは障害の種類を特定しないことだ。たとえば,言葉の異なる土地を訪れれば,だれでも行動に制約を受けることがある。このように「すべての人は何らかの障害を抱えて生活していること」を前提として,身体能力の差や体格・性別・年齢・国籍などにかかわらず,より多くの人々が利用できる製品,建物,環境の創造を目的とすることがUDの根本に流れる精神だ。 |
|
|
| ユニバーサルデザインの「普通」と「意識」 UDの考え方は,1974年「国際障害者生活環境専門家会議」において障害をもつ米国建築家ロナルド・メイス氏によって初めて提唱された。以来,UDをかたちとするための具体的な方針が示されてきた。ノースカロライナ州立大学デザイン学部UDセンターによってまとめられた「UDの7原則」がその代表である。また,本分野のわが国第一人者である独立行政法人建築研究所,住宅・都市研究グループ長の古瀬敏氏は,UDの基本思想に立ち戻って「いいデザインのための6つの要求条件」を提唱した。その中で,安全性や使い勝手とともに「価格妥当性」が挙げられていることがUDの本質を象徴している。たとえば,シャンプーとリンスを区別するために,シャンプーの容器にはギザギザがついているが,視覚に障害をもつ人だけではなく正眼者にとっても洗髪時には役に立つ。特別な装備やコストを必要とせずにUDが実現された好例だ。普通のデザインの中に意識を置くだけで「より多くの人々の利便性」を具体化することができるのだ。 |
|
|
| 街や建物のユニバーサルデザイン 駅やビルなど多くの人々が利用する建物では,UDがより重要となる。人々の社会生活を,まず「行動」のレベルで考えてみよう。たとえば,階段とともにスロープが備えられている例をよく見かける。車椅子の人はスロープを用いるであろう。しかし,障害の程度によってはむしろ階段の方が使いやすい人もいる。一般の人は階段を用いたり,乳母車を押している時などはスロープを用いたりするであろう。このように「行動」に選択肢を広げることが,より多くの人々の利便性を目指す街や建物のUDには重要となる。 また,エレベータはすべての人々に利便性に優れたUD性の高い装置である。しかし,その場所にたどりつけなければ意味がない。多くの人々を目的地に導くための情報の共有化,わかりやすいプランの考え方が重要となる。昇降機メーカー,衛生器具メーカーなどでは,使いやすい位置に操作ボタンを設けるなどのUD化商品の開発が進んでいる。これらの要素をつなぎ,その利点を最大限に引き出すためには,アクセシビリティも含めて総合的に設計することが重要だ。建築設計者の果たす役割は大きい。 |
|
|
| 鹿島のユニバーサルデザインへの取り組み 当社は「安全と安心」が実現される空間づくりを目指し,制震・免震技術に代表される先端的な取組みを続けてきた。シックハウスへの対応や,災害時の避難安全性能設計の取組みも,安心と安全を実現する姿勢を人間の五感による認知と行動に拡大していく広義のUDである。昨年9月に,業界にさきがけて当社の建築設計エンジニアリング本部内に新設されたUDグループも,具体的なデザイン手法のコンサルティングのほか,普通のデザインの延長でUDが実現できること,その意識を浸透させていくことが大きな役割の一つだ。 多くの人々が利便性を享受していることすら気付かぬままに,UDに優しく包まれている生活・・・。それが当社の目指す空間づくりであり,“普通のユニバーサルデザイン”なのかもしれない。 |
|
|
| UDの重要性が声高に叫ばれるようになったのは,先進諸国が本格的な少子高齢社会に突入したことが一つの契機である。高齢者に配慮した様々な配慮とともに子育てにやさしい社会を目指した,たとえば乳母車で移動しやすい街・建物のデザインなどにも眼を向ける必要がある。 |
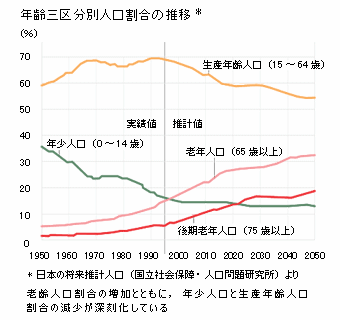
|
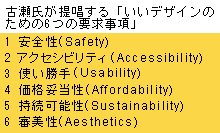
|
|
誰もが円滑に目的地にたどりつけるために取り入れられる“Way Finding”の発想。ここでは低視力者に配慮した「見やすさ,わかりやすさ」が実現された例と,それを実現するデザインのヒントを紹介する。一般には“視覚障害者=全盲”というイメージが強い。国内で視覚障害で障害者手帳を取得している人は約30万5千人。そのうち全盲の方は約2〜3万人と言われている。しかし,低視力で日常生活に困難を感じている人(ロービジョン:低視力者)は約100万人にのぼると推定されている。近視,遠視,加齢に伴う視覚機能の低下,さらには糖尿病性の視覚障害など“見えにくさ”は身近な問題である。全盲の方に配慮した誘導ブロックや点字などとともに,低視力者に配慮したUDが求められている。 「光」「色」「素材」を有効に使うことで,より多くの人に情報を伝えるデザインが実現できる。以下の事例に示すように,特別な設備や多大なコストを必要とせずに,意識してデザインするだけで視認性を飛躍的に向上させることができる。 |
|
|
|
光の使い方 照明の使い方を工夫することで,進むべき方向やものの位置がわかりやすくなる。 |
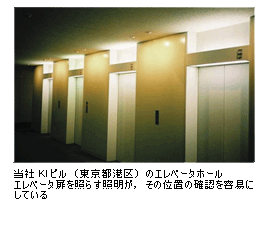 |
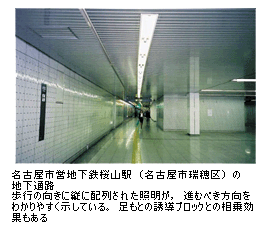 |
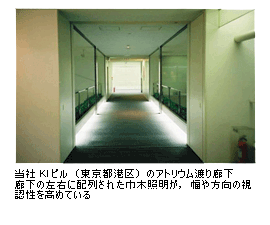
|
|
|
|
色の使い方 地(背景)と図(目的物)のコントラストをはっきりすることがキーポイントとなる。 |
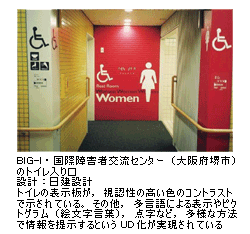 |
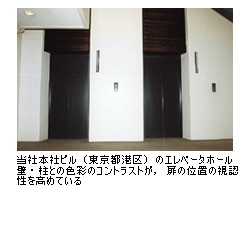 |
|
|
|
素材の使い方 足で踏んだり,触れたりしてわかる素材の感触の違いも,視覚情報を補完する重要な方法。 |
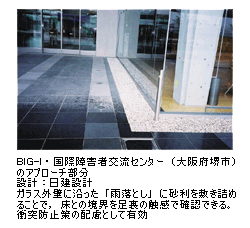 |
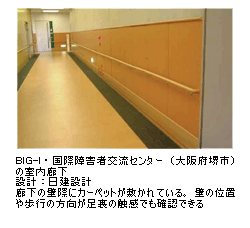 |
|
|