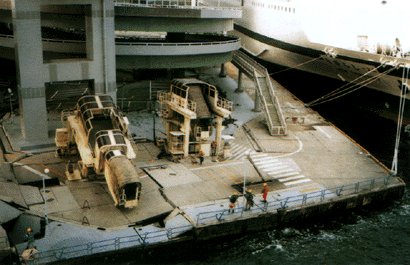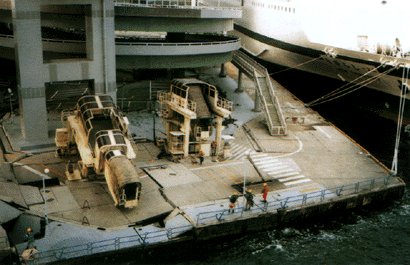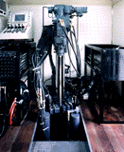NEW TECHNOLOGY
地盤データをリアルタイムに提供する
地盤調査車「GEO−EXPLORER」
忘れた頃にやって来るはずの天災―大震災―が,最近は忘れる暇もなく日本列島をおびやかしている。1月17日,震度7という圧倒的なエネルギーで兵庫県を襲った地震は,海沿いに開発された地域に「液状化現象」を発生させ,港湾構造物や工場施設が大きな被害を受けた。「敵を知り,己を知れば百戦危うからず」という言葉がある。敵を地震とすれば,己を知るとは十分に地盤を調査して,適切な対策を考えることであろう。
この地盤調査のために,精度が良く,多点の地盤データを短時間に取得し,リアルタイムに解析表示するシステムを搭載した地盤調査車「GEO−EXPLORER」が開発され,現在,阪神大震災の被災地で復旧調査活動に活躍している。
地盤調査
地盤調査といえば,ボーリングと標準貫入試験(N値という地盤の堅さや締まり具合の指標を求める試験)が主に行われてきた。このN値は,設計に使う色々な定数を推定できる便利な数値であるが,人為的なミスが入り易い欠点を有している。また,地盤はもともと均質なものではないが,N値中心の地盤調査では地盤のばらつきを設計に反映できる十分な情報が得られなかった。つまり,己を知る技術が不足していたのである。


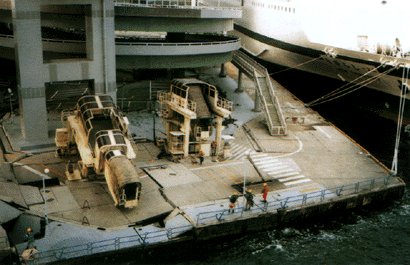
地盤調査車
「GEO−EXPLORER」は,多成分コーン貫入試験とMWD検層という2種類の方法によって地盤を調査する。
多成分コーン貫入試験とは,コーン(地質調査機器)を地盤に押し込む時の先端抵抗・周面摩擦力の他に,間隙水圧や地盤のS波(横波)速度を測定することができ,軟弱地盤の調査に適している。
MWD検層(Measurement While Drilling)は,ビットが回転したり,叩いたりして地盤を削孔する時の抵抗を分析して地盤の特性を評価するもので,やや堅い地盤の調査を得意とする。
これらの調査は,測定からデータ取得,解析,結果の表示までがコンピュータによって制御されるので,人為的なミスによるデータのばらつきはなく,本来の地盤特性を把握することができる。調査可能深度は80m,調査速度は従来のボーリング主体の地盤調査の数十倍に達するので,短時間に多点の地盤データが容易に入手できる。
また,東京工業大学・時松教授の指導を受け,東京ソイルリサーチとの共同研究によって,多成分コーン貫入試験による精度の高い液状化判定方法を開発した。この方法では,多点の判定が容易なので,敷地全体について「液状化の恐れのある」層を三次元的に把握し,地盤改良などの対策を合理的に計画できる。
地盤調査の常識を変える「GEO−EXPLORER」は,構造物基礎の合理的な設計・施工実現に向けて発進した。

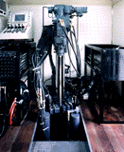
写真は鹿島月報より転載
All rights reserved, Copyright (c) 1995 KAJIMA CORPORATION