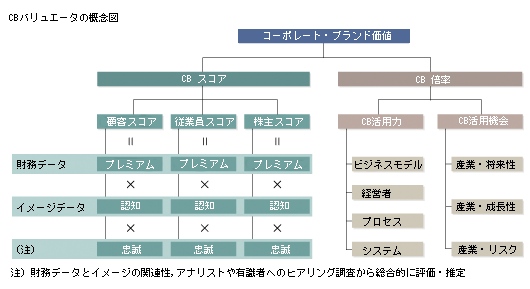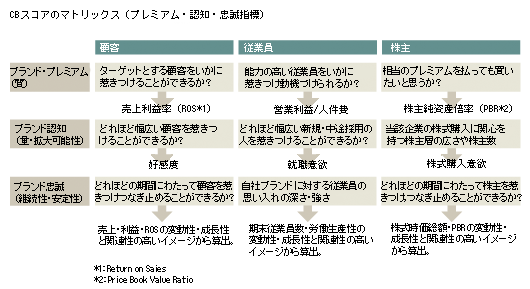| 特集:鹿島ブランドを考える・・・第3回 |
| 1 鹿島ブランドの「測定」 |
| 社内外からみた鹿島ブランド 企業が市場における差別的優位性を確保するために展開するブランド戦略。もはや一部の業種・業界では経営の主要テーマとして定着している。 ブランドは大きく「商品ブランド」と「企業ブランド(コーポレートブランド)」に分類される。前者は特定のイメージや付加価値をもった商品群を指し,後者は企業の姿勢やフィロソフィーを反映する無形の価値を示す。市場優位性を確保する強いブランドが形成されるためには,企業が社会に対する約束を実行することが何よりも重要である。企業が社会に提供する商品は,その具体的なかたちであり,社会や消費者はその約束を真摯に実行する企業の姿勢を評価し,相互に継続的な信頼関係が生まれる。いわば「商品ブランド」と「企業ブランド」は密接な補完関係にあり,いずれも社会や消費者と企業との長期にわたる絆によって形成される。ブランドが「つくるもの」ではなく「培われるもの」と言われる所以もここにある。 強いブランドは,企業内にも活力を与える。社員が会社を誇りに思い,「自分がこの会社を担っている」といった高い当事者意識と一体感が生まれ,ブランド力をより高めることができるのだ。さらに,社員の当事者意識の向上は,コンプライアンス(順法精神)を高め,ブランドを一気に失墜させる不祥事や不正行為の防止にも繋がっていく。 当社も企業経営におけるブランドの重要性に着目し,「建設業を主体とする当社にとってのブランドとは何か」「人,モノ,金,情報に次ぐ第5の経営資源となり得るか」などの基本的な検討に着手している。その第一段階として,外から内から見た当社のブランドを,可能な限り定量的に評価することに着目した。 今回の特集では,定量化の代表的な手法を用いて当社の「企業ブランド」を測定・分析した結果と,社員・役員を対象に行ったブランドに対する社内意識調査の結果について報告する。 |
|
定量的に評価される企業ブランド 近年,企業ブランド価値の定量的な評価が注目され,これを算出するいくつかの手法が開発されている。わが国の企業ブランド評価に関する第一人者である,一橋大学大学院商学研究科・伊藤邦雄教授が日本経済新聞社と共同で開発した「CB(コーポレートブランド)バリュエータ」は,その代表的な手法の一つである。 当社は本年8月に伊藤教授を本社に招き,「企業価値創造に向けたコーポレートブランド経営」と題する講演会を開催した。 伊藤教授は講演の中で,企業の新しい経営モデルとして「コーポレートブランド経営」の重要性を説き,その基本的な思想についてこう語っている。「過去10年,日本企業の経営議論は『米国型経営』と『日本型経営』の比較優位性を問うことに費やされてきました。これは,前者を株主重視型,後者を従業員重視型と決めつけた答えの出ない狭隘な議論です。株主,従業員に顧客を加えた,企業の重要なステークホルダー(利害関係者)のいずれをも軽視することはできません。そのような経営は,いずれ立ち行かなくなります。これからの経営に求められるのは,ホルダー間の価値の『対立』から『融和・統合』へと視点を転換した経営モデルを構築することです」 伊藤教授は,企業理念を象徴する企業ブランドを中心に据え,主要な3つのステークホルダーの価値向上を図り,利益の連鎖を生む体系を「ゴールデン・トライアングル」と名付けている。 それでは,伊藤教授によって示されたCBバリュエータによる当社の企業ブランド価値(以下CB価値)の測定結課および分析結課をみていこう。 |
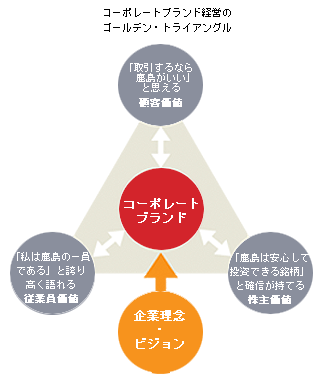
|
|
CB価値の推移 CBバリュエータで算出されるCB価値は,一言でいえば「企業ブランドを源泉として将来得られるキャッシュフローの現在価値」で,「CBスコア」,「CB活用力」,「CB活用機会」の三つの要素から算出される。 CBバリュエータによって測定された当社のCB価値の推移を下図に示す。1995年から1998年にかけて1/3程度に低下するが,その後は下げ止っている。ここには,上場している大手同業他社(3社)の平均値も併せて示したが,ほぼ同様の傾向を示している。この時期は,業界全体を通じてあらゆる財務指標が悪化した。特にCBスコアからCB価値に換算する際に参照される株式時価総額は,この期間,当社で1/2以下のレベルまで下落しており,その影響がCB価値の低下に大きく現れたと思われる。伊藤教授は日本経済新聞社と協力して,2001年より(データは2000年度をベース),全業種を通じたCB価値のランキングを発表している。第1位のNTTドコモは当社のCB価値277億円の200倍以上の5兆7千億円の価値があると算出している。以下,ランキングはソニー,セブン-イレブンジャパン,トヨタ自動車と続き,上位200社の中に建設業は1社も名を連ねていない。(注)* また,同業他社との比較において,当社のCB価値は1995年から現在にかけて最高値を維持している。その差は1998年に最小となったが,その後は優位性を回復する傾向にある。 |
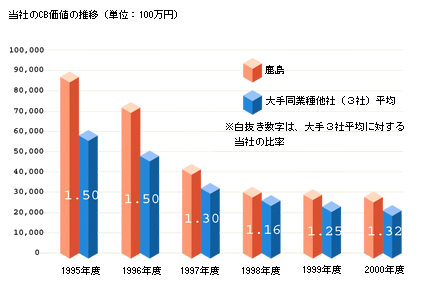
|
| (注)*本年秋に発表された最新ランキングでは,当社はゼネコントップの184位にランクインし,CB価値も404億円に回復している。ただし,最新のCBバリュエータは,(1)調査地域を米国まで拡大,(2)株主データに証券アナリストへの調査結果を導入,(3)従業員データに「新卒学大学生・大学院生」へのイメージ調査結・を参照,の3点の改良が加えられている。今回示したデータは,改良前のCBバリュエータによるもの。 |
|
ブランド力は回復傾向 キャッシュフローに換算する前の,企業ブランド力そのものを示すCBスコアの推移はどうであろうか。この期間に大幅に低下した株式時価総額を参照して算定されるCB価値ほどではないが,やはり1995年から1998年までの間に2/3程度のレベルまで低下し,その後は緩やかに回復している。各ステークホルダースコアの構成比率はどうであろうか。総和が最高値となった1996年は,比較的三者のバランスがとれているが,1998年までの株主スコアの低下が大きく,CBスコアに占める比率が1/4程度まで低下している。回復傾向となる1998年以降も比率は大きく変わらず,CBバリュエータの考え方からは,当社の株主への魅力が相対的に小さいと判断される。 |
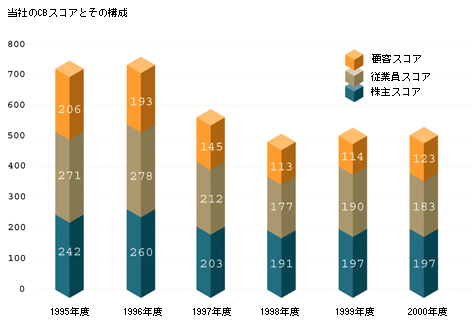
|
|
|
|
|
|
厳しい時代も顧客からの魅力は維持 さらに,詳細を見てみよう。下のレーダーチャートには,各ステークホルダースコアを構成する「プレミアム(質)」「認知(量)」「忠誠(継続性)」の個々の値を示した。1998年までの低下,その後の回復といった,全体的な傾向の中で,顧客プレミアムと顧客認知,および従業員プレミアムはほぼ一定の値を維持している。厳しい時代の中でも,品質を確保しようとする当社の姿勢が,顧客の理解を得た結果とも受け止められる。 以上,CBバリュエータによる測定および分析を通じて, ●当社のCB価値は緩やかな下落傾向にあるが,業界内部での優位性は確保している。 ●建設業のCB価値は,全産業に比較して相対的に低い。 ●ステークホルダーのうち,株主に関する価値の占める比率が小さい。 といった結果が得られた。 企業ブランドの価値を定量的に評価する意義はどこにあるのか? 伊藤教授は,「最近,多くの企業がブランドの重要性を認識し,その力を高めることを中長期の経営計画に盛り込むようになってきています。ところが,中身が空疎なことが多い。その原因は定量目標を置いていないことです。『測定できるものはコントロールできる。』定量化の意義はここにあります。定量化された目標が明確になれば,進捗状況や費用対効果の評価が可能なほか,アカウンタビリティの向上も図ることができるのです」と話している。 ブランドに関する議論は,ともすると個人レベルの価値観に強く依存する精神論,印象論といった定性的な議論に終始する。万人が同じ議論のテーブルにつき,目標を明確にしたブランド戦略を展開するために,その価値を定量化することが重要なのである。 |
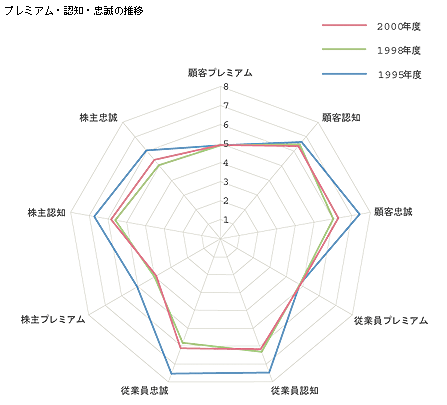
|
|
社会から見た当社の顔 CBバリュエータでは,認知および忠誠指標を算出するために企業イメージ調査の結果を用いている。その結果はどうであろうか。 このアンケートでは,すべての項目でポジティブな企業イメージに対する点数を答えるように設問されている。つまり点数が高いほど,社会は良い企業イメージを有していることになる。イメージの形成にはマスコミ報道の影響も大きいと思われる。この時期は,業界全体の厳しい状況が連日報道されたこともあり,財務内容と安定性の変動が大きい。 2000年の結果について,個別の項目を見ていこう。高い点数を得ている企業イメージ項目としては,「優秀な人材が多い」「安定性がある」「信頼性がある」「国際化が進んでいる」が挙げられる。これに対して,点数の低いイメージとしては,「個性がある」「活気がある」「成長力がある」「顧客ニーズへの対応に熱心」が挙げられる。前者の高スコアを得た項目群は,企業の歴史,実績および規模を評価するイメージであるのに対して,後者の低スコアの項目群は,将来に向けた企業の活力を評価するイメージである。 むろん,このアンケート結果は企業の実体を正確に示したものではなく,「今,当社は社会からこのように見られている」ことを示したものだ。しかし,企業の活気や成長力といった企業の将来像を映すイメージは,若い世代,すなわち就職マーケットに大きな影響を与えるもので,これらのスコアが低いことは,就職マーケットからの優良な人材の吸引力に問題が生じることも懸念される。広告・経営情報の開示・親しみやすさといった項目が低いことにも連動した結果と思われ,今後は,当社の長所をいかに外部に効果的に発信するかが,優良な人材を確保していくための課題となろう。 |
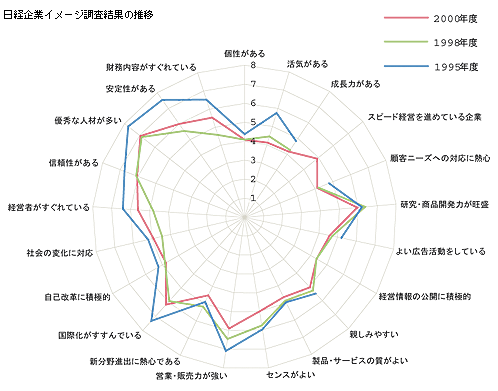
|
| ※スピード経営に関する質問は2000年より,経営情報に関する質問は1998年より実施 |
| 今回適用したCBバリュエータは,全業種に適用可能な汎用性の高い定量化ツールである。各種のスコア算定のもととなるアンケート調査も,ビジネスマンおよび一般消費者を広く対象としている。これに対して,顧客のほとんどが官庁や自治体,企業,法人であるといった建設業界の特殊性を考慮した場合,CBバリュエータによる測定が本当に相応しいか,といった議論もあろう。しかし,企業ブランドとは「つくるもの」ではなく,その企業の持つフィロソフィーと意思,明快かつ具体的な“約束”を真摯に実現しようとする姿勢が社会や消費者によって共感され,「培われる」ものである。当社にとっての顧客は,BtoBビジネスを主体とした「発注者」に限定されることなく,広く「社会」や「消費者」にも眼を向ける必要がある。社会や一般消費者の声を反映した今回の結果を素直に受け止めなければならない。 |
| 次ページ以降では,鹿島ブランドに対する社員の意識について,今秋に全社員向けに実施したアンケート結果をもとに見ていこう。 |
|1 鹿島ブランドの「測定」 |2 ブランドへの社員の意識 |