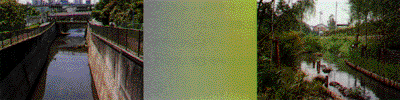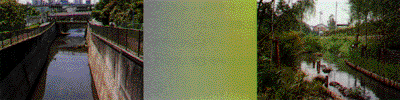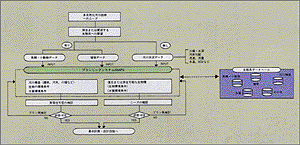NEW TECHNOLOGY
生物の多様な水辺空間の創造をめざして
水辺の多自然化工法
本来水辺には湿地があり、草花があり、昆虫がいて、水浴びをしに小鳥がやってきた。しかし治水機能を優先するあまり、水辺はコンクリートによって生き物と隔てられてしまった。
当社では、さまざまな生き物と共存できる水辺空間をめざした研究開発を行っている。今月号のNew Technologyではその研究の経過を紹介しよう。
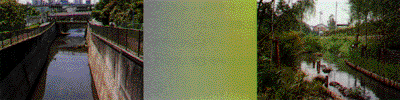
- 見直されるコンクリート三面張りの護岸
従来から河川の護岸改修にはコンクリート三面張りによる護岸が多く採用されてきた。しかし、直線化され、画一的で治水機能だけを優先させたこの護岸改修のあり方が見直され、景観や水辺の生物の生息に配慮した「多自然化工法」が近年注目されている。
「多自然化工法」とは、治水面での安全性を考慮しながらも、水辺の植物や昆虫、野鳥など多様な生物が共存する水辺づくりをめざすものである。環境先進国と言われるドイツやスイスで生まれたこの考え方や技術は、自然環境と調和した開発事業という点からも注目されているが、わが国ではその歴史は浅く、実績も少ないのが現状であった。






- 緑化試験場で展開されている基礎試験
千葉市花見川区にある当社技術研究所の緑化試験場では、水辺の多自然化のための基礎試験を実施している。立地条件が多様なほど多くの種類の生物が生息できるという考えに立ち、緑化試験場内の調整池に池、湿地、せせらぎ、堰など多様な水辺構造を持った生物空間を造成した。そして、それぞれの立地に合わせてアサザ、クサヨシ、エゾウキヤガラ、ノカンゾウなどの野生植物を植栽し、この水辺空間の生物相の移り変わりを経時的に調査している。
植栽3カ月後の調査では、植栽した植物が旺盛に成育するとともに、新たに30種類以上の植物の侵入が確認された。またヒメゲンゴロウ、ミズカマキリ、ギンヤンマ、ウスバキトンボなど、10種類以上の水生昆虫の生息が確認された。
野鳥についても半年の間にカワラヒワ、ハクセキレイ、ホオジロ、スズメ、カルガモなど20種類以上の飛来や水浴びが確認されている。
当緑化試験場は都市内に位置しているが、調整池が樹林に接していることや、複雑な水辺構造を造成したことなどから、生物の多様性向上は予想以上に早かった。このようなデータは、新しい多自然化の提案や設計、施工、維持管理のために必要なデータベースとして蓄積し、活用される。
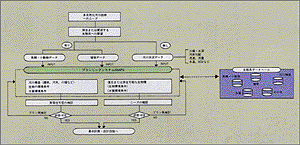
写真は鹿島月報より転載
All rights reserved, Copyright (c) 1995 KAJIMA CORPORATION