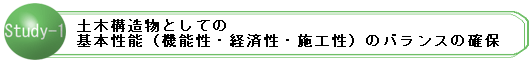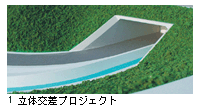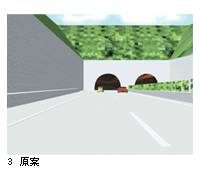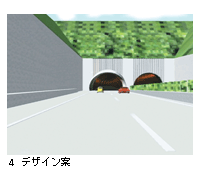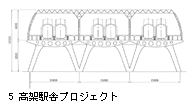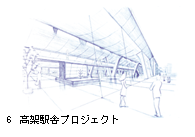| 特集:景観デザインと土木の「バランス」 |
| Chapter1 土木のデザインコンセプト |
|
土木構造物としてのバランスと風景のなかのバランス 豊かな景観の創造と自然環境の保全が求められるなかで,1990年代以降,土木においても景観デザインに関する思想や手法の形成,制度の構築が本格化してきた。たとえば2001年には土木学会の景観・デザイン委員会で「デザイン賞」が設立されている。 こうしたなかで当社では,景観デザインに取り組むにあたって,総合建設会社(ゼネコン)として土木構造物を建設してきた実績と経験を基盤としている。それは,土木構造物の前提となる機能性・経済性・施工性のバランスを確保したうえでデザインすることである。つまり,「土木構造物としての基本性能のバランス」が,第一のデザインコンセプトとなる。 第二に,いわゆる意匠を考えるにあたっては,「シンボル性」と「調和性」を結ぶデザイン性の指標軸を設定し,「風景のなかのバランス」を重視した設計を行っている。つまり,周辺の環境や構造物の機能に応じて,シンボル性を強調するか,調和性に重点を置くか,あるいは双方を融合させるかを検討し,実用的でバランスの良い景観の創出を当社はめざしているのである。 ここでは,それぞれの設計主旨の特徴がよく表れたデザインの事例をもとに,鹿島の景観デザインのコンセプトを紹介する。 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|

|
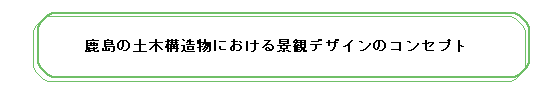
|

|
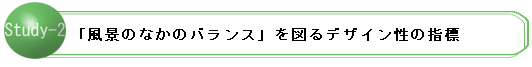
|
|
|
|
シンボリックな構造物においてもデザイナーの個人的な主義主張は求められず,地域の環境や風景のなかでバランスよく存在することが課題となる。 図5〜7の〈高架駅舎プロジェクト〉は,橋梁技術を活かした土木ならではの空間デザイン。街の伝説に由来する光の演出は,構造美のシルエットが骨格となっている。 図8〜10の〈富士通厚木グランド歩道橋〉では,シンボリックな造形を事業者から求められるなかで,CIマーク(∞)をイメージさせる平面線形で設計し,豊かな緑に映えるデザインとした。 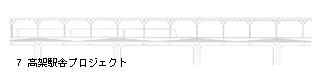
|
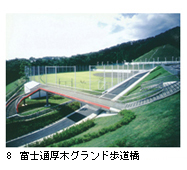
|

|
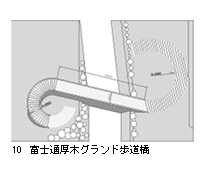
|
|
|
|
風景に調和し,バランスよく溶け込むことをめざす土木構造物では,造形だけでなくテクスチャーや色彩など細部にわたってデザイン検討を行っていく。 図11〜12の〈多摩川橋梁〉では鉄道鋼橋の色彩計画を手掛けた。周辺環境の色彩や特色,環境色の調査を実施し,橋梁形式をより美しくみせるカラーコーディネートを展開した。 図13〜15の〈鉄道高架橋プロジェクト〉は,連続立体交差事業にともなう鉄道高架化計画におけるデザインである。さまざまな視点からの見え方と周辺のイメージ調査をもとに,存在感を和らげるテクスチャーや色彩などをまとめた。 |
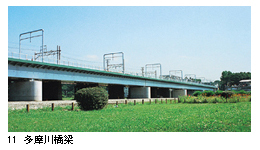
|

|
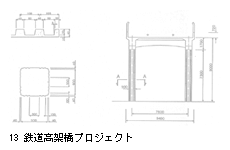
|
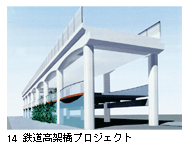
|
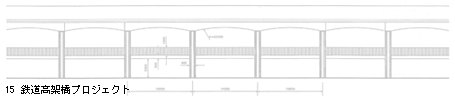
|
|
|
|Chapter1 土木のデザインコンセプト |Chapter2 橋梁美の設計プロセス |Chapter3 鹿島の考える「バランス」 |