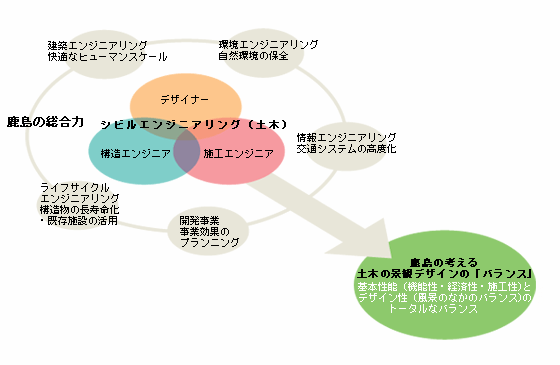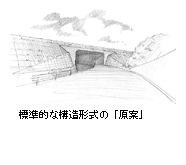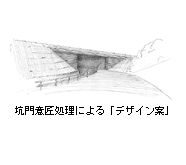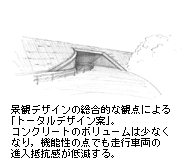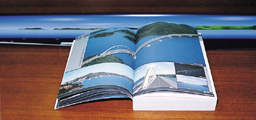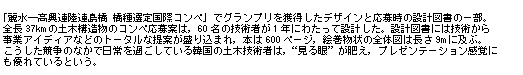|
|
interview
国際競争力となる土木の景観デザイン
杉山和雄千葉大学教授のヴィジョン
|
|
|
土木の景観デザインは今後,どのように展開していくのだろうか。橋梁をはじめとする国内外の景観デザインを手掛けている杉山和雄千葉大学教授にその展望を伺った。工業デザイン出身の杉山教授は,郵便局の次世代窓口や新型郵便ポスト,あるいは高速道路のETC(自動料金収受システム)ゲートなどのデザインの開発を主導するなど,幅広い分野でデザイン活動を展開している。また,土木の分野では大規模な国際コンペ(設計競技)で数々の1等入選を果たし,昨年5月に審査が行われた韓国の「麗水─高興連陸連島橋 橋種選定国際コンペ」においても,見事グランプリを獲得した。
|

 |

|
杉山和雄(すぎやま・かずお)
1942年 香川県生まれ
1966年 千葉大学工学部工業意匠学科卒業
同大学院修了後,米シカゴのデザイン事務所
(Latham, Tyler & Jensen Design Inc.)などを経て
1973年より千葉大学勤務。
1994年 千葉大学工学部工業意匠学科教授
現在,千葉大学大学院自然科学研究科教授。工学博士。
土木学会 景観・デザイン委員会委員。
専攻は,橋梁デザイン,インダストリアルデザイン,
デザインマネジメント。
おもな橋梁作品に,〈本四連絡橋:瀬戸大橋,大島大橋〉
景観設計,韓国ソウル「永宗大橋国際コンペ」最優秀賞,
〈東京湾横断道路:アクアライン橋梁〉などがある。
|
|
|
優れた評価基準をもつ土木
──土木だけでなく工業デザインでも活躍する先生の眼に映る“土木のデザイン”とは。
●たとえば“デザインの志向”という点では,建築は施主志向,工業デザインやプロダクツは消費者志向といえますよね。一方で土木は,まだまだユーザーの方を向いているとはいえません。現在の日本では,デザインを重視するかどうかは担当者個人の想い入れ次第であるのが実情です。
しかし,土木事業の“評価基準”は非常にしっかりしており,ほかの分野よりもはるかに優れています。なぜその工法なのか,なぜそういう造形になったのか──機能性・経済性・施工性など,多角的な観点から理論を組み立て,評価基準を明確に説明できます。建築のコンペの評価基準は感覚的な部分が多いですが,今後,市民の理解が重視される時代には,ほかの分野が土木に学ぶべきところがあります。
|
|
|
37kmを構築する景観デザインの手法
──昨年の韓国の橋梁コンペでの評価基準についてお聞かせください。
●「麗水─高興連陸連島橋 橋種選定国際コンペ」は,韓国南端の9つの島と3つの半島を11の長大橋梁でつなぐ全長37kmについて,地域計画も含めて行うプロジェクトの基本設計を競うものでした。橋梁,高架,道路線形,トンネルの数や配置など,すべての土木構造物をトータルに提案するのです。デザインや技術,コストはもちろん,観光による地域の経済効果の計画も求められます。
今回の私たちのデザインにおける評価基準のひとつに,「シークエンス景観評価」があります。この手法は,じつはテレビ番組の“予告編”自動作成システムの開発がベースとなっているのです。多チャンネル時代の番組選びは,文字情報ではなく,映画の予告編のように圧縮版の映像で選ぶようになります。この手法を膨大な視点場からなる景観デザインに応用したのです。
37kmを渡る間に橋梁や道路がどのように現れ,見えてくるのか──計画全体のなかで重要になる景観デザインのポイントを摘出し,その根拠を説明するうえで「シークエンス景観評価」は非常に有効でした。この手法はコンペの審査員たちも知らなかったようですが,私たち以降の応募者には,「シークエンス景観はちゃんと考えているのか?」と審査員が質問していたと(笑)。
|
|
|
デザイン勝負の時代
──今後の土木における景観デザインの位置づけはどのようになるのでしょうか。
●グローバルな競争時代の到来は,土木も例外ではありません。韓国では大規模な橋梁建設はコンペなどで行われており,韓国の建設会社が海外のデザイン事務所やコンサルタント会社とコラボレーションするのは日常茶飯事です。したがって,どの建設会社も技術的提案では優劣がつけ難いため,“デザイン勝負”になります。“安くて良いデザイン”が選ばれるのです。
このことは欧米でも同様ですが,経済効果を含めた事業アイディアが評価対象となり,工事の発注へと結びついています。私の研究テーマのひとつがデザインマネジメントのシステムですから,国際コンペでの経験をもとに,土木の発注形式についての寄稿や各種委員会への参画の依頼も増えていますね。
|
|
|
工法に相応しいデザイン
──総合建設会社(ゼネコン)の土木技術者へメッセージをお願いします。
●まず,国際競争時代に向けての力を蓄えることが重要だと考えています。そのためには,デザイナーとエンジニアの双方がお互いに勉強しあうことです。また,デザインと技術の融合のためには,教育が重要になります。
ゼネコンには両者がひとつの組織にいますし,何といっても施工技術が優れています。“工法に相応しいデザインの研究”を実現できるのはゼネコンならではの強みといえるでしょう。たとえば,高架橋の計画を行うとすれば,1.いかに周辺の交通を遮断せずに工事を行うか,2.そのための工法は,3.その工法に相応しいデザインは,という流れに沿って第三者に説明することになりますから。
繰り返しますが,土木における評価基準の論理の組み立ては,ほかの分野にはない優れたものです。これをさらに事業アイディアも視野に入れて磨けば,市民も理解しやすくなりますし,真に価値のある社会基盤が生まれることになります。その結果,自然と良い景観が創出されていくでしょう。
|
|