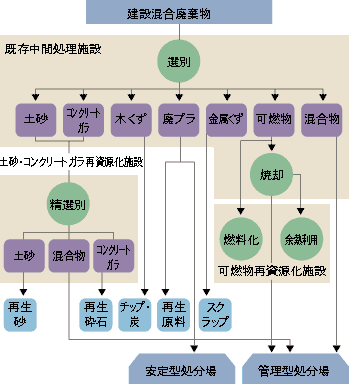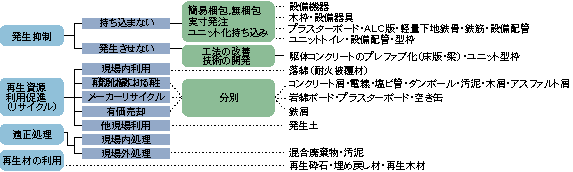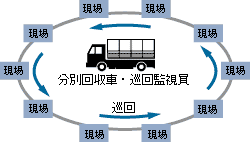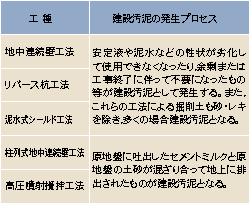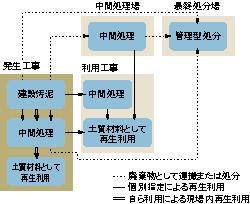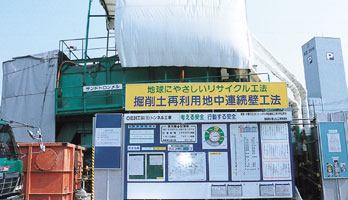|
特集:建設副産物のリサイクル ゼロエミッションをめざして 建設現場では大量の建設副産物が発生する。その中に廃棄物もあれば再生資源もある。特に現状でリサイクル率も低く処理上大きな問題となっているのが,混合廃棄物と建設汚泥である。数種の材料が混じった混合廃棄物の分別処理は建築工事での主要な課題だ。特に解体工事では木くず,紙くず,コンクリート塊,鉄筋くずから,ガラス,蛍光灯まで各種分別が必要とされている。一方,建設汚泥処理は大量発生する土木現場で大きな課題となっている。各現場ではそれぞれに方策検討を行い,リサイクル率の向上を図り,廃棄物の出ないゼロエミッション現場をめざしている。 建築工事における建設副産物3R (Reduce,Reuse,Recycle)活動の徹底 当社における3R運動は1991年度から始まる。代表的モデル現場を中心に展開されてきた。中には建設大臣賞受賞の科研製薬建設工事(現・文京グリーンコート,98年竣工)や南千住四丁目都民住宅建設工事(昨年竣工)があげられる。このノウハウは引き継がれ大規模現場から中小現場まで展開中だ。さらなる徹底のためには混合廃棄物のリサイクル率向上が課題となっている。近年は解体・リニューアル分野での強化徹底にも重点が置かれている。
東京支店での事例 ●3R運動の推進徹底を図る 「番町・麹町共同ビル新築工事」の現場では,協力業者とともに現場内で3R推進委員会を組織し,3Rの徹底によって廃棄物発生の抑制にあたった。とりわけ混合廃棄物排出計画の中では,削減目標(削減率30%)を具体的に算出し,月ごとの目標管理により大幅削減の実績をあげた。
●中小規模現場は巡回回収システムで 中小現場ではコストや空間制約上,また発生量の大小によって,細目にわたり分別保管することが難しい場合も多い。当社ではこうした中小現場でも分別徹底による3Rの展開が可能となるように,地域ごとに巡回回収するシステムを導入している。実際に処理コストは2〜3割減,混合廃棄物は4〜5割削減したというデータもある。
●解体工事はまず事前調査そして分別解体 解体工事においては事前調査により有害物質の有無を確認する。そして解体手順方法を検討し,分別解体工法を行うことを基本としている。「日本水産晴海冷凍工場解体工事」の工場及びアパートの解体では,まず内部造作物の撤去にあたり,水銀系廃棄物である蛍光灯を先行撤去後,内装解体業者が木くずと断熱材等を分別撤去。ほとんどコンクリート躯体のみになったところで躯体解体に入り,コンクリートガラを小割りし鉄筋と選別。ガラは敷地内の整地にも利用した。
土木工事における建設汚泥を様々な形で処理そして再利用 建設汚泥とは,建設工事に伴って,副次的に発生する廃ベントナイト(地盤安定剤の一種)泥水や,含水比の高い粒子の微細な泥状の掘削土等でそのまま他工事に流用できないものの総称である。具体的には車両に山積できないもの,その上を人が歩けないもの等の状態のものをいう。一般に中間処理(異物を除き脱水処理したあと土質改良のための安定処理を行う)した後,再利用したり最終処分したりする。
関東支店での事例
●現場内で再利用し地中連続壁を構築 埼玉新都心の地下を通過する高速大宮線の「OE24工区トンネル工事」では,開削型道路トンネル工事のための山留・止水壁としての地中連続壁(深さ約56m)を施工中である。ここでは掘削した土砂とセメントミルクを添加攪拌しソイルセメントとして打設,地中連続壁構築の主材料にしている。現状60〜70%程度のリサイクル率で掘削残土処理費も削減でき,環境保全・経済性ともに優れた画期的VE提案工法として注目されている。
|
|
|建設副産物をとりまく社会的背景 |建設現場での取組み・リサイクル事例 |循環型社会を見据えて |循環型社会とこれからの建設業 |