| 特集:建設業をよく知ってもらうために 鹿島の魅力発信者たち |
| |
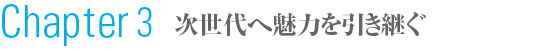 |
| |
| 当社は,世界に誇れる技術がある。 それは,技術者の絶え間ない新技術の開発によって,未来に受け継がれていく。 いま,どんな技術が生まれ,使われているのか。 技術研究所や展示会,科学技術館など,当社の技術に出会える場所はさまざまである。 |
| |
| |
| |
3人の中で最初からこの業務を担当している梅原さんは,「建設の技術がいかに人々の生活の役に立っているかをたくさんの人に知ってほしくて」案内役を志願した。 案内をするのに誰かが作ってくれたシナリオはない。技術資料を自分達で勉強し,直接担当の研究員の話を聞く。「最新の技術情報を発信するには,発信の担い手が完全に理解していることが前提」という。その一方で,見学者が何を求めているのか,知りたいことは何かというニーズを的確に捉えることに気を使う。 「私自身,新しい工法や技術を学び,情報を得る度に,建設業って何て面白いのだろうと感じる。その面白さが少しでも伝えられればいい」。誠実,丁寧に説明する。質問に答えられないことは,研究員に確認し,可能な限り回答する。 社会のニーズが多様化する中で,研究対象が巨大構造物から防災や地球環境技術に広がり,研究分野も多岐に分化した。それだけに訪れる人の関心の方向や深さもそれぞれ違う。 免震技術などは実際にその建物を見,その構造に触れることで納得してくれる。「これだけのことをしているから,きちんと安全なものが造れるのですね」。そんな感想が聞けるのが楽しい,と梅原さんはいう。百聞は一見にしかず。技研の施設を見学することで「鹿島の技術力」を分かってくれるのだ。 世界でもトップクラスの建設技術を生み出す現場にいると,地震や台風など災害の多発国で,人が安心して住めるのは,建設業の絶えざる努力があってこそ,ということを実感する,と語る梅原さん。「それなのに,建設業の暗い面ばかり強調されているのは残念な気もしますが,技研の見学で,便利で快適な普段の生活の基盤を建設業が担っていることを,改めて認識してくださる方がいると思うと,嬉しいです」。 環境やエネルギー,地盤・岩盤,情報通信技術関連の実験機能を集めて高度化した新実験棟も,4月から本格運用を開始した。梅原さんたちの活躍の場がさらに広がった。 「学生さんを案内することもありますので,その中の何人かでも,将来建設業を選んでくれたら嬉しい。建設業の魅力を発信できる最前線のひとつが技研であると思っていますから。これからも『一期一会』を大切に,使命感を持って仕事をしていきたいですね」。 |
| |

| |
| |
| |
2008年のある展覧会では,旧本社解体工事で導入された「鹿島カットアンドダウン工法」で切り出された鉄骨柱5体をメインに配置。モノとしての迫力と美しさを伝えて,複数のメディアに取り上げられた。「設計活動の特徴をアピールするには,最終成果物を図面,模型,写真で紹介するのが一般的だが,美術館での開催を意識して,建築を題材にしつつアートにも見える表現を採った。思った以上の反響があった」。 設計業務の醍醐味は,クライアントなどと一体になって,多岐にわたる要望を実現可能な提案にまとめていくプロセスに関与できること。その魅力をさらに分かり易く,楽しく発信できる方法を模索する。 |
| |
| |
| |
これらの活動に加え,2007年にスタートした日本科学技術振興財団のサイエンスボランティア活動にも名を連ね,こども向けの科学啓蒙教育の一環として,建設現場の見学会開催などを支援している。 「かつて故石川六郎会長は,経団連の『1%クラブ』活動を積極的に推進し,会社や業界のイメージアップに繋げた。企業のボランティアへの取組みは,会社イメージの形成に重要な役割を果たすと思う」という。個人的な思いから始めたボランティア活動が,会社の情報発信に繋がる一例である。 |
| |
| |
| |
「大学で『ものづくりの素晴らしさ再発見』といった冠講座なり,広報活動は必要です」という大湾さん。学生時代に見た「超高層のあけぼの」「黒部の太陽」のような映画は刺激的だったという。「建設業界がタイアップして,若者が建設を志向するような企画を提案すべきと思う」。環境再生も含め,社会基盤の整備に建設業界が貢献していることをPRする必要性を痛感している。 「自分が苦労して取り組んだものが仕上がっていき,仮囲いが外れて全体が見えたときの達成感は,建設業ならではの喜びです」。講演などで大湾さんが語る,会社の魅力発信に欠かせない“フレーズ”である。 |
| |
| |
| |
研究会はNPO組織(知的資源イニシアティブ)となり,伊藤さんは理事を務める。「主として時間外の活動を通じて様々なフィ−ルドの人と出会い,その中で価値観を共有する。図書館を街づくりの起爆剤として,既成の概念を越え,企画を創りあげていく楽しみがある」。 建設業の魅力は「人との出逢いが多いこと」という。外部の人も「人」を介して建設業を知り,最新の技術を知り驚く。しかし「感動」は建設に関わった人の熱い言葉からのみ伝えられる。「私たちが外へ飛び出して,会話を通じて『感動』を広げていく。建設業を知ってもらえる,遠いようで一番の近道かもしれませんね」というのである。 |
| |
| |
|
| |
| ■ Chapter
1 情報発信の最先端で ■ Chapter 2 鹿島環境学校の教授たち ■ Chapter 3 次世代へ魅力を引き継ぐ ■ Chapter 4 業界団体によるイメージアップへの取組み |





