| 特集:建築施工革命序論 |
| Revolution-2 座談会:総合力を現場に結集せよ |
|
|
| 当社はいま,全社横断的に技術と人材を結集し,現場に総合力を具体的に注ぎ込もうとしている。つまり,現場志向の知恵によってゼロベースから施工方法を刷新することで,革命を巻き起こし,さらなる利益の向上を目指している。そこには,建設会社の主役は現場であり,現場での創意工夫こそがエンジニアリングスピリットだという当社の伝統的な志向が基盤となっている。
ここでは,各部門の第一線に立つ4人に,その意志を聞いてみた。座談会に登場いただくのは,現場を代表して小田急海老名分譲マンション新築工事事務所の荒木修治所長,現場の良き相談相手となる建築技術本部の荻原行正本部次長,工法の前段階として構造設計を行う建築設計エンジニアリング本部・富田昭夫グループリーダー,そして建築技術部門を統括する役員であり,数々の現場の所長から支店建築部長,横浜支店長を歴任してきた南谷修副社長である。 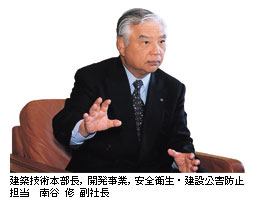 「考える時間」をつくれ
「考える時間」をつくれ──現在,赤字で受注した工事,いわゆる「赤字工事」が,当社だけでなく建設業界全体において企業経営を圧迫し,大きな問題となっています。とくに民間工事の多い建築分野では,こうした現況からの脱却が求められているようですが。 南谷 建設業では,旧来の確立したひとつの方法が安いとは限りません。それぞれの場所や環境の特性を十分に理解したうえで,そこに合理化工法を加味し,いかにつくり込むか──これがじつは一番大切なことだと思うのです。 現在,この「つくり込み」が欠けていると思っています。赤字工事であっても時間がないから旧来の方法でつくってしまう・・・。赤字であっても,最も適切な工法を採れば,それを解消する確率は非常に高いのです。 さらに時間に追われていると,新しい工夫を検討する間もなく,従来どおりの方法で行ってしまいます。たとえ1ヵ月間,仕事を止めても,きちっと計画すれば利益が向上する可能性はうんと高くなると思いますね。そういうことを皆さんが考えたら,一段と利益は良くなるはずなのです。 ──現場の良き相談相手として建築技術本部(建技本)がありますが,本社の技術管理部門,施工技術開発の立場から,現場が抱える問題点とは何でしょうか?  荻原 やはり,「考える時間」がなかなか取れないのが現場の現状だと思いますね。いまは技術情報が溢れていますから,そのなかから自分たちの現場に使える技術を整理し,自分たちのものにするということが難しくなっています。建技本としては,新しい考え方や技術情報を整理して現場に提供することで,現場が新しいチャレンジを行えるように協力していくのが役目だと思っています。 また,受注競争は,これまでのように低価格競争ではなく,「知恵のコスト競争」になると考えています。このようななかで私たちは現場をいかにサポートし,利益に貢献できるかが問われていると思っているのです。 ──海老名のマンションの現場では「考える時間」はいかがでしたか。 荒木 この現場では,ある程度の時間と,私が着任する以前のつくり込みの時間がありましたので,そうした面では非常に有利に仕事の展開ができたと思っています。 得意な方法でつくり込め ──現場の前段階となる設計でも,さまざまな工夫や役割があると思います。建築設計エンジニアリング本部(A/E)で構造設計を担当されている立場からは──。 富田 さきほどの「つくり込み」という点は,設計が関与しなければならない部分だと思います。耐震性や安全性を考えた設計は当然として,どのように建物をつくるか,どうしたらつくりやすくなるか,という点で考え,たとえばKIP構法、NEOS構法、NEOカラム工法といった新しい構工法を開発していくのが構造設計のひとつの役割です。そうした技術を建物のつくり込みのなかに取り入れ,現場の利益向上や工期短縮に役立つように考えるのが私たちの役割であると思っています。 主役は現場 ──現場はまず利益確保,そしてさらなる利益向上が求められています。利益向上の特効薬はあるのでしょうか? 利益の確保のために新しい工法を考えると言っても,現実的にはそこまで現場が踏み込むのは難しいような気もしますが。 南谷 そのとおりだと思いますが,さきほど私が「現場」と言ったのは,現場の人が主役にならないと,どんなに良い案も実行に移せないからです。実際に,現場の立場で鹿島の総合力を結集し,それを活かせるか──これは大変難しいことです。 当社の総合力は,絶対に他社には負けないと思います。この総合力を引き出す人たち,そして従来のやり方を変える勇気を奮い立たせる人たちとは,コンサートマスターのようにタクトを振る指揮者なのですね。現場を管轄する全国の各支店のなかに,このような指揮者がどれだけいるか,また,どれだけ強い実行力をもち,先を見てタクトを振れるかが最も重要なのです。当社の演奏者は,現場も,設計も,技術研究所(技研)も,建技本も,超一流の人ばかりなのです。しかし,まとまらなければオーケストラにはなりませんね。 そして,第1バイオリンとなる現場に元気がなければ,タクトの振りようもないわけです。現場が元気を出す,それをみんながサポートしていく,これが一番だと思います。 ──現場の立場からすると,「そうはおっしゃいますけどね」というご意見もあろうかと(笑)。 荒木 そうですね(笑)。今の現場の状況は,非常に厳しい──価格競争や工期短縮の問題など,それぞれの現場でさまざまな苦しい状況を抱えていると思うのです。しかし私たちは,あくまでもひとつのプロジェクトの責任者として,社内の意見や技術力をフルに活用していかなければいけないと,つねに意識しています。また,このような苦しい状況だからこそ,明  るく,元気よく仕事をしたいと,いつも心がけています。 るく,元気よく仕事をしたいと,いつも心がけています。挑戦が新たな利益の可能性を生む ──海老名の現場では革新的な工法を採用していますが,所長としての心境はいかがでしょうか? 荒木 従来工法と比べると,立ち上げ当初は計画や検討のために大きなマンパワーが必要でした。しかし現場の技術者として,やはり新しい挑戦が必要だという意識はつねにもっています。 今回の現場の場合,確保すべき利益目標を,従来の工法から生み出すのは無理だといわれていました。新しい技術を駆使して挑戦することは,利益の生み出し方がまったく違うと思います。利益追求の方策が違いますから,利益額はひょっとすると従来の2倍,あるいは3倍になるかもしれないという可能性も秘めているわけです。その可能性を自分で追求する楽しみというのは,技術者冥利につきますね。 難しい問題に挑戦して,ただ辛いとか苦しいとか思うのではなく,挑戦することに面白みと楽しみを感じるような仕事ができれば一番良い,と私は思います。 南谷 忘れてならないのは,海老名の工法を実行するには多くの社内のバックアップが必要なことです。たとえば,従来の観念では考えられない超大型の建設用リフトを導入するには厚生労働省の許可が必要で,安全環境部や機械部の全面的な協力がありました。当社のそういう総合力はすごいですよね。また,海老名のように総合力が発揮できた現場というのは,利益だけでなく,いろいろな面でうまくいきますよね。 「常識」を捨てろ 南谷 これまでの建設業の生産システムは,極端に言えば「横並び」でした。20年前と何が変わったかというと,工場生産化・プレキャスト化の比率が多少向上した程度です。製造業で技術革新もなく,十年一日のごとくの工場でしたら,とっくに淘汰されていますよね。 だからこそ考えてみてください。従来の「常識」は,もう非常識かもしれないのです。私たちがいま考えている新しい生産システムとは,従来の常識をぬぐい捨てたうえで,いかに合理的につくるかということです。今までのやり方を全部捨てたゼロベースで考えたら,ずいぶんと違うものができるだろうと思いますね。 たとえば競技場の400mトラックがあって,上がスタート,下がゴールとすると,専門家ほどインコースを取ろうとしますね。幼稚園児は絶対にしません。ゴールに向かって直下に一直線にフィールドを横切って行きますよ。そこには「トラックを走る」という常識がありませんから。確かに最短距離は直線なのです。そういう発想を私たち自身がなくしているのではないでしょうか。 こうした意味で,つねに原点に帰って,従来の常識を捨てたなかで生産システムを考えたら,これまでの「不合理」がもっと浮き彫りになると思います。たとえ既存の技術でも新しい発想のもとで組み合わせれば,新しい生産システムができるかもしれません。そう考えると,建築というのは面白いし,現場の人にとっては宝の山みたいなものじゃないかなと。 「最短距離」を走れ  ──しかし,辛い宝の山ですよね。 荒木 辛い面も当然たくさんありますが,それだけに遣り甲斐があるということです。新しい工法で施工するには心配がつきもので,想定どおりに実現するのかと──だれもやったことがないわけですから確証はありません。まったくの想定外のことが発生するかもしれません。それを一つひとつ丹念に確認して作業に取り掛かりますが,それでも見落としがあるかもしれないという心配が・・・。 南谷 しかしそれは技術者冥利でしょう・・・。 荒木 楽しんでいる余裕はありませんが,現場でお客様に工法のご説明をしていると,「この現場は何か楽しそうにやっているね」というお話しを受けたこともあります。外からはそう見えたのかもしれませんね。 荻原 新しいことを開始するには当然,リスクがあります。そのリスクをいかに顕在化させるかという意味でも,専門情報を多くもった技術者からの全社的なバックアップが必要だと思います。しかし,その技術者がリスクを強調し過ぎたり,否定的な意味からのチェック項目を出したりするのと,逆に一緒につくっていこうと思って問題点を出すのとでは,雰囲気が大いに違ってきます。注意すべき点は提案しますが,一緒になって乗り越えようという姿勢が必要なのですね。 富田 私たちが新しい構工法の設計を採用して現場に提示すると,最初は躊躇する声が結構多いですね。以前,現場の所長さんと私のあいだで工法の結論が出ず,関連部署で協議を重ねたことがありました。新工法の採用に至るまで時間が掛かりましたが,一端「やる」と決まると,当社は現場をサポートする関連部署の皆さんが高い技術をもっていますので,非常にうまくいき,やってみて良かったという結果になりました。 タクトを振る指揮者,マエストロのような人が,やはりどこかにいないと,施工担当者としては躊躇するといいますか・・・。とくに,それが新しい工法だと先が読めず,不安になるのですね。施工担当者,サポート体制を含めて,設計の早い段階から的確にチャレンジの方針を決めていく人材の育成が必要であると思います。 利益は「所長の哲学」が生む ──いま,何かにつけて,現場の所長さんにすべての責任を集約するようなかたちが多いですよね。 南谷 現場の所長さんは,やはり建設業の主役なのです。当社の利益の根源は,そこの所長の哲学みたいなものがあって,その哲学によって利益が生み出されると思うのです。 海老名の新しい工法も,実際に在来工法より安いのか高いのか,所長は非常に苦労したと思いますね。その苦労や,生産システムを変えるリスクはだれが負うのか? それは現場の所長じゃないですよ。現場の人が主役を演じられるような舞台をつくり,サポートをする──それは本社,支店の役目です。主役の現場に不安をもたせてしまったら,やはり駄目です。 荻原 既存の技術も新しい技術も,土木の技術までも含めて,その現場に適合できる技術の数を用意しておく──これまで建技本は用意ばかりに気を使い過ぎたところもあると思います。これからは,プロジェクトの特性に合わせた「技術の組み合わせ」を提案できるような,そして現場と一緒になって考えられるチームを柔軟に・・・。それができる仕組みを建技本のなかでつくっていきたいと思っています。 コストダウンの急所は構工法  ──海老名の工法をやろうと言ったのはだれですか。 南谷 タクトを振る人でしょう。しかしそれを決定したのは現場ですよね。本当の気持ちを言えば,22tの梁をリフトで上げるのを「だれが考えたのか」と聞かれたら,「馬鹿なやつがいた」としか言いようがないと思います(笑)。従来の常識からみれば,外れたところにあるわけです。しかし,生産システムとしては,当たり前のものとして考えられる要素のひとつだと思うのですね。普通なら「馬鹿な」と言われて一蹴されることが,今回は最適な工法だったと思いませんか? 荒木 そのとおりですね。たとえば,海老名の敷地は非常に風が強いのですが,普通のタワークレーンを使えば吊り下げの距離が長くなり,重い部材が揺れることになります。その点,今回の生産システムはリフトで揚重しているため,風の影響を非常に受けにくいですから,強風で作業中止となる日がほとんどなく,順調に効率よく進んでいます。 荻原 構工法のほかに,土工事や杭工事にも,仕上げ工事にも,それぞれに新しい技術や考え方はあります。しかし,建築のなかで合理的な考え方を活かし,それによって工期を短縮してコストダウンできるポイントは,やはり構工法だと思うのです。購買などの調達も大切ですが,構工法は工夫や知恵が最も活かせる部分です。だからこそ,ここを攻めていくべきだし,構工法が工事全体のペースメーカーであると思っています。 知識を知恵に変えるのは支店 南谷 こう考えると,ひとつの技術に固執するのではなく,その場所に適した,その所長に適切な生産システムを見極めるのが大切なのではないでしょうか。建技本,技研,A/Eといった皆さんの知識を,現場や支店で知恵に変えていくこと──つまり,個々の技術やノウハウを鹿島の総合力として現場に結集することが最も重要なのです。では,それをどこで実際にやるのかというと,やはり支店でしょう。 皆さんの個々の能力をどのように組み合わせ,どのように現場に注ぎ込み,それを現場がしっかり受けとめて工事を実行していく──それだけのことですし,それが一番大切なのです。 |
|
|
■Revolution-0 いまこそ施工革命宣言のとき ■Revolution-1 タワークレーンのいない超高層工事 ■Revolution-2 座談会:総合力を現場に結集せよ ■Revolution-3 躯体工事を攻めるクリエイティヴな現場たち |