| 特集:生物多様性と鹿島の取組み |
| |
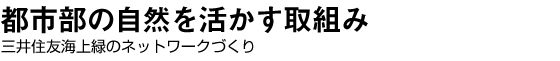
| |
| 大学の高層校舎が目立つ東京・神田駿河台に,ひときわ緑の濃い区画がある。 三井住友海上駿河台ビルである。 20年余にわたって貴重な緑地を維持し,地域の環境改善や景観形成に重要な役割を果たしてきた。そしていま北側隣地で,さらに都心の自然を広げ,活かすプロジェクトが始まっている。 |
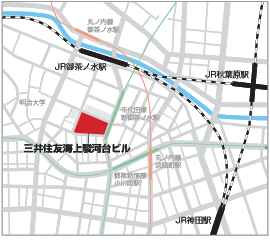 |
| |
地域と共に豊かな自然を 三井住友海上駿河台ビルは,1984年に当時の大正海上本社ビルとして当社JV施工により竣工した。「地域の人々と共に栄える」「地域の付加価値を上げよう」とのコンセプトのもとに建設された25階建のビルである。当時はまだ環境保全を意識した建物は少なかったが,建物周辺にヤマモモなどの街路樹を植栽し,低層棟の屋上に2,614m2の庭園を設けるなど,緑地を最大限に活かす敷地計画が施され,当社も協力した。 三井住友海上駿河台ビルは,1984年に当時の大正海上本社ビルとして当社JV施工により竣工した。「地域の人々と共に栄える」「地域の付加価値を上げよう」とのコンセプトのもとに建設された25階建のビルである。当時はまだ環境保全を意識した建物は少なかったが,建物周辺にヤマモモなどの街路樹を植栽し,低層棟の屋上に2,614m2の庭園を設けるなど,緑地を最大限に活かす敷地計画が施され,当社も協力した。街路樹や緑地は歳月と共に豊かになり,2003年に屋上庭園の再整備も行われた。2004年には「屋上緑化・壁面・特殊緑化技術コンクール屋上緑化大賞(環境大臣賞)」を受賞した。2001年に合併して三井住友海上となったのを機に,屋上菜園の無償貸出や市民環境講座,社内での野鳥モニタリング活動など「緑の活用」は拡大。“都市のオアシス”は,地域の高い評価を受けるようになった。 都市再生特別地区を申請 同社はこのほど,隣接地の別館を解体(当社JV施工)して,東京本社の拠点統合を行うことを決定。緑豊かな本館と一体となった敷地計画を目指した。それを強力に推進するのが,地域と一体になった緑環境ネットワークの構築と,公共貢献と建物面積の確保が可能な東京都の都市再生特別地区の申請だった。 「生物多様性の理念を主導する企業として,都心部の動植物の生態系維持に寄与したい。そのためには,皇居や神田明神に連なる緑の繋がりが必要と考えました」と,同社総務部地球環境・社会貢献室の藤野敬文課長専門役はいう。特区申請は,緑地帯を地域全体で捉える新しい考えが評価を受け,認可された。 |
| |
ハヤブサの営巣を目指す 同社の緑地創造には,当社のエコロジカルネットワーク評価技術(これまでの鹿島の取組み参照)も関与している。「この評価技術を通じて,駿河台地域が野鳥ネットワークのコアとなりうる場所だと認識できた」と,同社不動産部の山本聡部長は語る。同社の「MS愛鳥倶楽部」のモニタリング活動も活発で,新館完成後は日本3例目となるハヤブサの営巣を目指したいと関係者の夢は広がる。 同社の緑地創造には,当社のエコロジカルネットワーク評価技術(これまでの鹿島の取組み参照)も関与している。「この評価技術を通じて,駿河台地域が野鳥ネットワークのコアとなりうる場所だと認識できた」と,同社不動産部の山本聡部長は語る。同社の「MS愛鳥倶楽部」のモニタリング活動も活発で,新館完成後は日本3例目となるハヤブサの営巣を目指したいと関係者の夢は広がる。「都市部における生物多様性の観点からすると,ビオトープなどの擬自然を創るよりも,いまある地域の自然を活かすエコロジカルネットワークの考え方の方が先進的なのではないか」と,山本部長は話してくださった。 別館の解体は2009年7月ごろ終わり,超高層ビルの新館完成と緑地再生は2012年夏の予定である。 |
| |

| |
| |
 メディアは,生物多様性の保全に関して,企業にどんな責任と役割を期待しているのか。企業はどう生物多様性と向き合い対処していけばよいのか。 メディアは,生物多様性の保全に関して,企業にどんな責任と役割を期待しているのか。企業はどう生物多様性と向き合い対処していけばよいのか。産経新聞社論説委員・科学部長の長辻象平氏に聞いた。 |
| 「山川草木悉皆成仏(しっかいじょうぶつ)」や「草木国土悉皆成仏」という言葉がある。日本人の間で古くから伝えられてきた仏教思想が息づく生命観,自然観が反映された表現である。 「生物多様性」という生態学用語のエッセンスは,この悉皆成仏という文字で,すべて言い尽くされているのではないか。 生物多様性と言われても,たいていの人は,その何がポイントなのかよくわからない。いろんな生物が生息していることも,確かに多様性の概念だが,その一部にしかすぎない。ひとつの種内に存在する遺伝的なばらつきもまた生物多様性なのだ。 このように,何となくわかっているようで,なかなかつかみ所のないのが生物多様性である。それに引き替え,山川草木悉皆成仏からは,言わんとするところが明確に伝わってくる。自然界の生命は,その階層を超えてすべて平等であるというアピールだ。 生命の本質に差がないのは,ヒトもムシも同じDNAでその設計図が描かれていることで明らかだろう。また,ヒトのDNAにたくわえられた全遺伝情報(ゲノム)の塩基配列にも意味のある部分(遺伝子)と意味のない部分が存在し,しかも意味のない配列の方が圧倒的に多い。一見,不要な部分がなければ成立しないのが生命や生態のシステムに共通する自然界の法則なのだろう。 地球の生物は,40億年に近い時の流れの中で,環境との相互作用を繰り返しながら種分化を進め,豊かな多様性を実現させた。灼熱の原始地球から海と大地が分かれ,大気ができた。分化は地球の営みである。その一環である生物種分化の蓄積を潰したのが20世紀文明だ。19世紀以前は無意識のうちに多様性を維持できたが,21世紀は意識して保たなければならない時代となった。 商業価値のある品種だけを育てる農業は,多様性と衝突しやすいが,建設業も生息地への干渉で多様性を損なう可能性を有している。都市は植生の立場から見ると砂漠の一形態である。世界の都市化は進み,全人口の半分の32億人が都市生活者だ。都市の主要部を占める建築物も不毛の要因になりかねない。 忘れてならないのは,生物多様性は環境と対応しているということだ。その意味で,環境との適合性を尊重する建築の価値体系が必要なのではないだろうか。今の建物はオフィスも住宅も全国画一的である。それどころか地球規模で世界画一的でさえある。 日本列島には四季があり,気候も多様性に富んでいる。単一広大な環境に暮らす大陸の民とは感受性が違う。生物多様性の基本精神を生得的に理解している民族が日本人ではないか。基本を忘れた多様性への対応は,表層的な取組みに終始しやすい。日本の建設業各社には,自然に手を加えながらも多様性を損なうことのない,さらに欲を言えば,それを育む新たな環境技術を構築し,世界に浸透させてもらいたいものである。 |
 産経新聞社論説委員・科学部長 産経新聞社論説委員・科学部長長辻象平氏 ながつじ・しょうへい 京都大学農学部卒。 1974年,産経新聞社入社。 平凡社アニマ編集部などを経て現在,産経新聞論説委員,科学部長,中央環境審議会臨時委員,作家。 著書に『江戸の釣り』(平凡社新書)『闇の釣人』(講談社)などがある。 |
| |
| |
|
| |
| ■ これまでの鹿島の取組み ■ 地域の生態系保全に貢献する ■ 社有林を守り育てる取組み ■ 都市部の自然を活かす取組み |