| 特集:技術研究所の60年とこれから |
| |

| |
| 研究者にとって必要な研究の場のあるべき姿を求めること。技術の完成度を高めて研究成果を飛躍させる場とすること。 飛田給での歴史を大切に環境を創造すること。この3つのコンセプトにより飛田給研究センターの再整備が着々と進められている。 |
| |
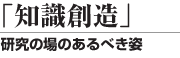 |
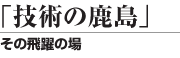 |
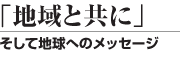 |
||
| 社会からの要望は高度化,多様化,複合化している。これらの動きに対応し,独創的な研究開発を行うには,異分野研究者同士のコラボレーションの必要性が増している。研究者個々の保有している知識やアイディアが共有され,これらが有機的なつながりを持つことで,研究者の発想,解決手段の引き出しが増える。これが研究者集団の潜在能力を高めることになる。 これらの背景から,当センターのリニューアルに際して,個々の研究者が思索をめぐらし,分野の異なる研究者たちが企画などを呼び水に交流する空間(新実験棟「ナレッジストリート」)を設けるなど,アイディア創出の一助となる工夫を随所に凝らしている。また,ICTを初めとした先端技術,社会ニーズの変化はスピードアップしており,これらに柔軟に対応できる可変性を有する「次世代ワークプレイス」を目指した建築空間としている。 |
当センターでは,当社の保有する研究開発成果を選んで,当センター建物に適用し,継続的に実構造物での実験を行う。 研究・技術開発で生み出された技術は,実際の建物や構造物に使われて初めて本来の成果が得られると考えているからである。つまり,当センターは「技術のブラッシュアップの場」としての機能も果たしている。そのため,今回,完成した新実験棟にも10数件の開発成果を適用し,より完成度の高い,顧客が満足できる技術の提供を目指している。 実証実験をその場で体験共有する,いわば「実験スタジアム」である。 (適用技術についてはChapter 4を参照) |
「地域や環境との共生による快適環境の創造」も,当センターの大事なテーマの一つ。飛田給に技術研究所が移転してきて約半世紀,その歴史を受け継ぎ,さらに大きな実りを得ていかなければならない。 当社は,武蔵野の森,多摩川などの周辺の自然環境との調和,共生を視野に入れ,快適環境の創造を目指す。そのため,新実験棟では屋上緑化や環境分野の研究設備・機器を多く配置し,最先端のテクノロジーを開発する。 また,自然環境との共生を図るだけでなく,地域コミュニティと共に歩んでいく必要がある。そのため,近隣小学校など各種団体の見学会開催,地元への一部施設の提供など,これまで以上に地域社会との交流の機会を広げていく。 |
| |
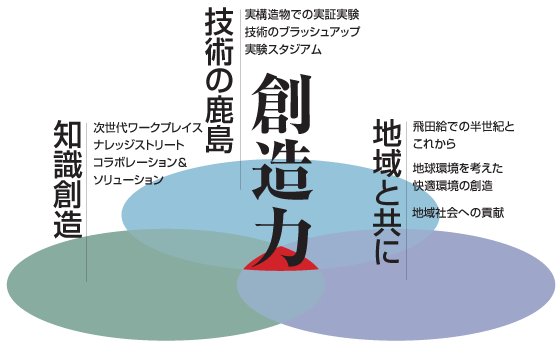 |
| |
|
| |
| ■ Chapter
1 技研のこれまで ■ Chapter 2 技研のいま ■ Chapter 3 技研のこれから ■ Chapter 4 これからの知識創造型ワークプレイス 新実験棟 技術ガイド ■ Chapter 5 これからの「知識創造」の担い手たち |