| 特集:いよいよ始まるW杯サッカー |
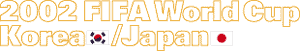 静岡スタジアム・エコパ
|
|
||||||||||||||||||
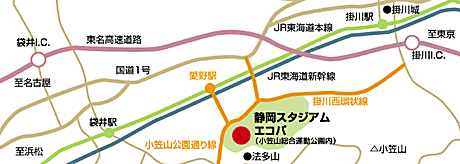 |
| 可動席で国際大会にも対応 静岡県の小笠山北西の麓に広がる小笠山運動公園。自然に囲まれた緑豊かな約269haの敷地に,自然と触れ合うことができる野鳥の森や様々なスポーツ施設が配置されている。小笠山運動公園エコパは,この中核施設として位置付けられている。エコパの愛称は,「エコー・歓声のこだま」と「エコロジー・環境」を意味する“エコ”と,「パル・仲間」「パーク・公園」の“パ”を合わせた合成語である。公募の中から選出された。 エコパは,埼玉スタジアムを除く他のスタジアムと同様に総合競技場として建設された。ピッチ外周には,9レーン1周400mの陸上用トラックが走っており,国際大会の開催も可能な第1種公認陸上競技場でもある。しかしW杯の際には,サッカー観戦スタジアムとしてフィールドのスタンド壁面から機械式の可動席が出現する。スタンド内に収容された7列5,236席はフィールド上をトラック近くまで移動し,スタンド固定席と一体となる。その結果,スタジアム全体で収容人数は46,113人から51,349人に増加し,日本のW杯スタジアムの中でも埼玉スタジアムに次ぎ3番目の規模となる。 デザインと施工性を追及した鉄骨トラス エコパのコンセプトは,最先端のテクノロジーと豊かな自然が織りなす新たな風景の創出。外観のデザインは,周辺の環境に完全に調和している。なだらかな曲線を描いた膜屋根は山並みのウェーブを表し,ふわっとした雲を感じさせる。外周をとりまく無数のY字型の柱は木々をイメージし,周囲の木立に融合したデザインとなっている。 このスタジアムの思想は,設計と施工の共同作業により見事に具現化された。設計者の一人である斎藤公男・日本大学教授の指導のもと,スタジアムの施工が始まってからも議論を繰り返し,デザインのディテールや施工性をも追及した。特に屋根のフォルムをかたちづくる鉄骨トラスは,スタジアムのイメージを左右する重要なものでもあり,画期的な施工方法が検討された。 屋根を支える鉄骨トラス一つの大きさは,長さ50m,重さ70t。スタンドへの取付は,クレーンによる一本吊りで足場をまったく使わないため,工期を大幅に短縮できる合理的な施工法が考案された。通常,スタジアムの大屋根は,建設途中,仮設の支え(ベント)を設置しなければならない。エコパでは,それぞれ完全に独立した鉄骨トラスが,各々で膜屋根を支える構造としたためベントが不要となった。 鉄骨トラスの製作は,現場内の製作ヤードで進められた。完成したトラスは,スタンド外側からクレーンで吊り上げ,スタンド最上部に設置された。スタンドへの接合は,備え付けられた台座に載せ,後は後方に垂れたバックステーケーブルをスタンド外周部のY字柱に固定させるだけという簡単なものだった。そのため,クレーンの吊り上げから取付け終了まで費やした時間は2時間程だった。 こうして,ピッチ側にクレーンを据え付けることもなく,ピッチ工事にも早く着手することができた。また,鉄骨トラス組立ての際,安全ロープや必要な昇降階段などの設備もあらかじめ取り付けておいたことで,安全性の向上にも大きく寄与できた。 |
 |
 |
|
| 可動席はスタンド内部に収納されている | ||
 客席上空に張り出した鉄骨トラスの長さは50m。 スタンド上部の台座に設置されている |
 |
 |
|
| 地上部で組立て,クレーンで吊り上げる | ||
 スタンドへの設置は台座に載せるだけと非常に簡単(上) 鉄骨トラス後方から出たケーブルはY字型の柱に固定されている(右) |
 |
| 工事概要 場所:静岡県袋井市 発注者:静岡県 設計:佐藤総合・斎藤公男 建築面積:30,875m2 延べ床面積:81,200m2 収容人数:51,349人(可動席含む) 工期:1998年3月〜2001年3月(横浜支店JV,他JV施工) |
|
|FIFAワールドカップの全貌 |宮城スタジアム |埼玉スタジアム2002 |新潟スタジアム・ビックスワン |静岡スタジアム・エコパ |
