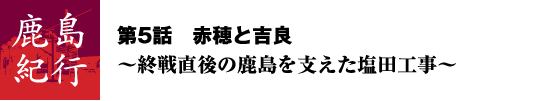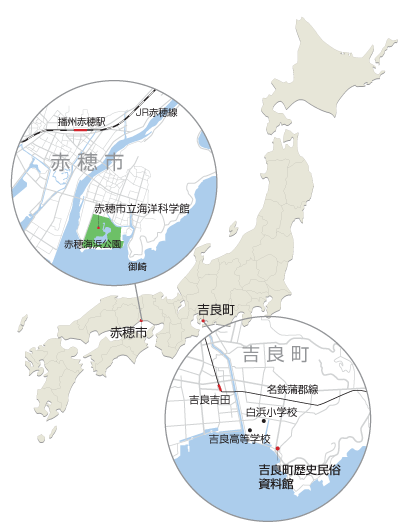| 「土木屋はアイデアが出ないと務まりません。現場では作業に最適な工具や機械を自ら考え,作り出すのです。土木の原点を学び,実践できた現場でした」。小島さんは,粘土相手の2年間をそう振り返るのである。1990年に退職。いまは京都府八幡市に住む。
白浜吉田塩田は1972年に廃止された。いま本浜や白浜には高校や住宅が建ち並び,当時の面影はない。白浜の近くの吉良町歴史民俗資料館には,入浜式塩田や塩焼小屋が復元され,当時の塩作りの様子を伝えている。
一方,播州塩業が造成した赤穂西浜塩業組合の塩田跡は,発電所施設や工業団地などに変わり,一部が塩業組合を引き継いだ製塩会社の工場になっている。イオン交換膜による製塩法の採用で塩田は姿を消した。工場近くの道路脇に「西浜塩田三ツ樋浜一番跡」と刻まれた石柱があった。赤穂市御崎の市立海洋科学館の「塩の国」コーナーには塩田が復元され,塩が来園者に配布されている。
赤穂と吉良は江戸期から製塩が盛んだった。赤穂浅野家と吉良家とは製塩で競合関係にあり,これが忠臣蔵で知られる赤穂事件の遠因になったという話もある。吉良が赤穂に産業スパイを放って技法を探らせたが,捕らわれて処刑され,そうした確執が対立を生んだ,という筋立てだ。
しかし製塩技法は地形などによって異なり,技法自体も難しいものではないため,塩業史の研究者たちもスパイ説の根拠はないという。吉良町教育委員会学芸員の三田敦司さんは「塩田地主による大規模な製塩業を営んでいた赤穂に比べて,吉良は個人経営による小規模なもの。販売方法も目的も全く違っており,スパイなど考えも及ばなかったと思います。吉良上野介義央公は領民の信頼も厚い名君で,いまも地元民の誇りです」と話してくれた。
三田さんによると,白浜吉田の塩田復興には当時最先端の赤穂の製塩技術が採り入れられたという。「鹿島さんの赤穂での実績を知って,工事をお願いしたのかもしれませんね」。
赤穂とは,赤穂義士ゆかりの自治体が毎年開催する「忠臣蔵サミット」や,吉良町の「きらまつり」と赤穂市の「赤穂義士祭」の物産展の相互乗入れなどで,友好を深めているそうだ。
|