| 特集:21世紀の社会資本整備 |
| Chapter0 これからの社会資本整備 |
| 社会資本を取り巻く環境の変化 戦後,高度経済成長の時代を経て,今日までわが国に整備・蓄積されてきた道路やダム,橋などの社会資本――。その基本的な役割は,安全で快適な社会基盤を築くとともに,それを可能とする公共投資は,建設事業を通じて「人」 や「もの」を移動させ,消費の拡大を促してきた。こうした効果は,日本の経済成長のサイクルに組み込まれ,世界第二位の経済大国へと押し上げる原動力ともなった。 今日の日本は,先進国としての成熟期を迎え,緩やかで継続的な成長を目指すべき時代を迎えている。増え続ける国家財政の赤字もあって,今後は,予算の抑制などにより,公共投資が長期にわたり減少方向に推移することも避けられない。このため,今までの経済成長を支えてきたシステムや社会構造の改革を図り,限られた公共投資によって,いかに効率よく社会資本を整備するかが,喫緊の課題となっている。 また,高度経済成長の初期に整備された橋やダムなどの土木構造物は,リニューアルや更新の時期を迎えようとしている。さらに,地球環境の保全もますます重要な命題となっており,環境に配慮した社会資本整備のあり方を一層考えなければならない。 こうした経済・社会の成熟や,環境との共生という多様な観点から,社会資本を取り巻く状況は,大きな変革の時期を迎えているのである。 |
|
キーワードは,「民間活力」「維持・保全」「都市再生」「環境」 このような状況において,建設業の担う役割も多様化してきている。 その中でも,社会資本整備に伴う建設事業では,コストの縮減が最大の課題であることは論をまたない。従来,公的機関が果たしてきた役割にも民間の技術力やノウハウを導入し,さらなる合理化・効率化を図る取組みも始まっている。 また,耐用年数を経過した構造物に対しては,補修・補強等のリニューアル技術だけでなく,ライフサイクルコスト(LCC)に基づいたメンテナンスの最適化を図る,マネジメントシステムなどのライフサイクルエンジニアリング(LCE) が注目されている。 さらに,効率的な社会資本の整備という観点からは,日本経済を牽引する役割を担う都市部への集中的な整備を図る,「都市再生」が重要視されている。これまでの社会資本整備で蓄積されてきた建設技術は,都市部での開発にも大いなる力を発揮するであろう。 それでは,これからの21世紀の社会資本の整備がどのような方向性をもって進められていくのかを,(1)民間の力を活用した新しい発注方法,(2)使い継ぐ社会資本の維持・管理・機能向上,(3)都市再生の基盤となる集中的・効率的整備,(4)環境共生型社会への対応,の4つの視点から,当社が手がけている工事や技術開発の事例を通じて,見ていきたい。 |
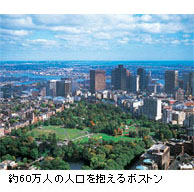
−ボストン・ビッグディッグプロジェクト 学問と芸術の街として知られているアメリカ・マサチューセッツ州のボストン。都市環境と都市機能の抜本的な改善を目指した「ビッグディッグ」と呼ばれるプロジェクトが進行中である。街の中心部を通る高速道路は,建設から50年以上が経過し老朽化が進み,朝夕の交通渋滞は周辺の環境を悪化させ,街の機能も分断していた。このプロジェクトでは,高速道路を約14kmにわたって地下化し,その跡地に市民の憩いの場となる公園を整備するものである。  巨大な穴掘りを行うことから,”ビッグディッグ(Big Dig)”というニックネームが付けられた。事業費の約70%が連邦政府などから拠出されており,こうした取組みは長期的なビジョンを持った都市計画から実現できるものである。今後の日本の社会資本整備のあり方に−つの方向性を示してくれる事例であるといえよう。
巨大な穴掘りを行うことから,”ビッグディッグ(Big Dig)”というニックネームが付けられた。事業費の約70%が連邦政府などから拠出されており,こうした取組みは長期的なビジョンを持った都市計画から実現できるものである。今後の日本の社会資本整備のあり方に−つの方向性を示してくれる事例であるといえよう。 |
|Chapter0 これからの社会資本整備 |Chapter1 民間の力を活用した社会資本整備 |Chapter2 次代に使い継ぐ社会資本 |Chapter3 「都市再生」を促す社会資本 |Chapter4 環境と共生する社会資本 |