| 特集:生物多様性と鹿島の取組み |
 |
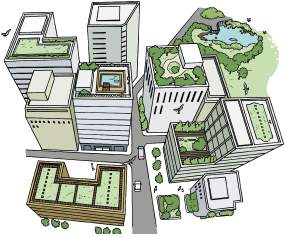 地球環境保全への関心が高まる中,キーワードとして使われている言葉に「生物多様性(biodiversity)」がある。 地球環境保全への関心が高まる中,キーワードとして使われている言葉に「生物多様性(biodiversity)」がある。人間は,衣食住を他のいのちに依存して生きている。生物多様性の問題は,多様な生物の保全保護を通して,人間が他のいのちと共生しながら,自らがどのように生き延びるかという問題でもある。 それは企業も同じである。いかに生物多様性と向き合い対処していくか。 すべての企業に課せられた命題になっている。 当社はいち早く2005年に「鹿島生態系保全行動指針」を制定し,生態系と建設事業の共生に向けた活動を行ってきた。 今年4月に「企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)」の設立メンバーに加わったほか,5月にはドイツで開催された「生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)」で,企業が生物多様性の保全に積極的に取り組むことを目標にした「ビジネスと生物多様性イニシアティブ」のリーダーシップ宣言に署名した。 当社は生物多様性の減少を地球環境への警鐘と捉え,これまで以上に生物多様性保全の貢献活動を進めていく。 |
| |
| 今年2月の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)報告」によると,CO2など人間活動による温暖化ガスの排出により,21世紀末の地球の平均気温は20世紀末比で最大6.4度上昇するという。その結果最大59cm海面が上昇。大気中の残留CO2が増えて更に温暖化が進む「負の連鎖」が起きると警鐘を鳴らした。 気温の上昇率は高緯度ほど大きく,北極海で夏に氷が消滅する可能性があり,ホッキョクグマの生態などにも悪影響を及ぼすという。既に生き物異変や温暖化の足音は,サンゴ礁の消失や蝶の北進化,世界各地を襲う豪雨や猛暑など様々な方面で忍び寄っている。生物多様性の宝庫・原生林の環境破壊も進んでいる。 |
| |
 生物多様性の保全は,地球温暖化防止と並んで21世紀の人類に課せられた大きな課題といえます。国連では2001年から5年間,世界1300人の専門家を集め,地球全体の生態系に関する総合的評価を実施しました。その報告では淡水や森林資源の提供,災害制御,遺伝資源など生態系がもたらしてくれる多くの便益が,この半世紀に人為的理由により悪化したこと,生物の絶滅速度が高まっていること等が指摘されました。日本でも2002年に「新・生物多様性国家戦略」が策定され,生物多様性・生態系保全が社会共通の認識になっています。 生物多様性の保全は,地球温暖化防止と並んで21世紀の人類に課せられた大きな課題といえます。国連では2001年から5年間,世界1300人の専門家を集め,地球全体の生態系に関する総合的評価を実施しました。その報告では淡水や森林資源の提供,災害制御,遺伝資源など生態系がもたらしてくれる多くの便益が,この半世紀に人為的理由により悪化したこと,生物の絶滅速度が高まっていること等が指摘されました。日本でも2002年に「新・生物多様性国家戦略」が策定され,生物多様性・生態系保全が社会共通の認識になっています。都市で生活していると生物多様性の価値はなかなか実感できません。中学校の理科で学んだ「光合成」,申すまでもなく,植物が外界からCO2(二酸化炭素)と水を取り入れて,太陽エネルギーにより有機物を作り出す生態系の営み,この繰り返し循環してきた自然の営みを前提として,人間の営みが成り立っていることを思い起こす必要があります。このことから,自然との共生に基づく持続可能な社会の形成が,21世紀に生きる私たちの最大の課題になっていると思っています。 社会基盤を構築する建設業は,自然界に直接手を加え生態系に影響を与えることになります。そのため鹿島は業界に先駆けて「鹿島生態系保全行動指針」を策定,生物多様性と自らの建設事業の共生に向けた活動を行ってきました。さらに,長年蓄積した生態系保全技術を顧客や地域・社会に積極的に提案し,建設事業を通じて良好な生態系の保全・創出に役立つことを目指しています。 |
| |
|
| |
| ■ これまでの鹿島の取組み ■ 地域の生態系保全に貢献する ■ 社有林を守り育てる取組み ■ 都市部の自然を活かす取組み |