 |
 |
 
| ●耐震設計基準は地震被害を教訓に見直されてきました。 |
| 年代 |
地震
(マグニチュード) |
死者・
行方不明者数 |
全壊棟数 |
耐震設計基準の変遷 |
| 1891.10.28 |
濃尾地震 |
M8.0 |
7,273 |
14万余 |
|
| 1923.09.01 |
関東大地震 |
M7.9 |
10万5千余 |
10万9千余 |
| 1946.12.21 |
南海地震 |
M8.0 |
1,330 |
11,591 |
| 1948.06.28 |
福井地震 |
M7.1 |
3,769 |
36,184 |
| 1964.06.16 |
新潟地震 |
M7.5 |
26 |
1,960 |
| 1968.05.16 |
十勝沖地震 |
M7.9 |
52 |
673 |
| 1978.06.12 |
宮城県沖地震 |
M7.4 |
28 |
1,183 |
| 1983.05.26 |
日本海中部地震 |
M7.7 |
104 |
934 |
| 1995.01.17 |
兵庫県南部地震 |
M7.3 |
6,436 |
104,906 |
| 2000.10.06 |
鳥取県西部地震 |
M7.3 |
0 |
435 |
| 2001.03.24 |
芸予地震 |
M6.7 |
2 |
70 |
| 2003.09.26 |
十勝沖地震 |
M8.0 |
2 |
116 |
| 2004.10.23 |
新潟県中越地震 |
M6.8 |
49 |
3,185 |
| 2005.03.20 |
福岡県
西方沖地震 |
M7.0 |
1 |
133 |
| 2007.03.25 |
能登半島地震 |
M6.9 |
1 |
686 |
|
| 2007.07.16 |
新潟県
中越沖地震 |
M6.8 |
15 |
1331 |
|
| 2008.06.14 |
岩手県・宮城
内陸地震 |
M7.2 |
23 |
30 |
|
| 2011.03.11 |
東北地方
太平洋沖地震 |
M9.0 |
21,613 |
127,291 |
|
|
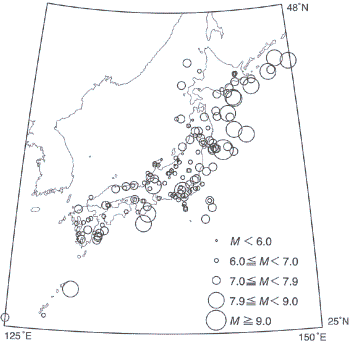 |
| 出典: 理科年表 平成27年版 |
| 日本付近の主な被害地震の震央(1885年以降) |
|
 |
福井地震(1948)
〔柱・壁が少ない建物の崩壊〕 |
|
 |
新潟地震(1964)
〔液状化現象による倒壊〕 |
|
 |
十勝沖地震(1968)
〔短柱のせん断破壊〕 |
|
 |
宮城県沖地震(1978)
〔ピロティ部分の崩壊〕 |
|
| ●阪神・淡路大震災においても多くの建築物が被害を受けました。 |
| ■ |
被害は、1980年(昭和55年)以前の建物に集中しました。 |
|
 |
■ |
ピロティ形式の1階の破壊が、顕著に見られました。 |
|
 |
■ |
鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造の建物では、中間層で破壊した例が多数ありました。 |
|
 |
■ |
鉄骨造建物では、柱と梁の溶接部や柱脚での破断が目立ちました。 |
|
 |
 |
| 柱のせん断破壊 |
|
|
 |
| ピロティ柱頭の崩壊 |
|
|
 |
| 短柱のせん断破壊 |
|
 |
| 1、2階の崩壊 |
|
|
 |
| 中間層(6階)の崩壊 |
|
|
 |
中間層崩壊に伴う
渡り廊下の落下 |
|
 |
| 鉄骨造フレームの大変形 |
|
|
 |
| 鉄骨造柱・梁接合部の破断 |
|
|
 |
| 鉄骨造柱脚の破壊 |
|
| 参考文献 |
| |
| 鹿島都市防災研究会 |
|
都市・建築防災シリーズ2 建築物の地震被害 |
| 文部科学省国立天文台 |
|
理科年表 平成27年版 |
|
|
|
|