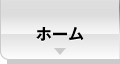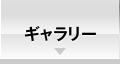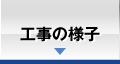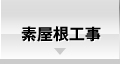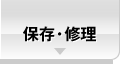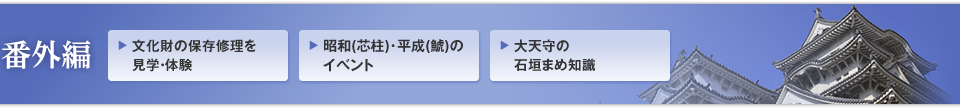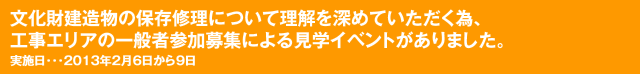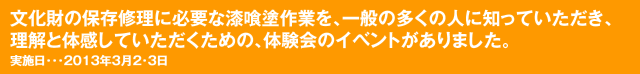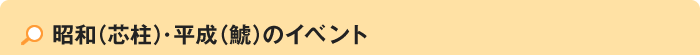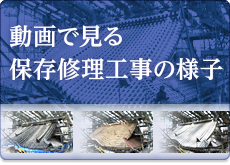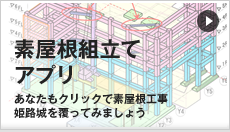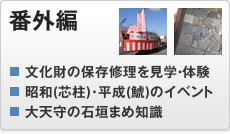五重の屋根保存修理完了状況を身近での見学会が、4日間で2000人規模で実施されました。

五重の屋根(素屋根の8階)完成状況を、今しか見れない鳥目線の見学会です。

現在、城の漆喰塗作業を行っている左官職人の指導による、丸瓦の目地漆喰塗の体験会です。

お遊びで、城の型に漆喰を塗り込み、本漆喰でお城の絵を描いたものを、おみあげとして作成しながら、親しんでいます。

棟込瓦部(屋根の頂部)のモックアップに、左官職人による実践作業として、目地漆喰中塗を行っています。

五重屋根(最上部)の大棟の鯱瓦を新調しました。祝曳き前に素屋根8階の据付場所にて鯱瓦の清祓いを行いました。

鯱瓦の祝曳きのために先導用の宝船がこちらです。

鯱瓦の祝曳き用レプリカの子供用祝い神輿も用意されました。

鯱瓦の祝曳き前のお披露目除幕式です。ようやくみなさんにお披露目することができました。

宝船の先導による祝曳きです。

武者行列の甲冑隊も参加されました。

御幸通り商店街を市民参加による、平成の鯱の祝曳き
姫路駅前(昔の外堀近辺)を出発する様子です。

大手前通りを市民参加による、昭和の大柱(芯柱)の祝曳き
姫路駅前(昔の外堀近辺)を出発

奈良県で製作した鯱二尾が国道2号線(昔の中堀)を越えて本丸へ移動しています。

岐阜県木曽の山奥より調達した芯柱が国道2号線(昔の中堀)を越えて本丸ヘ移動

姫路市民参加の子供達による祝太鼓も披露されました。

姫路市民参加の子供による祝太鼓

大手門入城、いざ本丸ヘ!

大手門入城、いざ本丸ヘ!

鯱の壮絶で崇高な姿、重さ330kg、高さ1.86m
(奈良の瓦工場にて奈良と姫路の鬼師による共同製作)

今まで350年支えてきた柱と入替の重厚な芯柱
(約1m角柱に加工)

本丸ヘ行く前に、三の丸広場にて、素屋根をバックに一般市民ヘお披露目しました。

本丸ヘ行く前に、三の丸広場にて、素屋根をバックに化粧直し待ち (四角型の柱に加工)
大天守の石垣積みは、池田輝政による築造時の物ですが、
姫路城には、各時代の各種の積み方の石積が残っています。

池田輝政時代の1601年からの築造による大天守の石垣積みです。 (修理工事前の大天守南面)

大天守の隅角部の算木積みの写真ですが、扇型の勾配で反り返った美しい曲線が見れます。 (南東の角)

石垣積み
城郭の石垣の石積み技法は、歴史を重ねるごとに高度化してきました。
時代時代に用いられた石積みの技法を紹介します。

野面積(のづらつみ)
<羽柴時代>
戦国時代の城に見られる自然石に手を加えずに積む技法

打込接ぎ(うちこみはぎ)
<池田時代>
江戸時代など、石同士の面に手を加え接点を増やして積む技法

切込接ぎ(きりこみはぎ)
<本多時代>
石を完全に加工して密着させ隙間なく積む技法