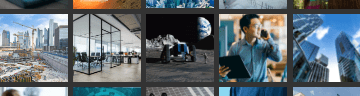田中
河内川橋工事は日本最大級のアーチスパンを誇るバランスドアーチを建設する工事です。全社から橋梁工事に知見のある技術者が設計・施工に参画していますが、誰もが「非常に難しい」と口にしています。

平山
私は設計担当という立場で2019年にこの現場に来ました。詳細設計は2016年から行われています。発注段階での基本設計をもとに、施工面や工程面での課題を2~3年かけて洗い出し、施工中から完成して橋梁が供用されるまでのすべての段階での構造設計・細部設計を実施し、その詳細図面を作成するのに3~4年かかりました。そして2024年にようやくすべての図面が整いました。
通常の橋梁の設計では図面枚数は多くても500~600枚というところですが、河内川橋では約4,600枚もの図面を作成しました。また、鋼とコンクリートの複合構造でしたので、鋼橋会社をはじめとする社外の設計協力会社の力を借りて設計を進めました。

柑本
本当に長いプロジェクトになりました。私は施工担当として2016年からこのプロジェクトに参加し、途中2019年から2年半ほどプロジェクトを離れています。2019年の時点ではまだ本設構造物が何一つ出来上がっていない状態で、施工ヤードまで資材等を運搬するインクラインや工事用トンネルなどの仮設工事の最中でした。

横山
とにかく新しいことへの挑戦の連続でした。例えば、アーチを支える橋脚では、工場で製作したプレキャスト埋設型枠を帯鉄筋とともに高さ90cmのプレファブユニットとして組み立て、これをタワークレーンで4段ずつ積み上げる方法を採用しました。これによって従来工法の約2倍のペースで施工が可能になりました。新東名高速道路の早期の全線開通に向け、こうした施工の合理化は重要なテーマでした。

平山
プレキャスト化やプレファブ化は重要な課題でした。事前に工場で作れるものは作っておき、現場でそれが所定の位置に設置できるよう、調整方法やバッファの確保にはとても気を使いました。社内の施工経験者と協力し、実施工をシミュレーションしながら、どの程度のバッファが必要かなどを考えて設計を進めました。そして実施工の段階では、設計担当者と施工担当者が同じ事務所で机を並べ、意見を交わしながら、最終調整方法やバッファの使い方を決めました。

柑本
設計担当者がこれほど深く施工に関与するのは、異例のことですよね。それだけでも特別なプロジェクトだと感じています。

平山
設計担当者が本社の設計部署で設計を終わらせた上で、施工担当者の立場として現場に赴任することはよくあります。しかしこのプロジェクトでは、設計が完了する前に施工が始まっており、施工のスケジュールに追われながら現場で図面を書いていくような状況のときもありました。施工を止めないために施工担当者と調整しながら設計を進めていったわけです。施工担当者から変更要請が来ると1ヵ所では済まず、同じ様な全ての箇所を書き直さなくてはならないこともありました。さらに、施工中の橋の形状を計算値と実測値とを比較して管理する作業については、現場に居なければ難しかったと思います。

柑本
アーチ部構築の大ブロック化も施工の合理化に寄与しました。基本設計ではアーチは橋脚を中心に片側23ブロックに分割して構築する計画でしたが、1つのブロックを長くして16ブロックに減らしたわけです。それによってアーチを構築する回数を7回減らし、移動作業車が移動する回数やコンクリートを打設する回数も7回減らすことができました。

平山
とはいえ、ブロックを長くすること自体、簡単ではありませんでした。設計も一からやり直す必要がありました。構造設計には主要な施工用機械の重量が不可欠なため、横山さんをはじめとする機電チームに相談して重量を検討していただき、その数字をもとに設計し直しました。そういった一つひとつの積み重ねが、合理化に結びついたと思います。

田中
アーチ部材が張り出し終わった箇所から、張り出した部材を連結する作業を進めています。この閉合部の施工についても河内川橋特有の施工条件があるので、毎週、確認の機会を設け、施工計画を複数の目でチェックしてから施工に着手しています。そうしないと大きなトラブルになりかねません。今までにないものを造っているので、河内川橋での取り組みの一つひとつが今後につながるノウハウを生み出していくと考えています。

横山
田中所長の言うように、今までにやったことがないというのが最大の魅力であり、難しさであるのは間違いありません。私はこれまで橋梁工事を3現場経験しましたが、この現場では初めて経験することばかりです。
例えば通常のコンクリート橋では平らな面に移動作業車を組み立てて、作業が終わったら解体して次の作業場所へと移動させます。ところが河内川橋は移動作業車を組み立てるアーチの最大傾斜が38度もあるので、組み立てるには傾斜の影響も考慮しなければなりません。どんな難工事でも大体は似たような前例があるもので、その時のデータを見たり、社内の経験者に聞いたりということができるのですが、今回はそうした前例はあるものの、経験者が退職していたり、記録が不足している部分もあり、移動作業車のメーカーの協力も得て、慎重に検討を進めていきました。

田中
資材の運搬ルートにも苦労しました。

横山
通常は現場に資材を運び込むために工事用道路を造るのですが、この現場は急峻な谷間にあって傾斜が大きすぎるため、斜面に沿った工事用道路を造ることができません。そこで、左岸には斜面を斜めに昇降する“巨大エレベーター”のインクラインを設置しました。また、右岸では山の裏側から斜面に到達するトンネルを掘削し、工事用道路として利用しています。一方、鋼・コンクリート複合橋なので、大型の鋼部材など、通常のコンクリート橋工事に比べると重量物が多いのも特徴です。そこで大規模建築工事等で使用する大型のタワークレーンを配置しています。

柑本
さきほど横山さんが話したように、未経験の工事であるということが一番のハードルであったのは間違いありません。私も横山さんと同じく、通常の橋梁工事の経験はあるものの、ここでは見たことがない材料や経験したことのない施工方法などへの挑戦の連続でした。その際は協力会社と協力し、トライ&エラーを繰り返しながら進めていくしかありません。お互いに知恵を出し合い、結果をフィードバックして、またチャレンジするという繰り返しです。その意味ではとてつもなく手間と時間がかかりましたが、未知の領域に挑んでいる醍醐味は大きかったです。