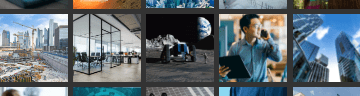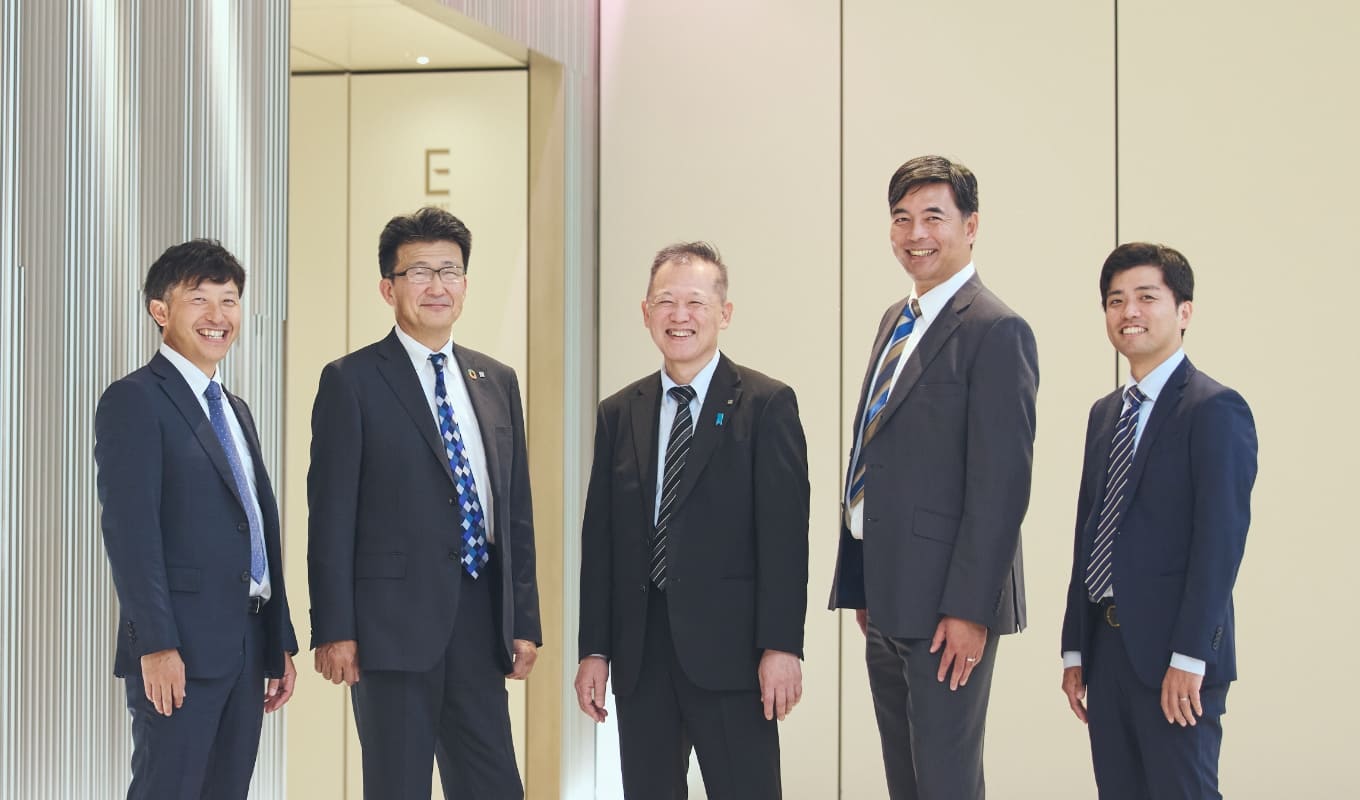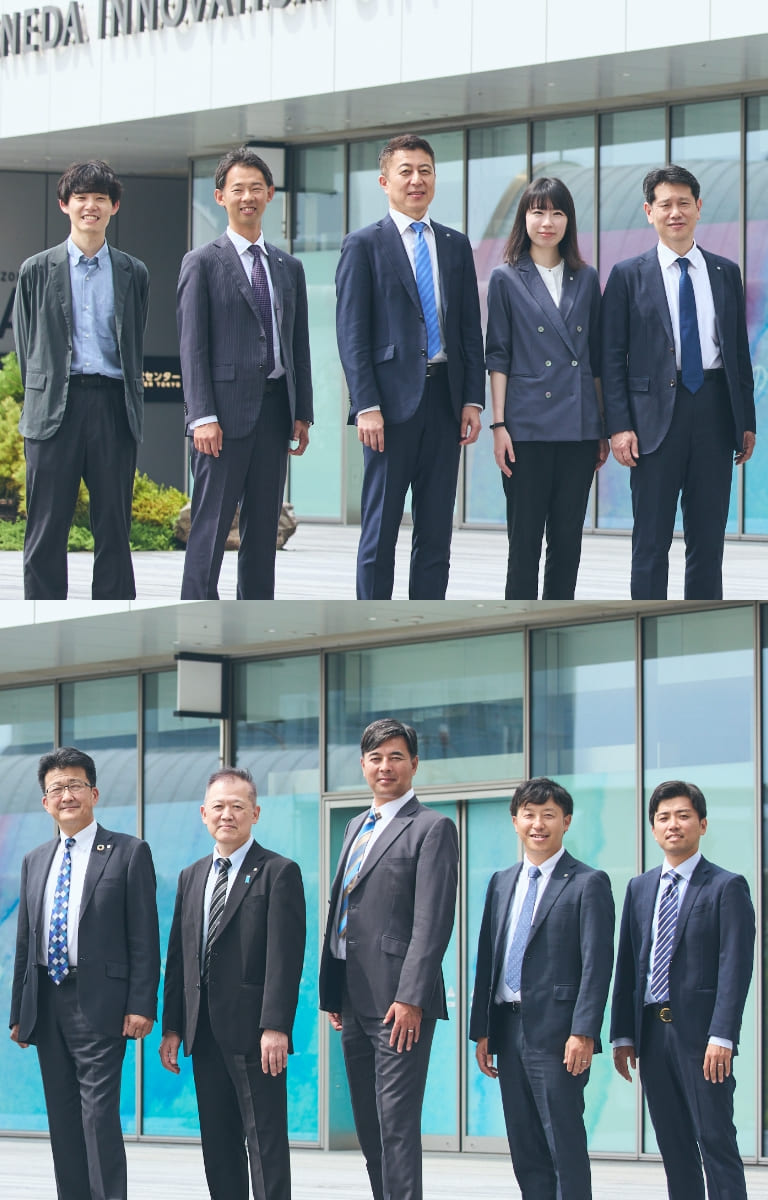加藤
羽田空港跡地について、大田区が新産業創造・発信拠点の形成を目指して官民連携で開発を進める、延床13万㎡を超える大規模開発プロジェクトです。その土地利用コンペで、鹿島が代表企業を務めるコンソーシアム「羽田みらい開発株式会社」が当選したことから始まりました。

谷口
ドラマ『下町ロケット』に描かれたように、大田区は全国有数の中小企業集積地として知られ、高い技術力を誇る町工場が多数軒を連ねています。一方で生産年齢人口の減少や後継者不足などが深刻化しています。こうした中で大田区は持続可能な都市の創造を目指し、先端産業と文化産業の拠点をつくるという大規模開発案件でした。

長井
コンペで我々が選ばれた背景には、鹿島ならではの高い提案力が評価されたと自負しています。羽田の地と縁深く、建設事業を通じて関係を構築している企業の方々とコンソーシアムを組成できたことなどが当選につながったと思っています。例えば、京浜急行電鉄様や東京モノレール様などに構成員として加わっていただけたことで、天空橋駅改札との直結を実現できたことも、大きな要因だったと思います。

加藤
また、医療系施設を入れることで、世界最高水準の医療技術を地域産業との協働開発で推し進めていく医工連携の実現も、鹿島ならではの提案でした。

大橋
私が今でも思い出すのは初めてこの土地を見たときのことです。見渡す限り何もない広大な更地で、本当にここに街ができるのかなと思ったものでした。そんな中、先端産業と文化産業の拠点というコンセプトでゼロから街づくりを行ったというのは、鹿島としてもレアなプロジェクトだと思います。鹿島ならではの構想力が十分に活かされたと思います。

加藤
もともとこの場所は羽田江戸見町・羽田穴守町・羽田鈴木町という3つの町が存在していました。第2次世界大戦終了後、GHQがこの土地を空港として使用することを決定し、住民約3,000人が48時間以内に自分の土地を明け渡すよう、命じられました。80年近く経った今でも、当時の住民の子孫の方が近隣には多数暮らしていらっしゃいます。更地とはいえ、本来は自分たちの祖先の土地だったという思いが皆さんの心に残っており、その配慮も我々にとって大きな課題でした。

長井
そこで加藤さんを中心に開発メンバーは近隣の町会を訪ね歩き、皆さんの想いに耳を傾けました。お話を聞くと、やはりこのエリアに対する皆さんの思い入れは非常に強く、そうした声一つひとつを丁寧にうかがった上で、開発計画に反映させていくことが重要だと感じました。

加藤
この土地の歴史について我々がどう認識しているのかを問われることもありましたし、町会の皆さんと膝詰めで話し合うことで地元に賛同される計画を進められたことは、我々にとっても大きな財産になりました。このプロジェクトに限らず、住民の皆さんと真摯に向き合うことは絶対に必要です。開発と聞くと華やかなものづくりのイメージが強いですが、一方でこうした地道な取り組みも重要であり、それも開発ならではの醍醐味であることを、学生の皆さんにはぜひ知っていただきたいと思います。