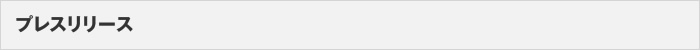[2025/09/02]
611KB
南海トラフ地震「半割れ」を想定した広域連携BCP訓練を実施
生成AIを活用した建物の被災状況判定システムを導入
鹿島(社長:天野裕正)は8月28日に、南海トラフ地震の発生を想定した、広域連携BCP訓練を実施しました。本訓練は南海トラフ震源域の東側を震源とする「半割れ」が発生したとの想定で行いました。具体的には、午前9時に南海トラフの東側(横浜、中部、関西支店の3エリア)で三重県沖を震源とするM8.0、最大震度7の地震が発生し、その後に南海トラフの西側(四国、中国、九州支店の3エリア)に南海トラフ地震臨時情報「巨大地震警戒※1」が発表されるものとしました。
訓練の概要は次のとおりです。
- 大きな被害が予想される横浜・中部・関西の3支店
- 津波や液状化により、交通インフラや通信、電力などのライフラインが停止したと想定し、各事業所や施工中現場の被災状況を把握
- 人的・物的な支援を本社に要請 - 「巨大地震警戒」が発表された想定の四国、中国、九州の3支店
- 避難対象地域に位置する現場や、居住する従業員を把握し、どのように避難指示を出し、どのように事業継続していくかを検討
- 後発地震の発生に備え備蓄品を再点検し、次第に被災エリアの支援に移行していく流れを確認
- 本社に立ち上げた災害対策本部
- 関東、東京土木、東京建築、北陸の4支店と連携して被災エリアの支店に人的・物的資源を支援
- 当社で開発中の「生成AIを活用した建物の被災状況判定システム」を訓練に導入
- 全支店において、当社と緊急時連携協定を締結している主要協力会社が被災した場合を想定し、協
力会社の事業継続のために、当社ができる具体的支援を協力会社と共同で検討
これらの訓練により、後発地震に対する備えを行いつつ、当社の資源を最大限活用して事業を継続し、一日でも早い社会機能の復旧と顧客の支援を目指します。
鹿島は今後も、発生し得る様々な状況を想定した災害対応訓練を実施し、「事業継続力」を強化するとともに、建設会社の使命として社会全体のレジリエンス向上に貢献していきます。
※1 南海トラフ地震の震源域でM8.0以上の地震が発生し、続いて巨大地震が起こる可能性が高まった場合に発表される

災害対策本部会議
主な訓練内容
- 広域での本・支店連携訓練 南海トラフの東側を震源とする「半割れ」地震が発生した場合、東側は地震の揺れによる被害に加え、津波や液状化により、交通インフラや通信、電力などのライフラインが停止し甚大な被害を受けると予測されています。一方、西側では、南海トラフ地震臨時情報「巨大地震警戒」が発出され、後発地震に対する備えを進めなければなりません。そのため、本訓練では、被災が大きい東側の横浜、中部、関西の3支店を受援支店、被害が軽微な本社および東京土木、東京建築、関東、北陸の4支店を支援支店、「巨大地震警戒」が発出された西側の四国、中国、九州の3支店を防災対応支店に分けました。
- 物資輸送訓練 災害により鉄道や主要道路が寸断された際には、一刻も早く現地を調査し、復旧作業を開始することが当社の責務です。そこで当社は、ヘリコプターを活用し、実際に人員・物資の輸送を行う訓練を繰り返し実施しています。今回の訓練では、ヘリコプターで東京都から静岡県へ人員・物資を空輸しました。静岡に到着後、支援物資をヘリコプターから社有車に積み替え、事前に検討したルートで人員・物資を当社の静岡営業所に陸送しました。
- 安否確認訓練 社員・派遣社員および国内グループ会社に所属する約2.7万人を対象とした「従業員安否システム」の登録訓練を、全社一斉に行いました。従業員が復旧活動に従事するため、まず行うべき事項として家族の安否確認を位置づけています。今年7月に発生したカムチャツカ半島地震を踏まえ、本訓練でも地震発生後の津波到来を想定し、時間差で2度にわたって安否を確認する訓練を行いました。加えて社員各自が家族との連絡手段を複数用意していることを確認するとともに、実際に家族と連絡を取った上で、その安否を「従業員安否システム」に登録しました。さらに、家族の職場や学校、自宅など、有事の際の避難場所をそれぞれの自治体のホームページで確認し、各家庭内で共有しました。
- 生成AIを活用した建物の被災状況判定訓練 当社本社ビル(東京都港区)において、当社が開発中の「生成AIを活用した被災状況自動判定システム」にて地震による建物の被災状況を判定する訓練を実施しました。本システムは、地震によって柱や梁等に発生したひび割れを撮影し、それを画像データとして取り込むことで、AIが建物の被災状況を判定するものです。今回は建物に描いた疑似的なひび割れを用いて訓練を実施しました。被災状況判定をさらに迅速に行えるよう、訓練で得られた知見を活かし、本システムを改良していきます。
- 工事現場の初動対応訓練 当社は、工事関係者が安全を確保し、避難するための初動対応を「震災時における現場対応指針」にまとめています。また、火災発生などによる二次災害の防止を目的とした「災害発生時における二次災害防止計画」を定めています。本訓練では、各現場がこれらの初動対応を具体的に整理した上で、改めて「避難場所(集合場所)」を確認、決定しました。また、各現場は「BCP-ComPAS」による想定震度をもとに、被災状況を想定し、これを「災害時現場速報システム」に登録することで、全社共有しました。
地震発生直後は受援支店における通信回線が遮断されている状況を想定し、本社および受援支店はMCA無線※2等を使用して、連絡体制の確立と災害対策本部の立ち上げを行いました。併せて衛星インターネット「スターリンク」を使用した通信接続訓練も実施しました。
その後、社会の通信インフラが次第に回復していく状況を想定し、本社および各支店は各種災害時システムを利用した情報共有や、人的・物的資源の授受を行う訓練を実施しました。具体的には、受援支店は当社独自のリアルタイム災害情報共有システム「BCP-ComPAS®」※3により、各事業所や施工中現場の震度予測を確認するとともに、各現場が「災害時現場速報システム」に入力した被害状況を確認し、対応の優先順位を検討しました。本社災害対策本部および支援支店は、「緊急支援物資管理システム」に入力された支援要請に基づき、支援物資の集積場所や輸送方法・ルートの検討、応援人員が活動するための宿泊場所の確保など現実に即した訓練を行いました。
一方、南海トラフの西側地域に「巨大地震警戒」が発表されたと想定し、四国、中国、九州の3支店は防災対応支店として、どのように事業継続していくのかを検討しました。具体的には、避難対象地域に位置する現場や当該地域に居住する従業員を確認した上で、どのように避難指示を出すのかシミュレーションし、そのフローを確認しました。さらに、後発地震に備えて防災対策の再確認を実施、被災エリアの支援のために派遣できる社員や支援物資の確認・整理を行い、「緊急支援物資管理システム」にて本社・支援支店と連携する訓練を行いました。
※2 過去の大規模災害時に行政機関やインフラ企業で活用された災害に強いとされる無線
※3 BCP-Communication and Performance Assistant System

BCP-ComPASで示した想定震源域と震度マップ

ヘリコプターを活用した物資輸送訓練の様子

訓練用に描画したひび割れ
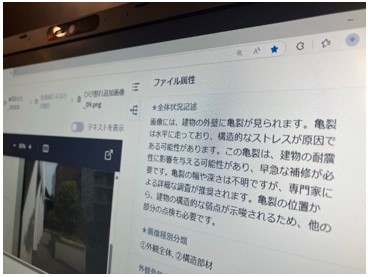
システムが写真から被災状況を自動判定
訓練の最後に行われた災害対策本部会議において、天野社長から次の総括がありました。
「今回の訓練では、南海トラフの“半割れ”を想定しての訓練であったが、季節、天候、発災の時間帯なども含め様々なケースをイメージした上で、本社や支店がどのように連携するのか、社員の各家庭においてはどういう行動をとるべきかといったことを、シミュレーションすることが重要である。また、施工中現場では、施工の段階によって地震に対する危険度も異なるので、注意を要する現場を常に把握しておくことも必要だと考える。教育や訓練を繰り返すことで、非常時の通信機器の使用法、水や食料などの備蓄品の保管場所など、誰もが分かるようにしておかなければならない。訓練で得られたデータやナレッジを一つずつ積み重ね、面的に広げていくことで、事業継続力をさらに強化していただきたい」
プレスリリースに記載された内容(価格、仕様、サービス内容等)は、発表日現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。