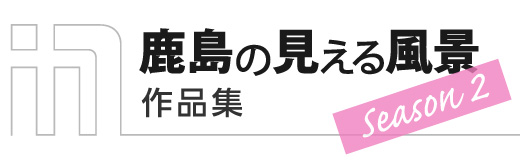素朴で温かみあふれる土鈴
和風造作のミニチュア
各国に,その土地に根ざした固有の建築をかたどったミニチュアの伝統がある。銅や鉄製,各種の金属を用いた鋳物による成形品,プラスチックの製品,陶製,石製など,その材質も造形もさまざまだ。
たとえば土鈴(どれい)などは,他国にない日本独自のミニチュアだろう。ここでは社殿や伽藍,塔などをかたどったもの,民家や町家を表現したもの,祭りの山車を模したものなど,各種の土鈴を紹介しておきたい。
いずれも素朴さと温かみのある,和風趣味の造作である。粘土を素材とした焼き物であるがゆえに,隅や角を曲面としなければいけないといった制約があり,建築物を細部まで精緻に再現することは難しい。だからこそうまく特徴を捉え,デフォルメをする必要がある。
土鈴ならではの遊び方がある。上部に通された紐を持って振り,音を確かめることだ。低くゴロゴロと鳴るものもあれば,高くカタカタと響くものもある。見た目も愛らしいが,音色の違いも楽しい。建築の姿をしたミニチュアではあるが,音を奏でることもできるという点において,土鈴は実にユニークである。

各地の社殿や町屋を表現
土産と宮笥
土鈴は,空洞とした内部に丸玉が残るように工夫した素朴な味わいのある焼き物である。古代の人々も使っていたらしく,石笛や土笛と同様に遺跡から発掘されることがある。なんらかの祭祀に用いられたようだ。
その音色に,魔物を払う効果があると思われたのだろう。福岡の英彦山(ひこさん)神宮で,「がらがら」と称する球状の土鈴が配布されるようになったのは鎌倉時代のことだ。「水守り」として田畑に埋めたり,玄関の軒先に飾って魔除けに用いたという。近世になると,神仏を参詣した際に持ち帰る土産物として,鮮やかに絵づけを施した縁起物や魔除けの土鈴が,各地で制作されるようになる。
わが国における土産の発祥を見ると,神社との関係が深い。本来は土地の産物を意味するべく,「どさん」と称したようだが,いつの頃からか「みやげ」と読み換えるようになった。言葉の由来を探ると「都笥」「宮笥」「屯倉」「都帰」など,さまざまな表記にたどり着く。「見上げ」,すなわちよく見て選び差し上げることの意から転じたとする説明もあるがどうだろう。語源に定説はないが,今のところ神社で配布されたものという意味合いの「宮笥」に由来するとする見方が有力とされるようだ。
ここでは神社にゆかりのあるミニチュアとして,春日大社や嚴島神社など,聖域の参道に並ぶ灯籠をモチーフとした土鈴も紹介しておこう。これらの土鈴は,神域と私たちを繋いでくれている。まさに,その土地の所産である「土産」であると同時に,神社からいただく「宮笥」なのだ。

神社の灯籠がモチーフ
ミニチュア提供:橋爪紳也コレクション