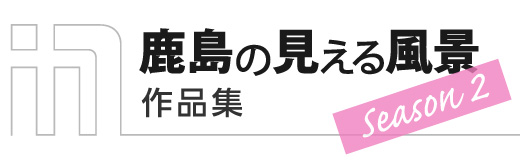リマの中心街, ミラフローレスの海岸線
©Christian Vinces/shutterstock.com
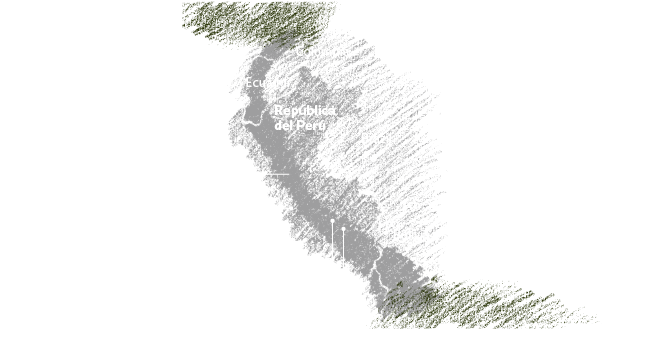

旧市街のリマックの通り。木造バルコニー建築が連なる
©Simon Mayer/shutterstock.com
南アメリカ大陸西岸,太平洋に面した砂漠地帯を流れるリマック川の河口に,ペルーの首都リマがある。リマは人口1000万人を超える南米太平洋岸最大の巨大都市だ。首都再開発により,富裕層が新たに開発された近代的な新市街やゲーテッド・シティに移り住んだことで,大統領宮殿や大聖堂などを擁する旧市街は,庶民の街として賑わっている。20世紀前半以降,繰り返し開発が進むリマは,さらに地方からの人口流入を受けて今なお日々拡大し続けている。

ハンカチを手にペーニャでマリネラを踊るペア
かつてインカ帝国の中心であったペルーは,植民地支配の拠点としてペルー副王領となり,首府リマが置かれた。以後,1776年に大西洋岸にブエノスアイレスが開港し大西洋航路が主流になるまで,リマはスペインによる南米支配の要でありもっとも先進的な都市であった。

バランコの老舗ペーニャ,ドン・ポルフィリオ
*
アンデスの国というイメージが強いペルーであるが,20世紀半ば以降アンデス地域に住む先住民や混血の人たちが大量に出稼ぎに来るまで,首都リマの人々にとってアンデス世界は遠い存在であった。当時のリマっ子たちとは,植民者であるヨーロッパ由来の人に加え,強制連行され奴隷化されたアフリカ系の人々とその子孫(以下アフロ系子孫),そして両者の混血によって構成されていた。
そのリマを代表する伝統的な音楽といえば,「ムシカ・クリオージャ」だ。この音楽は,20世紀初頭に「バリオ」と呼ばれた旧市街の下町で生まれたパーティ音楽だ。バリオの宴会では,ヨーロッパから伝わり土着化したワルツやポルカ,さらにペルーでアフロ系音楽の影響を受けた即興性の高い舞曲マリネラなどが,狭い長屋で明け方までお酒と冗談とともにとめどなく演奏され,歌われ,踊られてきた。また愛する家族や恋人に歌を贈る「セレナータ」は,今なおバリオの音楽家たちの間で愛されているロマンティックな伝統だ。
バリオでは,地元の作曲家による身近なレパートリーが長らく宴会で歌い継がれてきた。なかでも20世紀初頭に活躍したフェリペ・ピングロは,決して実らぬ身分差の恋の苦しみを歌った「庶民(エル・プレベジョ)」に代表される名曲を数多くつくり,今なおペルー最高の民衆作曲家として愛されている。このバリオの伝統文化はやがて,音楽メディアの登場とともにラジオやレコードを通じてスター歌手を生み出し,20世紀半ばにはペルーを代表する音楽となった。プライベートな宴席で歌われていた音楽も,いつしかペーニャと呼ばれるお酒を飲んで踊れるライブハウスでプロの演奏を聴くものへと変化した。

亡き人の誕生日を祝う宴。
かつて誕生日は1週間祝われていた
この音楽が上流階級にも愛されるようになった背景には,上流階級出身でありながらムシカ・クリオージャの革新者で「アフロペルー音楽」の擁護者であったチャブーカ・グランダの存在が大きい。「ニッケの花(フロール・デ・ラ・カネーラ)」に代表される彼女の洗練されたワルツでは,リマの上流階級が憧れる古き良きリマが郷愁とともに歌われた。また代表曲のひとつ「ため息の小橋」は,彼女が小さい頃よりよく谷間を見下ろしながら未来を想像していたというリマのバランコ地区にある古く小さな木橋が舞台だ。かつて別荘地だったというこの小さな海辺の町は,今では首都の拡大によってリマに飲み込まれ,芸術家たちがアトリエを構え,音楽ライブが日夜行われる活気ある地区となっている。

バランコにある「ため息の小橋」と歴史地区
©Ian Dagnall / Alamy Stock Photo

リマへの郷愁を歌い人々の心を揺り動かした
チャブーカの像がバランコを見守る
**
また先述のアフロペルー音楽もリマを代表する音楽のひとつだ。沿岸部の民衆音楽としてペーニャなどではムシカ・クリオージャと一緒に演奏されるが,アフロペルー音楽は1960年代以降活発化したアフロ文化復興運動から生まれた新しい民衆芸術だ。この音楽は,奴隷時代の伝承や仕事歌などを再構築し,さまざまな打楽器を使ってリズムを複雑に組み合わせたポリリズムにのせてコール&レスポンスで奏でられる。
その象徴的な楽器には,ペルーで奴隷として使役されたアフロ系子孫が生み出した,木箱に座り前面上部を手で叩いて演奏するカホンと呼ばれる打楽器がある。その代表的な奏者《カイトロ》・ソトが歌った「トロ・マタ」は,発表の翌1974年にはセリア・クルスがサルサで歌って一気に有名になった。このカイトロのカホン演奏を聴いたフラメンコギター奏者,パコ・デ・ルシアがカホンをフラメンコに導入したことで,カホンは一気に世界へと広まった。

現代アフロペルー音楽を代表するカホン奏者,コティートのライブ風景
また2002年にペルー人初のラテングラミー賞を受賞したスサナ・バカの「マリア・ランドー」も,他人のために働くことを余儀なくされる奴隷の苦しみを歌った名曲だ。ムシカ・クリオージャやアフロペルー音楽は伝統的な枠組にとどまらず,サルサやジャズ,クラブ音楽などと融合しながら新たな挑戦も続けている。

鮮やかな色彩に心ときめく街リマ

美食の街リマでは下町の食堂でも
思わぬ名店に出会う
***
非商業的なバリオのムシカ・クリオージャのリバイバル運動も盛んだ。特筆すべきは20世紀初頭の古いスタイルを踏襲するラ・カテドラル・デル・クリオジスモ(クリオージョ主義の大聖堂)の活動だ。毎週金曜日の夕方,主催者宅に友人たち——バリオの音楽家や詩人,愛好者たち——が三々五々集まると,車座になってピスコ(ブドウの蒸留酒)を飲みながら音楽に興じ,冗談や思い出話に花を咲かせる。民衆音楽のもっとも根源的な在り方がそこに息づいている。彼らの音楽への尽きることなき熱情の源泉は,ハラナと呼ばれる音楽と笑いのある祝祭的な場を共有し,つくり上げていく刹那的喜びにこそあるのだ。

カテドラル・デル・クリオジスモ。
宴の伝統が現代に継承される
[Listening]
Valdelomar Dávila/De Familia: Pureza de una tradición(2011)
バルデロマル家とダビラ家というリマの二つの音楽一家が奏でる伝統的でありながら超クールなムシカ・クリオージャの名盤。民衆音楽を継承する核のひとつが家族であることがよくわかる一枚。
※視聴する際は、音量にご注意ください。