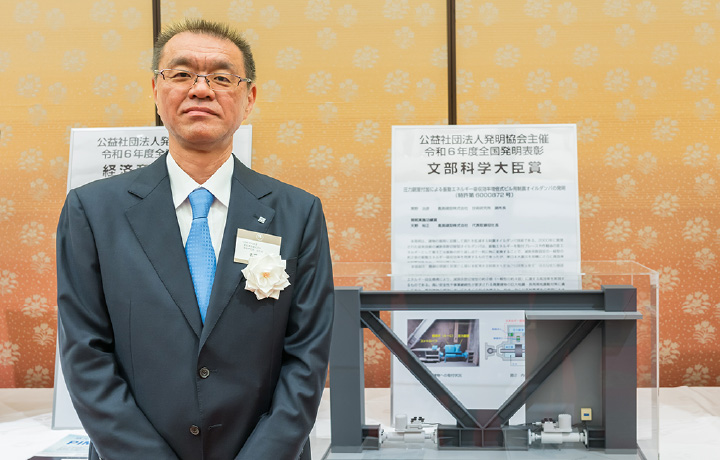栗野副所長
全国発明表彰「文部科学大臣賞」
受賞インタビュー
技術研究所副所長 栗野治彦が、令和6年度全国発明表彰(主催:公益社団法人発明協会)において、「圧力副室付加による振動エネルギー吸収効率増倍式ビル用制震オイルダンパの発明(特許第6000872号)」で「文部科学大臣賞」を受賞しました。
受賞後の副所長インタビューをご紹介します。
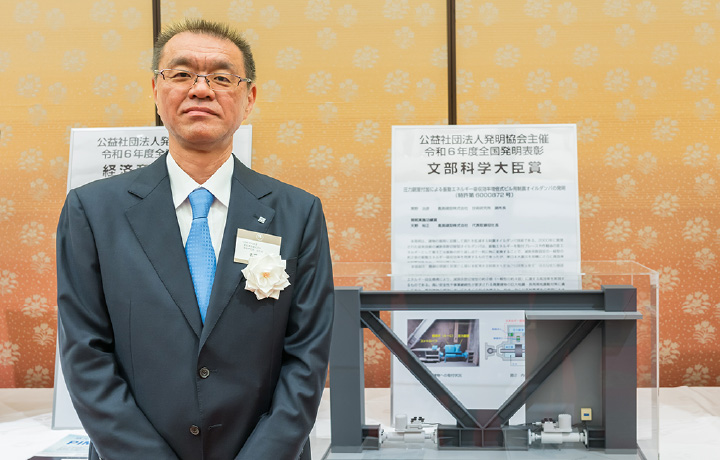
栗野治彦副所長
Q. 研究者を志したきっかけは?
新宿の超高層ビル群や代々木体育館に感銘
私は九州出身なのですが、大学進学で初めて東京に来て、新宿の超高層ビル群や代々木体育館を間近に見て感銘を受け、建築構造の道を進もうと思い、大学/大学院では鉄骨構造の研究室を選びました。就職する際には研究室の先輩にあたる技術研究所の方に鹿島に誘われ、迷いなく決めました。当時から「構造なら鹿島」と信じて疑わなかったからです。雰囲気的に配属先は技術研究所だろうと思っていましたが、いざ入社してみたら小堀研究室(当時)に配属され、「制震」の研究をするように命じられました。制震という言葉はもちろん、動的なことにも馴染みがない状態でスタートしたわけですが、それが自分の核となる専門分野になるとは夢にも思っていませんでした。幸運/良縁によるテーマとの出会いに感謝しています。
Q. 今回の受賞のポイントは?
新発想のエネルギー回生機構
対象となった発明は、鹿島の制震オイルダンパの最新機種「HiDAX-R®」で、受賞のポイントは、「15年以上におよぶ従来技術のノウハウを最大限生かしつつ、限界に達していると思われた制震効率をさらに向上させる独創的なエネルギー回生方式を発見し開花させた。」という点です。ここでいう従来技術とは、2000年に開発したオリジナルのHiDAXを指しています。HiDAXはオイルダンパに内蔵した制御弁の開閉状態を切り替えて、建物の振動エネルギーをブレースや作動油の歪エネルギーとして蓄えては、振動の折り返し点で瞬間的に開放し熱に変えることで、一般のオイルダンパの約2倍のエネルギー吸収効率を発揮します。このエネルギー吸収効率は減衰係数の制御で実現可能な理論限界値であることが分かっていましたので、これを超えるには「新しい何か」が必要でした。それを思い付くのにHiDAX誕生後長い時間がかかりましたが。

表彰式にて記念撮影。発明協会 内山田竹志会長(中央)、天野社長(右)
ブレイクスルーを実現したのは、自動車のブレーキ制御などで用いられているエネルギー回生の原理を制震オイルダンパに応用した新発想のエネルギー回生機構です。HiDAX制御の過程でブレースや作動油に蓄えたエネルギーを一旦補助タンクに回収し、それをダンパの制震効率を高めるアシスト力として再利用するというものです。エネルギーの形を変えずに回収することで振動エネルギーの30%程度を再利用することに成功し、限界と思われていたHiDAXの約2倍、一般のオイルダンパの約4倍という画期的なエネルギー吸収効率を実現しました。追加する部品は、タンクや制御弁といった実績豊富な汎用部品のみであり、コストや信頼性など実用システムとしての要求を高い次元でクリアしている点も高く評価されたものと考えています。
Q. 制震研究を始めた当時について
「制震でやることは終わった」と言われたショックからスタート
私は1991年に入社しましたが、当時の制震研究の大きな流れは機械の分野などで発展した最適制御理論の導入を主としたアクティブ制御方式の研究でした。1989年には錘型のアクティブ装置AMDを搭載した京橋成和ビル、1990年には油圧の可変剛性システムAVSを搭載した技術研究所21号館制御棟が完成していました。当時の小堀研究室の先輩から、「今頃配属されても制震でやることは終わった。」と言われた時のショックはちょっと言葉で言い表せないのですが、実はそこからがスタートだったのです。地震時の建物の揺れを止めるにはとても大きな力が必要ですし、地震動は非定常、という条件の下では線形システムを前提とした最適制御理論の援用では当然行き詰まるわけで、「建築構造に相応しい制御方式」を考える必要がありました。その思考実験の延長線上にHiDAXシリーズがあるのです。
Q. 研究を志す若い人達へ
へこたれないで追求し続けてほしい
成熟した技術分野で新しいことを考えるのは容易ではありませんが、必ず突破口はあります。新しいこと、奇抜なことを考えるのは若者の特権です。人から否定されても「原理的に正しい」と思ったなら、へこたれないで追求し続けてほしいと思います。新しい発見・発明を生んでくれる特効薬はありません。誰もが見てきたはずの何の変哲もない風景に隠されている「まだ発見されていない何か」を自分が最初に見つけたい、という強い気持ちであらゆる観点から考え続けること。そのための武器となる基礎理論の習得は必要です。そうした姿勢で取り組んでもらえれば、これからも若い人たちから、「まだこんな発想があったのか!」という新しい技術が生まれてくるはずだと信じています。