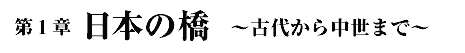
|
|
| 1-2 鮫が作った浮き橋 | ||
|
大国主の国曳きの神話で有名な出雲には、『いなばの白兎』という伝説があり、白兎が鮫をだまして、鮫の橋をつくらせ、それを伝って向こうの島を渡ったという話が伝えられています。 国曳き神話は、たとえば北欧のデンマークなどにも残されており、『遠くのものを引き寄せたい、歩いていけないところへ行きたい』という願いは、人類共通 の夢なのかもしません。 |
||
|
|
| 1-3 人類が作った最初の橋 | ||
|
丸木橋 人が架けた最初の橋は、歩いて通る道のつながりとして作られたものと思われます。大昔の橋は、自然の倒木を利用した丸木橋であったり、川の流れに飛び石をおいただけのものだったのでしょう。 人は文明が起きる古代から、道具を使い、経験的に橋をつくる技術を学んできました。 そして、現代に見るような長大な橋を建設する技術を自らのものにしてきたのです。 |
||
| |
| 1-5 日本の三奇橋 | ||
|
日本には三奇橋と呼ばれる橋があります。 山梨県大月にある猿橋。木曽の桟橋(かけはし)、山口県岩国の錦帯橋の三つが、日本三奇橋にあげられています。 このうち、木曽の桟橋は深い渓谷沿いに桟道をつけ、その先に渓流を渡る橋があったようですが、現存しないのでその構造は不明です。おそらく、大月の猿橋と同じような構造であったのではないかと思われます。 |
||
|
|
| 1-7 岩国の錦帯橋 | ||
|
錦帯橋 ©米田 守 岩国の錦帯橋は木の橋としては、世界的にみても素晴らしい橋です。この橋は江戸時代の初めにつくられたのですが、川の中に飛び飛びに島をつくり、そこに石で橋脚を建て、アーチ型の橋桁を木で渡しています。こうした工夫によって洪水にも流されることなく、現在でも当時の姿のままに残すことができたのです。 |
||
|
|
 |
※このコンテンツは、2001年に開催されたインターネット博覧会出展時のアーカイブです。