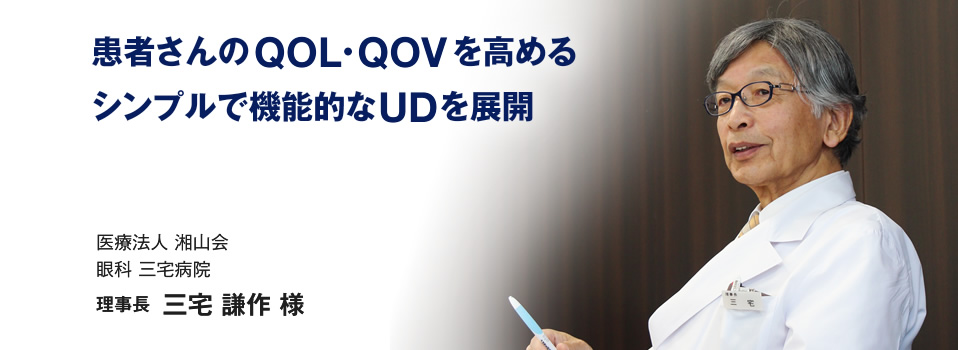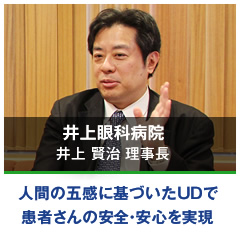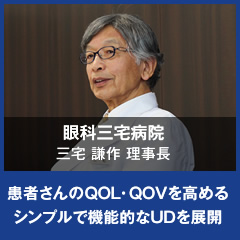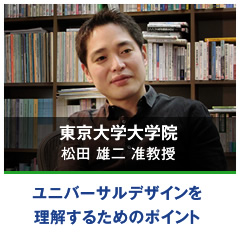60有余年の歴史を通して眼科医療のパイオニア的役割を果たしている「眼科 三宅病院」。2015年に建設した新病院では「シンプル」と「コントラスト」をキーワードに多彩なユニバーサルデザイン(以下UD)を採用し、ロービジョンの方に優しい環境を実現しました。その具体的な取り組みや意思決定のプロセスについて、三宅理事長にお聞きしました。
患者さんがストレスなく、安心して利用できる病院を目指して
新しい病院建設を計画されたきっかけを教えてください。
以前の病院は、開業から60年が経過し、その間、増改築を繰り返してきたことで、建物としての一貫性を失っていました。施設内は複雑で無駄が多く、手術室は手狭で、動線も非効率的になっており、そうした問題を解消して一貫性のある計画にするとともに、設備の刷新と耐震性の向上を図るべく、新病院建設に踏み切ったのです。
新病院をつくるにあたって、特に重視したのはどんなことですか?
患者さんが利用しやすくストレスの少ない環境とすることと、現場スタッフの意見を十分に取り入れることの2点です。たとえば動線が合理的になれば、患者さんが移動する際のストレス軽減につながりますし、安全性も高まります。また、スタッフも合理的に動くことができるため、無駄なエネルギーを使うことなく、本来の業務に集中することができ、医療の質を高めることにもつながります。
病院という場所は、患者さんのQOL(Quality of Life=生活の質)とQOV(Quality of Vision=視覚の質)を高める環境であるべきです。医療側にとっても、患者さんに配慮する観点は大事です。それを実現する具体的な手法として、鹿島さんからご提案いただいたのがUDでした。UDの理念は、われわれの想いとも非常によく合致するものでしたから、新病院では本格的にUDに取り組むことにしました。
視覚・聴覚・触覚のコントラストでロービジョン者をサポート
新病院で採用されたUDについて、具体的に教えてください。
特に「コントラストを強める」ということは、ロービジョンの患者さんのQOLとQOVを高める上でとても効果的です。そのため新病院では、さまざまなかたちでコントラストに着目しました。
まずは視覚のコントラスト。ロービジョンの方でも見分けやすいように、床は濃いブラウン、壁や椅子は白に統一しました。各種のサインやピクトグラムも、地色とのコントラストを際立たせて、文字や図を視認しやすいように工夫しました。さらに、トイレは背壁面を濃いグレーにすることで、白い洗面器や衛生陶器を発見しやすいようにしました。
視覚的なコントラストだけではなく、聴覚・触覚的なコントラストも採り入れました。一例を挙げると、通路エリアの床には固めの塩ビシートを使い、待合室には柔らかめのタイルカーペットを採用。これは足で踏んだ感じや足音の響きに違いを出すことで、エリアの変化に気づきやすくすることが狙いです。ほかにも照明を適切に配置することで、空間の奥行や、手前にいる人のシルエットをより認識しやすいようにするなど、随所にUDを採用しました。
こうした五感に訴える、あるいは、五感に響きやすい、細かい配慮をすることで、全体的に待合などでの事故防止にも役に立っていると思います。
コントラストを強め、見分けやすく統一感のあるデザイン



手術に起因する合併症を1例も出さないという伝統を継続
三宅病院は、眼内レンズをはじめとする眼科医療のパイオニアとして知られていますね。
そうした医療の機能面で、特に注意したことはありますか?
当院は、眼科の一次・二次・三次医療のすべてをカバーする多様な機能を有しており、手術件数は年間6,000件にのぼります。こうした病院の性格が十分に発揮できる環境の整備のため、特に手術部門を充実させました。最新機器の導入も想定し、また、術者や介助者の妨げにならないよう、十分な広さを持つ手術室を4室新設しました。広さだけではなく動線も劇的に改善され、理想に近い手術室ができたと満足しています。

手術室に高清浄度を維持できる空調システムを導入
また、TASS(※)を一例も出していないことは当院自慢の伝統ですが、その伝統を継続して維持していくため、高清浄度を維持できる空調システムも導入しました。手術に起因する合併症を防止することは、病院を新築するときに注意すべき問題の一つだと言われています。
病院を新築してから1年が経ちましたが、TASSを1例も出さないという伝統を、また1年伸ばすことができました。
※TASS:Toxic Anterior Segment Syndrome=白内障手術などによる非感染性炎症疾患
現場スタッフの意見を、病院建築の専門家が具現化
新病院のデザインは、どのように決定されたのでしょうか。
私が重視したのは、病院としての清潔感と均整を備えた、シンプルなデザインにすること。
それを実現する具体的なプランニングやデザインは、鹿島の病院建築専門の設計者から提案していただきました。
また、医師、看護師、検査技師らからも、それぞれの持ち場の問題点や改善要望を挙げてもらい、デザインに反映させました。経営陣が細かい意見を言わず、現場を熟知するスタッフの声を大切にしたことは、新病院をよい病院にするうえでとてもよかったと思っています。
鹿島さんはスタッフの意見もうまく集約し、適切な提案をしてくれたと思います。完成した病院はまさに私のイメージ通り、シンプルで品のあるデザインになっていて感動しました。
鹿島のプロフェッショナルを信頼しておまかせしたことで、意思決定が早まり、スピーディに建築を進められたのもよかったですね。私も含めて、スタッフのモチベーションにも良い影響を与えていると思います。
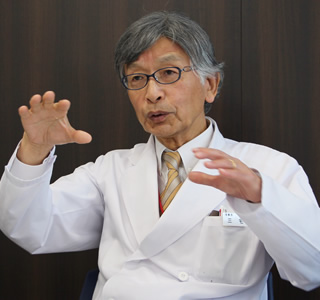
設計者の提案を受け、患者さんとスタッフの動線を明確に分離
新病院で、特に気に入っているのはどんなところですか?
診察室の外周に、スタッフ専用の通路を設けたことです。正直、鹿島さんからこれを提案されたときは迷いました。ただでさえ敷地が狭いのに、そんなところにスペースを割くのはもったいない、どうせなら診察室や待合室を広くしたいと思ったのです。

スタッフ専用の通路
しかし、いざ完成してみると、スタッフ専用のエレベータを使い、患者さんがいる場所を通らずに病院内を行き来できる構造は想像以上に便利なものでした。動線を明確に分離したことでスタッフの作業効率は格段に高まり、患者さんも煩わしさを感じなくてすむ。動線の大切さを改めて実感しました。
しかもスタッフ専用通路には吊戸棚やカウンターをズラリと配置し、収納スペースも兼ねているので、まったく無駄がありません。パソコンも置けるし、手洗いもあります。
私は診察の合間に論文を書くことが多いのですが、スタッフ専用通路を利用することで、とても効率的に行うことができるようになりました。これはとても嬉しいことで、プロの提案を信用して本当によかったです。

動線の明確な分離により、待合スペースもスタッフの行き来がなくなり、患者さんが煩わしさを感じない落ち着いた空間に
ソフトとハードの両輪でロービジョンケアを推進
最後に、鹿島へのご要望がありましたらお聞かせください。
すでに日本は世界に先駆けて超高齢社会を迎えており、今後も高齢化はさらに進むと見込まれています。これは、加齢に伴う視覚障がいを持つ方が増えることを意味します。
人は情報の多くの部分を視覚から得ていますから、高齢者がアクティブに暮らせる社会を実現するには、ソフト(医療)とハード(環境)の両輪でロービジョンケアを推進する必要があります。
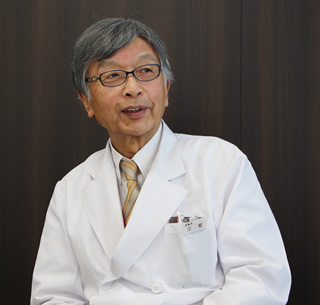
このうちソフト面、すなわち眼疾患の予防や治療を行うことは、われわれ医療関係者の使命です。一方、まちづくりなどハード面の担い手は、鹿島さんをはじめとする建設会社にほかなりません。
先進的なUDを採り入れたことで、新病院はロービジョンの方にも優しい環境になったと自負しています。しかし、患者さんにとって病院は人生のごく一部でしかありません。彼らがいつでも、どこでも安心して暮らせるようになるには、社会全体の環境整備が必要です。
鹿島さんにはUDのリーディングカンパニーとして、病院に留まらず、広く建築において、ロービジョンの方に配慮した環境づくりをさらに推進していただきたいと期待しています。